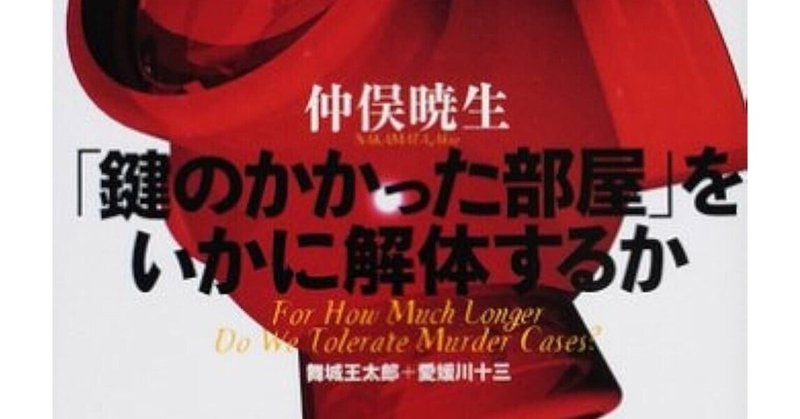
テラヤマシュージ・ツールキット
唐十郎さんが奇しくも寺山修司と同じ日に亡くなったのを受けて、21年前に『別冊文藝 寺山修司』に書き、絶版になってる私の3冊目の文芸評論集『「鍵のかかった部屋」をいかに解体するか』に収めた寺山修司論を、久しぶりに公開します。
1983年に47歳で寺山修司が亡くなったとき、19歳だった私は、寺山の本をまだ一冊も読んでいない。寺山修司が入院していた河北病院は私の父方の実家のある東京の阿佐ヶ谷にあったから、彼の死を知って連想したのは駅からも見えるあの病院の大きなカンバンだった。寺山が亡くなってその享年を知ったとき、もっと年寄りだと思っていた彼が意外と若いことに驚いた。
一冊も本を読んでいなくても、寺山修司が「書を捨てよ、町へ出よう」という本を書いた人だということは知っていた。でも1960年代生まれの私たちはとっくに「書を捨てた」世代だった。
高校生時代の私はごく一時期『ビックリハウス』という投稿雑誌の熱心な読者だったことがある。この雑誌の最初の編集長が萩原朔太郎の孫だとは聞いていたが、劇団天井桟敷の関係者だったことは知らなかった。だから、「素人による投稿雑誌」というコンセプトのルーツが、寺山の演劇や詩における活動にあることにも気づかないでいた。この頃かなり好きだったスターリンの遠藤ミチロウが母への愛と怨嗟を歌った「お母さんいい加減あなたのことは忘れてしまいました」に寺山と似た東北訛りを聞き取りながらもその意味をよく考えなかったし、いまでも本が出るたび読んでしまう橋本治が当時書いていた若者向けの軽い雑文の文体が寺山のそれにそっくりなことにも、そのときの私はまだ気づいていなかった。
私が1989年に25歳ではじめて就職したのは東京のタウン誌『シティロード』だった。でも、この雑誌が数年後には廃刊になってしまうことが示すように、「町へ出よう」とかつて寺山がアジテートした東京という都会は80年代にはバブル経済に食い尽くされ、「町」としての意味を失っていく。その事実を、私は自分が十代終わりから二十代はじめにかけて通ったいくつかの映画館やライブハウスや喫茶店が消滅していくのを見ることによって知る。「シティロード」の版元が倒産して私が失業した90年代のはじめには、私たちが「出ていく」ための町なんて、もうどこにもなくなっていた。
寺山修司の本を私がまともに読んだのは、たぶんこの失業時代に阿佐ヶ谷の古本屋で買った「鉛筆のドラキュラ」(思潮社)がはじめてだと思う。私と寺山との間では文学の趣味に重なるところがほとんどない。実家の近所に住み、父と同じ高校を出ている詩人の谷川俊太郎に多くのシンパシーを感じていた私は、したがってこの本に収められた文学論や演劇論にほとんど共感しないのだが、二つの論考「ラジオ・迷路・耳なし芳一」「ウォーホル論を複製する試み」には目がとまった。このとき、ようやく寺山修司の世界と私とのチューニングが合う。 前者の冒頭で、寺山はブレヒトの『ラジオの理論』から次のように引用している。
社会がまだラジオを受け入れるにいたっていない時代に、技術はそれを出現させる状態にまで発展しえたのだ。公衆がラジオを待望したのではなく、ラジオが公衆を待望した。ラジオをめぐる状況をいっそう厳密に特徴づけるなら、素材が公衆の必要にもとづいて製作の方法を待望したのではなく、制作の方法が不安気に素材を捜しもとめているのだ。万人にむかってあらゆることを語りかける可能性が、とつじょとして生み出されたが、よくよく考えてみると、語りかけるべきものはなにもなかった。
寺山がこの言葉を引用した1973年、まだインターネットどころかパソコン通信でさえ日本では生まれていない。しかし、私がこれを読んだ1993年には違った。書を捨て、町へ出ても何もなかったが、もう一つの「出口」があるかもしれない、という予感が、その頃の私になかったとは言えない。
東京という都会がトポスを喪失していくのと並行して、電子メディアのなかにひとつの「スペース」が生まれてくる。サイバースペース、という言葉で名付けられた電子ネットワーク上のアドレス空間は、寺山が「大工町寺町米町仏町老母買う町あらずやつばめよ」とかつて歌った世界とはまったく違うロジックで構成される世界だった。インターネットはこのとき日本ではまだ本格的に普及していないが、1960年代に淵源をもつカウンターカルチャーとコンピュータカルチャーの蜜月が信じられていた時代ではあった。私はようやく廉価になりつつあったマッキントッシュ・コンピュータを購入し、失業時代を乗り切るための相棒と決めた。
「シティロード」で一緒に働いていた原雅明くんがその頃アップリンクから創刊された「骰子」という雑誌の編集者となり、その縁で浅井隆さんともこの頃初めて会った。マルチメディアと呼ばれていたコンピュータによる表現や出版の試みをどう考えるか、一晩徹夜で議論したのもこの頃だった(そういえば浅井さんも元天井桟敷の人だ)。同じ頃、ボイジャーという表参道にある小さな会社が「電子書籍」という聞いたことのない試みを始めていることを知った。1994年に私が「サイバースペース」の可能性を楽観的に信じる立場をとる「ワイアード」という雑誌の日本版の創刊に関わることになったとき、一つだけ本気で確かめたかったのは、電子メディアは書物や都市の代わりを果たすことができるのだろうか? という、いつの間にか自分のなかでふくれあがった問いだった。
ボイジャーは、誰でも自分で電子的に本が出版できるというふれこみで、「エキスパンドブック・ツールキット」というコンピュータ・プログラムを製作・販売していた。そして、かれら自身がこのキットをもちいて作った(ほとんど唯一の)作品が、寺山修司の詩やエッセイ、戯曲、映画などをおさめたマルチメディアCD-ROM『書を捨てよ、町へ出よう』だった。マルチメディアという言葉は数年で廃れたが、寺山修司のような人の残したいくつもの記録の断片(作品、と言っていいのかどうかわからないのであえてこう言う)をパッケージするには、当時としてはCD-ROM以外の方法はなかったのかもしれない。
さきに紹介した寺山によるブレヒトの引用の「ラジオ」を「インターネット」に置き換えると、ほとんど今でも通用するメディア論的な考察となる。しかし、寺山はべつにインターネットを予言していたわけではない。「ラジオ」に代入されるべき言葉は、おそらく寺山自身だった。
「公衆が寺山修司を待望したのではなく、寺山修司が公衆を待望した」のだし、たぶん 「万人にむかってあらゆることを語りかける可能性が、とつじょとして生み出されたが、よくよく考えてみると、語りかけるべきものはなにもなかった」というのも、寺山修司自身のことだったのではないか。
もちろん、「なにもない」ということは悪いことではない。「なにもない」ということを語りかけるような表現形式やメディアはそれまでになかったのだし、寺山のなかに「なにもない」からこそ、寺山の周囲に集まった膨大な人たちは、ツールキットとしての寺山を使って「なにか」が表現できたのだろう。宿命的な母との関係を抜きにしても、寺山修司はそういう点でも、アンディ・ウォーホルによく似ている。 寺山修司の歌集「血と麦」の巻末には「行為とその誇り」という歌論というか詩論というかメディア論というか、よく性格のわからない評論が収められており、そこにはこんな一説がある。
私はときどき、詩がどうしてこんな風に思考と行動の廃墟になってしまったのか、と思いかえしてみることがある。多分、それはカリフォルニア派の詩人が指摘するように活字のせいなのだ。「グーテンベルクの印刷機の発明が詩を堕落させた」ことは殆んど間違いない。
「活字」という言葉がすでに死語になってしまった今からではわかりにくいが、たぶん寺山が「書を捨てよ、町へ出よう」と言ったときに念頭にあったのは、グーテンベルク的な意味での「活字」的な書物のことだったろう。それを「イコン的な書物」と言い換えてもいい。
ところで、私はいまこの原稿を、ウィンドウズ2000の上で走る「Adobe In Design 2.0」というDTPソフトの上でダイレクトに書いている。求めに応じて書いた文章なので、これはまず印刷され、商業的な文芸雑誌のある欄を埋めることだろう。しかし、私はいずれこの文章を、インターネットで公開するつもりだ。べつにインターネットで文章を公開することが、書物に印刷されるよりも「思考と行動の廃墟」から遠いと牧歌的に考えているわけではない。私にはまだ、活字=書物と、都市と、電子空間の間の関係がわからない。
「空には本」。寺山修司の最初の歌集はそういう題なのだと、今回の小論を書くために彼の残した著作にひとつひとつ目を通していくなかで、私ははじめて知った。最初から最後まで、私と寺山修司とはそういうふうにすれ違っているのだが、それで連想したのが「青空文庫」という、インターネット上のテキスト・アーカイブのことだ。ここでは著作権切れの古典作品や、著者の了解を経て転載された著作権の切れていないテキストが、無料で閲覧・ダウンロードできる。けれどもここに寺山のテキストはない。まだ死んで20年しかたっていないからだ。
ただ、寺山が最初の歌集を「空には本」と命名したことと、「青空文庫」という発想には、どこか、共通した牧歌的なイメージがあるように思う。
公衆がインターネットを待望したのではなく、インターネットが公衆を待望した。
この言い換えは果たして正しいだろうか。
寺山修司もアンディ・ウォーホルも、「よくよく考えてみると、語りかけるべきものはなにもない」人だった。でも、ツールキットとしての寺山は、ウォーホル同様、いまでも使い途がある。
本当なら、私たちはいまさら寺山修司の作品など読み返さなくてもいいはずなのだ。寺山修司をいま読むとしたら、「○○によって待望されている自分」というくびきから自身を解放するために、あれだけたくさんのガラクタを残さなくてはならなかった一人の20世紀人を知るためだけだろう。
1996年にステレオラブが出した名盤『エンペラー・トマトケチャップ』には、寺山修司の「トマトケチャップ皇帝」の影響なんてカケラも見られない。テラヤマシュージはすでにワールドワイドなポップイコンのひとつになってしまった(あの東北弁を聞いたことのない若い世代にとってはなおさら)。でもそれは、寺山自身が望んだことだろうか。
イコンになるよりは、寺山修司はコンドームやノリやポストイットやバンドエイドになりたかっただろう。渋谷の東急ハンズで文房具や避妊具のように売られて、惜しげもなく使うだけ使って捨ててられることのほうが、サブカルチャーの世界で伝説化されたりイコンにされたりするよりずっとましだと考えただろう。誰だってそうじゃないか? 生き続けるより、早く死ぬことによってツールとして広まることができるのだとすれば、人が早くに亡くなることにもまんざら意味がないわけではない、と思う。
*初出『別冊文藝 寺山修司』(河出書房新社)
copyright 2003 Nakamata Akio
This work is licensed under a Creative Commons License.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
