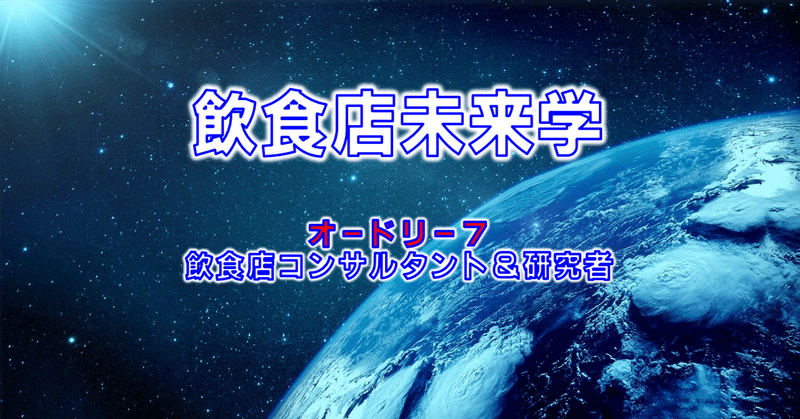
飲食店未来学53:飲食店のメニュー価格の値上げととるべき対策は?
2~3年前までは、食材メーカーの値上げは、2~5%の小刻み値上げを年間3回~5回させてきました。しかし昨年2023年の秋以降は、7%以上の値上げ、今春に至っては10%~30%の値上げも行われています。
全飲食店の公的食材原価率平均値はおよそ36%です。中大型店では、食材と調味料を含めて、1か月に150品目~200品目を仕入れています。毎月個のどれかが値上がりしています。
食材メーカーが年に数回値上げできるのは、「使わざるを得ない食材」だからできるのです。カゴメのケチャップ、キューピーのマヨネーズなどです。
食材を変えると味が変わるため、変えられないのです。
一方で価格転嫁をするために、仮に飲食店が年数回値上げをしたらどうでしょうか?結果はわかっています。値上げのたびに来店客数が減ります。
飲食店の価格転嫁値上げメニューのコツ
これは本当の話です。実際に行ってきたノウハウです。お客さまを減らさずに値上げ(価格転嫁)させるのは、なぜそうするのかを理解できれば、かんたんなことです。
●値上げメニューの投入は年1回~年2回まで
値上して月とともに馴染んで忘れかけた頃に値上げする。痛みを和らげながらソフトランディングすることが大切です。
●2回実施のとき1回目は大きく2回目は小さく値上げする
私の本に詳しく書いていますが、あとの値上げが前回より大きいと客離れを起こしますね。あくまでお客さまに認めていただき、定着するためのノウハウです。
1年に15%~20%の値上げが必要な時代
少しだけ値上げすることで我慢している飲食店は、家賃がかからない、家族経営で人件費が比較的安い、利益率が良い商売などです。客数が減ることを恐れて数%の値上げをしているところは、赤字が膨らみ、やがては消滅します。
潰れるか、価格転嫁という値上げを勇気を出して行うか、二者択一を迫られます。一歩を踏み出さず、躊躇して何もしない場合は、自滅するしかありません。すべての飲食店がこの踏み絵を踏む立場です。
●10%を超える値上げは2回に分けて実施する
15%の値上げの場合は、10%~12%を春に値上げして、半年後に5%~3%を微調整値上げする。この時気をつけることは、部門別に一律の値上げでなく、個別のメニューの「オーダー率」を目安に値上げ額を決めることです。
個別に決めるとなると時間もかかりますし、実に面倒です。しかしこの面倒くさいことを完了するからこそ、価格転嫁が成功するのです。そういう意味では、楽な一律値上げをした会社はすべて売上減を覚悟しなければなりません。お客さまの声(オーダー数)を聞き分けながらの値上げが正しいのです。
ていねいは値上げであれば、万一オーダー数が維持的に下がっても、値上げ後30日間~40日間ほどで回復します。
●値上げと値上げの間に一季節置く
値上げ後3か月でまた値上げすることは、W値上げの印象を強くします。忘れる前に重ねてしまうからです。最低限、ひと季節は馴染ませる期間を作りましょう。春の値上げが終われば、夏を過ぎた秋以降の値上げが良い。
詳しくは、この本をご覧ください。(オードリー7の著書)
旧著者名 流石種
(了)
飲食コンサルタント業30年の経験を通じてお知らせしたいこと、感じたこと、知っていること、専門的なことを投稿しています。 ご覧になった方のヒントになったり、少しでも元気を感じて今日一日幸せに過ごせたらいいなと思います!よろしければサポート・サークル参加よろしくお願いします
