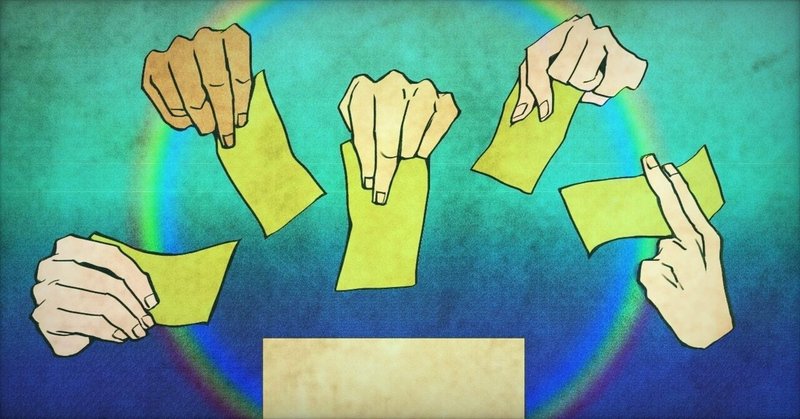
会派と野次:地方議員に会いに行ってきた
こんにちは。
「議員に会いに行く」を今年の目標のひとつにしており、少し前に地方議員との対話会に参加してきました。
参加者の方について思ったことはこちらの記事にまとめております。
どの議員を選ぶか
目的
・保育園について相談したい
・議員がどのような報告をしているのか聞きたい
・参加者の層を知りたい
議員の選び方
・女性議員(初対面なので同性の方が話しやすい)
・政策に共感できる
・インターネットの発信内容
HPやSNSを更新していない方が多く驚きました。
「支援者になっていただく方はこちら」といったフォームがある程度の方も。
いや、いきなり支援できませんけど・・
とがっかりしました。
スケジュール更新してくれれば、定期報告に参加出来ますが、いきなり電話して会いに行くのはハードルが高く機会損失ではないかと思いました。
それともあえてハードルを上げているのでしょうか。
議員さんの印象
私が会いに行った議員の方は
・野党所属
・50代女性
・第一期(新人)
選挙期間中、信号待ちしていた私に話しかけてくれたことも後押しになりました。
報告会に行ってみての印象
私の質問・意見にも丁寧に答えてくださり、真摯に活動されていることが分かり、応援したいと思いました。
良い意味で非常に等身大の方だったので、畏れ多くも(選挙諸々は置いておいて)特別なものを持っていない私でも地方議員になることができるようにも感じました。
会派
他の参加者の方のご意見で、会派に関する苦言がありました。
第一会派に何度も陳情をしているのに議会に取り上げてくれない。
ダメならダメで良いのに、取り扱わないならその旨知らせてもくれない。
陳情を全て取り上げる会派もあるそうですが、多くは会派ごとに委員長と副委員長で陳情を取り扱うか否かを決めるのが慣例となっているそうです。
私は会派のことなど考えたこともなく驚きました。
トンデモ案件が来るのも予想がつくので、全件というわけにはいきませんが、その方の陳情は真っ当なものでした。
取り扱わないのであれば何らかの方法でフィードバックがあっても良いのではないかと思いました。
そして議員の方の発言の行間に、会派のパワーバランスで苦労されている様子を感じました。
次は他の会派に所属する議員に会いに行ってみようと思います。
野次
もうひとつが議会における野次について。
「傍聴によく行くが、酷い野次を飛ばす議員がいて、辞めてしまうんじゃないかと本当に心配になる」
報告会に参加していたご老人の発言です。
私は区議会の傍聴をしたことがなかったもので、他の参加者の方にも野次について伺いました。
「首長が女性になり、明らかに当たりが強くなった」
「女性区議が増えていることにジジイ議員たちが焦ってるのではないか」
悲しい現実ですね。
つばさの党の選挙妨害を見る度に
こんな大変な思いまでして出馬なんて
私には到底できない
と思ってしまいます。
議会もそんな足の引っ張り合いばかりと思うと悲しいですし、私も現実を見るために議会の傍聴に次は行ってみようと思います。
議会や役所がより良い方向に向かうよう、私が出来ることを考え続けます。
今日のChatGPT
相手が女性議員である場合はあたりも強くなる傾向はあるのでしょうか。
女性議員に対する野次や批判が男性議員に対するものより強くなる傾向は、多くの国の議会で見られる現象です。以下にその理由と影響を説明します:
1. **ジェンダー・バイアス**:多くの社会には、依然として性別に基づく偏見やステレオタイプが存在しています。これが、女性議員に対する野次や批判が男性議員よりも強くなる原因となることがあります。
2. **内容の違い**:女性議員に対する野次や批判は、しばしば性別や外見、人格に関するものが多く、政策や意見に対する批判とは異なる傾向があります。これは、性差別的な発言やハラスメントに繋がることがあります。
3. **歴史的背景**:多くの国で、政治の世界は歴史的に男性が主導してきたため、女性議員が増えるにつれて、既存の権力構造に対する反発が現れることがあります。これが野次や批判の一因となることがあります。
4. **影響**:女性議員に対する過度の批判や野次は、議会の議論の質を低下させるだけでなく、女性議員の心理的負担を増加させ、政治参加への意欲を削ぐ可能性があります。これにより、女性の政治参加やジェンダー平等の推進に対する障壁が高まることがあります。
5. **対策**:多くの国や議会では、ジェンダーに基づく偏見やハラスメントを防ぐための規則や教育プログラムが導入されています。また、女性議員自身や支援団体が、こうした不適切な行動に対して声を上げることで、改善の動きが進められています。
このように、女性議員に対する野次や批判が強くなる傾向はジェンダー・バイアスに根ざしたものであり、その影響を軽減するための対策が求められています。
2. IPUのアフリカに関する2024年の調査
3. 「Women in Parliaments: World Classification」(世界議会女性分類)2023年のデータ
ちなみに報告会の参加者の大半が政党支持者、次いで政治へ関心が強い方、選挙出馬を考えている方でした。
自分の生活に関わることですので、自分事として捉えつつ、もっと気軽に政治と関わる機会が増えるといいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
