
コンパウンドスタートアップ、「既存のお客様に価値を届けきる」がムズすぎる件
こんにちは。圧倒的に使いやすいプロダクトを届け、ワクワクする働き方を実現したいmichiru_daです。
以前、所属しているLayerXのコンパウンドスタートアップならではのカスタマーサクセスの取り組みを紹介しました。
今回は、2023年4月以降の「既存のお客様にもっとバクラクの価値を届けて、業務をバクラクにする」ための活動(事業目線でいうエクスパンション活動)の実態についてまとめようと思います。
先に結論を書くと「バクラクのエクスパンション活動は、やりがいと工夫しがいがメッチャある、けどメッチャむずい、ぜひ一緒に挑戦してくれる仲間がほしい」となっておりますが、
コンパウンドスタートアップの活動記録としても、バクラク事業部で働くイメージをつけていただく上でも、参考になると嬉しいです。
現状のチーム構成、顧客接点のイメージ
既存顧客向けのエクスパンション活動について、2022年度はカスタマーサクセスのオンボーディング時のご提案一本足打法でした。
より多くのお客様に価値を届けるため、現在は巻き込むチームを増やしながら、組織的に取り組みを拡張しようとしています。
現在関わっているのは以下のようなチームです。

ざっくりした役割分担は以下ですが、まだ殆どのメンバーが兼任なこともあり実態としては 「自立駆動人材が自らの力でなんとか日々の顧客接点を切り開いている、属人的・荒野」な状態です。
サイクルにあわせてタッチ:お客様のご利用フェーズにあわせ接点を持つ
CSのカスタマーサクセスマネージャー(CXM)
CSのエクスパンション専門チーム(CSQLチーム)
スポット的にタッチ:今はニーズが少ないお客様へ課題訴求をする、検討開始されているお客様へ接点を持つ
カスタマーマーケ
カスタマーセールス
新サービスのGTMチーム

こちらの体制での活動は1ヶ月半になりますが、やってみてわかったことは、「届けたい価値は山程ある」一方で、「どこから手をつけるべきか、その解像度から上げねばならない」ということでした。
実際なにがむずかしいのか?
施策を実行するなかで、悩ましく思ったポイントは以下の3つです。
お客様・市場の変数が複雑で、優先度が付けづらい
horizontalなマーケットなので、お客様の業界・属性が様々です。業種によって業務フローが異なったり、ITツールとの距離感も全く違う
顧客の規模感もSMB~MMB~エンプラと多様化しており、課題意識も多様化
電子帳簿保存法や、インボイス制度など、業務影響の大きい法制度対応が複数行われているため、タイミングによってサービスの訴求価値も変える必要がある
リリース2年で提供プロダクトが4つに、誰に何を提案すべきか迷う
お客様の自走化を進めている背景もあり、オンボーディング時点でのお客様との関係構築度合いにばらつきがある
お客様のサクセスと、検討意欲を醸成していくバランスが難しい
いろいろなお客様がいるため、お客様によって検討スピードや優先度が異なる。「今困っていること」に加えて、「今検討しないと将来お客様が困ること」もご認識いただき、検討優先度を正しく判断いただくのが難しい
コミュニケーション接点が成熟させられていない。たとえば、「今お電話する」という接点だけだと、法制度対応の追加情報や、同業他社の事例紹介など、必要な情報を提供しきるのが難しい。継続的に情報提供を行い、自社に役立つものをキャッチいただきたい
情報提供活動のなかには、「導入済サービス・業務のサポート」がどうしても必要になる。社内のISメンバーに手伝っていただくなどのリソースアロケーションも一筋縄ではいかない
目標の引力にも立ち向かわねばならない
どうしても日々の目標が検討案件の創出数になり、事業目線の目標に引っ張られてしまいがち
結局はお客様のサクセスがあって結果としての事業成長につながると思っているので、都度ベンダー目線の提案になっていないか、対価<提供価値に立ち返る必要あり
まとめると、以下の問いの答えを探し続けている状況といえます。
・多様なお客様の状況、待ってくれない法制度などの市場変化があるなかで
・複数のソリューションを抱えながら
・どのお客様に、どのタイミングでどのような背景を問いかければ、「それは今検討しないと私たちも困るね」と腹落ちしていただけるか?
・それは、どのようなコミュニケーション接点の形をしているのが最善か?
今後どうしていくのか?
そのため、現在、は様々な施策可能性があるなかで、今価値を届けるべきお客様を特定し、最善のコミュニケーションを取り、たくさんのトライを経て優先度をつけて戦略をつくっていく、まさに仕込みのタイミングといえます。
前Qまではオンボーディングフェーズのお客様への提案活動をメインとしていましたが、今Qからはリニューアルのタイミング等でアダプションフェーズのお客様とコミュニケーションをとったり、カスタマーマーケ/セールスチームと連携し、各種接点でコミュニケーションを増やす検証を始めました。
ご契約時のオンボーディングのタイミングでの情報提供
ご契約更新時のサポートmtgでの情報提供
お客様のフェーズにあわせたサポート架電
様々な切り口のお役立ちウェビナー
お客様のセグメンテーションごとのサポート架電
まだドンピシャでお客様に役立つ切り口が特定できていないので、むずい…歯がゆい…という気持ちではありますが、
今Qは「どのタイミング・セグメントのお客様が、どんな手段で何についてコミュニケーションが取られると好ましいか?」のデータを貯め、次のQで注力する組み合わせを発見していく予定です。
また、同時にsales、オンボーディング段階でわかったお客様情報を適切に引き継ぐ仕組みや、チームを超えた提案ノウハウの共有、お客様の検討状況の管理など、最終的なお客様のサクセスに向けてチームを超えて解決すべきイシューも山積みであることがわかってきました。
今後はお客様への直接の働き方だけではなく、社内でチームを超えて課題に向き合い、長期的・持続可能な価値デリバリーの仕組みも構築したいと考えています。
結局、お客様との対話で生まれる発見が大事
ここまで書いた通り、LayerXは「実際にN1のお客様と向き合ってみること」を大事にしており、事業の突破口もお客様との会話のなかで見つかることが多いなあと感じています。
最近も、チーム問わず「お客様との会話で、どんな観点で会話すると価値を想像いただきやすかったか」が毎日リアルタイムでシェアされています。

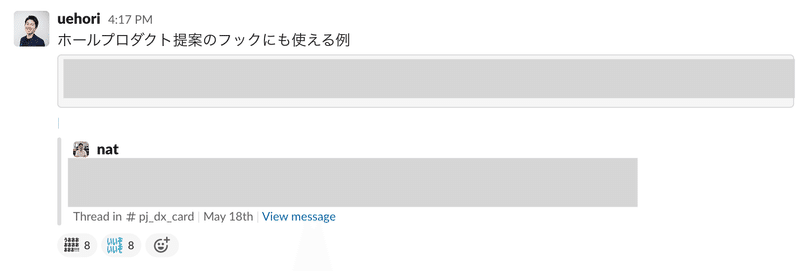
実際やってみる中でもTier分けやthe modelの仕組みを意識はしていますが、最終的な価値のデリバリーとは、現場でお客様とコミュニケーションしながら、その時一番価値を実感いただける切り口を磨いていく営みだと感じているので、
今後も、いきなりスマートなやり方を見つけるのではなく、地道にお客様と向き合って反応を見ながら、今のお客様にフィットする提案パターンを見定めていきたいと思います。
まとめ
改めてお伝えしたいことは、「バクラクがお客様をバクラクにできる余地は、まだまだめちゃくちゃある、のに全くやりきれていない、やりようは無限にあるけど人が足りない!!!」です。
わたしは1年半ほどLayerXにいますが、「すべての経済活動をデジタル化する。」というミッションは、お客様が業務をデジタル化・不要な業務をなくしたサクセスの先に実現があると確信しています。
日々、お客様のバクラクになったお声を聞く度に、「ちょっとは日本のDXに貢献できているかなあ」とも思うのですが、バックオフィスの業務・ペインはなかなか幅広く、まだまだ「全体を通してバクラクにできている!」とは言えません。
以下のキーワードでピンと来る方、一緒に「すべての経済活動をデジタル化」していきませんか?
お客様に届けたい価値が山程ある
正解がわかってないカオスな環境が好き
現場でお客様に向き合って検証するのが楽しい
少しでもワクワクしていただいた方はぜひカジュアルにお話しましょう!!!
