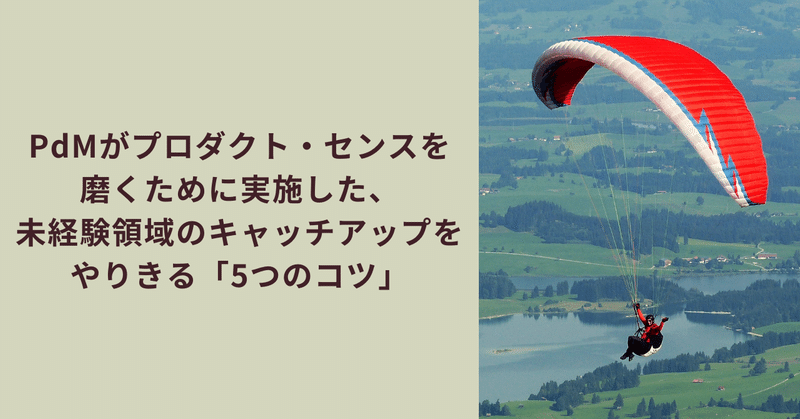
PdMがプロダクト・センスを磨くために実施した、未経験領域のキャッチアップをやりきる「5つのコツ」
こんにちは、LayerXのmichiru_daです。
私は元々コンパウンドスタートアップでカスタマーサクセスを担当していましたが、2023年4月からはバクラクのID管理・認証基盤のプロダクトマネージャー(PdM)をしています。
PdMが未知の領域に向き合う機会は数多くありますが、カスタマーサクセス出身である私は、とてつもなく既知と未知のギャップがある状態からキャリアをスタートし、徐々に専門的な知識を身につけていきました。
今振り返ると、ここでいう「専門的な知識」とは、@bunbuno0 さんが以前まとめられていた、プロダクト・センスに近しいものだなと感じます。
“"正解に限りなく近いものへ辿り着くための手段のストック"がプロダクトセンスという言葉になるような感じがしました。
また、"自分では取り扱えない問題に対して、誰に助けを求めれば良いのか分かる"ということも含めて、自身の経験から理解できるということもセンスの一つです。
これらをまとめて「プロダクトセンスとは何か?」に対する答えとしては、様々な経験や学習を通して得られた情報によって、直感レベルで製品のニーズを理解できる力 と言えそうです。”
解像度が低いドメインで、かつ認証やセキュリティの領域に取り組んだことはとても苦労も多かったのですが、
本記事では、PdMが全く知らない領域のプロダクト・センスを身につける一歩目としてやってよかった「リサーチ」 と、その5つのコツについて書こうと思います。
【告知】認証基盤のプロダクトマネジメント、ここが大変&ここがオモロい編は、来月2023/11/29にpmconfでお話できればと思います!
守りの投資、後回しになっているなあ…対応の優先度難しいなあ…と思われている方、ぜひ遊びにきてください〜!💓
カスタマーサクセスから認証基盤のPdMへ
PdM異動直後の私は
・ビジネスサイドでしかシステム開発に関わったことがない
・情報系の資格も持ってない
・機能はわかるけど裏側の知識は何もない。いくつか単語は聞いたことあるかも?
のような状態です。
事業はそんな自分を待ってくれるわけもなく、直近半年で向き合ったイシューは以下のようなものでした。
・内部統制の支援とは
・不正アクセス防止
・脆弱性対応
・SaaSのセキュリティ統制のあるべき姿
・SLA
・監査ログ
・バクラクのユーザー概念って、誰のもの?
etc…
プロダクト・センスを磨く一歩目としてのリサーチ
正直最初は「分野も技術もナニモワカラナイ・・・わたしがやれるんかいな・・・えぇ・・・」という気持ちでいっぱいでしたが、
認証、監査、あるべきユーザー基盤など、最初は理解できなかったトピックについても、①事前のリサーチ ②リサーチに基づく仮説立て ③有識者やユーザーへのインタビュー の繰り返しによって、一定再現性がある形で問題解決が出来るようになってきました。
特に、セキュリティや認証まわりについては社内にも知見が少ないこともあり、仮説検証前の①の事前リサーチについては、BigTechから日系SaaS企業まで幅広く、そもそものドメイン知識から深掘り、あるべき状態はなにか?から解明するようにしています。
結果、アウトプットを見た先輩PdMから「そもそも勉強になった」「解像度高いな」「これ、どうやったの?」と度々言われるようになりました。
仮説思考やユーザーインタビューについては既にたくさん知見が転がっているので、
ここからは、本当に何も知らない状態から知識不足を克服し、効果的な情報収集方法を通じて意思決定の確度を高めるためのリサーチtipsを共有します。
この記事を読んだ皆さんが、情報収集のプロになり、
・「よく知らない」が怖くなくなる
・ユーザーと話す時に、仮説を持って質問しやすくなる
・知見が社内でも共有されて、周りの解像度も上がりやすくなる
未来があることを願っています。
補足:リサーチが指すもの
参考までに、本記事でのリサーチの成果物・ゴールとしては以下を想定しています。
N1インタビュー前の準備としてのリサーチ: ユーザーインタビューを行う前に、仮説を立てるため・ユーザーとの信頼関係を築くための事前インプットとして行うもの
構造化されたレポート : 一定のトピックについて、初心者でも構造的に理解できる状態になったもの
リサーチの流れ
早速、実際行っている情報収集の流れを見ていきます。
1.準備
情報収集の前に、メモツールと付箋を用意しましょう。
2.論点リストの作成
実際に調査を始めるまえに、知りたいことや観点を付箋に書き出しておきます。 これにより、情報収集がより重要な項目に焦点を当てられ、時間を溶かす可能性を減らせます。
あくまでゴール意識を持つためのステップなので、この段階で、すべてを網羅的に書き出す必要はありませんし、構造化に時間を使う必要もありません。
また、「単に知りたいこと」ではなく、「何がわかると次のステップに進めるか?」という問いに答えるように書くと、重要な観点に絞ってリサーチを行うことができます。

今はChatGPTがシュッと考えてくれるので、とてもいい時代ですね。

3.スモールステップでの調査
2の観点で洗い出したキーワードで検索し、最初は初心者向けの記事を読むことからはじめましょう。
概要が掴めたら、徐々に詳細な文献の調査へと段階的に進めていきます。
たとえば、監査をリサーチした際には以下の順番で読み進めていきました。
・各種会計ベンダーが出している記事
・メディアや税理士事務所の記事
・経産省のドキュメント
・システム監査の本
4. メモ化と質問の追記
読みながら、大事そうな情報をメモしていきます。
構造化や体系化は意識せずに、気になったところをすべてメモします。
この段階では、重複や前後と論理関係がないことは特に気にしません。
綺麗にまとめる必要はないですが、見出しだけ適当につけたり、一言まとめ+引用コピペのかたちで記載しておくと後で見返しやすくなります。
また、メモするなかで、「◯◯と〇〇の違いは?」「さっきはこう書いてあったはずなのに、なぜこうなってる?」などの新しい質問や疑問が浮かんだ場合、質問があるとわかるようにメモしておきます。

5.完了基準の見直しと追加の調査
質問含めて1回書き出しが完了したら、2に戻り、一度完了基準を見直します。
リサーチが一周すると、追加の観点や、実はさほど重要ではなかったポイントの感覚が掴みやすくなるので、やはり重要だったもの・追加で調べるものに更新します。
そのうえで質問や新しい完了基準のまわりを更に深掘りしていきます。
6.情報の整理と要約
5のポイントを調べ終わったらざざっと書き出したメモを眺めます。
全体としてなんとなく納得感があれば、「初学者の自分が読んで嬉しい部分」だけを改めてまとめ直し、リサーチは完了です。
社内共有するとしたら、5まのでプロセスは省略し、6の重要な部分だけでokです。

5つのコツ
プロダクト・センスを磨くためにリサーチをやりきるという観点で、大事な5つのコツを改めてまとめます。
1. 「鳥の目」と「虫の目」を行き来する
調べる作業に入る前に、何が分かればゴールであるかを常に意識しましょう。
これは、闇雲に時間を浪費しないようにするための重要なステップです。
また、実際に手を動かして情報収集してみてから、再度ゴール設計を見直します。「解像度をあげる」と「ゴールを見直す」を行き来することで、一番はやく情報整理を行うことができます。
2.複数の情報源を活用する
締切までの時間やテーマによりますが、専門性が高いテーマの場合は複数の情報源を組み合わせる(ウェブ記事、経産省のドキュメント、書籍)と、より解像度・信頼性が高まります。
その際、いきなり難しい記事や本に手を出さないようにしましょう。私もweb→本でインプットすることが多いです。webのほうがやさしくキュレーションされていたり、短い記事の場合が多いので、挫折せずに調査を続けられます。
また、本を読む場合は時間がかかるので、気になったところに付箋をつけながらとりあえず素早く1周読んで、2周目で付箋のところだけ再読し、そこで初めて「理解」に努め、大事なところはメモに残すようにしています。

3.「わからない感覚」に敏感であろう
わからない部分を深追いしすぎないのは大事なのですが、「ここはヨクワカラナイ」という感覚そのものは大切にしましょう。
自分がわかっていないことは他の人もわかっていないことが多く、「解像度に差がつく」ポイントになりえるからです。
素朴な疑問は書き残しておき、実際にユーザーに質問する機会で実態を聞いてみましょう。
4.リサーチだけですべて正しい体系化をしようとしない
わからない部分があったときには、調べて解答が出てきたらラッキーくらいの気持ちで臨みましょう。
その時分からなくても、後々ユーザーや専門家へのインタビューでの検証すれば問題ありません。
あくまでリサーチは、その後の一次情報に触れるための準備です。リサーチだけで完璧を目指さず、あくまで仮説のたたき台をつくることに努めましょう。
5.調べる工程とキュレーションする工程はわける
最後に、リサーチとキュレーションのプロセスを分けましょう。
私を始めとして凡人が未知に触れるときは全体感を掴めてはじめて情報を構造化、体系化することができます。
最初から構造化しながら進めようとすると時間がかかるし手戻りも発生します。
最終的に早く成果を出すことが大事なので、集中して調べる時間と整理する時間を取る方が、結果としてはやくアウトプットを出すことができます。

わかったけど、認証基盤のPdMとしてのアウトカムは?
本文中でも記載しましたが、リサーチそのものは何も価値を生みません。
あくまで向き合っているイシューの仮説構築をしやすくする、ユーザーインタビューを行いやすくするための準備にすぎません。
リサーチのあとのユーザーインタビュー・仮説検証を経て、実際にID管理・認証基盤のPdMとして半年トライしたアウトカムや失敗経験については、改めてpmconfで詳しくお話できればと思います。
また半年挑戦してみて、認証基盤のプロダクトマネジメントは、リサーチで得られるような「あるべき・安全な状態」を作ることと、実際ユーザーの解像度をあげ使いやすさにこだわることを両立させる、超絶総合格闘技だなと感じています。
今後もカオスなコンパウンドスタートアップのLayerX バクラクの入り口を支える黒子として、取り組みたいイシューが山ほどありますので、
本記事を読んでいただき、バクラクやID・認証基盤に興味を持っていただいた方はぜひお話しましょう〜!
