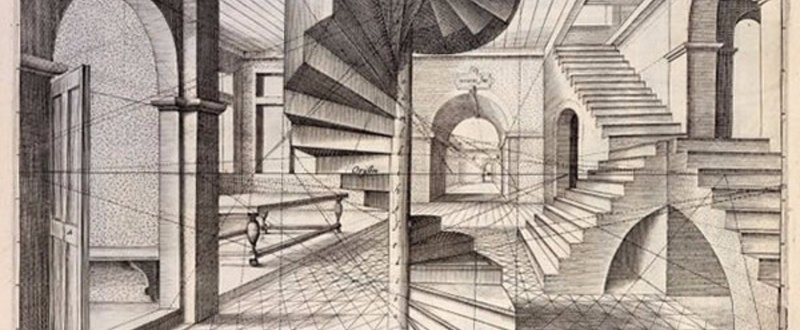
自分なくしの文法、あるいは戦争を防止する文法 --國分功一郎「中動態の世界」-感想文
自分の周りで今ちょっとした話題になっていて、なぜか医学書院 シリーズ「ケアをひらく」から出ている、國分功一郎氏が著した「中動態の世界」を読みました。この、「中動態」という言葉と、医学書院から出版されているという2点において、おそらくこの本はナラティヴについての本なのだろうという推測をしていたのですが、やはりそうでした。そして、自分の中では、今ヘルスケアの中で注目されているナラティヴ・メディシンとか、オープン・ダイアローグとか、信念対立解明とかのアプローチの妥当性をびしっと後押しする「文法」を教えてもらった気がして、とてもすっきりしたのです。本の内容は結構ゴリゴリの哲学、というか言語考古学で、ヘルスケアのアナロジーはほとんど出現しないのですが、ナラティヴ・メディシンとかオープン・ダイアローグとかに魅入られたヘルスケア・プロフェッショナルにとっては、その方法論的な基盤をがしっと支えてくれるという意味においてまさにジャストな内容であるといえます。「ケアをひらく」編集のSさん、さすがの目の付け所です。
私は人に「ナラティヴ志向とは、要するにどういうことなのですか?」と問われたとき決まってこたえる言葉は、「ナラティヴ志向とは、要するに、注意を人に向けずに出来事に向けていくことです」と答えます。この言葉を聞いて「そういうことか!」といってくれる人は10人中1人くらいで、9人は「???、それ、逆じゃないの?」というさらなる混乱を招いたりします。「ナラティヴ志向」というと、目の前の人のライフヒストリーをしっかり傾聴して、その人自身をしっかり理解すること、というようなイメージがあるので、だとしたらそれは「人に向かうこと」に他ならないだろう、という反論が生まれるというわけです。確かに、その理解は部分的に正しいのだと思うのですが、私が「ナラティヴ・アプローチ」から学んで「これだ!」と感じたことは、「支援者としての私と患者としてのあなた」にコミットし過ぎてしまうために、「あなた」を「私」が支配してしまうような構造から解放されるような感覚だったのです。そして、何がその構造を解き放ったのかといえば、臨床場面を「私とあなた」ではなく、「私の物語とあなたの物語が邂逅している場」ととらえるという視点でした。そして、そこで行われることは「出来事」であり、「私があなたに何をしてあげられるか?」というエゴの葛藤ではない、というようなある意味ドライ(私はあえて「ドライ」という言葉を使用せず、「湿度低め」と言っています)な感覚でした。その感覚が腑に落ちてから、少なくとも自分の臨床が楽になりましたし、患者さんや他職種プロフェッショナルとの対立を心地よいものとして感じることができるようになったのです。
オープン・ダイアローグについても私は似たような心地よさを感じていました。オープン・ダイアローグのコンセプトは「ジャム・セッション」であると私はとらえています。ジャム・セッションにおいては、ギターはあらかじめギターであって「ギターである自分」についてセッション中に考えることはありません。そして、中心もない。ここには「私にとってのあなた」とか、「私があなたに伝えたいこと」という意図が希薄(全くないわけではないです)であり、あくまでも中心は「奏でられた音楽」なのです。これは、人を軽くしていきます。そして、人が人に縛られるような強い不自由を解き放っていきます。このようなセッションを「言葉」を用いて行うのがオープン・ダイアログの手法なのだと思っています。
この二つのコミュニケーションに関するコンセプト、あるいは手法に共通するのは、「自分を主体から解放する」ということだと私は解釈しています。あるいは、「本当の自分を探さない」ということでもあります。自分が主体からがんじがらめにとどまっている状態では、自分が変容することに対する恐れがおのずと湧き上がってきます。その恐れから生まれるのが「定義にこだわること」だったり、「白黒はっきりさせること」だったり、「立場を明確にすること」だったり、「味方と敵に分けること」だったり、「認識や意見の相違を『誤解』ととらえること」だったり、「自分と異なる意見を持つ者をせん滅しようとすること」だったりするののではないか、ということです。
さらに言うならば、自分が主体の中に閉じた状態においては、自分の意識を絶対的なものとしてとらえがちです。例えば、一般的な急性上気道炎と思しき症状で来院された患者さんに対しての医師としての自分は、「常に同一なものでなければならない」といいきかせながら考え、行動するのだと思います。しかし、まったく同じ病歴で、全く同じ身体所見であったとしても、そこで医師が考えることはほかのさまざまなものに影響されています。例えば患者さんの人相だったり、声のトーンだったりです。あと、自分自身の体調だったり、前日に見た夢だったりにも影響されるでしょう。さらに言うなら、診療の場が病院か診療所か、午前か午後か、患者さんと自分との距離、このような様々なものによって自分の考えは影響を受けながら成り立っているはずなのです。自分を主体から解放することで、「ねばならない」というとらわれから自由になることができます。そして、相手にも寛容になることができます。そのようなことを私はナラティヴ志向から学びました。
しかし、なんとなくまだ腑に落ちない部分が残っていたのです。これは「視点」の話なのかもしれないけれど、どうやらそれだけの話でもない、とぐるぐるしていました。ナラティヴ志向は、単なるメタ認知とは大きく異なっているものだというのはなんとなく理解はしているのですが、どう違っているのかについてうまく言語化できませんでした。
そこで出てきたのが「中動態」という、かつては使用されていて今では使用されなくなった文法です。中動態の詳細については是非「中動態の世界」を読んでいただきたいのです。本書に書かれていることは、「かつて、能動態とも受動態とも異なる態があった。それが中動態である。そしてそれはいったんほろんだ。しかし、最近少し復権しつつある」ということです。なので、本当にガチの言葉の考古学が本書の内容です。中動態は能動態と受動態の間にあるものではなく、全く別のアプローチを持った態であり、能動態と受動態が「主体→対象」の明確な構造を持っている態である一方で、中動態は「出来事を記述するための態」である、というのが國分氏が本書の中で述べていることです。これは、私がはじめにナラティヴ志向について書いた「注意を人に向けずに出来事に向けていくこと」を、まさに文法として表現しているわけです。これはすごい!と思いました。ナラティヴ志向を支えていたものは、どうやら「視点」というよりは「文法」により近いものだったのかもしれません。
個人的な白眉が2つ。一つは能動態/受動態の差は、行為の方向性の差ではなく、行為が生み出すものが自由なものか、強制なものかの差なのだという理解。これは最近私が考えている「させていただく症候群」とも関係深く実に腑に落ちる視点でした。もう一つが、「意志を持つということは、考えないようにすることである」という言説。まさにそうだよねー!と。クリニカルパスなどに私は何かしらの強い「意志」を常々感じていたのですが、そうか、「考えるな!」と言われていたのかとすっきりしました。
なぜ中動態がほろんだのか、そして、受動態にとってかわられるようになったのか、ということに関して國分氏は本書の中であまり強くは言及していませんが、私はなんとなくその理由が理解できます。おそらく当時とても頭のいい人、あるいは特権的集団がいて、「戦争は儲かる」ことに気が付いたのだと思います。そして、同時に「戦争を起こすためには人間に陰性感情を惹起するような仕組みを作らないといけない。それはきっと文法だ」と気が付いたのではないでしょうか?その文法として「受動態」が発明され、同時に、どうやら人の陰性感情の惹起を防止していることに一役買っている中動態の文法を滅ぼそうと考えたのだと思います。
戦争が大好きだった当時の頭のいい人たちは、言語を争いが生まれる文法に変えることに成功しました。しかし、コミュニケーションのほぼすべてが言語のやり取りであると思っていたのかもしれません。まずは音楽の持つコミュニケーション力を見落としていました。オープン・ダイアログの最も重要なコンセプトの一つである「ポリフォニー」は、音楽用語です。音楽によるコミュニケーションは、基本中動態の文法で成立しているのです。同様にダンスも中動態の文法です。クラシック音楽は、一時期中動態文法を押し込めるのに成功していたのかもしれません。しかし、ジャズが生まれ、ロックが生まれ、そして最もプリミティヴな音楽であったダンスミュージックが最も新しいモードとして若いホモサピエンスたちの主要なコミュニケーションツールとなっています。私には、現代の社会は、アートが持っていた文法が今何千年の時を超えて言葉の文法に挑んでいるような状況にあるように見えます。そう考えると、やはり大きな価値の転覆がそう遠くない未来にやってくる気がし始めました。
ところで、みうらじゅんが、映画を見続けることを「自分なくしの道場」と呼んでいて、それを知ったとき私は「あああ、やっぱこの人天才だなあ」と思ったことを思い出したのですが、中動態はまさに「自分なくしの文法」と呼んでもよいかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
