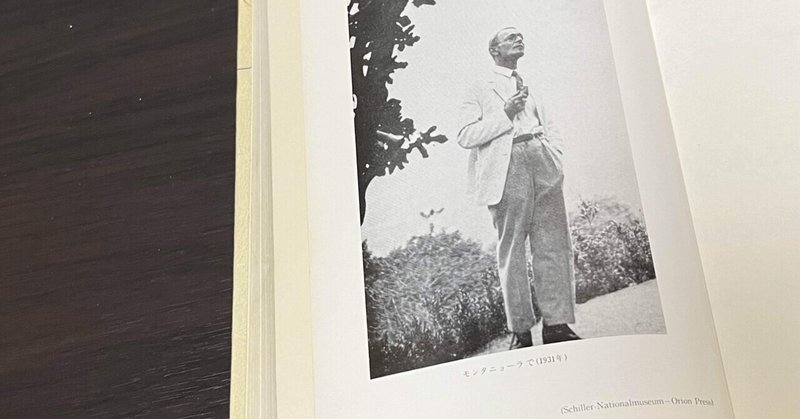
「荒野のおおかみ」を読んで
ヘルマン・ヘッセ
「荒野のおおかみ」
(Der Steppenwolf) 1927
狼好きなので、タイトルに惹かれて読んでみた。
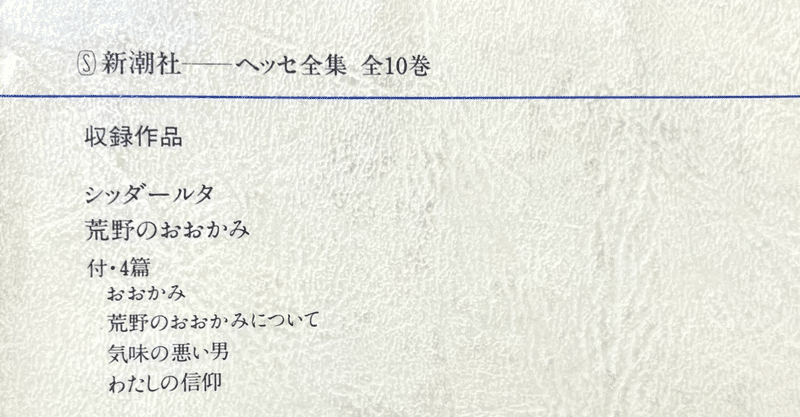
動物の狼ではなく、「荒野のおおかみ」を自称するヘッセ自身を投影した五十歳男性の物語だった。
巻末訳者(高橋健二)解説によれば《小説としての構想もととのっていない》《当初は読者を失望させ、嘆かせた》《いろいろな点で波乱を巻き起こした問題の多い作品》ということで、かなりクセ強作品のようである。
私はヘッセというと「車輪の下」しか読んでおらず、その内容も忘れている。
詩集を読んだかも知れないがそれも忘れている。
というわけでとくに先入観なく読んでみる。
構成は、4つのパートに分かれている。
<荒野のおおかみ・目次>
編集者の序文
ハリー・ハラーの手記
荒野のおおかみについての論文
ハリー・ハラーの手記、続き
「荒野のおおかみ」あとがき(1942年のスイス版)
《編集者の序文》は荒野のおおかみを自称する男ハリー・ハラー(ヘルマン・ヘッセとおなじH•H•)が引越して来た部屋の隣人が、この男に興味津々で観察しながら、魅力を感じるようになる視点で語られる。
終盤に、中世の残虐行為についてハリーが語る印象的なシーンがある。
ある一つの閉じた地域、一つの閉じた時代の中にあっては、人間はどんな残虐行為も受け入れてしまう。そこに別の価値観が流入し、出会い、混ざり合ったとき、そこに耐え難い軋轢が生じる、と。
語り手は、ハリーが抱える人間とおおかみという二面性と、この苦悩を重ね合わせる。多面性ということは、この作品の主要なテーマになっている。
次章《ハリー・ハラーの手記》は荒野のおおかみこと主人公ハリー・ハラーの一人称語りである。
この男は小市民的生活に馴染めず、憎悪し、孤独と絶望に苛まれている。
とはいえ、彼は利息で暮らしていけるブルジョワであり、きちんとした小市民生活圏から外れることなく暮らしている。
世間の俗なものに対する嫌悪、身の置き処のなさ、誰もが思春期に味わいそうな悩みなのだが、彼は五十になってもずっと自身の中に棲む「荒野のおおかみ」を持て余している。
そしてついには魔術的世界に踏み込んでいってしまい、幻想と現実が混濁してくる。
《荒野のおおかみについての論文》
前章の最後に入手した謎の小冊子に書かれていた論文である。
荒野のおおかみが何故か論文になって、概ね批判的に解析されている。
荒野のおおかみが、自身の内なる人間的なものとおおかみ的なものの共存に苦しんでいるというが、人というのはそもそも二つどころか無数の魂でできているものであると。
物語や演劇において描き分けられる様々な人格の登場人物とは、すなわち本来すべて一人の人間が持つ本質であるということだ。
インドの叙事詩の主人公は個人ではなく、個人の集まり、化身のつながりである。われわれの近代世界の中にも、個人劇や性格劇の背後で、著者はたぶんまったく意識していないだろうが、魂の多様さを表現しようと試みているような文学がある。このことを認識しようとするものは、そういう文学の人物を個人と見ないで、より高い統一体の(あるいは詩人の魂の)部分、側面、種々の様相と見る心がまえにならなければならない。たとえば「ファウスト」をこのように観察するものにとっては、ファウストやメフィストやワグナーやその他すべての人物から一つの統一体、超個人ができあがる。個々の人物ではなく、このより高い統一体の中に、はじめて魂の真の本質の何かが暗示されている。
《ハリー・ハラーの手記、続き》
ここから、厨二病拗らせ五十男の自己弁護を延々と聞かされることになり残りページ数を何度も見てウンザリするのだが、最初に登場した隣人のようにうっかり好感を持ちかけた時、古典的なありがちパターンが展開する。
酒場で天使のような若い娼婦に会うのである。
傷ついた男は母親代わりの若い女の子に自分をなんとかして欲しいと思っている。話を聞いてくれて理解してくれて叱ってくれて励ましてくれて命令して救ってくれてついでに愛撫もしてくれる天使のような存在である。
ただし、彼女は天使か堕天使か悪魔かただの人間か……
ハリーはやがて狂気の淵に堕ちて行き、《地獄めぐり(解説より)》を味わうことになる。
狂気の探究の果てに、
救いはあるかないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
