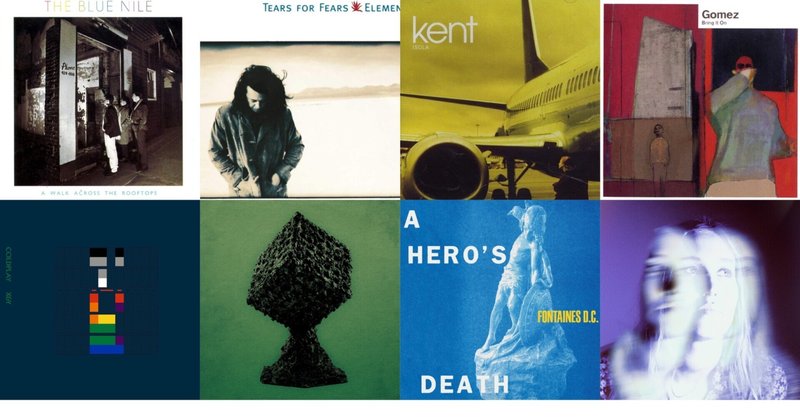
最近聴いているアルバム2022.01
去年の1月からこのシリーズを書いている。シーンの影で埋もれた名作であったり、全然評価されていないが実は優れていると感じる作品であったり、今の音楽シーンに通じる魅力を持つと感じる作品であったり、そういう作品を再探訪していきたい。
The Blue Nile 『A Walk Across The Rooftops』(1984)
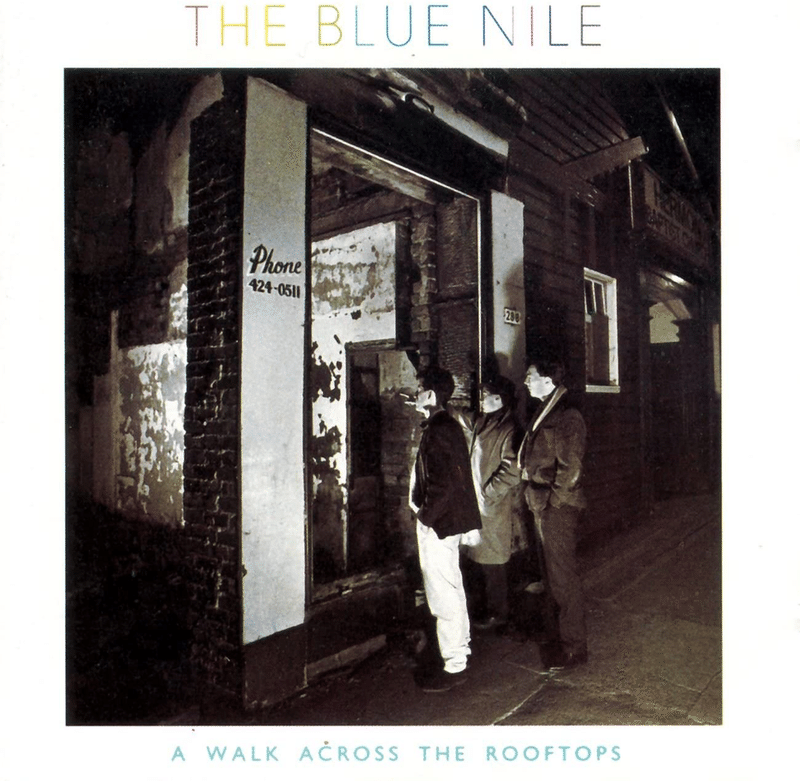
——ひとつの恋が終わりを迎えようとしている。お互い終焉に気付きながら道を模索するが、結局は破局を迎えるだろう、この雨に濡れるハリウッドで...葉巻をくわえ街角に佇む男が静かに、情熱的に歌う。街の喧騒の離れたところから眺める観察者としてのクールな目線。午前6時、朝靄の中再び動き出した街を見届けたところでアルバムは幕を下ろす。"Automobile Noise"
Tears For Fears 『Elemental』(1993)
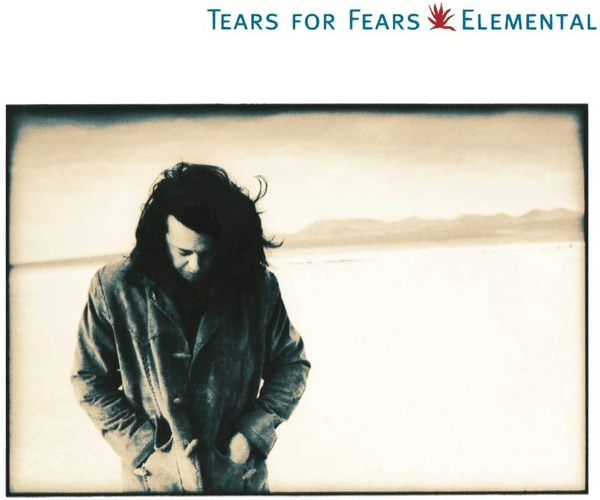
このバンドは「シンセポップ!」として捉え易い1stや2ndの曲はよく(安易に)引用されるし紹介もされる。しかし理想の音楽像を掴み取った3rdや本4thについては引用もリバイバルも起こっていないし、今後も起こらないだろう。理由は簡単で、ロックの全てを網羅したこの全能感は再現不可能だし、ヒップじゃないし、取っ付きづらいからだ。
TFF以降にそれをやろうとしたのは、私の知る限りPaul DraperとSteven Wilsonだけだ。迷いなく天才と言えるその2人ですら、TFFが手にしたスケールには及んでいない。「一周まわって再評価」なんてことがありえない、永遠に隠れた初版であり続ける作品と言えるだろう。"Elemental"
Kent 『Isola』(1997)
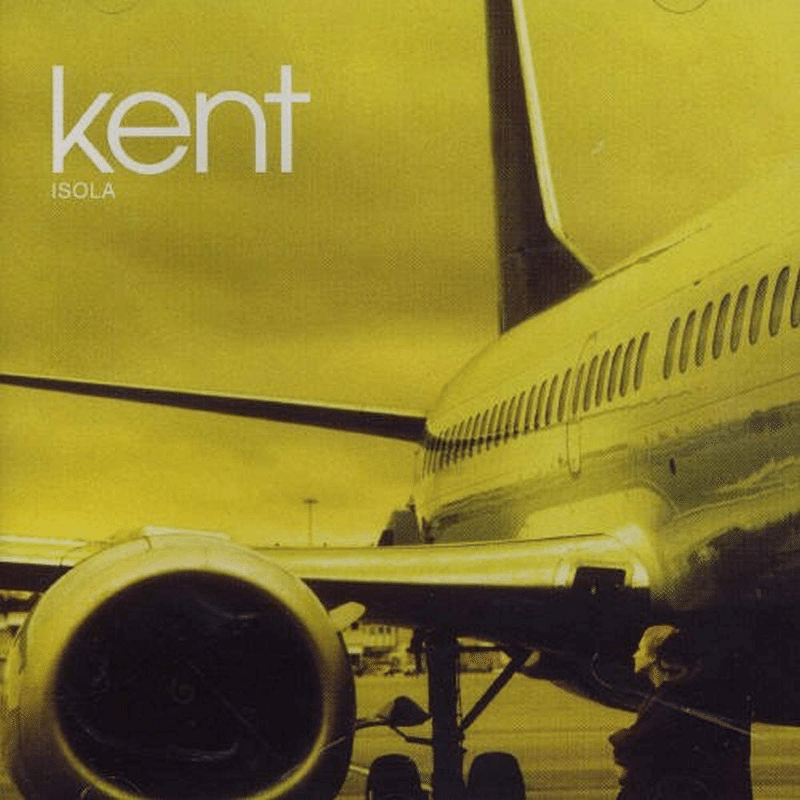
サイケデリックなギターサウンドと澄んだ空気、そして2022年にはあり得ないこのスケールの大きさ。終末を迎えた世界で鳴る凛としたアルペジオ。この張り詰めた空気を聴きたいがためにロックというジャンルを私は聴く。それ以外は暇つぶしだ。Om Du Var Har
Gomez 『Bring It On』(1998)
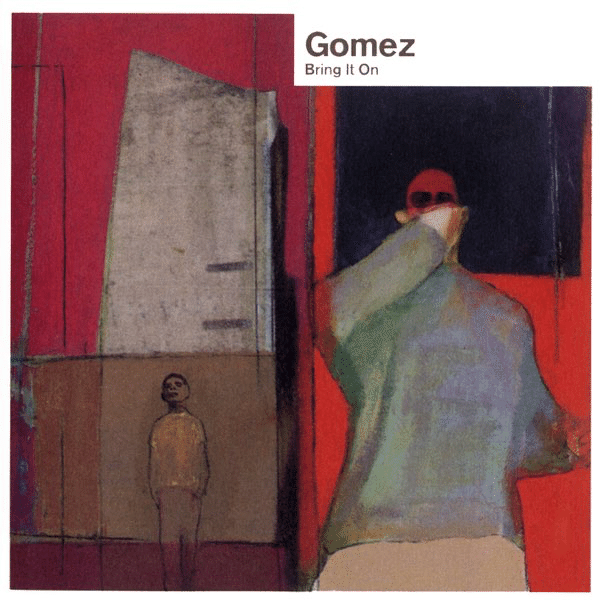
ロックのムーブメントというものが嫌いだ。二匹目のドジョウを狙ったバンドが溢れ出し、代わりに本当に優れたバンドが陽の目を浴びなくなってしまうからだ。ブリットポップなんてまさにその退屈な典型であったが、1997年頃に優れたバンドの出番がやっとやってきた。その中でも特に好きなのがGomez。技巧的なプレイ/編集と、それを感じさせない風通しの良いストレートな曲調。爽快感に溢れた渋ブルースの魅力に気づいてしまえば、もう抗えない。めっちゃオシャレだし、めっちゃエモい。最高。"Make No Sound"
Coldplay 『X&Y』(2005)
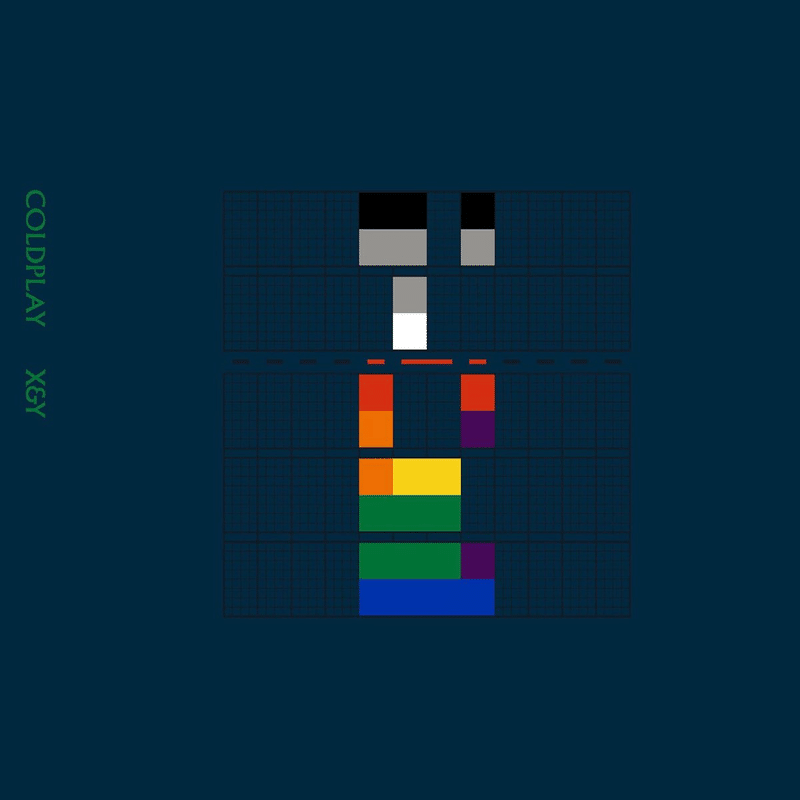
Pink Floyd, U2, Simple Minds, Tears For Fears, Echo & The Bunnymen, The VerveといったUKロック王道の正統後継者としての傑作。今聴いてもこの完成度は本当に異常だし、本作以降この路線で本作に並ぶのはMystery Jetsの『Curve Of The Earth』くらいだと思う。個人的に退屈極まりなかった00年代ロックにおいて唯一の本格派だと思っていた。
特に何も新しいことをやっていないし構成要素も基礎の基礎だけで出来ているが、個々のプレイのセンスとそれを組み合わせる完成度が異常に高い。革命的なアイデアやテクニックやアティチュードやプロパガンダなんて全くもって不要。ここでのChris Martinは、実に曖昧で抽象的で観念的でナンセンスなことしか歌っていない。超音楽第一主義。"A Message", "The Hardest Part"といった軽やかな曲にすら強烈な風格が宿っているのには、何度聴いても溜息が出る。
Merchandise 『After The End』(2014)
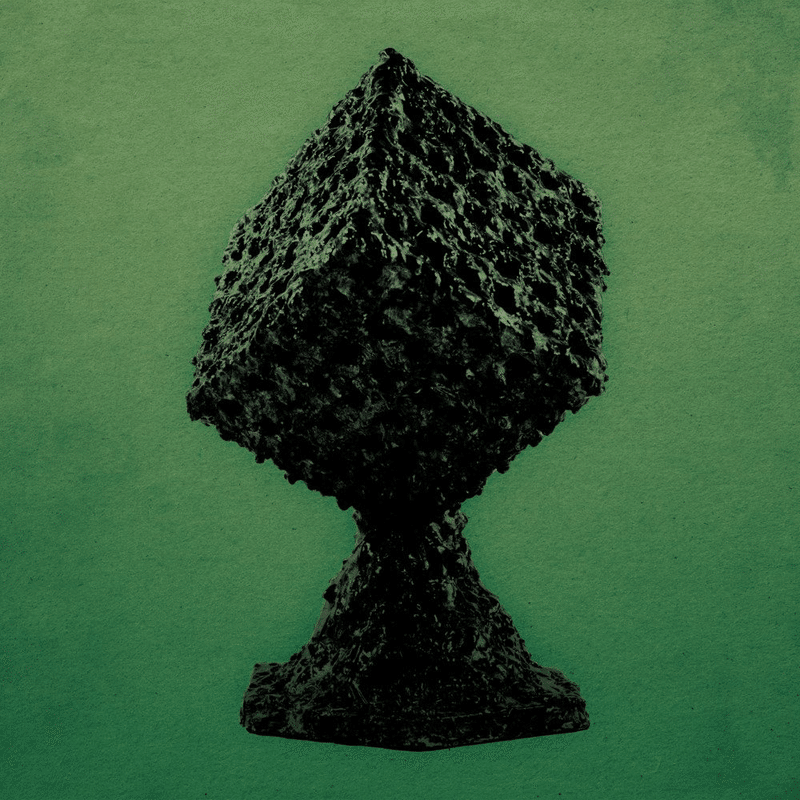
アコースティックギターを軸に据えた爽やかで軽快なニューウェーブポップ。木漏れ日のように広がるサイケデリアとシュールな非現実性、白昼夢のような雰囲気が心地良い。こういうバンドはたくさんいるけど、明らかにこのバンドは"何か"違うと思わせるものを持っている。最近初めて聴いたけど、一聴してそう感じた。昨今のポストパンク勢にもこういう柔らかいバンドがいればな、と思っている。"True Monument"
Fontaines D.C. 『A Hero's Death』(2019)
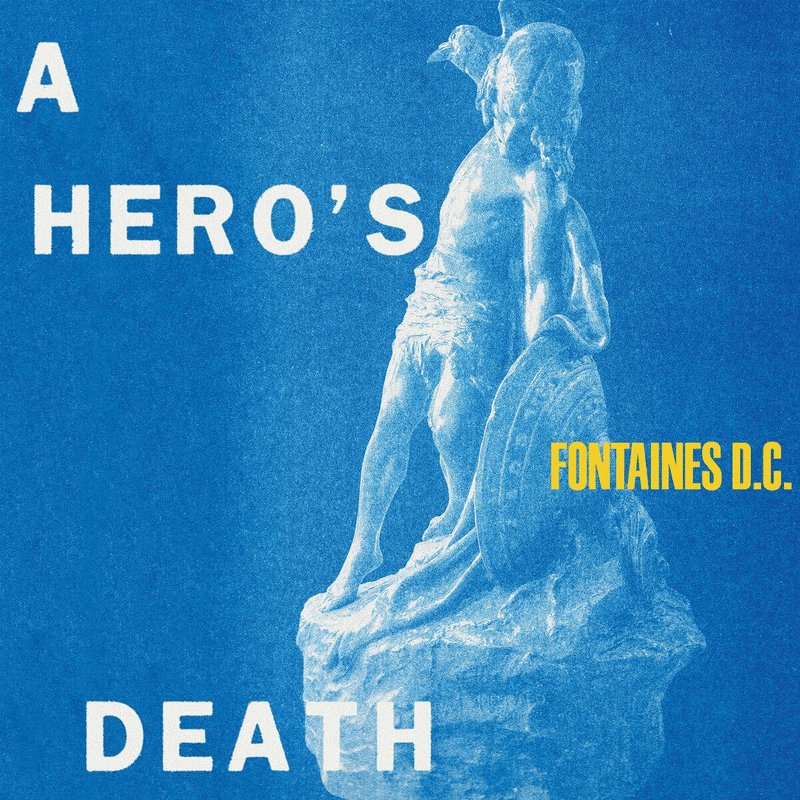
その新世代ポストパンクの中ではダントツ、というか唯一好きなのがこのバンドで、本作は80年代オリジナルのドス黒い輝きと新世代の青い炎を同時に感じさせる。同世代のポストパンクバンドは技巧系(理系)と直情系(体育会系)に愚別することができると思うが、このバンドはどちら側のバンドも持っていない薄暗い美学を強く放出している。単調なのに聴き飽きさせない独特のフックのセンスを持っているのも良い。リード曲が死ぬほどカッコいい新作が楽しみでならない。このバンドこそが20年代のトップランナーだと思い込んでいる。"Oh Such A Spring"
Hatchie 『Keepsake』(2019)

この人はめちゃくちゃ曲が書ける。昨今のソロシンガーにありがちな、「可もなく不可もなく・適度にキャッチーで特に文句もないメロディ」ではなく、確実に聴き手の心にグッと熱いものを残す力強く切ないメロディが書ける。それだけでいかに大きなアドバンテージだろうか。名曲の余韻と風格に包まれる"Stay With Me"は2019年ベストソング。
Muse - Won't Stand Down (2022)
Museの新曲。Mattew Bellamy節のマイナーメロディとEDM的シンセ、そして過去最もヘヴィメタルなギターが融合した傑作。今のロックに求められるのは包括性・破壊力・客観性と前に何かのレビューで書いたが、この曲はまさにそのトライアングルを突き抜ける。様々な要素を自然に取り入れ、有無を言わさぬ破壊力があり、ロックを目的ではなく手段として的確に利用する抜け目の無さと手際の良さがある。
前作の"Pressure", "Blockades"には「ロックであること」自体を目的としてしまった退屈さがあり、しかもそれにしては破壊力も足りないという中途半端な出来だったが、この曲はそれらとは根本的に比べ物にならない完成度がある。前作の曲の中では、ゴスペルとダブとロックを融合させた"Dig Down", ヒップホップとオルタナティブロックを融合させた"Break It To Me", トラップとスタジアムロックと融合させた"Thought Contagion"は傑作だと思ったが、それらを超えてMuseにとってここ10年で最も重要な曲だと思うし、今後のロックの指針となる曲だと思う。やはり20年生き残るバンドは凄い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
