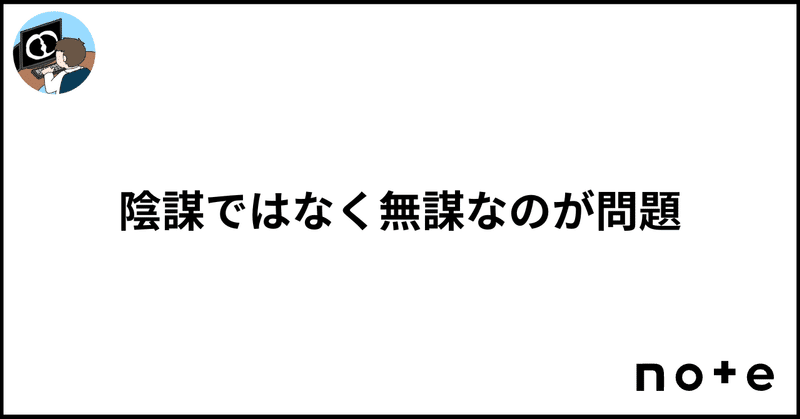
陰謀ではなく無謀なのが問題
当該記事のメインメッセージではないものの先日のネーモさんの記事の冒頭の指摘がすごく大事なポイントをおっしゃってるなあと。
この世界を裏側から操って人々を搾取し、酒池肉林の限りを満喫し、極上の幸福を味わう人物がいたのなら、この世界はどんなに簡単だったか。彼にギロチンをかけるだけで、すべては解決したのだから。
残念ながら、どうやらこの世界には黒幕は存在しない。いや、誰かにとっての黒幕は常に存在している。それはマルクス主義者にとっての資本家であり、フェミニストにとっての男であり、リバタリアンにとっての政治家であり、ネトウヨにとっての外国人だ。
「この世を操ってる黒幕はいない」
至極シンプルなこのメッセージですが、案外忘れられがちです。
実際、世の中では誰かを悪者にして糾弾する言説が毎日飛び交い、果ては陰謀論も根強く蔓延していることから分かるように、「この社会がおかしいのは誰か悪い奴が悪巧みをしているからだ」と考える癖が広くあるように思われます。
しかし、それは自分以外の「誰か」を買いかぶりすぎだし、また自分の影響力も過小評価しているのではないでしょうか。
もっとも、最終的には、「デカルトの精霊」や「水槽の中の脳」(映画『マトリックス』でおなじみ)よろしく、完全完璧に設計された「陰謀の存在」を厳密に否定することはできません。
ただ、陰謀は「陰」だからこそ「陰謀」なのであって、その存在を明確に確信しているとすれば、それはもはや「陰謀」ではないでしょう。厳密な存在の否定はできないけれど、逆に存在の肯定もできないのが陰謀というものです。
それゆえに「誰か悪い奴が悪巧みしている」というストーリーにこだわったり、陰謀論を掲げたりするというのは、ひとつの思考の偏りです。
おそらく、この思考が人気があるのは「悪いものごとが自分以外の誰か悪いやつのせいであってくれれば自分のせいではないと思える」という自己正当化にあるでしょう。問題を自分ごととして抱えずに、投げ出すことができる。「誰かのせいにする」のはすごく便利で楽なんですね。
たとえば、「クソどうでもいい仕事」を意味する「ブルシット・ジョブ」(江草のnoteでは頻出ですね)。
人類学者デイヴィッド・グレーバーが、こちらの同名の書籍『ブルシット・ジョブ』で提唱して一躍人気になった概念ですが、これにしても「誰か悪いやつや愚かなやつがブルシット・ジョブを作り出してる」かのような表現をされることがままあります。
ただ、これについては当のグレーバー本人が「誰かが企んでそうしてるというのではなく誰も何も企んでないことがこのブルシット・ジョブ現象の本質的な問題である」と書籍でもはっきり言及されています。
これは陰謀論というよりも、反陰謀論である。わたしが問うていたのは、アクションが起きなかった理由であるのだから。経済的趨勢には、ありとあらゆる要因が作用している。けれども、もしもそれらの趨勢が金持ちや権力者に厄介の種となったばあいには、当の金持ちや権力者たちは諸制度に圧力をかけ、介入しなんらかの手を打つよう決めるだろう。これが、二〇〇八年から〇九年にかけての金融危機ののち、一般の抵当権者ではなく、大手の投資銀行が救済された理由である。これからみるように、ブルシット・ジョブの蔓延はさまざまな要因によって惹き起こされている。わたしが問うていた真の問題は、なぜ、〔そのような事態に〕だれひとりとしてなんらかの手を打とうと介入し(お好みならば「陰謀を企て」)なかったのか、ということなのである。
なのですが、この「ブルシット・ジョブ」を「資本家の悪巧みである」とするなどの陰謀論的ストーリーで描きたくなる誘惑に多くの人が負けてしまいます。
なんなら、『ブルシット・ジョブ』の邦訳担当者である酒井隆史氏でさえ、そうなのです。
50年ぐらい前( 1960年代)には、ほとんど働かないですむような世界を多くの人たちがもとめはじめた時代がありました。そして経済学者の予想した通り、客観的にも、可能性としては、その実現は遠いものではなくなっていました。
ところが、世界を支配している人々からすると、それが実現するということは、人々が、じぶんたちの手を逃れ、勝手気ままに世界をつくりはじめることにほかなりません。そうすると、じぶんたちは支配する力も富も失ってしまうことになります。
そこでかれらは、あの手この手を考えます。
そのなかのひとつが、人々のなかに長いあいだ根づいている仕事についての考え方を活用し、あたらしい装いで流布させることでした。
その考え方とは、仕事はそれだけで尊い、人間は放っておくとなるべく楽してたくさんのものをえようとするろくでもない気質をもっている、だから額に汗して仕事をすることによって人間は一人前の人間に仕立て上げられるのだ、と、こういったものです。
こういった考えを強化させつつ、二度と仕事から解放されようとか、自由に使える時間が増やそうとか、人生のほとんどの時間を生きるためにだれかに従属してすごさなくてすむとか、考えないよう、支配層にある人たちは、その富の増大分をほとんどわがものにし、仕事をつくってそれに人を縛ったうえでばらまくのです。
このように、「ブルシット・ジョブ」の解説書において酒井氏は「世界を支配している人々による悪巧み」的なストーリーを提示しています。
もっとも、酒井氏自身はさすがにグレーバーの本意が反陰謀論であったことはちゃんと認識されていて、書籍内でその後に何度もその点を強調されています。
だから、安易に陰謀論を強弁しているわけではなく、「序章」に置かれたこのストーリーもあくまで導入のためのレトリックということではあるのでしょう。ただ、レトリックに過ぎないと言えど、これがわりと強い陰謀論的な描写であることに違いなく、その抗いがたい魅力の強さがうかがえます。
なお、実際に酒井氏のこの陰謀論的な描写をとりあげて「ブルシット・ジョブ論」批判をしているコメントを見たことがあるので、すごくもったいない失点につながっていると言えます。
このように、誰か悪いやつのせいにすること、ひいては陰謀論を掲げることに強い誘惑があるからこそ、そうでないことを強調することは重要でしょう。
世の中、陰謀があるのではなく無謀であることが最も問題なのであると。
ちなみに、この点「陰謀でなく無謀」というテーマは過去にこの記事でも少し触れてました。
すなわち、誰かが悪巧みをして社会を支配し操ってるの(陰謀論)ではなく、逆に誰も社会の手綱を握れておらずコントロール不能に陥ってることこそ恐れるべきじゃないかと江草は思うんですね。
飛行機が落ちそうになってる時に「パイロットが実はハイジャックテロリストだったんだ!」とか「空の神様がお怒りだからだ!」のようにいきなり「どこかだれかの何者かのせい」と決めつけるのではなく、まず「惰性でオートパイロットに任せっきりでそもそも誰も機体を操作してないのではないか」と疑うことからでしょうということです。
こと、民主主義社会においては手綱を握る責任者(パイロット)は他ならぬ私たち全員なわけですから、誰か人のせいにしてる場合じゃないのです。
江草の発信を応援してくださる方、よろしければサポートをお願いします。なんなら江草以外の人に対してでもいいです。今後の社会は直接的な見返り抜きに個々の活動を支援するパトロン型投資が重要になる時代になると思っています。皆で活動をサポートし合う文化を築いていきましょう。
