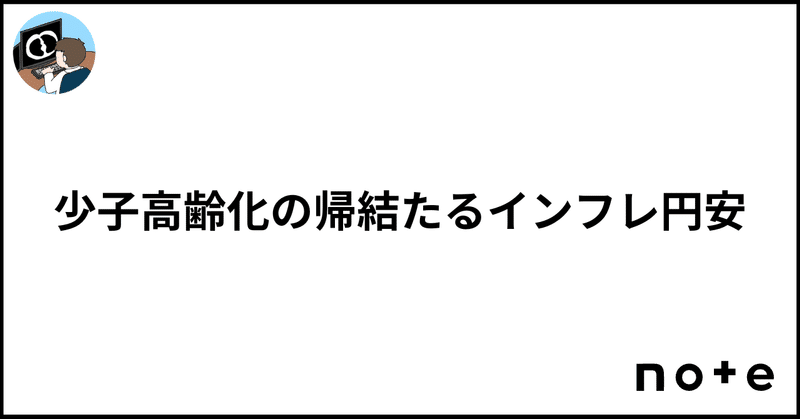
少子高齢化の帰結たるインフレ円安
一時ドル円が160円に達するなどして、急激な円安に世の中がざわついてます。

これに対し皆がパニックとなりつつあり、「為替介入しろ、日銀なにしてんだ!」的な圧力も高まっていますが、まさしく以前本で読んだ展開になりつつあって、こっそり個人的には「あ、コレ進○ゼミでやったやつだ!」という気分になってます。
その展開というのは、少子高齢化の帰結としての通貨安とインフレ、それに伴う金利上昇と中央銀行への政治的圧力の高まりですね。
元ネタは『人口大逆転』という書籍。以前感想文も書いたことがある本ですね。
たとえば、この書籍の主題はこんな感じ。
第二に、われわれが最も確信しているのは、世界がデフレ傾向から高いインフレ傾向へとしだいに移行していくということである。なぜか? 簡単にいうと、依存人口比率の減少はデフレ傾向を生む。なぜならば、扶養される人々が何も生産せずに消費する一方で、労働者は自ら消費する量よりももっと多く生産する(そうでなければ、第一、労働者を雇用して利益を上げることができない)からである。世界中における急速な依存人口比率の増加は、何も生産せずに消費する依存人口がデフレ傾向を生む労働人口を上回ることを意味する。避けることのできない結集はインフレーションということになる。
労働供給が減少すると労働者の交渉力は強くなることを経済学の教科書は教えている。そして、実質労働賃金と所得の労働分配率は再び上昇し始めることになるだろう。
※以下、引用は注記なければ同書
一言で言えば「少子高齢化だとインフレすっぜ」と言ってます。
本書の主要命題は、人口構成の大逆転が近い将来にインフレ率と金利の上昇を引き起こす、というものである。政府の債務比率が高くかつ人口構成による悪化圧力が継続する状況の下で、財務相と中央銀行の目的と目標は、まもなく、快い同調から衝突へと変わる可能性がある。
そして、インフレゆえに金利上昇圧がかかるけれど、金利の上げ下げはその数字いかんで明暗が分かれる人たちが数多くいるために、政治的対立の激戦区となってしまう。
それゆえに、名目上は「独立してる」とされてる中央銀行にも強力な政治的圧力がかかるというわけです。
物価の安定を目指す中央銀行の政策が高成長と低水準の課税という政治家の目標の障害になれば、政治家は中央銀行の独立性を終わらせるか大幅に制限する行動に出る可能性がある。そうなれば、あの自慢の独立性が、インフレ傾向が強まる将来に対する防壁としては、実は意外に脆いものであることが最終的に証明されてしまうかもしれないのだ。
金融政策もまた苦しむことになる。政府が中央銀行の独立性を歓迎し促進してきた熱意は、これから逆転するだろう。過去数十年にわたり、われわれが見てきたディスインフレ(物価上昇率が低下傾向にあるが、デフレにはなっていない状態)を説明するために、中央銀行は自らが行ったインフレ目標政策の成功にあまりにも大きな信用を与え、人口構成の変化にはあまりにもわずかな注目しか与えてこなかった。インフレと金利が低下している限り、財務相はハッピーであった。その幸福な状態が、高齢者の集団が膨れ上がり、それがインフレと金利を上昇させても続くであろうか?
われわれはそうは思わない。金融政策と財政政策の衝突はすでに起き始めている。しかも、われわれはまだその始まりにいるにすぎない。
中央銀行の独立性は、ほとんどのケースにおいて「張り子の虎」である。そのような独立性は総じて議会における立法によって実現されている。ある議会が立法した法律は、別の議会によって廃止できる。たとえ元の法律が温存されていても、中央銀行を意のままに動かすために、政府は一般に権限、または執行部の被任命者を変えることができる。中央銀行は本質的に政治的な組織である。そして、現在の法律上の地位がどのようなものであろうとも、彼らはそのことを知っている。
どちらかというとこの書籍は過度なインフレに悩んでいる欧米の論者の語りであるがゆえに、論者はインフレ抑制に支持的な態度を示されていますが(インフレを抑制したいという中央銀行の正当な試みが政治的圧力で妨げられてしまうという展開を嘆いている傾向がある)、インフレが始まったばかりの現在の日本においてはむしろ逆にもうしばらくインフレさせたい日銀(一応まだ金融緩和持続の姿勢を崩してないですからね)に対して「インフレ円安はけしからん、日銀は早く止めろ!」という外部からの政治圧がかかってるところがあります。
正確に言うと日銀内部ももちろん一枚岩ではないはずで、今後どういう方策を採っていくかを巡って現在進行形で濃厚な内部政治がうごめいていることでしょう。(江草も以前、日銀の中の人と軽く雑談した時に「理論上は可能でも政治的に難しいのよ」的な愚痴をちらっと聞いたことがあります)
で、日本が今後インフレ円安を容認するべきか拒絶するべきかという「べき論」はさておき、ここで紹介したかったのは、インフレ円安が少子高齢化を背景にしていることと、中央銀行は経済学的に動いているように見せてその実政治的に動かざるを得ない機関であるということです。
インフレになる経緯については上記の引用が十分に解説してるとしても、円安についてはもう少し追加で説明しておいた方がいいかもしれませんね。
インフレとは物価があがること、裏を返せば通貨の価値が物やサービスの価値に対して相対的に弱くなる現象です。
で、少子高齢化がインフレの強い要因としてあるのだとすれば、少子高齢化の程度はインフレの程度を規定しうるとなります。すなわち少子高齢化が著しい国の通貨はよりインフレ圧(通貨安圧)をより強く受けると言える。
そして、ご存知の通り、日本は世界でも少子高齢化最先端の国です。だから、他の国の通貨よりも少子高齢化成分に伴う通貨安圧がより多くかかる。
して、まだそこまで少子高齢化の悪影響が顕在化してない欧米は「むしろインフレしすぎた」としてこれまでの(わざとインフレさせようとしてる施策である)金融緩和策にブレーキをかけ始めたわけです。それで、(ほんとはもとから存在していた)相対的な「円」の弱さがここに来て一気に表出したというのが今の「円安パニック」なんですね。
しかし、「わざと」ではなく「否応無しに」インフレにならざるをえない「少子高齢化」という重たいネガティブ要素を伴ってる日本においては、アクセルを踏むも地獄(インフレ・円安)、ブレーキを踏むも地獄(債務破綻・不況)という極限的状況に陥り始めたというわけです。どちらにしても平和な落着が見えない。
そんな危機的な状況の中で(いやむしろ危機的状況の中だからこそ)、各ステークホルダーたちが自身の生存や既得権益を守るべく、中央銀行(日銀)を舞台にした政治的駆け引き(「為替介入しろ!」とか「金融緩和持続しろ!」とか)がますます激化している。
これが今起こってる事態なんだと江草は解釈しています。
(ちょっと補足しておくと、国内経済における賃金上昇を伴うスパイラル動態としてのインフレはあまり進んでなくて、国際経済における現象たる円安の側面がより目立っているというのが日本の現状としてより正確かもしれません。便宜上本稿ではインフレと円安を併記してますが実際にはこの両者にも温度差があるわけです)
まあ、元をたどれば、結局は少子高齢化がもたらした帰結なので、医者的なコメントを付与するならば「どうしてこんなになるまでほっといたんだ?」というのが正直な感想です。
ただ、それがいかなるハイステージ症例であっても、すでになってしまったものは仕方がないので、「どうにかならんものか」とここから頭をひねるしかないのですが、治療方法がどうしても侵襲が強いものになりやすい点は覚悟が必要ということにはなるかと思います。
(ちなみにこうした「少子高齢化問題」に加えて、「ブルシット・ジョブ」に象徴されるような「仕事の変質」の存在が世の経済を歪めてるし人々の議論がかみ合わない大きな要因となってると考えてるのが江草の立場なのですが、「仕事の変質」の話までするとよりややこしくなるので今回は割愛)
で、ついでに蛇足ですが、これだけ中央銀行が政治的圧力を受ける舞台となってることを考えると「経済学的なことは政治的なこと」と改めて確認すべきだなとも思います。(言わずとしれた「個人的なことは政治的なこと」のもじりです)
世の中、なんかこう「こんにちは、私は経済学です」という顔をして数字や計算を出されて表現されると、価値中立的で客観的な理論を述べられてるように思われがちですけれど、そんなことはついぞなくって、よくも悪くも経済と政治は濃密な関係性にあるということは現実として受け入れるべきなんじゃないかと。
いや実際、たまに「経済と政治は別なんだ」ということを明言的に語ってる論者さえいらっしゃるのですけれど、共産主義とか資本主義という経済システムどうこうで世界がかつて政治的に派手に二分してたことを考えても、経済と政治は不可分な関係性にあると考える方が自然でしょう。
「それらが別々であってほしい」という気持ちは分からないでもないものの、それは残念ながらいくぶん素朴で幼稚にすぎる認識ではないかと思います。(まあ不可分なのを承知の上であえて「別々です」という作り笑顔をするというのが一周回って「大人な態度」と見ることもできるかもですけどね)
正確に言えば、経済学の道具である計量とか論理自体は十分に中立的だし客観的たりえるとは思うのですが、そうした演繹的あるいは帰納的論理の基盤、すなわち経済学が目指すべきものとしての暗黙の前提たる「価値観」は中立的たりえないがゆえに、経済は政治と不可分なのですね。(医学がどれだけ科学的な装いをほどこしていたとしても元をたどれば「命は大事」という価値観を暗黙の前提としてるのと同じです)
で、全体的にうまく回っている(ように見えてる)時はまだしも、全体的にムギューとなってる時は、今の日本がまさにそうであるように、その暗黙の前提たる「価値」そのものについての政治的対立が顕在化しやすい。それは一見、経済学的な文脈であってなお、そうなのです。
これを認識したところで、ただちに気の利いた解決策が立ち現れるようなことではないので、苦境を認識することはただただつらいことではありますが、それでもまずは正確な病状把握から始めないとしょうがない、というのが「診断医」のサガなので、ついついこういうことを言ってしまうのです。申し訳ありませぬ。
江草の発信を応援してくださる方、よろしければサポートをお願いします。なんなら江草以外の人に対してでもいいです。今後の社会は直接的な見返り抜きに個々の活動を支援するパトロン型投資が重要になる時代になると思っています。皆で活動をサポートし合う文化を築いていきましょう。
