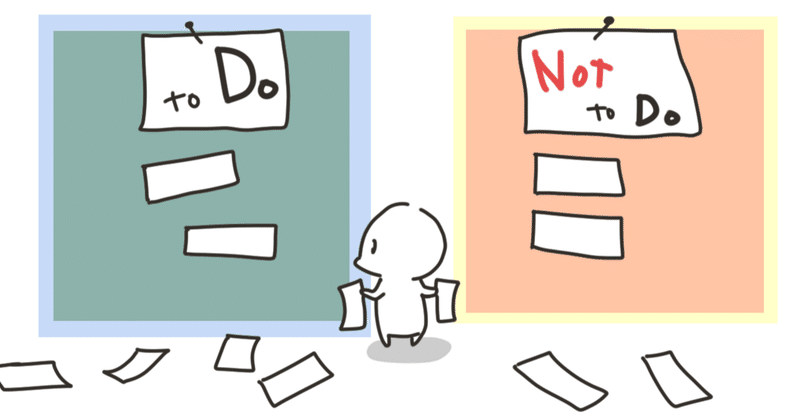
ASD(自閉症)の次男のTODOリストの視覚化
はじめに
私の次男が自閉症スペクトラム障害で、療育施設での学びから視覚支援によるスケジュールの提示やスケジュール毎にスペースを分けたり、そのスケジュールに関係がない物が目や耳に入りにくいようにする構造化等、色々と生活しやすいように支援を行っています。
そんな自閉症育児の中から、実際の我々の生活にも生かすことができると思われる事を紹介、提案します。
次男のスケジュール管理
人それぞれなので一括りでまとめてしまうのは乱暴ですが、少なくとも私の次男はTODOのリストを絵カードや写真などで順番にスケジュールにして確認させておくことで、落ち着いて次の行動に移せます。
例えば朝起きて、キッチンタイマーでベルが鳴ればスケジュールの着替えが始まります。着替えが終わると、次の絵カードの歯磨き、トイレ、学校道具をカバンに詰めて登校の準備を順番に手際よく行います。
そして、車に乗ると、写真カードで提示しているコンビニバス停に向かいます。絵カードや写真カードで提示する事で、行先がどこなのかを事前に知る事が出来、安心して車に乗っている間の時間を過ごすことができるのです。
これが休みの日に、カードの提示をせずおでかけをすると、行先までの時間が長いと不安になったり、思っていた場所と違っていれば車から降りようとしなかったりして悲しい気持ちにさせてしまうのです。
絵カード交換コミュニケーションツール
コミュニケーションの道具としてスケジュールをカードで提示するとお伝えしましたが、こちらから一方的に伝えるだけのツールではありません。
次男がカードを取り、自分が欲しい物、してほしいことを伝えるツールとしても活用しています。
ここで詳しくはお話しませんが、絵カード交換コミュニケーションツールとしてPECSというツールがあり、伝えたい事を色、物、述語など組み合わせて3語文、4語文とつなげて提示することで発語が苦手な方でもコミュニケーションを円滑に行えます。これを使えば伝わるんだ、といった成功体験を積み重ねる事で少しづつ提示してくれるようになるので、対象の方や親御さんは試してみてはいかがでしょうか?
一定発語のできるお子さんや知的障害があまり見られない方でも活用する事で生活が安定した例もあるようです。
旅行の際に気を付けたこと
旅行の計画などは視覚支援が有効でした。
事前に行く予定の場所、乗る乗り物、わかるならば食事する場所、メニュー、宿泊を兼ねるのであれば宿泊するホテル、部屋割りは誰と一緒か、等出来るだけ細かく、生活の変化に過敏だからこそ、事前に提示していく先々でも次はここに行くよー、ここで食べるよー、といった風に写真を提示することで予測がたち安定しました。写真や絵カードでは時間を示すのが難しい為、キッチンタイマーや時計の針を使って時間の予測を立てやすいように提示しました。今回は出来ませんでしたが、歩くのであればどれぐらいの時間歩くのか?どこまで歩くのか、目的地を提示する等、そのあたりは次の課題です。
自分に置き換えてみる
私は事前に段取りを組んでいる事は順番にこなしていくのは得意ですが、何も予定がない時に次々と動くのは苦手です。
スケジュールも出来るだけ順番に何時から何時まではこれ、といった風にしておいた方が動けます。また頭の中で考えているだけでは時間が過ぎてしまったり、遅れたときに修正や変更がしづらくなり、予定をこなすことが困難になったりします。
そこで、スケジュールを書き出す TODOリストを時系列で並べていくというのが効果的です。次男に提示しているような絵や写真を活用する事でより鮮明な意識が向き詰まったスケジュールでも効率よくこなせる自分がいました。
スケジュール通りにいかなかったときに元の木阿弥になってしまうのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、そんな時は変更カードが有効です。変更と書かれたカードを予定していて変更したい、変更せざるを得なくなった事のカードと入れ替えて、それ以降のスケジュールを修正していけば、スケジュールを立て直すことが出来ます。
こまかな視覚的なスケジュール化によって日頃のビジネス、プライベートの充実につながるかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
