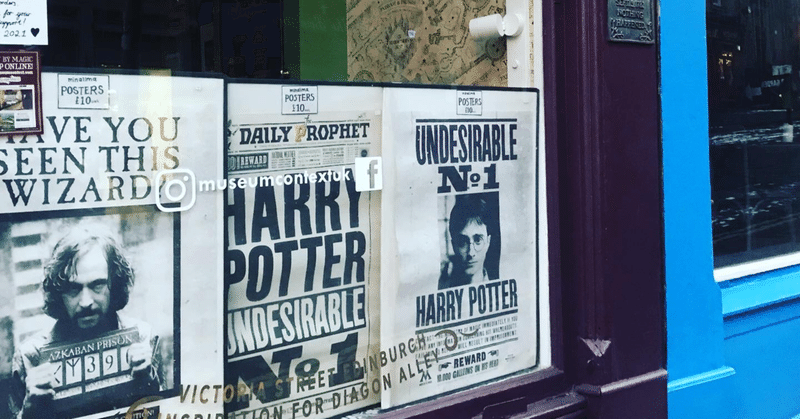
【エジンバラ 大学留学#5】Semester 1を終えた反省と改善
最初に
昨日ようやく1stセメスターの課題が終わり、来週からは2ndセメスターが始まります。その前に、恥も投げ捨てて、エッセイの書き方やアプローチについて自分なりに考えたことを残しておこうと思います。
現時点では、1stセメスターの最終の課題の結果は出ていないので、改善したアプローチが正しいかはわからないのですが、とりあえず今思うことを残しておこうと思います。
1stセメスターの授業の簡単な紹介
(1) Source of knowledge(SoK)
知とは何か、世界をどう見るかについて考える科学哲学の授業です。
難しいけど、1番面白く、最も練られていた授業。
僕がいる学部は教育学部なのですが、他の学部と比べてもかなり厚くやる印象です。
(2)Sports Marketing Communication(SMC)
マーケティングコミュニケーションの授業。
担当の先生が2人いるが、正直テーマが結局よくわからない授業でした。
多分前半の先生は、マーケティング、後半はマーケティングコミュニケーションを担当。
特に前半の先生は、マーケティングの知識は全然体系化されおらず、今ホットなスポーツトピック(例えばコロナとスポーツとか、SNSマーケティングの実例)を急に扱うので、いまだに何がやりたかったのか不明という。
先生自体は好きなのですが、授業の内容自体はんーという感じでした。
個人的には、まずはテキストなどで理論を勉強して、実務に落とし込まないと厳しいなあという印象。
(3) Sports Resource Management
マネジメントの基本的な知識を学ぶ感じ。
例えば、ミッション、戦略、SWOT分析、人的資源管理とか。
先生の印象はよく、授業はわかりやすいけど、一方で範囲は広範な分、内容はかなり基本的で、学部レベルという印象。社会人経験者には少し物足りないという印象。
1st Semesterの結論
スポーツビジネスを中心的に学ぶなら、Loughborough の方がいいのではないだろうかという印象です(サッカーだけに着目するならリバプール とか)。
エジンバラは、ビジネスは弱いかもしれないです。
一方で、後期はパブリック関連の授業なので、ビジネスとパブリックの両方を学べるのがエジンバラ の強みだと思います。
多分元々社会学的な学部だけど、ビジネスも入れなきゃということで、無理矢理ビジネスを入れた感じ。そのため、ビジネスに関する授業の質はそこまで高くないという印象でした。
(追記:後期の授業を受けた感想だとやはり、スポーツと社会学の授業の質は高いと思いました!)
あとは、教育学部関連の授業の質が異様に高い感じがするので、実務サイドよりも哲学とかアカデミックなことが好きな人はいいかもしれないと思います。
各授業ので出された課題は以下のとおり
(1) SoK:
自分が選ぶ2つのパラダイム(e.g.Positivism,Realism)について比較しながらのエッセイ2千字
(2) SMC
中間 自分で選んだスポーツ組織のマーケティング戦略について
最終 自分で選んだスポーツ組織のマーケティングコミュニケーションについて
(3) SRM:
中間 スポーツリーダシップのAcademic ポスター
最終 中間で選んだリーダーの組織のマネジメントレポート
各課題のFeedback及び改善は以下のとおり
(1) SoK:
ーDiscussionが必要とのコメント。
Discussionとは、反対意見、限界など、異なる立場からの意見を出し、それでも自分はー自分の主張を変えないということをアピールすることですね。
”Discussion”とはなんぞやについては後述しますね。
(2) SMC:
ーより深い理解をするためにDiscussionが必要とのコメント。
この成果物にはかなり自信はあったけど、グレードはBで少しショック。
先生と1 on 1セッションをしたところ、(多分全員の生徒は把握してないけど)、
資料にDiscussionの記載がないなら、この場合、プレゼンなので、プレゼン中に言及すべきというコメントをもらいました。
いずれにしてもより深い理解をするためにDiscussionが必要というのは、こちらの世界の常套句であることを痛感します。
ただ、何がDiscussionなのという質問に対する回答はよくわからなかったです。(こちらの先生は、クリアに答えてくれることはない。方針だけ示してあとは自分で考えてという感じです)
(3) SRM:
ー初めてのAcademicポスターで、どのようなものが自分の理解を示すのかわからず。下手に情報を入れ過ぎて、よくわからないというコメントがあり。(これは同意)
全体的な感想
英語力の問題もあるけど、割と苦しんだ印象。特にディスカッションの方法。ただ、ここから色々試して、こちらで評価されるポイントをつかんでいきたいなと思い、結構ワクワクしています。
改善アプローチについて(個人的に一番大事)
現実と心構え
頑張ったけど、他の人に負けている。ということを受け入れる。
そういえば、僕は学校では、どちらかというと落ちこぼれだったことを思い出した。笑。なので、社会人やったんだぜというプライドを捨てて改めてドベからスタートしていこうと思います。
実際他の若い学生にぼろ負けしているところもあるので。謙虚に謙虚に。
とはいえ、まあ、仕事でもないのでそんなに気にせず、楽しみたいとと思います。
足りない能力、視点、間違っていたと思う反省点
・課題の要求するポイントを掴む力
・英語力
・本当に何がイシューかを考えていなかったかもしれない点。
◆深い理解をしていた?
◆答えをうまく見せようとしていなかった?
◆結局表層的な理解になっていなかった? etc..
・問題を複雑にしすぎていた
対策(メモベース)
◆とにかくDiscussion
Discussionの意味については、諸説あるが、思うにイギリスは、違う意見を出し合うことが良いとされる文化なのだろうと思います。
SoKで学んだことは、とにかくイギリス人は、演繹法的な整理、分類が大好きだということ。
そのような思考があるから、ディスカッションを通じて、どの層のどこでお互いの意見が食い違っているのかを確かめ、その上で合理的な解決策を見つけようとしている気がします。
例えば、パラダイムでいうと、そもそもPositivistとInterpretivistのように世界の根本的な見方が違うのか、それとも同じパラダイムの中で意見が相違しているのか等。
お互い違うのはいいことで、違う分岐点を探すという意味でDiscussionは必要なんだという理解をしました。
実際のエッセイでは、何がDIscussionかというと、なんのことはない反対意見や限界、問題点などをきちんと引用し(ないし自分の考え)、その上で、プロコン比較をしてあげればいいのだと思います。
比較することでどこの部分が異なっているのか、共通なのかを探すことができます。
その上でなぜ自分がこのポジションを取るかを名確認します。
常に片方がいいということはないという姿勢が大事だと思います。
これって言われてみるとかなり当たり前のことではあるけれども、日本だと、どちらかというと問題点をDiscussionするよりも、すでに自分の中ではディスカッション した内容は記載せず、プレゼンがMECE(もれなくダブりなく)であることや、問題の重要度や解の質が重視されている気がして、Discussion部分を抜いて書いてしまっていました。
こちらのアカデミックでは、どちらかというとMECEであることよりも、狭いテーマを、ディスカッション して見せるスタイルが求められているようです。
どちらが有用ということはないけれども、留学している以上郷にいれば郷に従えということで、最終からはあえてそういった記載を残すようにしてみた。
◆シンプルでいい。(あまり色々な理論を使わない)
→前期の例がある場合は、まず踏襲する。オリジナリティを考える前に、まずは基礎を固める。少ない理論で深いディスカッションが良い。
◆適切な引用。むしろ少なめで自分の意見。
→適切な引用とは、引用数ではない。結構自分の意見を書いてもいいし、むしろ自分の意見を述べる方がきちんと評価されている気がする。
あと、最新の論文を引用した方がベター
◆Proof reading and Tutor面談を利用する
→早めに仕上げることが重要。
◆構成に時間がかかりすぎている。
→基礎となる文献、テキストをを決める(1−3つでいい)
◆”素直”に成績の良い人のアプローチの真似をしてみる。
→この”素直”にというのが結構大事。わかっちゃいるけど、自分らしさを出したくなる気持ちを抑える。
◆フィードバックコメントに、最新の論文を引用することとの記載が。んんーであれば言っておいて欲しい。こちらも授業で先生が昔の論文を引用していたから、引用したのに。。そのコメントはないぜという印象。しかしながら、最新の論文を引用することは心に刻もう。
さて、長くなってしまったので、具体的なエッセイの書き方のアプローチ方法、スケジュールや改善した方法やについては、次の記事で書こうと思う。
では!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
