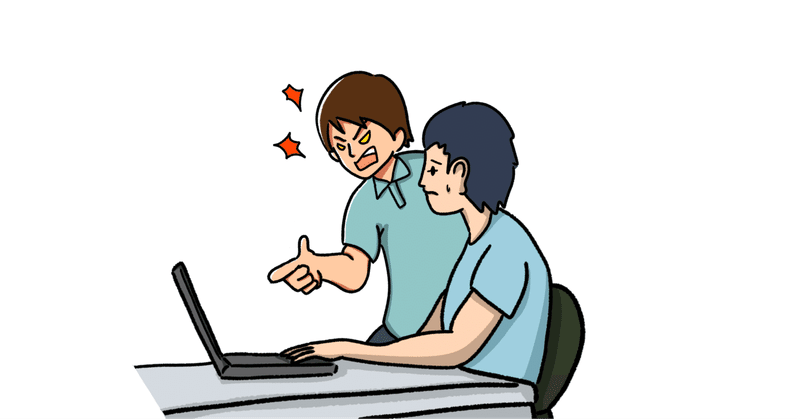
「させられる」意識について
こんにちは。
社会福祉士、精神保健福祉士のぽこです。
◇なぜ「損をした」と思うのか
今日は、損得に関する思考をシェアします。
このテーマについて熟考したきっかけは、仕事中のこんな会話。
上司「Aさん。来週末に研修行ってきて。」
Aさん「わかりました。」
上司「あ、今回の研修は実費ね。交通費は出るから、申請しておいて。」
Aさん「・・・はい。」
こんな会話です。
そして上司がいなくなった後、もちろんAさんは実費での研修に不満を述べていました。
この時、Aさんは少し損をしたような感情を抱いたのではないかと思います。
今までは私も同じように感じていましたが、少し思考を深めてみたら考え方が変わりました。
損をしたと感じるのは、Aさんの”やらされている意識”が原因だと気がついたからです。
・させられていること
要は、今回の研修に対してAさんが納得いっていないというのが問題なのです。
自動車税の請求に文句を言いたくなったり
ゴミの有料化に不満があったり。
私たちは日常の中で「納得していない内容に払わされている」という感覚に対して不快感を抱きます。
私は、この「払わされている」感覚にアプローチできれば、身の回りのあらゆることに対する損得勘定=不快感を減らすことができるのではないかと思いました。
冒頭では研修の費用について例に挙げました。
もし仮にこの研修が、本人にとって興味のある内容だったらどうでしょうか。
状況は変わっていたかもしれません。
上司に言われなくても、自ら研修を探してくるかもしれません。
業務外の時間で、しかも実費で快く参加できたかもしれない。
研修に行くか行かないかという選択に対する主体性一つで、物事の進捗は大きく変わります。
また、もう一つの例で挙げたゴミの有料化。
ゴミ処理の現状に対して問題意識を持っている人であれば「払わされる」という感覚ではなく「払うことを選択する」という意識に変わっているはずです。
その意識の差は、非常に大きいのではないでしょうか。
・当事者感を忘れていないか
私たちにもっと必要なのは「当事者感」ではないだろうかと思うのです。
社員に必要な研修を判断するのは上司の仕事で、自分ではないという他人感。
ゴミを処理するのは行政で、私たちは関係ないという距離感。
そういった物事と自分との間にある距離を、私たちは遠く見積り過ぎているのではないかと思います。
私たちは、分業された今の社会での生活に慣れています。
分業されているということは、物事を完遂する上で、全てを知らなくても済んでしまうということです。
その一部分だけを担っていればいいという認識は、私たちから当事者意識を奪います。
私たちは効率的な世の中に生きていると思いがちですが、実はあらゆることを自分のコントローラブル範囲外に追いやっているのかもしれません。
・「私事」
身近な出来事に対して、他人事ではなく自分事の意識を持つ。
それだけで、世界で起きている出来事に対して納得しやすくなります。
なぜこんな大変な思いをしなくちゃいけないのか。
なぜ毎日忙しいのか。
そんな抽象概念的な不快感に対しても、自分なりの答えが見つかるかもしれません。
物事を「させられている」という距離感で捉えるのではなく、「自らそう選択している」という距離感で捉え直す。
意識してみてはいかがでしょうか。
ということで、物事との距離感について考えてみました。
読んで「ちょっと生きやすくなったな」と思ってもらえるような記事を目指しています。
では、また💐
いいな!と思ってくれたら、ぜひサポートをお願いします!! いただいたサポートは本業、発信活動のために使わせていただきます。 皆様の温かいサポートがとても嬉しいです。ありがとうございます!
