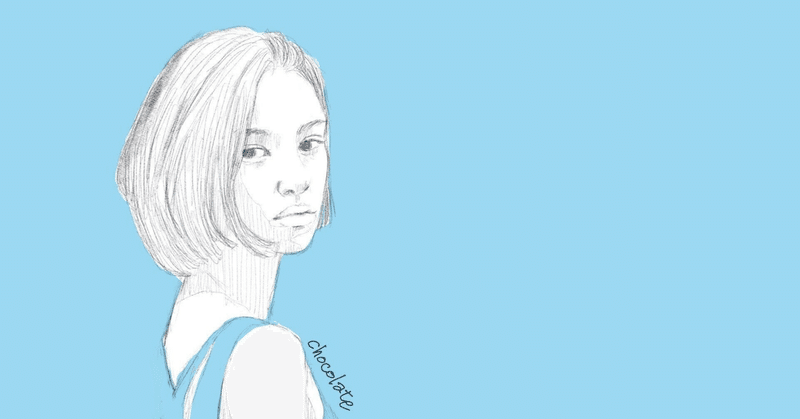
3分小説「結婚たち/入場曲」
葵はラブソングが嫌いだった。
まったく共感できなかった。
カラオケに行くとどうしても意地悪な人間になった。
なんとなく聴いたことのある流行りのラブソングの歌詞を読むことになるからだ。
「ほんとこんなこと思ってる人いなくない?」
ハイボールを飲むとますます意地悪になる。
フライドポテトで油のついた指で画面の歌詞を指した。
「だいたいさ、もっとさ、浮気されたとか、暴言吐かれたとか、金貸したとか、そういう歌があるべきじゃん。うちらのトークの大半がそうなんだし」
カスミが笑いながらムービーを撮っている。
「出た、葵のラブソングディス」
「私が歌詞を書くならね」
「お、作詞?葵先生がついに作詞家デビューだ、曲名は?」
「・・・『尽くすな』」
「うわ、重っ」
そのころ、葵は二十一歳だった。まだ誰かより自分に夢中だった。
「では入場の曲は新婦さまがお選びいただくということで」
「はい。ちょっと時間ください」
会社を定時に飛び出した葵は、品川駅にあるカフェでウエディングプランナーと打ち合わせをしていた。婚約者は海外赴任中で結婚式の準備はほとんど葵がしなければならなかった。最近は正直仕事どころではなかった。
彼とは合コンで出会った。葵が二十八歳のときだった。もうそろそろ合コンもどうかと思っていた時期だったが、人数合わせでどうしてもと会社の後輩ちゃんたちに頼まれた。
「はじめまして。西村葵っていいますー。人数合わせですー」
周りが年下だと急にベテランキャラを演じてしまう自分も嫌だったが、このキャラでいけば楽にさっさと帰れるかなとも思っていた。でも、そういうわけにはいかなくなった。裕介と出会ったからだ。
「俺も人数合わせっすよ」
目の前に座っていた裕介からそう言われて、葵は彼をちゃんと見た。
「いやいや主役っぽいよ」
彼は明らかに目立っていた。後輩ちゃんたちも早く彼と話したいだろう。
「え、西村さん、もうなんかこの合コンはテキトーに済まして帰るモードになってるでしょう?」
「え、なんでわかる、あ、いや」
「だって俺のこと主役っぽいだなんて嘘が下手すぎて」
もちろん嘘じゃなかった。
本当に今日の男の子たちの中で彼が一番素敵だと思っていた。
「謙遜ですか」
「いやいや、西村さん、やめてくださいよ。なんのゲームですか」
葵は知った。出会いとは自分の人生において『明らかに目立つ人』と会うということだと。それが自分にしか分からなくても。
「なんて曲だった?初めて会ったとき、店で流れてたの」
裕介はイギリスにいるので仕事終わりの彼と電話をしようとすると、葵は真夜中まで起きていることになる。
「あー、何度か話したよね、で結局は分からないままで」
「新郎新婦入場で流す曲を探しててね。出会ったときのっていうのも候補かなと」
「まさに入場にふさわしい」
「とにかくラブソングだったよね」
「けっこう濃いめのラブソングだったと思う」
葵は思わず笑った。
「え、なに?」
「いや、私が結婚式の入場で濃いめのラブソングかー」
葵はその一曲を探すため、当時のヒット曲を聴きまくった。通勤の電車の中やカフェでの仕事中、もちろん家でもラブソング漬けになった。
薄め濃いめなどいろいろあったが、たぶんこれだというものを見つけた。というより、たくさん聞いた中で一番好きだなと思う曲にした。裕介にも送ったら「これだよ、これ。ありがとう」と言っていたがたぶん確証なく言っているし、葵が良いなら、ということだと思う。
結婚式当日、葵は見つけたラブソングが大音量で流れる中、披露宴会場に入場した。友人テーブルではカスミが大笑いしながらムービーを回している。あのときのカラオケを思い出した。もし私がいまラブソングを書くなら、
人数合わせで 行った合コン
まばゆいあなたが 私を見てた
嘘じゃないのよ あなたが一番
まるで目印 ついてるみたいに
店で流れる ラブソングだって 祝福してる
(語彙力)
葵はカスミの前を通るときにカメラ目線で「やっぱラブソング最高だよ、この野郎」と言ってやった。
終わり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
