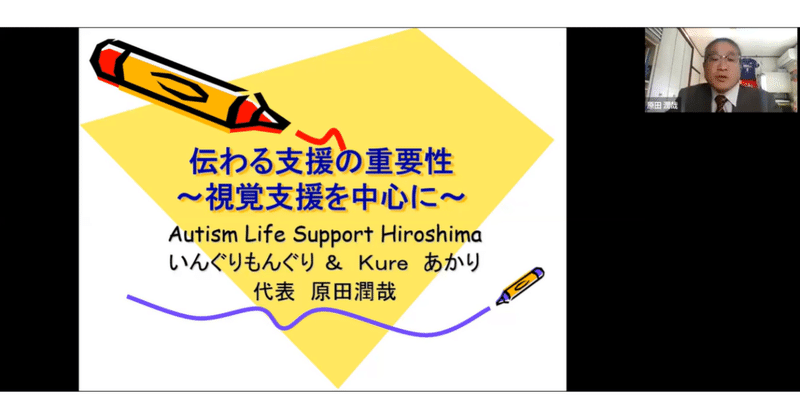
伝わりやすい見て分かる支援
こんにちは。NPO法人日本インクルーシブ教育研究所の石井です。先週、11月6日(日)、第7期学習・発達支援員養成講座7回目『伝わる支援の重要性 〜視覚支援を中心に〜』をオンラインライブで開催しました。
講師は自閉症の専門家でありAutism Life Support Hiroshimaいんぐりもんぐり&Kureあかり代表の原田潤哉先生でした。原田先生は不登校の子の支援や高機能自閉症児・アスペルガー症候群児の支援活動を経て、現在は障害のあるきょうだいを持つ子への支援、広島障害児心理研究会や広島自閉症治療教育・支援研究会の活動など、幅広く活躍されています。
それでは受講生からいただいた感想を紹介しましょう。
・今までの講座の内容とリンクするところは復習しながら視聴することができました。また、初めて聞く情報が盛りだくさんで、もっと学びたい気持ちになりました。特に「これは必須!必ず身につけておいていただきたい!!」と書かれていたPECSは、ホームページも紹介していただけたので、ぜひ学ぼうと思います。また、コミック会話は自分でも活用していましたが、ソーシャルストーリーズTMは知らなかったので、本を購入したいと思います。おすすめの本もたくさん教えていただけて本当にありがたいです。【教員】
・自閉症スペクトラムに着目した講義はとても学びがいがありました。身近にいる人に思い当たることがたくさんあり、伝わる支援の必要性と具体例がとても参考になりました。聴覚支援から視覚支援への移行は一手間ふた手間かかることから、ついつい、安易な伝達手段を選びがちです。文字に換えて伝えることが個人のためだけでなく、みんなの役に立つユニバーサルデザインの方法であること。社会の環境、生活の環境を変えていくための一歩を踏み出さなくてはと思いました。感情処理のトラブルはつきもので、コミュニケーションで問題が起こるときの支援者の対応が、行動変容を起こすチャンスなのだと思います。当事者が何にこまり、その対応者の期待とのトラブルの現実のギャップがどこで生じたのか丁寧にやり取りしていく必要があります。コミック会話や一歩踏み込んだ視覚支援、紙ペンで事実を客観視していく時間のありかた。その学びを介在して伝える仲立ち、支援者がどのようにコーディネートしていくのか。その役割はとても大きいと思います.学校から就労の社会に確実に繋いでいけるのは,まだまだ親の役割も大きいのかもしれません。自閉症スペクトラムの傾向を持つ人は身近に、本当に多く存在している現状が推測できました。人と人とのコミュニケーションのあり方を社会全体が考え、誰1人取り残さないで生きる、活躍する社会に向けて、今日の講義を社会で生きる1人1人が踏まえておかなければならないと思いました。経験を通して失敗から課題を見つけ、確実に自分の力になっていくまで支え合う社会を作り出したいと思いました。たくさんの考え方や参考資料をご紹介いただき、勉強をさらに深めたいと思います。ありがとうございました。レジメだけの資料で、説明を聞く、メモを取るの両方が同時にできず、説明を聞き逃したこともありました。できれば。パワーポイントの資料があるとよかったとおもいました。ネット環境が安定しませんでしたか、その都度タイムリーに中谷先生が介入され、理解が途切れることなく進んだこと、ありがたく思いました。また、重要な情報をチャットや、クラスルームにアップしてくださり、たすかりました。【不登校教育支援センタースタッフ】
・このような学習をさせていただく以前、とにかく支援しないといけない、そう思って、子どもができることにもあれこれ手出し口出ししていました。子どもが何に困っているのか、それはどうしてか実態把握することは、支援のスタート地点と思います。その子自身に合わせた伝え方ができる3つ組の問題の話では、休憩のもつ大事な意味をあらためて理解しました。使い方に注意し休憩を普段から肯定的につかうようにします。具体的なゴールの姿をイメージして、本人を中心に置いて、どう組み合わせるかを繰り返して自問していきたいです。子どもが自分でできた、できたら楽しい、また、次は一人でやってみたいと自分に自信をもち、自ら意欲的にチャレンジできている姿を見るととてもうれしいです。今日のお話や紹介していただいた資料など、今までの自分の支援・指導に振り返ることができました。ありがとうございました。さまざまな講師の先生方から、色々な角度から学ぶことができます?【教員】
・視覚での支援のお大切さをあらためて理解することができました。いつも良い講座を受講させて頂き本当にありがとうございました【教育支援員】
・視覚支援について深く知ることができ、ソーシャルストーリーについては、今からもっとテクニックを高めていきたいと思いました。非常に参考になりました。また原田先生の講座を受けてみたいです。【教員】
・ここまで自閉スペクトラム症について学んだことはなかったかもしれないと感じながら受けさせていただきました。話の内容はたったの7%ほどしかなく、見た目だと55%と入ってくるという視覚優位というのには驚きましたが、よく考えてみれば、普段気にしていないから気づけていなかったけど、視覚で見てすぐ理解できるよう様々なところが工夫された中で生きていることに改めて気づきました。仕事上、自閉スペクトラム症の子と接することもありレッスンを行いますが、こちらが考えた内容を気に入らない、もしくは好んで取り組まない姿を見ると、その子には合っていなかったんだ、次からは内容を変えようと思って行ってきていましたが、1回やって好まなかったことは嫌いなわけではないことが多いこと、知らないから取り組みにくいだけというのを聞いて、今後のレッスンの組み方も変わるような気がしました。【児童指導員】
・自閉症のお子さんへの具体的な支援をたくさん聞けて参考になりました。やはり 講座を受ければ受けるほど日本の教育や社会の考え方の遅れ具合を非常に強く感じます。インクルーシブ教育とは 変わった教育ではなくて 一人一人がもともと多様であり その違いを認めることから始まるのだと思うのですがそれを是としない 認めない価値観が根っこにあるように思います。今日の講義でもお話がありましたが大人がまず休む 間違ってもいい 自分のペースでいい 価値観の転換が必要だと感じます。【フリースクールスタッフ】
・自閉症の子に伝わる伝え方がユニバーサル、ソーシャルストーリーズ、キャロルグレー氏、pecs、pep検査など海外のスタンダードな情報も知ることができました。【学童職員】
・これまでの講座で学んできた内容を体系的にまとめて下さった内容で、若干混乱していた頭の中の知識が整理された気がします。ASDを理解する上での3つ組みという考え方、感覚情報処理の問題、視覚優位であること等の他、ASDには3つのタイプがあり、受動タイプにはより対応に注意が必要であること、初めての経験は拒否する傾向にあること等初めて知る内容もあり、今後の支援に活かしていける講義だったと思います。講義中、音声が途切れがちな部分を丁寧にフォローして下さったり、参考となる著書などを都度紹介して下さり有難かったです。先生のスライドも併せて手元にあれば尚有難かったかなと思いました。ありがとうございました。【言語聴覚士】
・伝わる支援と聞いて奥が深いなと思いました。言葉は7%しか伝わってないなんてくどくど話していたら尚、伝わりませんね。ならばその子が必要とする言葉を短く伝えなければと思いました。その反対に視覚から入る情報は55%と、ほぼ見た目で動くこと納得です。ワークでも話されていましたが普段当たり前に見る標識などスッと頭に入ります。今は絵カードをポケットに詰め込んで次にコレ次にコレとやってるんですが、pecsのように自分でスケジュールを組み立て表現する方法がある方法は知りませんでした。幼少期からこの方法に触れておくと肯定感もアップしますね。私がコミック会話をすると子供たちは私の絵を見て笑うので内容が入っていないように思います。もっと絵も上手になれるよう頑張ります。ルームに移る時、私のパソコンだけ時間がかかるので時々スマホに切り替えてます。ケーブルも繋いでるのですが、ご迷惑おかけします。【保育士】
・自閉症について児童発達支援センターに勤めていた時に勉強していたことを思い出しながら先生のお話しを聞いていました。【行政職員】
・子供がASD傾向があると言われており、本や講座でこれまで色々聞いたことを総復習できたような、また新しい情報も聞くことが出来て良かったです。さまざまな具体的実践例を写真で見せて下さって、分かりやすく、取り入れみようという気持ちになりました。ソーシャルストーリーズやコミック会話、ぜひトライしてみます。体験する前に図解と説明で分かりやすく伝えるときに、最悪の結果も伝えることが大事というのもこれから心がけようと思います。「経験から学ぶ」の、初めて何かをする時は、「楽しむにはどうしたらよいかという想像力」を働かすスキルが必要という視点に、はっとさせられました。想像力を駆使できないとは、も考えてみます。【保護者】
・支援が伝わる=支援者が生き生きする、目がキラキラする、前向きになる。伝える側の選択で、できない、嫌だ!が、出来た、楽しい!になっていく。頑張りすぎの子には休んでもいい。こだわりすぎてる子には、好きなことにのめり込んでも良い。そういう選択もあることを、教えてあげるのが大切。視覚支援が自閉スペクトラムの方には必要なのが改めて、理解できました。インクルーシブで昔学んだソーシャルライティング講座の話が懐かしかったです。作ったストーリーが、指導や命令になりがちで何とかならないかと、実際佐賀にも行ってみました。病院の会議室で服巻先生の講義があったのですが、80名くらい参加されてて、圧倒されました。また、原田先生の講座があると良いですね。【保護者】
・今日の原田先生のお話しされた中に、自閉スペクトラム症の人は一回やって好まなかったことは嫌いなわけではない事が多いとお聞きして驚きました。 私の職場の小学校で特に低学年の子供達は初めての事に抵抗が激しいので諦めることが度々あったからです。これからはさまざまな療育の方法を交えながら、そして周りの方々と協力しながら個々に合った支援が出来たら良いなと思いました。その為にも私自身がまだまだ学ぶ必要があると感じました。たくさんの情報、資料を提供してくださりありがとうございました。【特別支援教育アシスタント】
・自閉症スペクトラム症の子どもたちを支援するときの具体的な方法や、原田先生の取り組みを紹介してもらえたのでスライド資料もありがたいのですが、今回の講義のようにレジュメがあればキーワードを直接書き込めるのでいいなぁ、と思いました。【保護者】
・視覚が言葉や音声よりも随分と伝える役割が大きいのに驚きました。ASDの3つのタイプの存在、特に受動タイプの存在、確かに置き去り、後回しになりがちだと思いました。それと、3度はチャレンジしてみるということを聞いて、「嫌がるからもうさせないでおこう」ではなく時を置いてまたやってみることも必要なのだと思いました。今回のパワーポイントの資料があれば声が途切れて解りにくくても参考にできたかと思いました。【子育て支援センター職員】
・光とともにの副島先生のアドバイス場面を見ながら、こんな先生が近くにいたらいいのにな~と思っていた矢先でしたので、この研修を受けることができて本当に良かったです。長期記憶・短期記憶・作業記憶の仕組みや、感覚過敏についてや、ASDのタイプにも様々にあること、カームダウンエリアは普段からリラックスできる場所にする、トークンシステム(4分の2でご褒美)やリマインダーやコミック会話やソーシャルストーリーズなど、試してみたいことが盛りだくさんでした。音楽発表会や運動会などで、耳ふさぎをする我が子を見て、普通を強要しすぎていたな。と反省しています。完璧じゃなくても良い。明るく・楽しく、スモールステップで、取り組んでいきたいです。原田先生のように、アドバイスしていただける先生がいらっしゃる機関は、沖縄にはないでしょうか?また、ネットやzoomで相談・コンサルタントできる機関はないのでしょうか?もし、ご存知でしたら、教えていただきたいです。【保護者, 放課後児童支援員】
回答:原田潤哉先生はZoom相談をされておりますので是非こちらからお問合せください。Autism Life Support Hiroshima いんぐりもんぐり&Kure あかり https://www.facebook.com/autismlifesupport/
・視覚優位のため、視覚支援は、ユニバーサルデザインであるということが参考になりました。【放課後児童支援員】
・原田先生の楽しい講座に参加出来て、良かったです。自閉症スペクトラム症児への様々な対応を学ぶことは、学校で働く上では外せないことのように感じています。援助要請と同じくらい、休憩の重要性を再認識しました。自閉症スペクトラム症の3つのタイプも、とても勉強になりました。職場の子どもたちをアセスメントしながら、支援に繋げたいです。【特別支援教育アシスタント】
・今回の講座中で一番印象に残ったのは、自閉症スペクトラム症には、3つのタイプがあること。孤立タイプ、受動タイプ、積極奇異タイプ。その中でも、受動タイプが一番見逃しやすいこと。指示をしたことを真面目に取り組み、責任感があり、過剰適応をしている事があるので、分かりにくいと言う事がありました。以前、そのような子に関わった事がありましたが、数年前は気づく事ができませんでした。頑張れる子だと断片的に思っていました。でも、どうしたらよいか分からず困っていたのだろうなと、今は想像がつきます。支援者が学んでおかないと、大事な時期の子どもたちに、相応しい関わりをしてやれないなと感じました。学び、実践の大切さがわかりました。いつもありがとうございます。今回も内容の詰まった講座でした。【塾講師】
ーーーーー
こちらは原田先生の講座後に理事長の中谷が行った『ワークと対話の時間』の感想です。この日は、原田先生の講座を聞いて気づいたことについて、Zoomのブレイクアウトを使って3~4人のグループに分かれて対話を行いました。
中谷先生が、ワークのところで、飛行場を例に、誰にとっても分かりやすい、利用しやすい環境についてのお話が印象に残りました。聴覚からの情報だけでなく、いかに伝えたいことが相互に伝えられるか、子どもを中心に考えることが大切だと改めて思いました。【行政職員】

ーーーー
さて、子ども達は学習が上手くいくと学校が楽しくなります。一方、学習につまずくと一気に学校が楽しくなくなってしまいます。子どものつまずきに気づき、それぞれに合った学習サポートについてお伝えします。講師は特別支援教育士スーパーバイザーの山田充先生です。11/19~11/25に動画で視聴できる講座です。詳細はホームページからご覧ください。NPO法人日本インクルーシブ教育研究所
不定期ですがメルマガを発行しています。日本インクルーシブ教育研究所の事業や講座情報等について書いています。メルマガご希望の方はこちらからお申込頂けます。購読は無料です。NPO日本インクルーシブ教育研究所メルマガ登録フォーム
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
