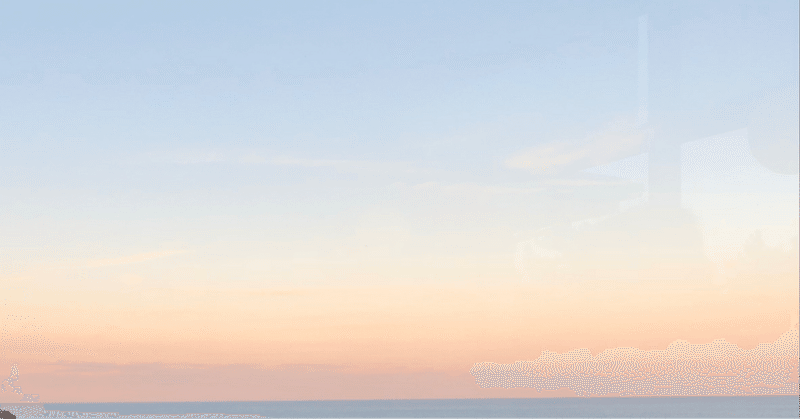
02. 夢のふしぎ
私にはずっと不思議に思ってる事があります。
どうして日本語・英語共に
眠っている間に見る物も、将来叶えたい物事も夢・dreamと1つの単語にどちらの意味も併せ持つのかという事が気になって気になって、仕方がないのです。
他の国はどうなのだろうと思い調べてみると、
フランス語、中国語、韓国語も同じようでした。
ではなぜ地域も文化もそれぞれ違うのにこのような事が起きるのか。
“夢”という単語だけに関わらず、人類の歴史は情報伝達が満足でない時代にも大体似たり寄ったりな出来事が起きているのも踏まえると総体意識っていうのはある程度あるのかなと言う気もするのですが、
私は夢という概念についてこう考えました。
(素人の一意見なのでサラッと聞いてください笑)
元々”夢”という単語には将来の希望としての概念はなく、寝ている間に見る物としての意味を成すものだった。
↓
寝ている間に見る夢では脳の記憶整理をするため実際に起こった様々な事象が組み合わさり見たこともないストーリーが出来上がる。(見たことないストーリーでも自分の培った潜在記憶なので事象化の確率自体は高い)
↓
正夢になる。
↓
夢に未来の時間的意味を持たせるようになる。
↓
将来の夢・寝ている間に見る夢
2つの意味が完成
とか?なんて考えたり。
そして夢は正夢にならなければ仮想現実となり、
未来に関しても選択の連続で未来はいくらでも変更可能であるため、頭に描く未来の映像は仮想現実である。
(これはあくまで時間やこの世の概念が仮想現実と言っているのではなく、未来に付随した各々の未来へのイメージの映像について仮想現実であると言う事です。)
寝ている間に見る夢が将来の夢の定義の補完として機能したり、共通項が見られる事から同じ単語になったのだろうか
などと考えていました。
有識者の方はどのように考えられるのでしょうね。
徒然なるままに、分かったような事をペラペラと話してしまいました。
ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
