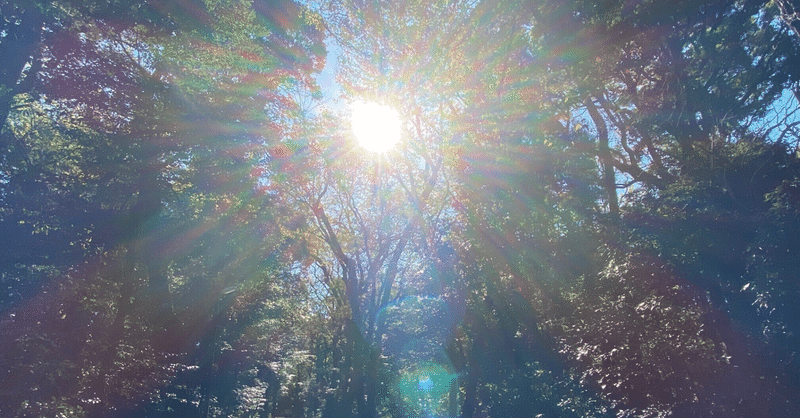
アンチワーク神話解説【アンチワーク哲学】
神話をつくった。百パーセント嘘だとされるフィクションでもなく、百パーセント真実だとされるノンフィクションでもなく神話である。本当か嘘か、誰にも断言できない神話である。
ざっくり言えばこんな話。アンチワーク神話とでも呼ぼうか。
昔の人類は物々交換ではなく、好きに貢献し合っていた。平等なまま都市をつくり農業を営むことが可能であり、それは国家やお金、格差の登場とはなんの関係もなかった。国家は権力欲の強い乱暴な男がつくった。そして彼は国民を逃がさないために壁をつくった。国民を都合よくコントロールするためにお金もつくった。こうして労働が生まれた。労働と金と国家は人々を怠惰でつまらない存在へと貶める結果となり、人々もその価値観を受け入れてしまった。現代になっても、その価値観は消えず、結果として社会は様々なトラブルを抱えてしまった。
さて、これと比較するために、もう一つほぼ真逆の神話を用意した。こっちは、多くの人が「たぶんこういうことがあったんじゃね?」と思ってそうな神話である。
こっちは以下のような話である。
昔の人々は物々交換をしていて、ある天才がお金を発明して物々交換の不便を解消した。また別のある天才が農業を思いついてみんながそれに飛びついた。農業を発展させればその管理の必要性によって国家が誕生した。国家が誕生し色んな悲劇はあったものの、現代になって大部分は解決された。
とりあえず雑に労働神話とでも呼ぼう。
労働神話は人々の意識に上ることはない。しかし、おそらく多くの人の価値観と、社会システムは無意識のうちにこうした神話の上に成り立っている。
「人は半ば強制されなければ、自由に貢献し始めるようなことはあり得ない」という前提がなければお金の存在が絶対視されることはないし、お金で半ば強制される労働も突然視されない。そして、お金の取引を強制的なものに仕立て上げる国家もそうだ(とはいえ、現代の福祉国家の役割は多岐にわたっていて、この神話を排除しても一概に国家の廃絶という結論が導出されるわけではない)。
また、農業や都市の建設など、大規模で労働集約的なプロジェクトは、権力による強制が必要不可欠であるという価値観も、こうした神話を基盤に置いている。
とはいえ、労働神話は、様々な考古学的、人類学的知見により否定されつつあるようだ。それに変わるシナリオも、あちこちで提示されている。
しかし、あくまで証拠に基づいてつくられた学術的なシナリオは控えめであり、人々の想像力へ訴える力が弱い。国民全員が『万物の黎明』や『負債論』『反穀物の人類史』『石器時代の経済学』といった書物に目を通し、理解するようなことは期待できまい。
労働神話が人々にインストールされているからと言って、彼ら全員が『国富論』や『社会契約論』を読み込んでいるわけではない。僕も読んだことがない。こうした書物のエッセンスが戯画化され、あちこちで簡易版が語られたからこそ、知らず知らずのうちに不文神話が形成されていったと考えられる。
なら、アンチワーク神話というオルタナティブを普及させるには、鈍器のような書物から汲み取ったエピソードを戯画化して、広めていく必要がある。
そこで僕が成文神話をつくったわけだ。これがあちこちで曖昧なままに語られていくことによって、不文神話はつくられていく。そうなればこれが神話であることすらも忘れ去られていくかもしれない。
とはいえハードルは高い。
労働神話という不文神話が強力なのは、それが現行の社会システムにピタリと合致するからである。オルタナティブなアンチワーク神話は現行の社会システムには合致しない。ただし、現代に蔓延る苦しみの原因を説明することは可能なので、その点が上手くかみ合えばいい広まるかもしれない。
苦しみを説明するということは、宗教に近い営みだろう。だが、まったく根拠がないわけではない。先述の通り、僕は鈍器のような本を文字通り穴が空くまで読んで、そこからこのストーリーを導出した。僕は僕がつくったアンチワーク神話がさほど現実離れしているとは感じない。少なくとも現行の労働神話よりはそうなのだ。
たとえば、「人類初期の経済がなにか?」という点について。
■人類初期の経済システムについて
そもそも、このテーマ自体がミスリード的である。「人類初期の経済システムがなにか?」と問われたときの最も誠実な返答は「そんなものはない」である。
地域や文化によってそれは大きく異なるだろうし、場面によってもまったく別の体系になるはずだ。食べ物を分け合うときは誰も計算を拒否して大盤振る舞いをしていたとしても、誰かが誰かにけがを負わせたときには「指一本=牛一頭」などといった複雑な計算式を適用する。そんな文化もあっただろう。だが、間違っても近隣の人々と日常的に物々交換をしているような社会は存在しなかったと言ってもほぼ差し支えないであろう。グレーバー『負債論』によれば、過去の人類学者たちは誰一人として日常的に物々交換を行っている文化を発見することはなかった。かわりに多種多様な経済システムの社会を発見したのである。
物々交換とは無償での貢献を誰しもが拒否するシステムである。自分がなにかを貢献したなら、同等かそれ以上の貢献を受け取りたい。そのような感覚が普遍的に蔓延しているのでなければ、物々交換は生じ得ない。が、そのような感覚で完全に覆い尽くされている文化はいままで(そしていまでも)存在しなかった。
とはいえ、初期状態の人類社会がすべて無償での贈与と利他心だけで覆い尽くされていたかのように記述するのもミスリードである。それがアンチワーク神話が神話である理由の一つであり、おそらくそんな社会はこれまでもこれからも存在しない。だが、物々交換の神話よりは説得力はあるだろうし、現実に近いはずだ。
この点は進化のプロセスから考えても妥当な結論であるように思われる。競争的な種は相互扶助的な種との競争に敗れる。長く生き延びるのは、明らかに無条件で支え合い、競争を避ける相互扶助的な種であった。人間とは個体の強さではチンパンジーに遠く及ばない。赤ん坊が大人になるまでの時間がかかりすぎるし、世話をするのにとんでもなく手間がかかる。とてもじゃないが協力しなければ種が成り立たない。だからこそ人間は無条件の相互扶助を進化させてきた。言い換えれば人間は相互扶助を欲望するように進化に動機づけられてきたのだ。
どちらかと言えば、底抜けの利己心とは(個体として圧倒的に人間よりも強い)チンパンジーの特徴なのだ。
■初期の労働(と、僕たちの目に写るもの)は遊びだった
さて、命令されることのない人々の社会において、生産活動はどのようなものだったのか? 僕たちが見下しがちな現代の原始社会をみれば、彼らの生産活動は労働と呼べる代物ではなく、遊びと見分けがつかない。
好きな時間に好きなだけ取り組む。だったらさぞかし、雑な仕事ぶりなのかと思いきやそうではない。彼らは現代のエンジニアにも構造が理解できない精工な道具や、雑草の一本も生えない整然とした畑をつくりあげる。彼らは楽しみながら生産活動に没頭しているのである(日本人なら、縄文土器のデザイン性をみて驚嘆した経験があるはずだ)。
■農業や都市は国家抜きで組織化されてきた
さて、牧歌的なエデンの園の話はここまでにしておこう。家族と友達としかかかわらないような小さな社会なら、貸し借りの概念を除外した相互扶助社会が可能かもしれないが、農業や都市を発展させていくためには、そうはいかない。そんなふうに思う人は多いはずだ。
一般的な神話では、人々は農業を発明し、社会規模を拡大するにつれて、ヒエラルキー構造を発展させざるを得ないと考えている(だから、僕が労働や支配のない世界を主張したとき、稀に「農業以前の社会に戻りたいのか?」という批判が返ってくるのである)。
実際のところ、農業をしながらヒエラルキー構造をつくらなかった社会。権力抜きで巨大な都市を生み出し何世紀も維持してきた社会などなど、様々な実例が存在していたらしい。
また、人類は古代の天才によって農業が発明した途端に、我先にと農業に飛びついたわけではない。農業の萌芽はあちこちにあり、季節によって農業と狩猟採集を行き来するような人たちもいた。狩猟採集民とは自然の中で暮らす人々であり、種を撒けばそこから芽がでることなど常識であり、それを大規模にやれば大規模な収穫が得られるであろうことも常識であった。実際にそれを試したりもした。だが、朝から晩まで農地に縛り付けられてまでそれをやる必要が彼らになかったというだけの話である。
結局のところ、農業、定住、都市、身分格差はセット販売ではなく、ばら売り可能で、互いにほとんど関係のない商品なのである。
■国家とは略奪者だった
みんながトップダウンの命令系統の必要性に合意して社会契約を結んだ。そして、善意溢れるエリートをトップに据えて国家が誕生した。
このようなぼんやり思い浮かべられているシナリオは、どうやら間違っている。初期の国家とは基本的に略奪者であり、暴力を独占しながら税を取り立てる運動体であった。古代の人々にとっては国家は単なる邪魔者だったのだが、それを暴力とプロパガンダでなんとか国家が必要であることを人々に納得させようとしたのである。
■まとめ
ざっと根拠を並べたが、ほんとうに「ざっと」である。詳しい情報は併記した参考図書を参照して欲しい。
さて、労働神話が誤りで、アンチワーク神話が正しいとなんとか説得できたとしても、たかだか神話である。多くの人々は、自分は事実だけを根拠にした合理的な価値観の所有者であり、神話などに左右されることはないと思い込んでいるように見える。そのため、古ぼけた神話に自分の行動原理が左右されていたとも思わず、新しい神話に身をゆだねようとも思わず「ふーん、そうだったんだねぇ」で話が済まされる可能性の方が高い。「なんてこった! 俺は騙されてたんだ! 現代社会のシステムはイカれてるではないか! 革命しよう!」などといきり立つ人はごくごく少数なのである。
もちろん、この神話を信じるからと言って、即座にお金や国家の廃絶という結論が導出される必要はない。お金や国家はたしかに邪な理由で誕生したし、さまざまな不具合が生じている。それでも、ある程度は有益な目的に貢献しているはずだ。根本的に取り除くかどうかは、また別問題である(僕は、だんだん骨抜きにしていき、最終的には根本から取り除くべきであると考えているが)。
しかし、アンチワーク神話は不具合を視界に入れ、その原因を説明する。その先にどのような結論が生まれるかはわからないとはいえ、視界に入れなければ始まらないのである。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
