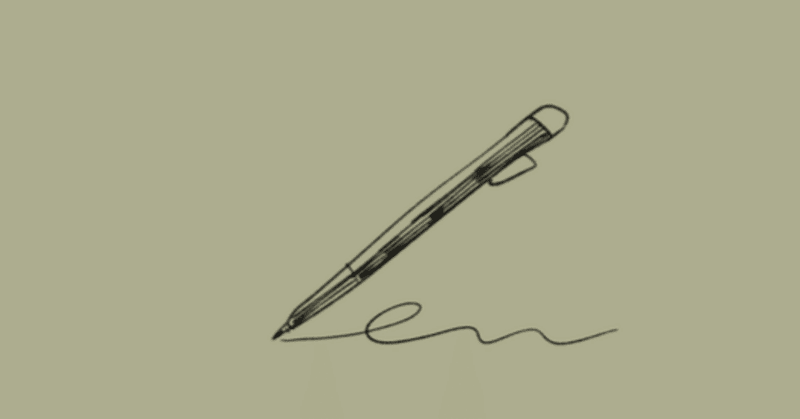
AIに負けない人間の創造力
生成AIという言葉もずいぶん一般化しました。文章やイラスト、映像や音楽まで。これまで人間にしかできないといわれた創作の領域にどんどんAIが進出してきています。
上の文章、「進出」だけ太字にしたのは意味があって。AIの進化を「侵略」と表現する人もいるんですよね。いわゆるAI否定派と呼ばれる人たちです。著作権や倫理的な問題はありますが、AIのことを知ろうとせずに、「嫌い!危険!」と拒絶するのはもったいないと思うんです。食わず嫌いだったものが美味しくって大好きになることもありますからね。
「知らない」と「嫌いは」という感情は似ているという記事の考え方がすごい好きなんです。簡単にいうと、知らないものは嫌いと勘違いしやすい、知れば好きになることもあるよ、という考え方です。AIに嫌悪感を持っている人の多くは「よく知らないから嫌い」と感じてる気がしてなりません。
デザインの現場でもAI化が進んでいます。ぼくは積極的に活用しようと日々AIの勉強していますが、知れば知るほど痛感することがあるんです。それは、AIに負けない人間の創造力です。
AIの凄さは、突き詰めると「驚異的なスピード」に行き着きます。逆に言えば、時間さえかければ人間はAIのアウトプットに追いつけるということです。プロのイラストレーターが数日かければAIよりも素晴らしい絵が描けます。絵心がない人でも、10,000時間も練習すれば相当な絵を描けるようになります。
でも、いくら時間をかけてもAIでは創造できない領域があるんです。たとえばこんな文章です。

このポスターは、朝日新聞読者賞(2023年度)の入賞候補作のひとつです。宮沢賢治「風の又三郎」の書き出しを引用した、“新しい読書体験” というテーマの作品です。
どっどど どどうど どどうど どどう
この書き出しは、
AIにはまだ難しいと思う。
この作品を見て、たしかにそのとおりだ! と思いました。どんなに膨大な学習データを与えても、こんな文章で物語をはじめるなんてAIにはできないでしょう。たとえできたとしても、それは宮沢賢治の模倣でしかありません。
AIの登場によって創作の裾野は広がりました。誰もがより高度な表現を手軽にできるようになりました。登山でいえば、今まで素人には5合目が限界だった山に、8合目まで行けるロープウェイができたようなものです。
そんな状況を見て、「最近の登山者はマナーがなってない」、「昔は8合目まで登るのに3年かかったもんだ」と嘆くことにどれほどの意味があるのでしょうか。
それよりも、「簡単には登れない山頂を目指してやる」と静かな闘志を燃やしたいとぼくは思っています。
そんなことできるわけないよ、という声が聞こえてきそうですね。でも、いいじゃないですか。たとえ登りきれなくても、上を目指すことに意味はあると思うのです。
紹介した作品以外にも朝日新聞読者賞の入賞候補作には、素晴らしい作品がたくさんあります。気に入った作品に投票することもできるので、ぜひ覗いてみてください。公開は5/8(水) 10時までみたいです。創作意欲が刺激される作品ばかりなのでオススメですよ!
https://www.asahi-aaa.com/dokushashou/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
