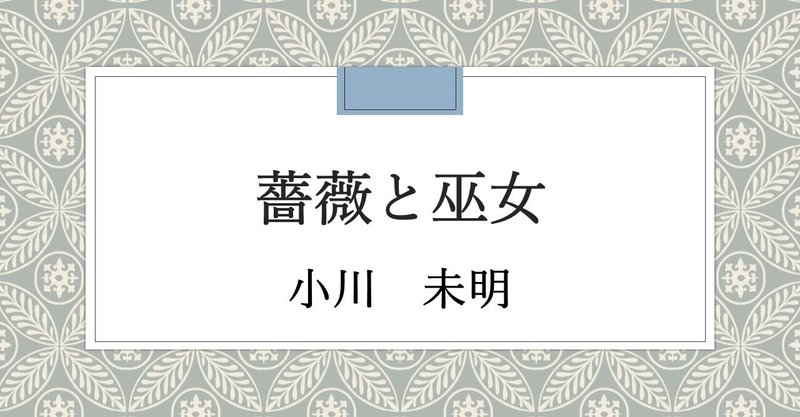
「薔薇と巫女」により小川未明の手がかりを探る
ほんの感想です。 No.31 小川未明作「薔薇と巫女」明治44年(1911年)発表
小川未明の童話には、二つの魅力を感じています。一つは、ひたむきに大切なものを慈しむ存在を描いていること。例えば、「赤い蝋燭と人魚」や「牛女」には、「我が子の幸せを願う母」が登場します。いずれも、強力ではない存在が、惜しみなく子を慈しむ心情が、哀調とともに感じられます。
もう一つの魅力は、「わからない」と感じてしまう作品が少なからずあることです。仮に喜怒哀楽が、桃色、赤色、青色、黄色で表すことができるとします。面白さを感じる物語では、色彩の移り変わりがあります。しかし、「わからない」作品は、この四色を混ぜてできた色が、多少の濃淡はあるものの延々と続くイメージです。「せめて、この濃淡の面白さだけでも味わいたい」、と思わずにはいられません。
以上のような小川未明への思いとともに、その短編小説「薔薇と巫女」を読んでみました。童話を書く前の小川未明の作品です。そのタイトルからは、均衡のよくない、妖しい雰囲気が伝わり、勝手に、物語の暗い先行きを妄想してしまいます。
―・―・―・―・―・―
「薔薇と巫女」は、ある夢を見た後に母を失った青年が、以後、「不思議な怖ろしい話」に興味を持ち、ある巫女を探しに旅に出る、という物語です。タイトルにある「薔薇」は、青年が夢の中で見た黄色い薔薇のこと。そして「巫女」は、彼の村のある家に訪れ、不思議な力を示したという女性のことです。
巫女の話を伝え聞いた青年は、巫女に会うため、彼女の家があるXという町に向かいます。その途上で、巫女が、ある金持ちの家の娘であることを知ります。そして、
・巫女が、幼い頃から異様な行動をして異常な力を発揮したため、家に閉じ込められていること。
・家の門を破って外の世界に出歩いているらしいこと。
といった話を耳にします。
旅により、不思議な巫女に対する気持ちは、熱を帯びていました。それは、次のように描かれています。
彼はそのような女を見たいと思った。そしてそのような女に愛されたいと思った。この好奇心は、彼を臆せずに秘密の門の中に導いた。ただ巫女の黒い大きな瞳でじっと見詰められたい。魔女の手に抱かれて、その鳶色の縮れた長い頭髪の下に顔を埋めたい。そして赤い頬と熱い唇に触れてみたいと旨の血潮が躍った。
結局、青年は、巫女に会うことができぬまま、故郷に戻り、この物語も終わります。
―・―・―・―・―・―
「この話は、何だったのか」と思いながら、「刹那の印象を感覚的に描く短編小説に精彩を放ち」という、岩波文庫「日本近代短編小説選 明治編」の小川未明に関する紹介文中の言葉を思い出しました。
青年が、夢に感じた暗く淋しい気分や焦燥感は、その後の物語で、視覚、触覚、聴覚に訴える言葉を通じて、再現されていると思えてきました。そして、旅の物語を通して、青年の夢の気分が、より、鮮明に感じられるとも思えてきました。
「薔薇と巫女」で経験した読み方は、小川未明の「わからない」作品を読む上で、ヒントになるかもしれない。そんな予感があります。
ここまで、読んでくださり、どうもありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
