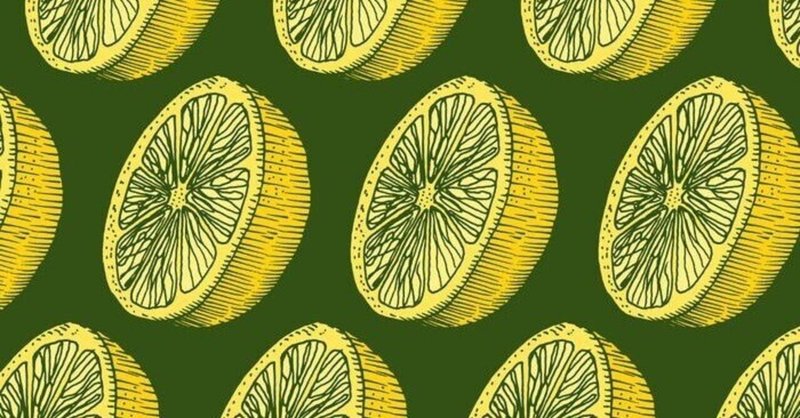
檸檬読書日記 キップをなくして、虎になって、井上ひさしは笑う。 5月6日-5月12日
5月6日(月)

もりもり。花も渋滞している。
集合体恐怖症はこういうのも駄目だったりするのだろうか。自分も若干あるのか、若干うってなってる。うっ。
自分で撮っておいてね。
綺麗が綺麗のままで終わらないこともあるんだなあ。しみじみ。
5月7日(火)

買った本。
ようやくカフカが買えた。
『十二支外伝』はBlueskyで教えてもらい気になって買った本。
12の動物のことが書かれている。これ、シリーズになっていて、他にも魚や虫や鳥なんかがあって、どれも良さそうで集めたくなる。得に虫が気になるなあ。欲しい。
そういえばカフカ、5月にも新刊が出るのだとか。ついていた帯に書いてあって、飛び上がる。今度は短編ではなく、言葉を集めた断片集らしい。
んー、気になる。買おうかなあ。
みやこしあきこ『ちいさなトガリネズミ』を読む。児童書。
トガリネズミの、何気ない日常を描いた作品。
この作品、本屋の店員にオススメされて読んだものなのだけれど、オススメされなければきっと出会っていなかっただろうなと。だから本当に感謝しかない。凄く好みだった。
絵も、アナログな感じが良くて、色鉛筆や水彩のふわっとした色合いに、鉛筆の影が雰囲気があって魅力的。トガリネズミも、可愛すぎない可愛らしさがあって、総じて可愛い。(何を言っているんだ?)
内容も、トガリネズミが朝起きて仕事に行って帰って寝るまでのことや、歩いていてテレビを拾ったことや、友達が家に来た日のことなど、本当に何気ないことが書かれている。日常中の日常。
けれどその何気なさが堪らなくよくて、自分もこの中に溶け込んでいくような、落ち着ける作品だった。
これから先も、こうやってトガリネズミの日常は続いていくのだろうなと思える終わり方で、2、3と続編が出て、何時までもこの世界が続いてほしいと願わずにはいられなかった。
なので是非とも2を、どうかどうか。
(Amazon貼り付け、元の大きさに戻ったのか。良かったー。やはりこの方が見やすくていいな。是非ともこれからもこのままでお願い致しまする)
ヴァンダ・プシブィルスカ『少女ダダの日記 ポーランド一少女の戦争体験』を読む。
(略)恐ろしい、恐ろしいことばかり。ああ、戦争は世界を破滅させるのだ。人間を滅ぼし、殺すのだ。恐怖をいっぱいにまき散らし、生活という生活、喜びという喜びの息の根をとめてしまうのだ。そして、なにものにも替えがたい、だれにとっても欠くことのできない友情--人と人とのその友情、民族のあいだの親善を傷つけ、踏みにじってやむところがないのだ!!
5月8日(水)
ああ、ようやく怒涛の3日間が終わった。
でも5月は結構忙しいんだよなあ。(遠い目)
リゾートで優雅にゆったり本読みたい。
いや、やっぱり家でのんびり本読みたい。(出不精なもので)
池澤夏樹『キップをなくして』を読み始める。
ふと気づくと、キップがなくなっていた。
外に出られなくなってしまった少年・イタルは、同じようにキップをなくして改札から出られなくなった子どもたちと共に駅の中で暮らすことに。
子どもたちの中には、幽霊となって駅中にとどまる少女・ミンちゃんがいて…。
ひとりぼっちになってしまうミンちゃんのために、子どもたちは動きだすのだった。
鉄道冒険小説。
子どもたちが駅名読みクイズをやるシーンがあるのだが、どうしてそう読むんだばかりで、1つも読めなかった。でもこれはきっと、殆どの人が読めない気がする。
小利別
愛冠
足寄
勇足
様舞
さぁ、なんて読むでしょうか。
(答えは1番下)
難しいすぎるよなあ。
北海道の地名はアイヌ語から来ているから、読めないものが多いらしい。
寺山修司『さみしいときは青青青青青青青 少年少女のための作品集』を読む。
でも、ほんとうにことばに重さなんてあるものでしょうか?
ぼくの答。
「ことばには重さはないけど、愛には重さがあるのです」
ほう。
5月9日(木)

「LADUREE」のマカロンをもらった。
味は、チョコとミントとフランボワーズとキャラメル。
中でもキャラメルが濃厚で美味。ミントは、歯磨き粉でなく本来のミント味でなかなか。後のふたつは間違いなし。
激甘だけれど、砂糖入れない紅茶と交互に口にすると砂糖代わりになってとてもよい。合う。
箱もなかなかお洒落。飾っておこうかな。
池澤夏樹『キップをなくして』を読み終わる。
「(略)死んだ者がどうなるか知っているかね?」
(略)
「別の世界に行く。現地から預かってきたものを返して、他のたくさんの魂と一緒になってしばらく暮らし、互いに混じり合う。やがて自分は自分だという気持ちが薄くなって、ぜんたいの中に溶け込んで、長い歳月の後、別の生命となってまた生まれ変わる。死ぬ前の自分のことはやがて忘れる。そういうことらしい」
「死んでからわかったんだ。人と比べちゃいけないんだよ。わたしだって初めはなんで自分だけがって思ったけど、でもこれはしかたないことなの」
この作者の考え方というか捉え方、とてもいいなと思った。
比べることは、本当に不幸なことだ。キリがなくて、落ちるばかり。そうは分かっていても、難しいんだけど。
でも、自分ばっかりではないのだと思う。だから比べたって仕方ない。与えられたものは人それぞれで、同じものはないのだから、比べたって違うのは当たり前なんじゃないかなと。
表面は良く見えても、それぞれに壁や悩みはある。お金持ちだって、幸福とは限らず、貧乏だからといって不幸とは限らない。
人だから、どうしたって他の人と比べたくなってしまう。けれど、一見幸せそうに見える人たちでも、それぞれに自分とは違う悩みや苦労がきっとある。自分だけではない、そう分かっていれば、だんだんと気にならなくなってくるのではないかなあと、思ったり。
駅で暮らすことになった少年少女たちは、子どもたちで暮らすことで、自分たちで考え行動する力を身につけていく。
癖のある人物が入ってきて、調和のなされていた世界が崩されたり、絶対だと思っていたものが覆され、強制的に考えなくてはいけなくなったり。子どもたちの中では小さく短い世界だけれど、人生を見ているようで、考えさせられることが多かった。
自分は知らないことだらけで、ほう、というものばかりだったけれど、鉄道好きならかなり湧く、堪らぬ1冊なのではないかなと。
鉄道に興味がなくても、駅内で暮らしたり特殊な仕事をしたり、ワクワクと楽しめる。
切なさもあるけれど、それぞれがそれぞれの道に進んでいく姿に胸を打つ、読んで良かったと思える作品だった。
この方の作品、初めて読んだけれど、とても好みだったから他の作品も読んでみたいなあ。探してみよう。
ヴァンダ・プシブィルスカ『少女ダダの日記 ポーランド一少女の戦争体験』を読む。
そうよ、パーシャ、この世はとても悲しいもの。けれど、わたしたちは悲しみのうちだけに生きてゆくことはできないんですもの。たとえまわりが灰色だとしても、せめてわたしたちの笑いがすこしでもあたりを明るくするように、笑わなければならないんだわ。わたしたちはこうどの笑いが、すべての者の胸に、人生によせるという希望をよび起こさなくては!!覚えていてね、パーシャ。この希望がポーランド人にはいまとってもとっても必要なのよ。だから、たとえ悲しみのどん底にいても、喜びと笑いは失ってはならないのよ!!そうなのよ、パーシャ!
どの国の人にとっても、どんな境遇の人にとっても関係なく、笑いと喜びは決して忘れてはいけないものだと思う。
笑っていたって、悪いことも辛いことも起きるかもしれない。笑いたくない状況の時だってたくさんある。だからずっとじゃなくていい。口角を上げて、笑うふりだけでもいい。気づいた時にニッと笑って、失わないでいてくれたら、世の中は少し明るくなるのではないかなと思ったり。そして自分自身の気持ちさえも。
5月10日(金)
ポップコーン用のトウモロコシの種を、面白半分で植えたら出てきてびっくり。
しかも10粒植えて9本出た。凄い発芽率。
このまま育って収穫出来るといいなあ。
スイカも芽が出てきたし、楽しみ。
中島敦『山月記』を読む。
何度も読んでいるというか、習っているけれど、当時は真剣に聞いていなかったのか真面目に取り組んでいなかったのか、今読むと違った印象を受けた。
虎になったということばかりに気を取られていたけれど、違う点で考えるとなかなか興味深い。
しかし、何故こんな事になったのだろう。分らぬ。全く何事も我々には判らぬ。理由も分からずに押付けられたものを大人しく受取って、理由も分からずに生きて行くのが、我々生きもののさだめだ。
そして獲物が目の前を通ると、人は消え、獣となる。再び戻った時には、既に血に塗れていた。
これは恐しいことだ。今少し経てば、己の中の人間の心は、獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えて了うだろう。
一体、獣でも人間でも、もとは何か他のものだったんだろう。始めはそれを憶えているが、次第に忘れて了い、初めから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか?(略)
己の中の人間の心がすっかり消えて了えば、恐らく、その方が、己はしあわせになれるだろう。だのに、己の中の人間は、その事、この上なく恐しく感じているのだ。
「虎」という獣に変身せずとも、人は同じような状況になる時がある。
それは、戦争で人を殺めてしまった時。
戦争になると、その地に住む人たちは理由も分からず、大人しく従って戦場に赴く。
戦争が激化すれば、己の中から人は消え、敵と言われた者たちを追い、命を奪っていく。勝敗がついた時、目覚め、人が戻り、手は血に塗れていた。
そして、なんてことをしてしまったのかと、恐ろしく思う。
けれどまた始まってしまえば人は消え、その方が楽だとだんだんと受け入れたくなる。正当化したくなる。でも同時にそれはとても恐ろしいことであり、いけないことだと、抗う。葛藤して葛藤して葛藤して…。
しかしやがて…。
発表した年を考えると…と思うところもあるが、作者自身、そんな意図はないのかもしれない。でもどちらにせよ、人というものを考えさせられるものがあった。
人は誰でも虎になりうる可能性があるのかもなあと。
昔昔に読んで当時は何も感じなくても、今読むと違う印象を抱くから、読み返すのも良いかもな。
ヴァンダ・プシブィルスカ『少女ダダの日記 ポーランド一少女の戦争体験』を読む。
しかし、恐ろしい時代だ。1時間、1日、1分とても、自分のいのちに人は確信がもてないのだ。
5月11日(土)
アニメ『葬送のフリーレン』を数日前から少しずつ観て、ようやく半分までいったけれど、なかなか良くて遅れてハマる。
流行っているのも頷ける。
何より、個人的にフリーレンの性格が凄い刺さる。あの淡々とした、感情の起伏が少ない感じがたまらん。
男女関係なく、冷静沈着で余裕のある人って好きなんだよなあ。
どうしよう、漫画買おうかな。
今買ってしまうか、完結してから買うか。うーん、悩む。(おめでたい悩み)
人気な作品なら絶版になることはないだろうから、完結してからでも大丈夫かな。うーん。
井上ひさし『四十一番の少年』を読む。
最初から最後まで切ない。苦しくもある。
井上ひさしといえば、ユーモアに満ちた人、というイメージがあったけれど、この作品にはそういう要素が一切ない。
3つの短編が収められているが、どれも孤児の少年の話で、繋がりはないものの、同じ辛さと切なさがある。
親と暮らしたいけれど、様々な理由でそうできない。
そしてどの少年も、弟を大切に想っている。
3つの短編、どの話も決して希望的な終わりというわけではない。むしろ最後まで切ない。特に最後の話など、最後が切なくて切なくて、少年の優しさに胸を締め付けら、それぞれの気持ちを思うと悲しくなってくる。
それでも、不思議と悲観的なものはない。だから重苦しく残ることはなく、ただただ切なさがじんわりと染み込んでいく。
この作品は、井上ひさしの幼少期時代の体験が含まれた自伝的小説ともいえるらしい。
井上ひさしは、幼くして父を亡くし、貧困から一家で暮らすことができず、養護施設に入れられてしまう。養護施設での生活は、苦しく辛いものだったようで…。ただ、この本に書かれている出来事が、全て事実に基づいているわけではなく、創作的部分も含まれている。
だからどこの部分が実際に起きたものかは分からない。けれど養護施設での生活が苦しく辛いものであることは変わりなく、そう考えると苦しくなる。
厳しい幼少期時代を過ごした人が、笑いを書き続けていたと思うと、考え深くもある。
そして、彼が書いた「ひょっこりひょうたん島」の歌詞。
苦しいこともあるだろさ
悲しいこともあるだろさ
だけどぼくらはくじけない
泣くのはいやだ笑っちゃおう
「泣くのはいやだ笑っちゃおう」
作品を読んだ後だと、違った風に見えてくる。言葉が深く刺さってくるようだった。
そしてこの後に言うのだ「進めー!」と。
解説で、「金達寿が、『人はあまり悲しくなると笑い出すものである』」と書いてあった。きっとそうなのだろう。
人は、ある線を超えると、笑いたくなる。それは本当に笑いたい訳でも、おかしいと思っているわけでもなく、自然と込み上げてくる生理現象のようなもので…。
だから井上ひさしも、あまりにも悲しくてあまりにも苦しく辛くて、笑うしかなかったのかもしれない。けれどそれだけではなく、彼はその笑いを糧にして、前へ進んでいった。笑いの道を選んだ。
もしかしたら「ひょっこりひょうたん島」の歌詞は、皆に向けたものでもあるけれど、井上ひさしがずっと自身に言い続けた言葉だったのかもしれない。そう、思ったり。
井上ひさしらしい笑いやユーモアはない。けれど、こういうものもいいなあと、新たな一面を見られて良かったと思える作品だった。
エドガー・アラン・ポー『黒猫 ポー傑作選1』を読む。
「ウィリアム・ウィルソン」を読み終わる。
早く何が起きたか言ってくれ。
それが最初に抱いた正直な感想。
引っ張られて引っ張られて、回りくどくて、凄くもどかしい。ただ、だからこそ惹き込まれる。先へ先へと読み進めたくなる。
ウィリアム・ウィルソンは学生時代、自分と同姓同名の少年と出会う。その男は背格好から誕生日まで自分とそっくりで、周りからも兄弟なのではないかと思われていた。
だが親族でも、ましてや兄弟でもなく、赤の他人で…ウィルソンは、自分と張り合える唯一の人物として、最初は恐ろしさはありつつ友情めいたものを持つ。だが、同姓同名氏は、反撃するようにウィルソンの口調・声を真似し、囁き始め、どんどんと自分と近づいていく。そんな同姓同名氏に恐怖を抱き、ウィルソンはとうとう逃げ出すのだった。
だが…。
まさに亡霊だ。
似たような作品はいくつかあるけれど、その中でも明解で読みやすかった。
やはりこの人の作品は、ニマニマ顔が目に浮かぶ。
5月12日(日)
今日はカボチャとオクラを植えて、ニンニクを収穫。

見せびらかしたいくらい今年はたくさん出来て嬉しい。

カモミールも咲いていたから収穫。
去年の種が零れたみたい。優秀じゃ。
干してお茶にする。カモミールティー。
凄くいい匂いで、お茶になるのが楽しみ。
石井千湖『文豪たちの友情』を読む。
「志賀直哉と武者小路実篤」編を読み終わる。
友情とは関係ないけれど、武者小路実篤の少年時代のあだ名が「おはぎ」というのが可愛いなと思った。
まんじゅうやお汁粉など、あんこ菓子が好きだったのが由縁だとか。
書簡の署名もときどき「OHAGI」になっている。かわいい。
可愛い。
武者小路実篤は、志賀直哉が忘れて自分に電話をかけなかった時、怒ってハガキを出したのだとか。
「僕はおこつてゐる、ほんとうにおこつてゐる、あとで電話をかけておこるが今はハガキで怒る」
可愛いな。
そして2人は失恋と歩き旅で友情を深めたのだとか。ほう。
どんなに好きだなあと思っていも、醒めるものだよなあと、また思い知らされる。
好きになってハマるのも早いけど、醒めた瞬間の切り替えも早いんだよなあ。基本的にはプラス方式だけれど、これは絶対駄目をやられてしまうとどんなに良いことをしていても、一気に興味が…。
自分でも呆れるほどのこの極端さをそろそろどうにかしたい。
そもそも最初にガッと上げるからいけないんだぞ、だから落ち着け自分。ひっひっふー。(?)
これからはフリーレンのように冷静に生きよ。目標。
あぁ、そろそろ本棚整理しないとなあ。
本が増えてごちゃごちゃしてきた。
来週、やる、きっと。
『キップをなくして』駅名の答え。
しょうとしべつ
あいかっぷ
あしょろ
ゆうたり
さままい
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
皆様に笑顔が溢れますよう、願っております。
ではでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
