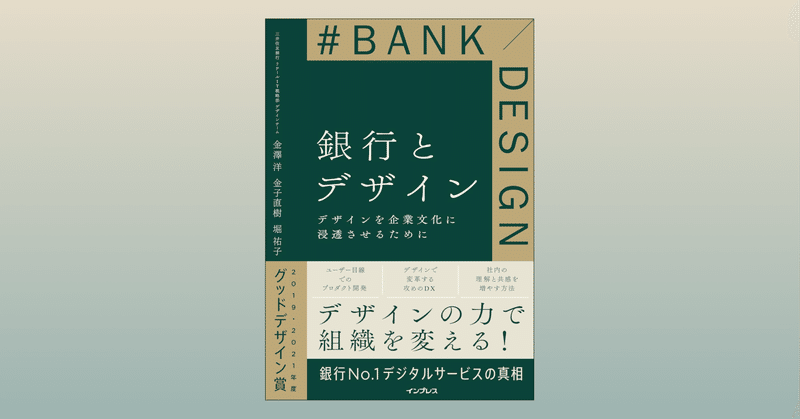
【読書録】銀行とデザイン デザインを企業文化に浸透させるために
一般的に企業にとってデザインという要素は必ずしも重要視されていない。たとえその役割をわかっていたとしても、外部の会社に委託してしまうケースが多いようだ。
三井住友銀行(SMBC)もそんなやり方を採用していた金融機関だったが、2016〜2017年、来るべきDX時代の機運を敏感に捉えデザインの可能性を重視することになり、著者であるUXデザイナーたちを自前のインハウスデザイナーとして採用した。
本書では、銀行という組織・文化の中でデザインの重要性を伝えたりUXを改善しようと奮闘したりするリアルな体験が綴られている。
デザイナー志望者として、とても面白い内容だったので簡単に紹介したい。
本書の構成は以下の通り。
第1章:銀行のデザインシフト
第2章:チームとしての始動
第3章:デザインチームの足跡
第4章:デザインチームの今
第5章:これからのデザインチーム
企業にデザインを浸透させる
著者たちはSMBCのリテールIT戦略部(個人や中小企業向け)に籍を置くことになった。
当初はデザイナーとして単に「見た目を整える」仕事も請け負っていたが、それではインハウスデザイナーとして在籍している価値が見出せないという焦りがあった。

そこでさまざまな企画にちょこちょこと顔を出し、意見を通わせるようにした。業務の全体像が大まかに見えることでSMBC全体のデザイン全体の検証・改善にもつながる。
それまで著者たちは、他の社員からはどう接して良いかわからない、何をお願いすればいいのかわからない「得体の知れない存在」としてみられていたようだ。
とにかく顔を出して仕事に関わっていくことでことで「こんな仕事もしてくれるんだ」と認知が進み、企画の上流段階で関われる機会が多くなったという。
これはデザインがまだ浸透していない会社において、とても良いやり方だと思った。
自分も学生時代に立ち上げた同好会から部活へ昇格させるという経験があった。とにかく全く関係のない分野でも積極的に活動を行って認知度を高め、結果的に他の学生や学校側に存在を認めてもらったことに通づるものがあると感じた。
入社して1年も経つと、個ではなくチームとして活動を本格化させていく。

まずはバラバラに活動していたデザイナーをチームとしてまとめるためにワークショップを行い目標やビジョンを策定、インハウスデザイナーと外部パートナー企業のデザイナーとの違いもはっきりさせた。
また社内にデザインを浸透させるための勉強会やワークショップ、noteでの情報発信など社内外へ活動を本格化さていった。
こうした努力もあり、徐々に「単に見た目だけを整える人」というイメージから「イメージを具体化し、顧客の価値を考えるUXデザイナー」へと変貌を遂げた。
リニューアルプロジェクト

著者が担当したプロジェクトにSMBCアプリ・コーポレートサイト・SMBCダイレクトの3つのリニューアルがあった。
このうちSMBCアプリは2019年のグッドデザイン賞を受賞するなど大きな足跡を残している。
これらのプロジェクトを進める中で実施したデザインに関する手法をいくつか紹介する。

まずは、デザインツールを導入したことである。
それまでExcelでワイヤーフレームを作り資料作成しパートナー会社へ渡して修正作業…という時間のかかるプロセスだったが、Figmaのようなデザインツールで企画担当者やパートナー会社にリアルタイム共有することで意思の疎通が容易になりスピード感を持って進められたという。
また、社内でデザインシステムを構築した。
それまでは企画担当者ごと依頼を出していたので、クリエイティブに一貫性がなかったが、デザインシステムに沿った開発ができるようになり品質が保たれることになった。企画担当者も伝えたいコンテンツだけに集中すればよいのでチェックの負担も軽くなる。

単にシステムを作るだけでなく、誰でも使えるデザインシステムにするためガイドラインも制作した。OK例とNG例で具体化したり、「どのような場合にこのタブを使うか」など詳細に説明したりしている。
この他にも、画像素材を自前で用意して他と差別化させる、多すぎるページを見直してスリムにする、構造を見直して離脱を防ぐなど工夫を凝らしている。
もともとSMBCは幅広い人材を受け入れる企業文化もあるということだったが、デザインへの理解が乏しかった文化でのチームの苦労は想像に難くない。
そんな中でもインハウスデザイナーならではの利点を存分に発揮し、デザインを業務に取り入れるという実績を残した点は素晴らしい。
デザイナーは「イメージを可視化できる」という大きな強みを持っている。この強みを活かして、他の職種と同じように会社に貢献できるという存在感をアピールするのはとても有効な手段だろう。
マネジメント層も売り上げや利益といった定性的なデータだけにとらわれず、こういったデザイナーの活動や意見を見たり聞いたりしてデザインの重要性をもっと理解してほしい。
デザインを少しでも理解すれば、結果的に企業にとってプラスになるのはまず間違いない。
SMBCが自前のデザイナーを持っていたこと自体知らず、たまたま手に取った本だったがリアルな経験談が豊富で実に興味深かった。
もしかしたらこういったケースの企業に勤める(または携わる)ことになるかもしれないので、参考にさせていただく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
