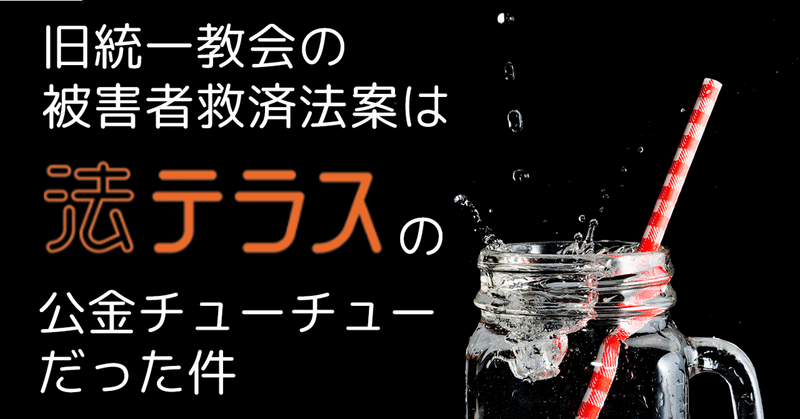
旧統一教会の被害者救済法案の正体は弁護士の公金チューチューでした
こんにちは。地方自立ラボ(@LocaLabo)です。
本日は、この度国会で審議される「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案」(以下、特定不法行為等被害者特例法)について考えてみたいと思います(本稿で対象とするものは2023年第212臨時国会で法案が提出されたものです)。ニュース等ではわかりやすく「被害者救済法案」と呼んでいるようです。
今回は次の理由で本法案については反対します。
1.日本司法支援センター(法テラス)という無駄な組織を使うことで延命を図っている考えられること。
2.弁護士の営業努力が生かせるよう規制をなくし自由化をすればもっと被害者保護がやりやすくなるのではないか。
3.役人による指定宗教法人の指定による事務の特例は恣意的な判断であり司法を越権するのではないか。
4.財産保全については完全に行政の行き過ぎであり役人にそこまでの権限を与える事には反対する。
法の具体的な内容
今回提出された法案は、施行より3年間の期限付き立法であり、既存の「日本司法支援センター」の業務に関して、旧統一教会から被害を受けたとされる人が弁護士に依頼する際の費用を立て替え払いすることができる業務が追加されることが一つ。
そして、宗教法人法において不動産の処分を行う際に報告が必要な事などを定めることがもう一つ、という法律となっています。
法律制定の理由については提出法案のpdfファイルに以下の通り記載されています。
現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本法案の目次は次の通りとなっています。
第一章
第一条・第二条
趣旨と定義
第二章
第三条~第五条
支援センターの業務の特例
第三章
宗教法人による財産の処分及び管理の特例
・解釈規定(第六条)
・指定宗教法人の不動産の処分等の所轄庁への通知および公告の特例
(第七条~第十条)
・特別指定宗教法人の財産目録等の作成及び提出並びにその閲覧の特例
(第十一条~第十三条)
補則
第十四条~第十七条
罰則
第十八条
附則
第一条~第六条
まず、第二条において「対象宗教法人」を解散命令請求が行われたものとされています。そして「特定不法行為等」として「特定解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者その他の関係者によるもの」とされました。
次に第三条から第五条において支援センターの業務の特例として「特定被害者(特定不法行為等に係る被害者)」を援助する業務を追加するとしています。主に被害者が民事手続きで弁護士などに支払う費用を立替えたりします。
訴訟などに際し、費用が掛かるため訴えることができない人がいます。その人たちのために立替えてくれる制度があります。昔は「扶助協会」と言いましたが、近年、国の事業として再編され「日本司法支援センター」(法テラス)となっています。これは後の章で取り上げます。
日本司法支援センターは「総合法律支援法」に基づき設置されました。旧統一教会被害者のためにあらたに個別法を作ることをせず、本法(特定不法行為等被害者特例法)の第四条で総合法律支援法の各条文を本法に合わせて読み替え特例業務を行うこととしています。
また、実際の運営にあたり本法の適用に疑義が生じる部分があるわけですが、この点については「政令で定める」としています。このほか「この章の規定の実際に関し必要な事項は、法務省令で定める」(第五条)とされているなど、具体的な支援センターでの取り扱いにおいては不透明な部分が多い印象です。
さて、本法の主要部分である第三章で「宗教法人による財産の処分及び管理の特例」が定められています。こちらは「宗教法人法」に定められている規定を「指定宗教法人」「特別指定宗教法人」については本法に従うものとされることとなっています。
第七条は「特定不法行為に係る被害者が相当多数存在することが見込まれ」「財産の処分及び管理の状況を把握する必要がある」場合、その宗教法人を「指定宗教法人」と定める規定です。暴力団対策法での「指定暴力団」みたいですね。ちょっと暴対法を見てみましょうか。
暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
本法では次のようになっています。
対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。
一 当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。(以下略)
まあ、ちょっと法律の引用ばかりで眠くなってきてしまうので、思いっきりザックっとまとめます。
本法は、被害者が多いとされている宗教法人を「指定宗教法人」「特別指定宗教法人」として定義し、それらの被害者が民事訴訟などを起こす場合に助けてくれる人がいる。そして国としては財産を処分してお金に変えるような場合は勝手にさせないよ、その他の財産も見られるようにしておくからね、という法律となっているのです。
マスコミの報道などでは「旧統一教会の財産が勝手に処分されないよう、保全措置をすべきではないか」などという論調が広がっていますが、この法律ではそこまで盛り込まれていないということがお分かりいただけるのではないかと思います。
法テラスは解消! 弁護士は自分の力で稼げ!
さて「日本司法支援センター」(法テラス)とは何でしょうか? 前身は財団法人扶助協会。
日本弁護士連合会が基金と寄付金によりスタートさせた団体とのことです。日弁連会長の昔話から確認してみましょう。
1952年(昭和27年)1月24日、日弁連の呼び掛けにより財団法人法律扶助協会が設立されました。基金100万円と寄付金160万円によるスタートであり、訴訟の結果相手方から利得が得られた場合を除き、扶助金は給付とされましたが、相手方からの利得のある事件が想定以上に少なかったため、たちまち資金難に陥ってしまいました。
1958年(昭和33年)には、国が支援に乗り出し、補助金が交付されるようになりましたが、相手方からの利得の有無にかかわらず扶助金は被援助者への貸付とされ、全額償還制がとられることになりました。これが今日まで続く償還制のはじまりです。財政当局としては貸付とすることで財政支出を最小に押さえることになりますが、資金難と法的支援の必要からの苦渋の選択でした。
その後、司法制度改革の中で総合法律支援法が成立し、2006年(平成18年)に日本司法支援センター(法テラス)が設立され、現在の法律扶助を担っています。
日弁連さんも公金チューチューだったんですね。(笑)
最初の方針は良かったのではないでしょうか。民事訴訟に対する扶助(最初は資金の給付だったが後に立替え払いに変わる)を行うというのは「赤ひげ弁護士」の姿をほうふつとさせるものがあります。法律に疎く、資力に乏しい人であっても、裁判を受ける権利が保障される。そういった市井の人々の立場に立った弁護士としての気概を感じます。手弁当で弱い人の見方に立つ弁護士を「赤ひげ弁護士」と言いますが、今でも弁護士のホームページを見ますと「赤ひげ弁護士を目指します」という人は多いです。「赤ひげ弁護士」として有名な人の評伝がありますので参考にしてください。
しかし、弁護士は商売が下手だった。せっかく作った扶助協会も資金難に陥り、国から補助金をもらうようになります。給付ではだめですね。「苦渋の選択」とは書いてありますが、法務官僚の天下り先としての「司法支援センター」設立に日弁連も参加し、お仕事をもらえる体制を国と共同で作ったわけですね。

今回のいわゆる旧統一教会の「資産保全」対策については議員立法が複数作られました。そして、法テラスを使う案が残りました。統一教会の被害者対策で法テラス? ん?という人が多いはずです。実は法テラス自体設立当初よりその存在感が薄いのです。「そらそうだ」補助金にどっぷりつかれば赤ひげの心意気なんかあるわけありません。法務省の「日本司法支援センター評価委員会」の報告書を見ても業務認知度は16%といいます。
〇日本司法支援センター評価委員会第76回会議『項目別評定調書(案)』p.134
https://www.moj.go.jp/content/001401079.pdf
資産保全にまで踏み込む法律とせずに「まあまあ、まずは法テラスを使ってみてくださいよ」と法テラスの存在意義をマッチポンプ的に作り出す作戦ですね。旧統一教会問題をこれまでの民事訴訟のなかでの解決策にとどまらせ、大きな問題としないで終結とする、なんとなく「アベガー」問題の再燃をしたい野党に対してうまくあしらっているような感じをうけます。
法テラスを利用することで行政と政局に対し一石二鳥的な対応策を考えたのではないかと思わずにはいられません。法テラスから仕事をもらっている弁護士にしてみれば「過払い請求」の次にそこそこ稼げる事案と考える人もいるのではないでしょうか?
そこでです!やはり旧統一教会の問題は従来のとおり、被害者が弁護士を頼って個別的に解決していく方向で行くべきなのではないでしょうか。そのためには弁護士がもっと自分の力で集客する力を持てば良いのです。長いこと漬かっていた補助金チューチューの生活から脱却しましょう。弁護士業務の規制があって自由に稼げないのなら、そんな規制もぶっ壊してほしい。法テラスなどというおためごかしの税金じゃぶじゃぶの組織とつるんでいたら、いつまでたっても浮かばれませんぜ。
弁護士がすべきは、法テラス解体を叫び、自分の力で集客することです!
特定不法行為等被害者特例法どころか財産保全は悪!
上記の通り、本法は旧統一教会から被害を受けたとする人への特例的支援を定める法律です。その実態としては従来どおり、被害者が弁護士に訴訟手続きを依頼することが必要です。特例を設けることで被害者に対して国も仕組みを作ったよ、というアピールはできますね。
さて、先に暴対法を引き合いに出しましたが、暴対法は都道府県の公安委員会が暴力団を規制する法律として非常に効果があったとされています。平成4年の施行から30年以上経過し、当時約9万人いた暴力団の構成員は現在では2万人程度だそうです。
しかし実際には単純に喜べる事態ではなく、新たな問題も引き起こしています。暴対法で対策できない事案の増加です。実質的には暴力団と関連性があるのに取り締まることができない「半グレ」問題です。半グレは明確な組織を持たずに集団での暴行や特殊詐欺、みかじめ料の徴収などに手を染めるとされ、トップの名前は分かっていても、組織としての活動実態はつかみづらいのが実情だそうです。これらの実態から専門家は次のように暴対法の改正に取り組むべきだと提言しています。
ますます潜在化する暴力団とそのあり様が変化している反社会的勢力について「どこまで規制をかけるべきか」が中途半端な状態で事業者にその対応を全面的に委ねられてしまっている問題、そして、最も本質的な問題である「暴力団を合法組織と認めてよいのか」といった積年の課題への対応など、今、改正を検討しておくべき理由が数多くあります。
暴対法はそれなりに効果を発揮し、暴力団構成員の減少をもたらしました。しかし結果としてイタチごっこ、法の網の目をかいくぐって新たな犯罪者集団が跋扈する事態を招いています。
果たして、本法が作られたからと言って、宗教法人が裁判沙汰になることを多数起こさなくなるか、分かりません。むしろ、きわどく裁判沙汰にすらならなければ問題ないという姑息な手段使って本法から逃れることを考えるのではないかと危惧します。
統一教会を始め、霊感商法やマルチ商法に関して、消費者庁において「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が開催されていました。会議は2022年8月から7回行われました。報告書が昨年(2022年10月17日)提出され、提言が発表されています。その中から旧統一教会に関する問題への提言部分を抜粋します。
1.総論
(1) 旧統一教会については、社会的に看過できない深刻な問題が指摘されているところ、解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法(昭和 26 年法律第 126 号)第 78 条の2に基づく報告徴収及び質問の権限を行使する必要がある。
((1)以下は略)
2.旧統一教会への対応等
宗教法人法第 81 条に基づく解散命令については、団体としての存続は許容されるとはいえ、法人格を剥奪するという重い対応であり、信教の自由を保障する観点から、裁判例にみられる同条の趣旨や要件についての考え方も踏まえ、慎重に判断する必要がある。
また、宗教法人法第 78 条の2に規定する報告及び質問に関する権限は、解散命令の事由等に該当する疑いがあると認められるときに、宗教法人法の規定に従って行使すべきものとされ、これまで行使した例はない。しかし、これらの消極的な対応には問題があり、運用の改善を図る必要があるとの指摘があった。
旧統一教会については、旧統一教会を被告とする民事裁判において、旧統一教会自身の組織的な不法行為に基づき損害賠償を認める裁判例が複数積み重なっており、その他これまでに明らかになっている問題(*3)を踏まえると、宗教法人法における「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」又は「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」宗教法人に該当する疑いがあるので、所轄庁において、解散命令請求も視野に入れ、宗教法人法第 78 条の2第1項に基づく報告徴収及び質問の権限を行使する必要がある。
3.法制度に関する事項
(上記2.*3の注記部分)
「日本の旧統一教会に献金させるのではなく、韓国の旧統一教会に献金させる、直接お金を持っていかせることも脱法行為とされている。これは二重の脱法行為であり、日本法の適用をさせない。もう一つは、外国為替管理法違反の行為、個々の信者にお金を持っていかせることによって脱法する。」といった指摘があった。
4.相談対応に関する事項
全国の消費生活センターにおける消費生活相談に加え、政府においても「旧統一教会」問題合同電話相談窓口を設け、悩みを抱えている方々から幅広く相談を受け付けた上で、必要に応じ、日本司法支援センター(法テラス)等の関係機関を紹介している。
法テラスのこともすでに触れられていますね。また報告書末尾に「消費者庁の所掌事務の範囲を超える事項については、消費者庁は、それぞれの行政機関における実施を強く働きかけるべきである」と記されています。つまり、今回の特例法の作成は消費者庁の研究会の提言なども踏まえた対応であることが伺え、政府として現在できることはここまでなのであろうと考えられます。
しかし、今後は教団財産の保全に向けて検討するという報道もされており、こちらは由々しき事態であると考えます。私の意見としては本法に財産保全が具体的に盛り込まれたり、端緒を開いたりした場合、この法案には断然反対します。
自公国側は5日の法務委に、施行後3年をめどに「財産保全の在り方を含め」て検討を加えると付則に明記した修正案を提出。立民議員が「3年後は悠長だ」と批判したのに対し、提出者の自民の柴山昌彦元文部科学相は「課題が生じた場合は3年を待たずに検討を加える」と理解を求めた。これを受け、立民、維新の国対委員長が会談し、修正部分への賛成を確認。立民の安住淳国対委員長は「財産保全に半分足をかけた。(自公国案は)ないよりはあった方がまし」
国や地方自治体が国民の財産を保全することを「差し押さえ」と言います。行政が個人の資産を差押さえすることは現行法令上可能です。海外における資産の差し押さえも「税務行政執行共助条約(租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書)」により可能となっています。これは韓国も締結しており韓国内にある財産を差し押さえ対象とすることもできるようです(日本人の財産という前提があるでしょうが)。
参院で今回審議される本法では財産保全の具体的方法が分かりませんが、旧統一教会の資産を保全するというのは、教団の資産を差押さえする法律なのでしょうか。本法の適用は主として「特定不法行為に係る被害者が相当多数存在することが見込まれる」宗教法人です。宗教法人法は宗教団体にその運営の性質に応じた法人格を与える法律です。今回の問題は被害を申し立てる人と教団との民事的な争いが多数見込まれることです。
その問題に対して教団の財産を国が保全する法律を想定した場合、一般の会社やある種の組織(例えば法人格を取得している自治会など)、ひいては個人に及ぶまで立法が可能になるんじゃないですかね? 他にもマルチ商法など類似の問題も他にたくさんあるのではないでしょうか。
これまで旧統一教会の被害者の多くの方は裁判などで教団と和解しているという報道もあります。すべて納得がいく解決ばかりではないと思いますが、あくまでも個人(家庭)の問題は教団との裁判か和解など、従来の法的な範囲での解決を模索するしかないのではないかと考えます。一般的に言って完全に納得できる裁判や和解のほうが少ないかもしれません。
しかし司法の判断というのは法治国家である我が国において唯一、紛争などに対し客観的法的判断をしてくれるものです。本法における「指定宗教法人」などという判断は条文を見る限り行政側の恣意的な判断にゆだねられているようです。これは裁判所の判断を越権していませんか?
宗教法人の財産を国が差押さえすることには大反対です。宗教法人だから制裁を受けるべきだという悪意すら感じます。もちろん私は統一教会には何の関係もなく、むしろ宗教を隠れ蓑に資金を集めている団体という認識です。
ですが「悪いヤツだから政府が監視して規制すべきだ!」という考えに私は賛成できません。なぜならそのお鉢はいつか私に回ってくるかもしれないからです。
「えっ?なんで?」と思ったそこのあなた、ぜひ下の自由主義研究所さんの記事をお読みください。「悪いものを規制する社会」がいかに恐ろしいかについてわかりやすく書かれています。(加熱式たばこ増税反対の署名もしていただけると嬉しいです😊)
私が財産保全に反対する理由の一番大きなものは、行政にこれまで以上の権限を与えるのは危険だということです。役所の権限や監視機能を強化と、国民の自由な暮らしは必ず反比例するのです。私たちは役人を選ぶことはできません。その人たちに今でも権限を与えすぎているのでこれ以上行政の仕事を、権限を増やすべきではないというのが私の立場です。
被害者の方は消費者庁や法務省がこれまで対応してきた範囲でより良い解決を目指してほしいと思っています。
弁護士の赤ひげ活動のために規制をなくせ!
役人が威張らない社会のために税金さげろ!
最後までお読みくださり、どうもありがとうございます。 頂いたサポートは地方自立ラボの活動費としてありがたく使わせていただきます。
