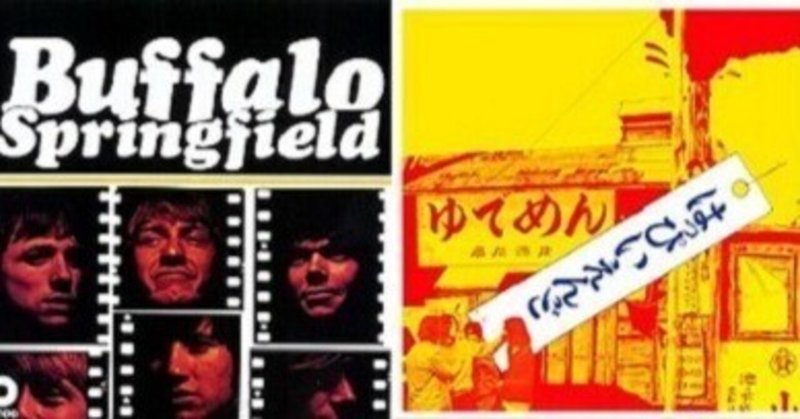
遥か遠くの島国にも及んだ西海岸のオルタナティヴなフォーク・ロック

今日、ご紹介させて頂くのは、米国西海岸と日本のフォーク・ロックです。
フォーク・ロックは、ビートルズやアニマルズを筆頭とするブリティッシュ・インヴェンション後、米国において主流となったジャンルです。
同ジャンルは、65年、ニューポート・フォーク・フェスティヴァルにおけるボブ・ディランによるポール・バターフィールド・ブルース・バンドを抜擢したエレクトリック楽器でのパフォーマンスや『Bringing It All Back Home』の発表と共に、成立しました。
東海岸におけるディランの革命は、米国各州から若きフォーク・ミュージシャンが集まる西海岸にまで波及し、同一派によるバンド結成の活発化へと繋がっていく事となりました。
フォーク・ロックは、米国ロックにおける基礎的なスタイルとして確立され、次々と頭角を現した後続のバンドと共に、目覚ましい音楽性やサウンドの進展を遂げている点において、当時最もオルタナティヴな音楽ジャンルの一つであったと言えるでしょう。
そのような変革の影響は、興味深い事に、米国の東海岸/西海岸から遥か遠く離れた東の島国/日本のフォーク・シーンにも伝播し、大滝詠一や細野晴臣を擁するはっぴいえんどは、日本のフォーク・ロックの礎を築きました。
その後、同ジャンルは、ロックの多様化や価値観の相違などを経て、やがてオルタナ/インディ・シーンによる再評価や再定義があり、また、驚くべき事に、はっぴいえんどの再発見もあり、先述の歴史的な流れは、国際的に共有される運びとなりました。
ロック・ミュージックにおける原点の一つであるフォーク・ロックは、オルタナティヴな成り立ちと音楽的な発展によって、ロック史における最も重要なページの一つを刻みましたが、おそらく今後においても新たな国々や世代たちによって更なる進展を重ねると共に、その歴史が改めて重要視される事になるでしょう。

『Buffalo Springfield』/Buffalo Springfield(1966)
作品評価★★★★(4stars)
バッファロー・スプリング・フィールドは、各々がシンガーとして北米フォーク・シーンでの下積みを経て、ロサンゼルスのサンセット大通りでの邂逅を機に、結成された6人組のバンドである。
彼らの1stである今作は、スティーヴン・スティルスによる先導とニール・ヤングの追随とリッチー・フューレイの引き立てによって、バンドの関係性や才能の萌芽が見て取れ、そのハーモニーとギター・ワークによる息吹は、若き世代の台頭と新たなフォークの訪れを告げてくれる。
この時点においては、調和が取れていた3人のSSWは、バンドがエネルギッシュ且つ実験的な方向性へと向かうと同時に、エゴイズムと緊張感が生じ、彼らは、空中分解と引き換えに、USサイケデリック・ロックにおける傑作を創り上げたのである。

『Moby Grape』/Moby Grape(1967)
作品評価★★★★☆(4.5stars)
ロックの中心地として選ばれたサンフランシスコから鳴り物入りのデビューを飾ったモビー・グレイプは、シスコ・サウンドの重要な一角を担うはずであったが、争奪戦を制したレーベルによる過度なプロモーションは、シーンからの反発を受け、バンドを不遇な状況へと陥れた。
彼らのデビュー盤は、リード・ギタリストであるジェリー・ミラーを筆頭に、メンバー全員がボーカル/ソングライティングを難なくこなし、いわゆるバンド・マジックを宿したサウンドとドライブ感で各ジャンルの横断も軽快にしてみせた。
その後、モビー・グレイプは、実験的なサイケやアル・クーパーらとのジャム・セッションへ取り組み、より意欲的な活動を試みるが、総じてバンドのキャリアは、マネージメントやドラッグの問題によって憂き目に遭うなど、未成熟な時代環境によって翻弄され続けた。

『Love』/Love(1966)
作品評価★★★☆(3.5stars)
フォーク専門の独立系レーベル/エレクトラのロックへの進出と黒人/白人の混合編成であるラヴのシーンへの登場は、西海岸のストリートに新しい風を吹かせると同時に、ロック史における社会学的な転換点となった。
彼らの1stは、ブラックなフレーバーとパンキッシュな演奏、フォーク/R&B/ガレージ/サイケの程よいブレンドを特徴とし、バンドの首謀者であるアーサー・リーは、後世のフォロワー/オルタナ世代にとって重要な参照点となる先駆的なロックを高らかに掲げてみせた。
サマー・オブ・ラヴの季節において、より音楽的な広がりを発揮させたラヴは、精神/意識革命に対する試みの中で、異彩の傑作を描き出してみせたが、このバンドもまた、その後遺症/アシッドの幻覚によって崩れ去ってしまったのである。

『Happy End』/Happy End(1970)
作品評価★★★★(4stars)
東西冷戦下、安全保障条約を巡って学生運動が吹き荒れる最中、私立大学生である4人の若者たちが嘗試していたのは、アメリカからニッポンへと輸入されたロックの音楽的な翻訳と、それを踏まえたうえでの新たな文体の確立であった。
フォーク系のインディ・レーベル/URCから発表されたはっぴいえんどの処女作は、都市の片隅で暮らす青年のモラトリアムを日本的な情緒と重ねて描写した作風となり、彼らは、その文学性を語感やビート含め独自のグルーヴによって体現させ、自国におけるロックの在り方とその可能性を示してみせた。
はっぴいえんどの試行錯誤とその成果は、翌年、日本語ロックにおける最初の金字塔となって表れたが、既に一人の作家として優れた独立性を確立していた彼らは、一つの時代からの旅立ちを告げるべく、自らの音楽的な背景となった西海岸へと降り立つ事となったのである。
それでは、今日ご紹介したアルバムの中から印象的だった楽曲を♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
