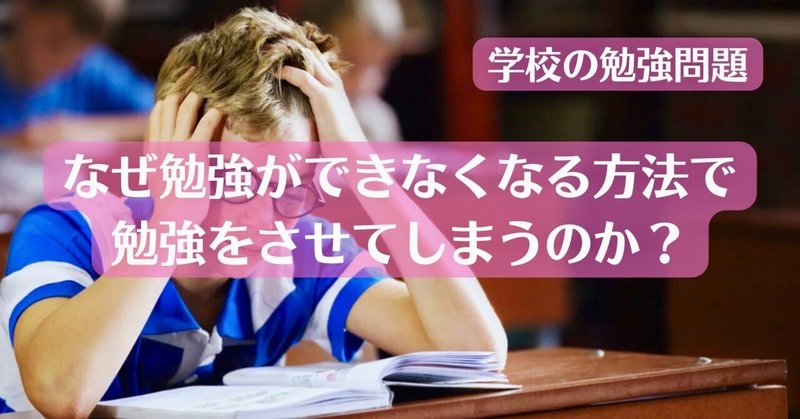
なぜ、勉強ができなくなる方法で勉強させてしまうのか?
なぜこれほどまでに、
学校では、"勉強ができなくなる方法"で、勉強をさせてしまうのか。
というくらいの状況が、近年はずっと続いている。
典型的にとられている手としては、プリントなどの「量をやらせること(量を増やす)」、同様に、「課題や宿題をやらせること(強制および量を伴って)」。
これらが学力低下へのアプローチだとするならば、(大量プリントや課題宿題の)出し手の側は、こんな安易な方法をとることはプロとして恥ずかしいことだと知った上で、もっと頭を使って策を練らなければならない。
一見するとこうした手法は、学力低下対策への正しいアプローチのように思われるがそうではない。
なぜか。
ここに潜む問題点を挙げておく。
・「量をこなせば、できるようになる」というのは、すでに学校での集団授業で「読解や理解が進んでいる(済んでいる)」という前提に立ったものであるという点。現代の子たちの学力の問題は、単なる量の問題ではないことに学校が気付いていないのではないか。
・課題宿題の目的が、いつの間にかすり替わっているのではないかという点。「やらせる・強制する」ことで「管理すること」が、実際のところは目的となっているのではないか。
・「やらせる、強制する」という手法は、暗に「従え」というメッセージを出しているという点。勉強を習慣化すると言いながら、権威や上下関係に「従属する」子どもを生み出すことにつながっているのではないか。
・大量のプリントと宿題課題が、勉強を単なる作業にしているという点。小中高と、長期にわたる課題への従属で、"勉強とはこういうもの"="勉強とは作業”という意識が作り上げられているのではないか。
・強制してやらせる行為が人を思考停止に導くという点。子どもたちはその現状に合わせて最適な行動を取るようになる。いわゆる最適化が起こる。限られた時間の中で大量の宿題をし、提出しなければならないのだから、"思考しない方が得だ"という最適化が起こっているのではないか。
ざっと5つ書いた。
さらにこの5つに加え、学校側の、学力低下に対する最初の見立ての誤りについて書いておく。
現状を見るに、学校としては「なぜ子どもたちの学力がここまで低下しているのか」を見誤っていると考えるのが妥当だろう。
単に量を増やすなり、強制的にやらせるなり、といった安易な手法では、どうにもならないというのが、僕の見立てだ。
かつてはそれで済んだ、かもしれない学力対策は、現代の子どもたちの特性が大きく変化したことを考量する必要がある。
それも含めた、見立て、だ。
それが見えると、そもそもの取るべき策が変わってくる。
最後に。
ここで言及した学校の手法の背景にあるのは、
「保護者へのクレーム対策」と「制御されなくなった(言うことを聞かない)子どもたちへの対応」があることを付け加えておく。
(これらについては長くなるのでここでは述べない)
いずれにせよ、学校には、そろそろ"勉強ができなくなる方法"から離れて欲しいと思う。
打つべき手は、他にある。
そしてそれをすでに何年も実践し、結果を出している身として、ここに記述しておく。
(おわり)FB投稿より
記事を気に入っていただけると幸いです。NPOまなびデザンラボの活動の支援に活用させていただきます。不登校および発達障害支援、学習支援など、教育を通じたまちづくりを行っています。
