
議員面会プロジェクトを通して私が伝えたいこと
愛媛での議員面会プロジェクトはどうだったのか
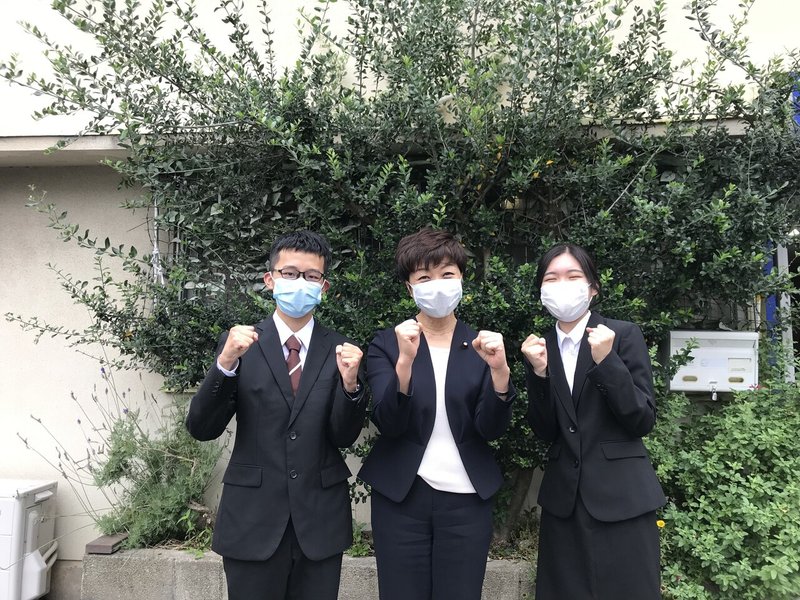
愛媛でやってきた議員面会プロジェクト。
議員に対して面会の申し込みの手紙を出す。
単純だが、直接的なアプローチ。私たち、国民の代表である国会議員は核政策について何を考え、何を思っているのか。それをメディアやネットといったフィルターを通したものではなく、ちゃんと生で聞く。
私にとって初めての取り組みで、プロジェクトが進むにつれて社会に働きかけるということの大切さを肌で感じた。
でも正直ずっと不安だった。
被爆地ではない地域で核兵器の問題について考えてもらう。それは果たして可能なのか。ただでさえ保守的な県で、核廃絶というとすぐに一定の政党や宗派に見られてしまう。最初から色がつけられる。どんなに中立な立場で議論がしたくてもできないかもしれない。主義主張を勝手に決めつけられて、私たちの思いに目を向けてもらえないんじゃないだろうかと。
加えて、議員の方々が学生のこの呼びかけに答えてくれるのか。この不安は何よりも大きかったように思う。新型コロナウィルスが蔓延し、いろんな社会問題が議論されなければならない中で、核兵器の問題を聞く。それどころじゃないのではないか?
そして、明日、明後日の生活がどうなるのかわからない市民の方がいる中で核兵器の問題を考えてほしいと声をあげること。私は環境が恵まれてるからこそできることなんだよな。と申し訳なさを感じられずにはいられなかった。
「核兵器の問題は命に直結する」
「コロナと同等の脅威である」
そう確固たる信念を持っていたものの、毎日命をつなぐことに必死な人達がいる中でそんなことをいうことができるのは生活が安定しているからという理由以外に何もない。そう思うと声を上げづらかった。
それでも今やることに意味があるという思いを貫いた。時間は待ってくれない。私が見たくない世界が起きてしまうことも時間の問題だと思った。あらゆる問題がある中で核兵器の問題が後回しにされていい理由もない。誰かが声を上げなければ。そういう思いやってきた。
結果、いろんな人に影響を与えられたんじゃないかと思う。
愛媛というまだまだ核兵器の問題が議論されない地で核兵器の問題という論点を持ち込むことができた。
国会議員への影響も少なからずあったと感じている。
うまくできなかったところもあったと思う。でもはじめてにしては上々だったのではないか。
対話というゆるぎないスタンス

私は愛媛で議員面会プロジェクトをするにあたり、「対話」に最後までこだわった。
「核兵器廃絶を求める」「核兵器禁止条約批准を求める」そういう私たちの思いを議員にぶつけるプロジェクトにはしなかった。
なぜか。
それこそが本当に核兵器廃絶を進めると思ったからだ。
「冷めている。」
そう思われるかもしれない。
実際に言われた。
「それじゃあ核兵器廃絶に本気じゃないように見える」
そうだろう。おそらくある一部の人達にとっては私のこのスタンスは核兵器廃絶に対する生ぬるさを感じさせてしまうものだと思う。でもこのスタンスは私が経験から学んだよりよい社会を作るための方法なのだ。
私は核兵器は絶対にないほうがいいと思っている。
たった一発で街を破壊し、人々の尊い命を奪い、その後の人生をもめちゃくちゃにするような兵器がこの地球上にあってはならない。街は復興しても人の心に復興はない。
核兵器が広島と長崎の人々に与えた傷は死ぬまで被爆者の背中に重たくのしかかる。
広島や長崎を見れば核兵器の非人道性は理解できるはずなのにそれでもなお核兵器が必要だと思う人はおかしい。人間として非道徳的だ。ありえない。
私はそう思っている。
じゃあ、核兵器が必要だと考えている人と話すとき、この意見を真っ向からぶつけたらどうなるか。
議論になるだろうか。
誰もが自分の大切にしたいことがあって、変えたくない、守っておきたい確固たる考えや信念がある。
この核兵器の問題においても同じだ。
「核兵器は日本国民の命を守るために必要。」
そう考えている議員が核抑止論を唱えているのだと思う。
じゃあ、そう考えている議員とどういう風に核兵器の議論をしていくべきか。
私はこの点を常に考えてきた。
そして私がここで忘れたくないと思っていたのは
そもそも議員は議員である前に一人の人間であり、私たち市民と同じである。
ということだ。
人間なのだから感情もあるし、怒ったり、泣いたりそういうこともあるはず。
それなのに私たちはどこかで
「議員だったらなんでも受け止めるべきだ。だって市民の代表なんだから」
という思考を持っていないだろうか。
わかる。間違ってはいない。だってそうなのだから。
でもそれは正しいのだろうか。
「議員なんだから市民の声を聞くのは当たり前。面会するのは当たり前」
当たり前なのだろうか?
そこから問い直したいと思った。
社会において当たり前はないはずなのに、どうして議員には当たり前を求めるのか。
私たちの求めるものを議員にぶつけ、その通りの返事がもらえなかったからといってそのことについていろんなところで議論をする。
傷ついたことに対して声をあげるべきではない。我慢しろという話ではない。
いけないことがあったのならばちゃんと考えるべきだし、言うべきである。
でも。
それを言い続けて何が生まれるのだろうか?
議員の対応・事務所の対応が悪かったことは一つの事実であり、それ以上でもそれ以下でもない。
そしてすべての議員がそうではないことは愛媛のプロジェクトを見ていてわかるはずだ。
愛媛県の議員、事務所の方はどの方も私たちに対して傷つくようなことを言ったり、罵倒したりするようなことは全くなかった。むしろすべての議員さんにおいて手紙に目を通してくれていた。
そんな人間関係の問題でぶつかりたくない。
本気でぶつかり合いたいのは核兵器問題の議論であり、人との関係ではない。
議員である前に市民で、市民である前に人間である。
議員は私たちと同じである。
人としてのリスペクトを忘れていけない。
そう思う。
誰も傷つかない状態、いやな思いをしない状態を作りだして、安心安全な環境において議論をしたい。
これは私たちの未来を創るための議論だから。
私が最後まで対話にこだわったのは議員の考えに関係なく、一人の人間として向き合いたかったから。違う意見を持つ人と話す際に「話を聞きたい」というスタンスが心地よい対話の場を創り出すと思ったから。そして何よりもよりより人間関係を築くことで建設的な議論をしたかったから。である。
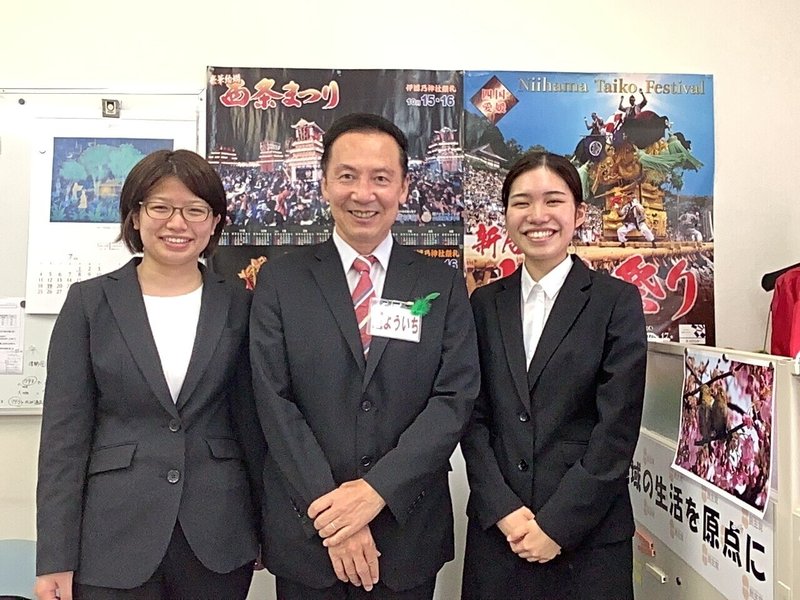
未来を作るのは私達。社会の主役は国民
どうしても議員の不祥事などのニュースを見ると、自分たちの代表に落胆してしまう。
でも落胆する前に考えなければいけないのは私達国民が代表である議員を選んでいるということだ。選んだ私たちにも責任はある。
私達が意識をしっかりと持って選挙に行き、この人になら自分の国を任せられるという人を選ばなければならない。
国民が主権者とはそういうことである。
政治は政治家が決めるものではない。私達国民が決めるものだ。
そして作りたい社会、見たい未来を作るのは私達である。
私は「一人一人が生きやすい社会を自らの手で作っていける」という確信を持つ人を増やすためにこれからも活動していきたい。
学費に使わせていただきます!
