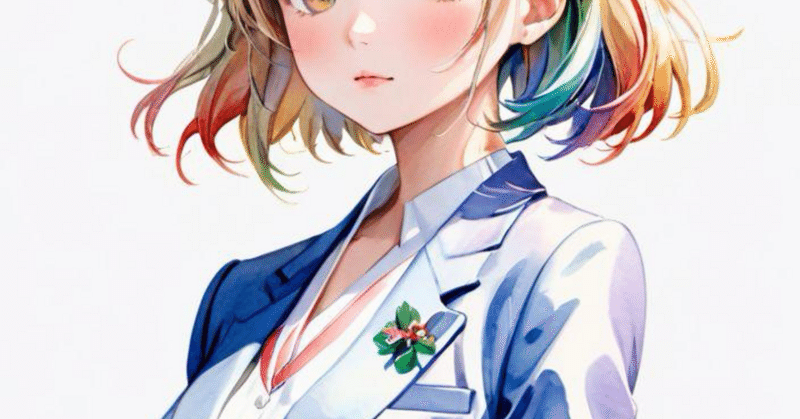
恋愛掌篇「陰謀論ノ彼女」
「スマホによって、我々はつねに国家に存在を把握されており、電磁波によって寿命も決められているの。だから、私は何も持たない」
経理部の鵜馬ふみはそのようにして自分が携帯電話の類を持っていないことを説明した。今日で交際から一年。長かった。
最初のデートにこぎつけるのだって、非常に苦労したものだった。社内では彼女を見かけることはあっても、他部署では話しかけることは難しかった。社内メールは管理部がチェックしていて、プライベートな内容は送れない。
結局僕は、新しいインボイス制度について経理部の意見を聞きたい、という口実で彼女を食事に誘い、自分の気持ちを打ち明けてデートの約束を取り付けた。
不思議だったのは、彼女が自分のほうから「インボイスは口実ですよね?」と指摘してきたことだ。その日は終始インボイス制度の話しかしていないから、なぜそう言われたのか。そのわけを、のちに彼女は「引き寄せ」という言葉で説明した。
「あなたたちはスマホをもっているから受信できないけれど、この世界には本当につながるべき人を導いてくれるアンテナがあるの。だから必要な相手は自然と寄ってくる」
僕は内心嗤っていた。非科学性の一切を否定して生きている僕にとっては、恋愛対象として見ている相手が、そのような不可解な信仰をもっていること自体が大いなるマイナスポイントだった。
けれど、それを指摘するには時期尚早だ。そういうことは、もっと関わりが深くなってからのほうがいい。それに、何であれ、自分が彼女に必要な相手と見做されたことは嬉しかった。
僕らは逢瀬を重ねた。時折、ふみが約束の場に現れないこともあった。スマホを持たない彼女はわざわざ僕に連絡を入れたりもしない。僕はそのことで不服を申し立てたが、やれやれね、それって雨が降ることに腹を立てるように愚かしいわよ、と一蹴された。納得はいかなかった。
そして、今日、彼女は国家の策略から逃れるために、会社を辞めるという。会社を辞めて、僕と同棲する、と。自分の暮らしの痕跡を消してしまえば、国家はこれ以上彼女を追跡することができないのだという。
僕は話を聞きながら、頭がおかしくなりそうだった。けれど、気持ちは複雑だった。この一年で、僕は彼女をさらに深く愛するようになっていたからだ。
同棲は、要するに、望むところだった。だから、僕は彼女の望みを受け入れた。
次の日は引っ越し作業だった。彼女は夜間に、できれば業者も介さずに引っ越しを完了させたい、と言った。そして、そのためには僕もまたスマホをもつべきではない、と言った。
僕は、彼女の言うことに従った。好きな相手の意向を拒否するなんてあり得ない。
作業は夜を徹して行われた。と言っても、作業をしていたのは、ほとんど僕一人だった。彼女は自分が動くと、呼吸が荒れて国家に傍受されやすくなる、と言った。だから、彼女の持っている荷物をほとんどすべて僕が一人で運ばなければならなかった。
けれど、冷蔵庫と箪笥だけは僕一人ではどうにもならない。かと言って、彼女が手伝ってどうにかなるわけでもない。そこで僕は幼馴染の田中を呼んでいいかと尋ねた。ダメよ、と彼女は最初のうち渋っていたが、田中は国家に対してつねに反感をもっているんだと告げると、スマホを持ってこないように、と念を押したうえで許可された。
真夜中に、それもいまどき公衆電話から呼び出されて、田中はかなり不服そうだった。スマホを持ってきてはならない理由を話すと「スピってんなぁ……」と呆れた。しかし、それでも彼は諦めて彼女の家にやってきてくれた。作業が終わると、酒でも飲んでいかないか、と田中に言ったが、明日はワクチン接種の日だから帰ると断られた。田中が去っていくのをみて、彼女はまたこう言った。
「ワクチン接種だって国家の戦略なのにね。恩人が国家に殺されるのを、あなたはみすみす見逃すの?」
さすがに僕はたまりかねて、こう返した。僕は君が好きだけど、このうえなく好きだけど、君の思想をまるごと受け入れると言ったつもりもないし、君の思想まで好きなわけじゃないんだ。そこは勘違いしないでほしい。すると彼女は答えた。
「思想って好くようなものじゃないし、理解できるかどうかでもない。たとえば、この世の人がどれほどハイデッガー哲学を理解できると思う? できないわよ。それと同じ。あなたは内心で私を陰謀論者だと思い、自分を科学の側にいる常識人だと思っている。そういうレッテル貼りで安心したいのね。でも、じゃあ、あなたが科学の何を理解しているの? 非科学の何を理解しているの?」
それは君だって同じじゃないか、と僕は答えた。すると、そのとおり、と彼女は言った。そして、長いため息をついた。私もあなたも何もわかっていない。それでいいのよ。なのに、なぜあなたは自分が正解の側にいるような顔をしたがるの? 君だって自分が正解の側にいるような顔を、と言いかけて僕は黙った。そんな顔を彼女はしていたのだろうか。ただ、彼女は自分の向かうべき方向に向かっていただけだ。それを正しいかどうか判断していたのは、僕のほうではなかったか。
「そんなことより、卵焼きを食べましょう。私、とても卵焼きが上手に焼けるの」
彼女は、僕の部屋のフライパンをしばらく眺め、匂いを嗅いだ。いい匂い。いろんな料理の記憶が残っているわね。あなたはフライパンを洗剤をつけて束子で洗ったりしない。それはとても大切なことよ。いかにあなたがうわべばかりの科学信奉者であるとしても、その点は評価に値するわね。そう言いながら、コンロの火をつける。
フライパンのうえでバターがとろけはじめ、よくかき混ぜられた卵がじゅじゅじゅうと音を立てて広がりはじめたとき、僕はこの世の真理がフライパンの上で姿を明らかにするのを見るような気がした。それは、ありていに言って科学的でもあり非科学的でもある神秘だった。
部屋のなかで、何かが動いた。
段ボウルだ。彼女の部屋から運ばれた荷物の中で、何かがうごめいていた。一つの段ボウルが左右に揺れていたのを見て、僕は何か生き物を持ち込んだなと思った。けれど次の瞬間、脳に誰かが語りかける。はーずれー。同時に、部屋に点在するいくつもの段ボウル箱がいっせいに揺れ始めた。
ふみは、しずかに僕を見据えて言った。ねえ、ネットのWi-Fiも解約してくれる? なんでだよ、と僕は震える声で尋ねた。でも、彼女は料理の手を止めずに答えた。理由は無限にあるけれど、一つ答えるなら、もうすぐ卵焼きが出来上がる。それは私があなたのために作った料理で、それはあなたのためのギフトなの。あなたはそのギフトを受け取る資格をもっている。けれど、資格をもつ者は、それなりの犠牲を払わなくちゃ。だって、これ以上ない恵みを受け取るわけだから。
段ボウルたちがいっせいに、また揺れ始める。それが何によってそうなっているのかなんて、どうでもいいことだった。段ボウルたちは、ただ理由もなく揺れているのだ。そして、恐らくは彼らは電波を嫌っている。その事実に科学的理由が存在しないことは、火を見るより明らかだ。
僕は当たり前のことに気付いた。非科学的な出来事に、科学的根拠なんてあるわけがないのだ。そんなことが何かのエビデンスになるわけがないじゃないか。
卵焼きができあがり、ふみはそれを皿に載せて僕のもとへやってきた。
「さあ、食べましょう」
それを食べることがいいことなのかどうか。
もしかしたら、僕は今すぐにこの荷物ごとふみを追い払うべきなのかもしれなかった。それこそ、まだここに田中が残っていたらこう言うだろう。ミイラ獲りがミイラになったな、と。
だが、そうではないのだ。人生はまだ続いており、僕はまだ今のところ彼女ともう少し一緒にいたい、ただそれだけなのだ。
だから僕が科学的に立証可能なこと以外信じておらず、段ボウルが蠢く理由が解明できないとしても、そんなことは些末なことに過ぎない。
スプーンで卵焼きを掬った。その味に舌鼓を打つと同時に、身体じゅうに福音が鳴り響き、それに呼応するように段ボウルたちが踊り始めた。
そして、僕は悟ることになった。ああ、もうこの恋は、後戻りはできないのだ、と。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
