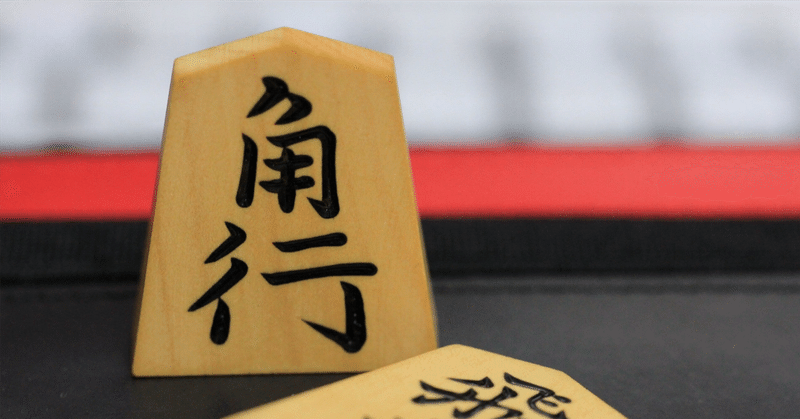
熱戦になれ、豊島将之と藤井聡太――連載「棋士、AI、その他の話」第25回
藤井聡太七冠は豊島将之九段の将棋を愛している。そう彼が公の場で言ったわけではないが、将棋ファンの間では、それは共通認識になっている。何故か。彼が「最近気になった将棋は?」「昨年のベスト対局は?」といった質問にことごとく豊島九段のものを挙げているからだ。だから少なくとも、七冠が豊島の将棋に強く注目していることは間違いない。
かつて豊島は、藤井の天敵と呼ばれていた。初対局から6連続勝利したのだ、無理もない。だがその後は5勝22敗と大きく水をあけられている。これは藤井が豊島の将棋を見切ったというわけではなく、単純に藤井の棋力が向上したからだろう。現在は非公式レーティング上でも大きく差がついた。
では内容も一方的なものばかりなのか、といえばそんなことはなく、むしろ紙一重で勝敗が入れ替わるような僅差の将棋が多くある。そもそも今の藤井聡太とギリギリの勝負ができるというだけでも有数の存在なのであって、豊島は名実共に現代のトップ棋士である。ただし、対藤井聡太戦の場合、単なる棋力という側面からは測れないものがある。例えば豊島と同程度の非公式レーティング値を持つ渡辺明九段は現状、藤井に対して接戦に持ち込むこともできていない。つまりここには相性の問題があり、他との比較として豊島は藤井と「相性が良い」ということになる。5勝22敗でも相性が良いとなってしまうわけだから、どれだけ藤井聡太が突き抜けているかがよく分かる。
豊島の将棋のどこに、藤井を惹きつけるような魅力があるのか。「序盤、中盤、終盤、隙がない」とは豊島を評して言われる言葉だが、それは何か目立って突出した武器があるわけではないことも示している。というより、全てのレベルが高いから突出しようがないのだ。それでもなお長所を挙げるなら、行き届いた序盤研究と、丁寧に紡ぐ中盤力、ということになろうか。彼の将棋はバランスが良い。そして端正な王道でもある。藤井が学んだ部分は多いだろう。
そんな豊島の将棋は、AIとの鍛錬により培われたところが大きい。タイトル獲得にあと一歩手が届かない状態が続いていた豊島は、2014年、電王戦に出場して将棋ソフトYSSに勝利する。事前の練習対局は実に1000局に上ったという。そこで将棋ソフトの強さを知った豊島は、ある時を境に対人の研究会を全て辞め、ソフト研究のみに没頭する道を選んだ。それは単なる序盤研究というだけでなく、スパーリングのようなことまでやっていたらしい。そして2018年、ついに努力が実を結び、棋聖のタイトルを獲得するのである。なお、現在は対人の研究会にも復帰している。将棋ソフトだけでは学べないものがあるということに気づいた、ということだ。
そんな経緯をみると、豊島が自らを「一般的な棋士」だと評していることにも納得できるものがある。16歳でプロ入りし、タイトル獲得6期を数える者がそんなことを言えば怒られそうなものだが、それが嘘偽りない彼の思いなのだろう。何といっても、比較対象は藤井聡太なのだ。羽生善治なのだ。そこには絶対的な才能の壁がある。それを最前線で、肌で感じ続けているのが豊島という棋士だ。
ここから先は

アナログゲームマガジン
あなたの世界を広げる『アナログゲームマガジン』は月額500円(初月無料)のサブスクリプション型ウェブマガジンです。 ボードゲーム、マーダー…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
