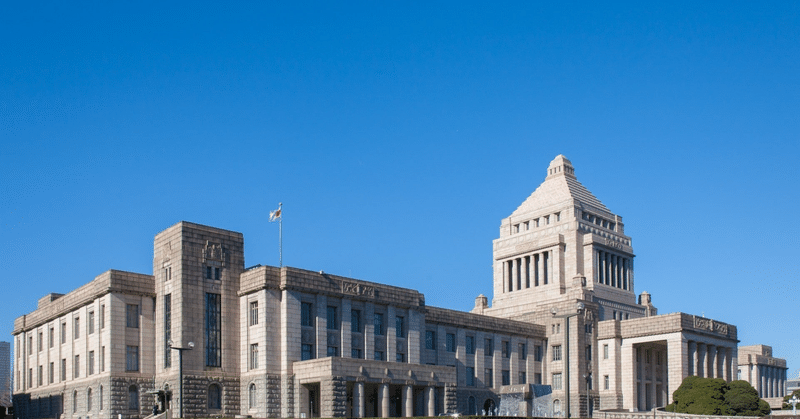
福山哲郎議員(立憲)2024年3月22日参議院外交防衛委員会
福山哲郎議員がハーグ条約について質疑していたとのことので書き起こします。
追加です。今日の外交防衛委員会では、ハーグ条約についても質疑をしました。政権時、私はハーグ条約の締結と国内実施機関の整備に関わりました。現在、日本は外務省領事局・ハーグ条約室を中心に対応しており、国際的には評価の高い運用をして頂いています。…
— 福山哲郎・立憲民主党 (@fuku_tetsu) March 22, 2024
皆さま、今日はお伝えしたいことがあります。こちらの動画をご覧ください。外交防衛委員会で外務省が明言してくださいました!
— ちょっと待って共同親権 (@chottomatte_ks) March 23, 2024
⚠️「ハーグ条約と共同親権はなんの関係もない」(3月22日付外交防衛委員会、56分くらいから)https://t.co/0cBmBXBPng#共同親権を廃案に #STOP共同親権 #拡散希望
福山議員
次の話題に行きたいと思います。
今、法務委員会では共同親権・単独親権・民法改正の議論が出ております。少し国際的な状況と誤解がある部分があるので、そのことについて外務省にお尋ねしたいと思います。
今年の4月1日で、日本でハーグ条約が発効して10年になります。実は私が官房副長官の時にハーグ条約をまとめるのに、ずいぶん関係省庁を集めてやりました。方向性をある程度出した後政権が代わりました。
実は2009年の政権交代の前から、欧米からは日本のハーグ条約を何とかしろという声はすごくあって、政権が代わった後ですね、欧米諸国から日本はハーグ条約を何とかしてくれという声がすごくありました。その声を受けて、私が外務省や厚労省、警察、総務省とずっと調整をして一定のスキームを作ったうえでこの状況になりました。
ですから、今外務省がこのハーグ条約に関して、領事局の中にハーグ条約室を作ってご奮闘いただいていることについては心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。
因みに、現在ハーグ条約の締約国は何か国になりましたか。
外務省領事局長
現在、日本を含めまして103か国でございます。
福山議員
外務省はどのような体制でハーグ条約関係の業務にあたっているのか、ハーグ条約の実施に関わって役割としてどう果たしていただいているのかをお答えください。
外務省領事局長
先ほど委員がご紹介いただきました、現在領事局にハーグ条約室というものがございます。そして条約では、各国で中央当局を定めることになっておりまして、正に日本の場合には外務大臣が中央当局、そしてその実務をこの領事局ハーグ条約室が担当しております。
このハーグ条約室には現在、法曹関係者、児童心理専門家、DV対応専門家等を含む21人の職員が勤務しております。そしてこの体制の下でハーグ条約に基づく援助申請の受付審査、子の所在特定、当事者間の連絡の仲介、裁判外の紛争解決手続き機関やハーグ条約案件に対応可能な弁護士の紹介、さらには面会交流支援機関の利用に関する費用負担等を行っております。
福山議員
これですね、当初なかなか進めにくかったのは、海外で結婚されて、例えば日本人の女性が子どもと一緒に日本に帰ってきた、相手の海外の男性が例えばDVであったりしたときに、日本人女性が子どもと一緒に日本へ連れて帰ってきたときに、欧米からすると、それは連れ去りだと。ハーグ条約はいったん戻すことになっているんです。必ず戻して、その結婚して子供を育てていたところで対応するべき、裁判を受けるべきだという状況だから、必ず戻せという話になるんです。この戻すのが、例えば僕は男性か女性どっちが悪いのかは別にして、子どもと一緒にそこに戻ったら本当に危険だと。そういう方に、ハーグ条約を締結すれば自動的に戻すのかということで、日本国内の日本人の女性で、子どもと一緒に帰ってきた人達からすごい不安の声がありました。逆もありました。日本から子どもを連れて海外に行ってしまっている人に対してどうするのだという声もありました。日本は当時条約を批准していなかったので、戻すことができなかった。
だけど戻すことが前提だと本当に危険なこともあるので、実はそういった色んな女性や男性も含め子どもと一緒に帰ってきたような方々を救済するような機関、NGOとも話し合いをしながら、実はこのハーグ条約の批准にこぎつけました。
その時に、今領事局長が言われたように、日本の外務省が人も集めていただいて対応いただいています。これは別に返す返さないを決めるんじゃなくて、返還の援助の申請とか、それに対する援助の窓口をつくるというのが基本的に外務省の役割だったんです。
正直言うと、各省庁でこの条約室を誰がもつのかで、各省庁全部嫌がった中で外務省にお願いをして引き受けていただきました。今ハーグ条約の運用に関して、日本の条約室を含めて、日本に対して10年前当時作れとさんざん批判的だったんですけど、今国際社会からどういう評価をいただいているかお答えいただいて良いですか。
外務省領事局長
委員から今ご説明いただきましたけれども、外務省を中心に、今ハーグ条約室を運営しておりますが、その結果、条約に則った対応が日本政府全体としてもできているということで、関係各国からは基本的に高い評価を出ていると考えております。
福山議員
局長にイエスかノーで答えていただきたいのですけど、さっき僕も申し上げましたが、これは返還援助申請を受けている外務省窓口になってやったり、面会交流援助を受けて対応したりする業務であって、親権を決めたり、親権のあり方を議論する条約ではありませんよね?
外務省領事局長
そもそもこのハーグ条約ですが、子の監護権・親権をどちらの親が持つのか、子がどちらの親と暮らすのか等、子の監護に関する事項について決定することを目的とはしておりません。
この条約は、監護に関する事項について決定するための手続きは、子が慣れ親しんできた生活環境がある国で行われるのがその子にとって最善であるという考え方に立ちまして、あくまでもその子を、子がもともと居住していた国に戻すための手続き等について定めるものでございます。従いまして、ご指摘の通り、ハーグ条約の仕組みと単独親権か共同親権かといった親権に関する議論とは全く別のものでございます。
福山議員
はっきりお答えいただいてありがとうございます。
もう一点、その子が慣れ親しんだ、生まれて居住してきた当該国の制度が、共同親権であるか単独親権であるかということも、このハーグ条約においては全く別のものだという話でよろしいですね?
外務省領事局長
委員ご指摘の通りでございます。
福山議員
今回、共同親権・単独親権の議論が法務委員会・法務省でやられるときに、よくこのハーグ条約を日本が批准しているんだからやるべきだとかいう少しミスリードな議論があるので、今日は外交防衛委員会の場をお借りして、外務省からご苦労いただいているので、そのことの実態も含めお話を伺いました。
実際に返還されている例、返還しないでいいというのは当該国の裁判で行われるわけですけど、返還事例や不返還の事例って何か具体的にありますか。
外務省領事局長
例えばでございますが、日本から外国への子どもの返還が求められた事案のうち、130件についてこれまで子の返還、または不返還の結論に至っております。このうち、返還との結論に至ったものは約6割にあたる77件ということになっております。
福山議員
4割の53件が不返還ですから、それぞれ状況に応じて判断してくれるということだと思っております。
国際社会では日本の運用については先ほどの話のように評価を受けていて、そして今回の日本国内における民法改正の共同親権・単独親権の問題はまったくハーグ条約とは別物だということがご答弁ではっきりしたので、とてもありがたいと思います。
その前提に従って、今回の共同親権の民法改正については。何が子どもの幸せのために大事なのかという観点で徹底的に議論をしていきたいと思いますし、慎重に議論をしていただきたいなと思っておりますが、それは法務委員会のことなので、これで今日ハーグ条約の件については終わらせていただきたいと思います。本当に丁寧にご答弁いただいてありがとうございます。
また外務大臣、本当に実は条約室頑張ってくれていてですね、大変丁寧にいろんなことをやっていただいています。本当に海外からお子さんを連れて帰ってこられた方を、例えば探して相手と連絡をとって面会の話とかというのは、外務省の仕事かと当時相当言われたんですけど、他にやれるところがないというので引き受けていただいた経緯があるので、そこについては大臣におかれましてもぜひ目をかけていただければありがたいと思います。
他にやりたいこともあるんですが、時間がなくなりそうなので、ちょっと早いですがこれで今日の質問は終わります。ありがとうございました。
以上
誤字脱字がありましたらご容赦ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
