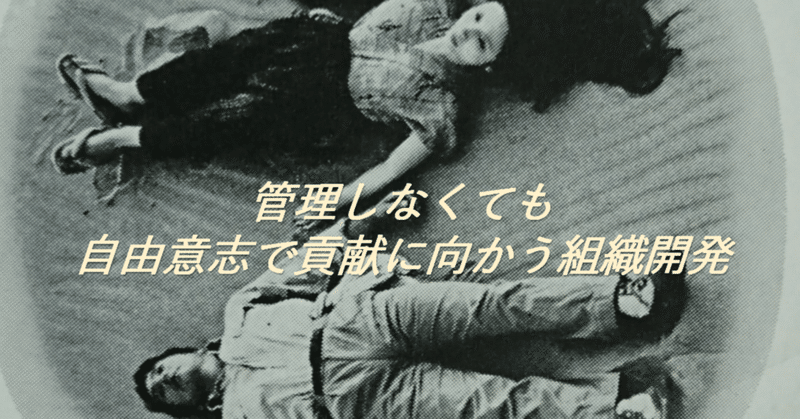
管理しなくても自由意志で貢献に向かう組織開発
誰しもが、自由でありたいと思うでしょう。しかし、自由とは「自ずに由る」ということであるなら、従うべき確かな自分が無ければ、必然的に自由ではいられないということを示している言葉だとも受け止められます。例えば安部公房は、その著『砂の女』で、蟻地獄のような砂の穴の外に出ること(自由になること)と、砂の中に安住すること(自由を放棄すること)の選択を迫ることで、自分を取り戻すこと、自分が自分であり続けることの困難さを著しました。ありていに言えば、管理下で従順にいるほうがラクであり、自分らしく生きるほうが辛いということの葛藤を著したのです。夏目漱石は『草枕』で、さらりと「智に働けば角が立つ。情に棹さおさせば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」と言ってのけましたが…。
自由であることは、何の根拠もなく、好き勝手に発言できることではないでしょう。ましてや、好きなもの(都合の良いこと)だけに囲まれていることでもないと考えます。もし、このような姿を“自由”とするなら、社会(個々人の関係)は分断を招くだけとなるでしょう。中世であれば、対外的にも関わる範囲は狭く、日常においても身分によって生活圏が異なっていたために、分断された小さな集団の集合体として社会を形成することができました。しかし、身分もジェンダーも境界とならず、世界もグローバル化によって一体化している現代でこのような社会を再現することは、現実的ではないと思われます。
にもかかわらず、現代において権威主義が復活しているのは、役割や価値観の固定化が安定を生むからかもしれません。安定(他者と比較すること、従って他者を羨むことをする必要がない社会)は、それなりに快適だからです。だから、特定の専制君主が登場することはイヤでも、それがAIなら良いかもと、本心ではシンギュラリティを歓迎する向きなら多そうです。殊にバーチャル空間では、何の根拠もなく好き勝手に発言することも、好きなもの(都合の良いこと)だけに囲まれていることも可能にしてくれるような錯覚を与えてくれるので尚更です。ましてやAI(ロボット)が人間の奴隷になって生産の全てを担ってくれたら、人は古代ギリシャ市民や平安貴族よろしく、日々、思索や和歌に耽っていれば良く、誰もが贅沢に暮らせて平等な社会が実現するかもしれないと夢想するかもしれません。しかし、それは誰かがAIをコントロールしていることでもあり、結果的に誰かの従順な家畜に堕してしまうことになるのですが…。
結局のところ、「辛いことはしたくない。だからといって畜生道(自由を放棄する道)でも構わないとまでは考えない」という人が多いのではないでしょうか。そして、大勢に流され、ポピュリズムが蔓延しても、それを自分の意志と言い張ろうとするでしょう。しかし、自己創造を行うこと(自由であること)と、人間は連帯しなければならない(一人では生きていけないので、共に生きていく仲間を見つけなければならない)ということは、理論的には交わらないものだと考えられます。それらが交わるのは、バーチャル空間で見せられる幻想ではなく、偶然に起こるということです。だから、その偶然をより確かなものとするために、属する組織を選ぶという行動が必要になるのだと思います。換言すれば、組織を選ぶという自由さえ実行できれば、「TAROMANのようには生きられない」という葛藤に身を置くこともなくなるのではないでしょうか。
例えば就活において、社風と呼ばれる企業文化に重きを置いた職業選択は、合理的であると言えるでしょう。したがってインターンシップは、企業文化を擬似体験する場として活用するのが良いと考えます。また、一定期間、身を置いた場所から離れることも、自身の思考(価値観)が変転する以上、当然のこととして受け止める必要があるでしょう。
社会的動物である人間が自由であるということは、精神的にも物理的にも移動が制限されない状態にいることであるように思われます。このような移動の自由を手放さない限り、人は自由でいられるのだと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
