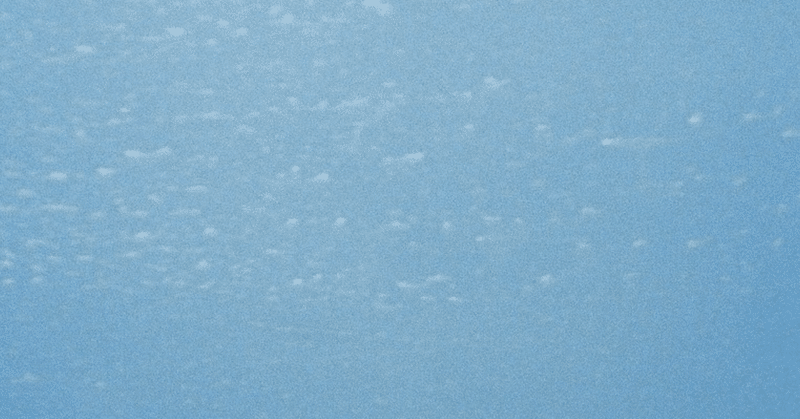
小説『澄んだ地獄で笑いなよ』冒頭部「さよなら」全文試し読み
こんにちは。大滝のぐれです。
この度制作しました新作小説『澄んだ地獄で笑いなよ』の冒頭部「さよなら」全文をこちらに掲載させていただきます。
川でおぼれかけた男ふたりが付き合い始めたことからはじまる、長い語りと過去の風景、いちゃいちゃしたり髪を染めたりお兄さんと海に行ったり好きだった子の結婚式に行ったりいちゃいちゃしたりする生活を切り取った、幸せと絶望と快楽と怒り、そして失敗のBL小説です。

こちらの本編は同人誌形態での販売となります。
B6 180ページ 700円(直接頒布価格)となります。
・直近で入手可能な同人誌即売会、イベント一覧
・5/19(日) 文学フリマ東京
@東京流通センター
第二展示場 う-36 ウユニのツチブタ
こちらのwebカタログの気になるを押すと、後ほど一覧で見れたりしてスムーズです(他の頒布予定の小説の内訳も見れます)↓
・5/26(日) COMITIA148
@東京ビッグサイト
東2ホール し36b ウユニのツチブタ
あらすじ
この世界はおれたちをことあるごとに透明化する。
会社のバーベキュー。おれとカナタは川でおぼれて死にました。そういうことにしておいてください。勝手に帰ったし会社も辞めたし。でも実際はどっこい生きている。地獄は継続されている。
服を着たり脱いだりしながら、いちゃいちゃしたり髪を染めたりカナタのお兄さんと三人で海に行ったり昔好きだったやつの結婚式に行ったりいちゃいちゃしたりする日々。おれたちはふたりで楽しいし気持ちいい。どろどろのぐちゃぐちゃ、べちゃべちゃのずぶずぶになるのがいい。
幻滅した? こんなの聞いてないと思った? でも忘れてないか。おれたちは『特別』でも『括り』でもない。皆と同じ『ひとり』だよ。
死にかけた男ふたりが、笑い合って送る生活。そのしあわせと怒り、悶々とした日々の日常系。
・澄んだ地獄で笑いなよ 冒頭部「さよなら」全文
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さよなら
●
休日のバーベキュー場は白飛びしそうなほどの強烈な日差しに包まれている。ここ数日は終電まで仕事を、いや一日だけ徹夜があったか、いやそれは先週かも、やっぱり昨日? うまく考えがまとまらない。その状態でおれは笑みを作る。周りで肉を頬張り、酒を流し込む会社の同僚や上司たち。その顔はたぶんここに車を走らせ到着したときから、いや数時間前に会社前へ集合したときからずっと笑顔に固定されている。それをぼんやり眺めていると、そばにいた同僚が手に持った缶ビールをおれの持っているそれにかちん、と打ちつけてきた。缶やプラコップを傾ける会社の人たち、肉の焦げたにおい、のどを滑るぬるい苦味。それらすべてがおれの全身を抱きとめていく。
「あー! 須藤さんそんなの向けないでえー! 打たないで!」
「うはは、くらえ俺のビッグマグナム! ビシャー!」
「いやー! 見てよみんな、びしょびしょー! すどうさぁーん、やめてくださいよぉ」
「ふぅ。気持ちよかった。なあ、だろ」
「あっちょっとやだ触らないで、あ、や、やだー、なんかきもぉーい」
おれたちがいるコンロの近くで、どぎついアロハを着た須藤という上司と、おれと同期入社の女性社員がはしゃいでいる。そのさまを眺める他の社員のようにおれも笑おうとする。が、唇の端がくいっと持ち上がるだけで、どうがんばっても声を発するまでにいたらない。クーラーボックスを開け、氷水で満たされたそこからすこし迷ってオレンジジュースの缶を取り出す。プルタブを起こして一気にあおると、きんと冷えた甘味が胃へ落ちていくのがわかった。
「隙あり! あっ、あっ、いくぅ」
須藤さんが叫び、ふたたび水が同期めがけて放出される。が、そこにはもう誰もいなかった。びしょびしょの女性社員は、駆け足で近くのテントに向かっている。さえぎるものなく直進した水が、鋭い線を描き飛んでいく。その先には別のグループが使う大きなコンロがあった。降り注ぐ水が、そのうえの肉や魚やピザをじっとりと濡らす。こちらに負けないぐらいの大声ではしゃいでいた彼らが、文字通り水を打ったように静かになる。ごついチェーンのネックレスをした男と、蜘蛛やカラスのタトゥーが肩に入った金髪の女が、こちらをじっと見据えながらおもむろにコンロを離れる。
社員数名が口をきゅっと引き結び、おれの横を早足で通り過ぎる。須藤さんが水鉄砲を放り捨て、ずりずりと後ずさる。その姿はどんどん頼りなくしぼんでいく。空っぽになった缶を握りながら、おれはその場に立ち尽くす。すこし迷ったが、周りにいた大多数の同僚の動きにならうことにした。背に腹は変えられない。おれが出ていったところでどうにかなるとも思えない。
今いた場所よりも川から近いところに置かれたコンロへ逃げ込むと、そこには直属の高倉さんという上司とその同僚の一団がいた。肉は焼いておらず、彼らは網の上に置いた大きなアルミトレイの中で焼きそばをつくっていた。そのさまを眺めていた数名が、避難してきたこちらに気づいて顔をあげる。瞳だけが動き、視線がくっと後ろにずれる。強固な笑みは崩れない。むしろ、さらに頑強に作り直された。
「パパー、まだなのー。ナユ、おなかすいたよぉ」
「ちょっと待ってなあ」
高倉さんが、フライ返しを握った手の甲で額をぬぐう。かたわらには彼の腰よりもすこし高いくらいの背をした女の子と、膝へ座らせたその子をなだめる女性がいる。社内行事には家族や恋人なら連れてきてもいいというきまりがあった。あたりを見渡すと、他にも見慣れない顔ぶれがいくつか確認できる。
「おお、樫野」
「お疲れ様です」
高倉さんの隣に陣取ると、流れるようにフライ返しを渡された。そのまま焼きそばの調理を交代する。麺の中に入った大ぶりのほたてやバラ肉、にんじんや玉ねぎなどがホイルの上でごとごと揺れる。
「助かった。ちゃちゃっと頼むわ、娘が待ってるから」
そう言って彼は折りたたみテーブルに載った缶ビールをあおった。椅子に座っていた奥さんはすでに立ち上がっており、次に焼く予定と思しき冷凍ピザや肉の準備をしている。その足元では、娘さんもクーラーボックスを開けてチーズを取り出していた。
「お前バーベキュー何回目だっけ」
「あー、覚えてないですね。てか高倉さんも覚えてないですよね」
「まあね」
「あ、多分ゲロのときが最初ですよ」
「ああーあれね、勘弁してほしかった」
入社して最初に参加したバーベキューで、おれは高倉さんに異常な量のビールを飲まされ彼の体に嘔吐していた。太ももまで川につかった状態で向かい合いながら飲んでいたため、顔をそらすのが間に合わなかったのだ。あーあ、なにやってるんだよ、しょうがねえな。そう言いながら、彼は着ていたTシャツをためらいなく脱ぎ捨て、腰までの深さがある場所に移動して流水でそれをすすぎ始めた。あの、本当にすみません。その背中へ声をかける。皮膚の下についた筋肉と、そのまわりにわずかにまとわりついた脂肪。なんとなくこの光景、アングルに見覚えがある気がして別の意味でとまどう。
その瞬間、おれの頭は大きな手のひらでわしわしとなでられていた。そんな顔するなよ、気にすんなって。飲み会なんざ粗相してなんぼなんだから。高倉さんはそう言ってにいっと笑った。まただ。またか。心の端にあるおれの冷静な部分が、小石のような言葉を吐く。が、止めることはできなかった。バーベキュー場があたたかな光に包まれていく。下半身をひたす川の水だけが、その熱を収めるよう主張してきている。
その日以降、高倉さんは色濃い影となっておれの枕元に立つようになった。時が経ち仕事で理不尽にどなられたり突き放されたり体を小突かれたりしても、一転してお前のためを思ってやってるんだぜと言われたり飲みの席でお前以上にできた後輩いないよいつもごめんななどと優しい言葉をかけてもらったりしても、それは変わらなかった。むしろ、『厚み』が増したぶん、扱いやすさのようなものすら感じていた。要素が多くなったため、さまざまなことを考えることができる。俺、実はさ。そんな枕詞で始まるようなこと、開示される事実。それを付加するのはおれのむなしい特技だった。だから、夜な夜なおれはそうしてティッシュを丸め続けた。
「にしても暑すぎる、まだ七月始めでしょ」
そう言って高倉さんはうーん、と伸びをした。タンクトップがそのぶんめくりあがり、わずかに肉のついた腹があらわれる。腹筋の輪郭と、まばらに生えたへそ周りの体毛。軽い咳払いをして、焼きそばをフライ返しで混ぜ返す。視界の端で彼はストレッチも始める。がっしりとした体のあちこちが、様々な角度に曲げられたり伸ばされたりしていく。筋肉もそんなになければ体つきもいいわけではないおれとはまったく違うもの。こんな体に組み伏せられたら、ぜったいに逃げられない。
そう思った瞬間、雲の塊が頭上の太陽を覆い隠した。あたりに広がる景色や食べものや人に、薄い暗がりが膜のようにはりつく。やっぱあちーな。高倉さんがタンクトップの肩紐に手をかける。そうですね。おれもTシャツの首元をつまむ。
そうしておれと高倉さんは全裸になった。彼が、立ちつくすおれにいきおいよく抱きついてくる。地面に映ったふたりぶんの影が、あいまいなひとつの塊になるのが見える。汗ばんだ皮膚と筋肉、その下の骨がおれに押しつけられていく。後退気味のセンター分けの髪、笑うと目元と口の端によるしわ、剃り残しのあるひげと大きな唇。向き合ったその顔を見るたびに体温が上がる。たまらなくなり、おれはそこに近づいていこうとした。汗のにおいと放り出してしまった焼きそばのにおいが、一緒くたになって鼻をかすめる。口を引き結んだ高倉さんの顔が、徐々に大写しになっていく。
が、そこで急に視界がぶれた。突き飛ばされた、と思う間もなく、後頭部と背中に衝撃を感じる。起き上がろうと石ころの上で身をよじるが、高倉さんが馬乗りになってきたのでそれは叶わなかった。高倉さんがにいっと笑う。筋肉で膨らんだ右腕が、ゆっくりと振り上げられる。
その瞬間、鮮烈な痛みと破裂音が体を突き抜けた。てのひらの形をしたひりつきを胸に感じながら、おれは食いしばった歯の間から息を漏らす。魚のようにびくびくとはねる間にも、高倉さんは同じ場所を何度も執拗に平手打ちしてきた。別に我慢はできた。でもあえておれは声をあげた。楽しいと思っているのでそうした。待ち望んでいたのでそうした。
「うわ、勃ってんじゃん。おい、なあ、聞いてんの。もっと強くしてほしいか。え? 言ってみろよ。ほら。なあ」
高倉さんの弾んだ声におれは答えられない。限られた視界の中であたりを見回すと、他の社員やグループはもちろん、高倉さんの奥さんや娘さんまでもが、何事もないようにバーベキューへ興じているのが見えた。とつぜん裸になったおれたちはあまりに異質なのに、誰もそれに気づいていない。透明。おれたちは水や空気と同じだ。
奥さんが、娘さんが。それでもおれは言ってみた。もっともらしいことを口にしてみた。が、あえなくそれは無視される。太ももが、ぱしんと叩かれる。おれの体から足や尻をどけ、彼は膝立ちの状態になった。言葉はなくともやるべきことはわかっていた。すばやく起き上がり、おれは体をひっくり返して四つん這いの姿勢を取る。犬みてえ。背後で高倉さんがけらけらと笑う。わんっ。冗談めかして吠えると、突き出した尻を叩かれた。わんっ。おれは犬になった。
四つん這いになったおれの下半身に、高倉さんが熱くて固いものを押しつける。目をつむると、頭の中でそれははっきりとした輪郭を持ち始めた。荒い息。こすりつけられるそれ。おれは先ほどよりも大きな声で吠えた。すると、なんの前触れもなく尻の肉をわしづかみにされた。普段は外気に触れていない部分が広げられ、そこに指が浅く出入りする。
「なあ、樫野、いいか」
高倉さんの動きが止まり、汗ばんだ体がおれの背中へしなだれかかっていく。先ほどとは打って変わって、尻から離れた彼のてのひらは優しくおれの全身をなで始めていた。首をめいいっぱいひねり、今度こそおれは高倉さんの顔へ近づいていく。ほんとうに、いいんですか。答えを予想しながらおれは聞く。眼前に広がった彼の顔の目元や口元に、しわがきゅっと寄っていく。仕事で怒鳴られ殴られ責められ、それでも最後には飲みの席などで向けられる、その笑顔。
「いいよ」
酒臭い息が顔の上を転がる。その言葉におれはうなずいた。うなずくしかなかった。考える間もなくうなずかざるを得なかった。てのひらが体から離れたかと思うと、それは股下へ潜っておれのちんぽを握り込んだ。あいたもう片方の手で、尻の穴が広げられる。その先を、予感する。
その瞬間、唐突に彼のくしゃっとした笑顔と、あそこを包んでいた感覚が消え失せた。きた、と思う間もなく、尻へずどんとした重みのある衝撃が走った。四つん這いが維持できなくなり、地面へうつぶせに倒れ込む。歯を食いしばってうなりながら、主に股ぐらに広がる痛みに耐える。足によって尻をぐりぐりと押さえつけられているため、それが弱まることはない。
「たかくらさん、たか、くら、さ」
「ははは、嘘だよ」
お前だって、わかってただろ。サッカーのパスのような要領で蹴られ、体をごろんと仰向けにされる。服従の姿勢。わんと鳴いた瞬間にちんぽを踏まれ、おれは声にならない叫びをあげる。悲鳴なのか喘ぎ声なのか自分でもわからない。嫌だ逃げたいという気持ちとやめないでずっとこのままでという気持ちがないまぜになる。困惑したあそこは固くなることを選んだ。高倉さんが、弧を描いた唇を指でなぞった。これがいいのかよ、へえー。博物館のキャプションを読むような調子の声が降り注ぐ。やっぱり、こうなってしまったら逃げられないんだ。ふと頭に浮かんだ言葉に、身じろぎをとめる。が、遅れて快感がやってきてたまらず腰をよじった。
ちんぽやその根元をくりくりいじられながら、終点がすぐそこまできているのを感じる。湿った息とあえぎをそのままにして、はいのぼってくる気持ちよさに身を預けようとする。が、計ったようなタイミングで高倉さんはそこから足を離してしまった。いつの間にか光量を取り戻しつつある太陽光に照らされ、汗と体液にまみれるおれ自身はぬらぬらとにぶく輝いた。
「なんで、なんでなんでなんで」
「まだだめ。俺がいいって言うまでだめ」
「むり、もうむりぃ、おねがい、おねがいします」
もう、我慢できない。でも、だめなのだ。それは許されない。高倉さんに許可をもらわないといけない。すべては彼にかかっている。もし飽きられてしまったら、永遠に快感は得られない。でもおれもそうやって楽しんでいる。織り込み済みの関係。いつから結んだものなのか。視線の先で、ちんぽがぴくりと下へ動くのを見た。が、それは力を増した高倉さんの足によって元気を取り戻してしまう。頭が、白く染まっていく。河原に広がる景色に、遠ざかっていた鮮やかさが戻ってくる。雲から太陽が顔を出す。屹立した塔が、音を立てて崩れ落ちる。
「高倉さん、焼きそばできましたよ」
「おっ、サンキューな」
紙皿に載せたそれをなんでもないような顔をして彼に渡し、その言葉を聞きつけ群がってきた他の人に同じ要領で配っていく。それが一段落すると、端の方に残った麺と野菜のかけらを自分の皿に乗せた。ひそかに食べたいと思っていたほたては跡形もなくなっている。先ほどビールを飲んでいたあたりで、高倉さんは家族と楽しそうに焼きそばを囲んでいた。もちろん服は着ている。脱いだ形跡はとうぜんない。箸につままれたほたてが、娘さんの大きな口の中へ吸い込まれていく。冷めかけた焼きそばを口に運びながら、おれは下を向く。ズボンの中でまだふくらんだままのあそこと目が合った。あれは幻じゃない、たしかにあったことなんだ。そう主張しているようにも見えた。
意味不明なことを言ったり仕事を教えてくれたりもういいよ知らんと突き放したり酔って抱きついたりしてくる彼と、妻や子供へ笑いかけたり手を握ったり目線を合わせるためにかがんだりする彼が、同じ人間として目の前に立っている。こういうことでもなければ、おれはその半分しか見ることができない。マシュマロでも焼くかと思い立ち、かたわらにあったそれを竹串にさして火にかける。焦げないようにくるくると串をまわしていると、高校生のころにやっていたモンスターを狩るゲームのことを思い出した。草食モンスターの肉を、こうやって火にかけるのだ。そのときに流れる曲やシステムボイスを、おれと当時いちばん仲の良かった友人はよくふたりで真似していた。部活の後。昼休み。休日の彼の家。あらゆるところで耳にしていたはずのそれは、もうどこからも聞こえてこない。焦げたマシュマロの端に火が灯る。あたりにただよう甘い香りに、不快な、つんとしたにおいが混じる。
「あっちー! 泳ぐぜー!」
その瞬間、おれの横を誰かがすばやく走り抜けた。その風圧で火は消えたが、肝心のマシュマロは地面にぼとりと落ちてしまった。ああ、というおれの声と自身の軽快な叫びの余韻を置き去りにして、その人物は川に勢いよく足を突っ込んだ。日焼けした高倉さんとは対照的な白い背中、サイドに三本のラインが入った青色の水着、シュノーケルで押さえつけられて髪の毛がもこっとした頭。それらが、深い緑に染まった水に飲み込まれていく。
「あいつはほんとに元気だな」
「え、ええ、そうですね」
いつのまにか隣にいた高倉さんがそう言うのであいまいに笑った。落としたマシュマロを片付けながら記憶を探るが、やはり彼を社内で見かけた覚えはなかった。この会社ではよくあることだった。知らない顔が我が物顔で社内を闊歩していたかと思うと、毎日顔を合わせていたはずの人の姿が急にいなくなってしまう。
そんな彼は水の中でぷかぷかと浮かんだり泳いだり、そうしていたかと思うと急にどぷんと潜ったり逆立ちをしたりして遊んでいた。水しぶきがそのたびにばしゃばしゃと舞い上がる。川はおれや高倉さんがいる河原の石の上とは違い山側の奥まったところにあり、容赦のない日差しとは無縁の場所になっていた。きっと、かなり冷たくて気持ちいいことだろう。おでこの汗を手の甲で拭い、Tシャツの裾をつまんでぱたぱたとあおぐ。履いている水陸両用のナイロンパンツの右側、膨らんだポケットの中身が太ももとこすれる。足をおおうマリンシューズとも目が合った。
「なあ、肉どうすんだよこれ」
「え、えっと」
怒号が響き、おれと高倉さんは顔を見合わせた。そうだ、須藤さん。おれはこの近くで起きていたことを久方ぶりに思い出す。無視だ、無視。彼のささやきを聞きながらそれでも声のほうを見ると、彼が後退しながらこちらへ近づいてきているのが見えた。子犬のような目が、ちらちらとおれたちへ向けられる。が、その視線は誰ともかち合わない。河原の石。落ち葉。誰かが放置したゴミ。サンダル。靴。足。川面。おれたちの目はどこにも繋がらずせわしく動き、映る世界から須藤さんの姿を切り離していく。その過程で、彼に水鉄砲を打たれていた同僚の姿をおれは見つける。てのひらで顔をあおぎながら、彼女はテントの中で酒片手に社長や他の社員と談笑していた。ゆるくて楽しいバーベキューは続いている。今いる場所に誰もがぴったりと固定され、明るくフレンドリーな空気を放つ役割をまっとうしている。
暑い。急にその気持ちが強くなった。絶え間なく体をつたっているのを感じていた汗のしずく、まとわりついてくる湿気が、とにかく耐えがたいものに思えてきた。高倉さんが放つ酒臭い息を感じながら、おれはその場で足踏みをする。涼やかな空気をまといながら流れゆく川は、もう目の前にある。が、高倉さんの体や須藤さんのおびえた様子を意識するたび、それはすこしずつおれのもとから離れていってしまう。が、対照的に妄想はこちらへ急速に近づいてきた。ふたたび日が陰り、高倉さんが組み伏せたおれの中へずぶずぶと入ってくる。指ではない。太い蛇だ。感情の一端を時と場合によっては言葉よりも如実にあらわしてしまうそれが、おれの中のいたるところへ牙を立てていく。
もう、嫌だった。なにも言わない真面目な顔の裏でこんな想像をしてしまう自分自身も、こういったものを人生のところどころで幾度も差しはさまれ見せつけられ、でもそれ以上のことはぜったいに現実に起こり得ない、こんな世界も。
大口を開けて荒い息をつきながら、遠くで流れる川へ目を向ける。そこにはシュノーケルを身につけ心底楽しそうな様子の男がいる。潜ったり浮き上がったりしながら、彼は魚よりもはるかにぶかっこうな、でも人間にしかできない動きで軽やかに泳ぎ回っていた。あーやっべ、きもちいい。高倉さんの声が吐いた息に溶けていく。それを想像の中で聞く。ほら、もっと飲もうぜ。現実の彼が水滴のついた缶ビールを差し出してくる。ゆっくりと缶を手に取ると、汗ばんだてのひらがすっと冷たくなった。
おれは足踏みを止めてしまう。目線だけは川面に注ぐが、それもビールを飲んでいると逸れがちになっていく。おれはきれいにごまかしてしまえる。今までの人生でも、幾度となくそうしてきた。この会社に入ったときも、学生時代を過ごしていたときも、もう細部を思い出せないできごとが起きたときも、今まさにおびやかされている須藤さんをながめている、このときだってそうだ。下からは妄想のあそこ、上からは飲んでいるビールに体を占領されながら、高倉さんとなにかを話す。内容はあまり頭に入ってこない。それでも意識だけは、川とそこを泳ぐあの男にあった。
だから、おれはすぐに気づくことができた。小さな違和感だったそれは、ほどなくして確信に変わる。先ほどまであんなに軽やかだった彼の泳ぎが、精彩を欠き始めていた。シュノーケルからぴょろぴょろと水が噴き出すことが増え、水面からたびたび出ていた頭が目元以外を残してまったく見えなくなった。視線も、川底ではなく岸のほうに向き続けている。あんなに激しくあがっていた水しぶきも、まったく見られない。いつかネットの記事で見た、おぼれている人の特徴が頭をよぎる。文章といっしょに掲載されていたイラストと、目の前の彼の姿が、ぴったりと重なっていく。
いやいや、そうはいってもふざけているだけかもしれないだろ。頭の中で声がする。マリンシューズを履いた足にぐっと力が入る。でも、もし本当におぼれているとしたら。頭の中で響く悲鳴のようなあえぎと、須藤さんの叫び声が重なる。血管の浮いたごつい手に胸倉をつかまれ、彼は宙に浮いていた。
「おい、てめえら一緒のグループなんだろ、こいつがやったことどう落とし前つけてくれんだよ。なあ」
怒号が河原に響き渡るも、笑顔と幸福にまみれたバーベキューは揺らがない。さすがに社員の家族や恋人がどぎまぎとし始めたが、それはそうなったそばから肉の入った皿や飲みものの入ったプラコップを手渡されたり、会話に引き入れられたりバドミントンセットやビーチボールを差し出されたりすることで鎮静化がはかられていく。須藤さんを宙に掲げたまま、男や金髪の女たちが白けたような表情であたりを見回す。唇がひくつき始めるのを感じた。胸元のTシャツを引き寄せ、顔面の汗をぬぐう。
「やあ、みんな楽しんでるかな」
やけに大回りをして、テントから社長がこちらに近づいてきてくる。頭頂部でお団子にした髪、派手なバンダナとタイダイ染めのTシャツ、耳にはまったぶっといイヤリング。丸っこい体をどすどす揺らしながら、彼女は須藤さんのほうをいっさい見ることなく社員やその家族と乾杯をしていった。お疲れ様です! 最高です! 楽しいです! ありがとうございます! いずまいを正し、その場にいる全員が深く礼をする。おれもそうしてしまう。
「よかったよかった。でも、そんなにわたしにばかり感謝することはないんだよ。この場は、ここにいるみんなが力を合わせて『創った』ものなんだから。いやあ、それにしてもね。みんな。これが平和なんだよ。こうして酒やおいしいものを楽しんで語らえば、おのずとこうしてそれは実現するんだよ。わたしは、世の中にそれを知らしめるような仕事をしていきたいんだ。だからみんな、ここにいる自分以外の全員に、感謝するようにね。『PEACE,LOVE,ACTION.世界は私たちがよくしていく』だよ」
社訓の一節をまじえつつ、うっとりと彼女は語った。周りの社員たちが、口々に感謝や喜びの言葉を口にし始める。
「樫野、いつも本当にありがとう!」
高倉さんがおれの肩をぐっと抱く。あー、いく、出すぞ、出しちまうぞ。彼の腰の動きが早まり、おれの中にはまったものが輪郭をいっそうくっきりさせていく。たかくらさん。あえぎの隙間で、彼の名前を呼ぶ。応答はない。がんがんという衝撃と、尻の肉をぎゅっとわしづかみにされる感触だけが返ってくる。ちかちかし始めた視界の中、地面に手をついたおれはひたすら川面に目を向けている。そこにはまだあの男がいた。が、その体はうつぶせの状態でぷかぷかと浮いているばかりで、動くことはない。濡れそぼった髪。色を失った肌。水も空気も吹くことのないシュノーケル。妄想のくせに、それはやけにリアルに思えた。
高倉さんの腕が肩から離れ、彼は社長の元へ駆け寄っていく。折りたたみテーブルに須藤さんが突き飛ばされ、酒のびんが割れる音と悲鳴が響く。その中でも、おれは水に沈みかけている彼を見つづけた。妄想と違い、彼はまだかろうじてもがいている。
本当に、気づいているのはおれだけなのか。でも。いや。だって。おれの声色をしたなにかが、頭の中で絶えずわめく。ぎゃり、と足元で石がこすれる。愛と平和が。楽しいね。てめえふざけんなよ。謝れ。殺すぞ。それに、おれの周りで発せられる音が載っていく。ポケットに手を突っ込む。その中のものを、ぎゅっと握る。舌打ちが響く。
それが自分の口から出たものだと気づいたのは、川のほうに大股で歩きだしてからだった。あらゆる狂騒と高倉さんの裸とちんぽが遠ざかり、体が強烈な日差しから逃れていく。手を入れていた水陸両用パンツの右ポケットから、握りしめていた真っ黒なゴーグルを取り出す。バーベキューが始まったときから、その用意をしていたときから、ずっとそこにしまっていたものだ。それを装着し、Tシャツを脱ぎ捨て後ろに放る。振り返ることなく、おれは眼前の深い緑へ体を滑り込ませた。
瞬間、体へ張りつく汗やじっとりとした暑さ、むわんとした食べ物のにおいが溶けるように消え去った。黒みがかった視界の中で、透き通った水と流れる小さな葉や枝、川底の石やその近くを泳ぐ魚だけが広がる。すべての不快感が過去のものになる。冷たい。気持ちいい。本当は、もっとはやくこうしたかった。川に飛び込んでいく彼を見て、ずっとうらやましいと思っていたのだ。飛び込めるほどの深さがあるのはわかっていたが、こうしていざ入ってみると思ったより深く、流れも強い。気を抜くとこちらもおぼれてしまいそうだ。
手を伸ばせば彼にさわれるくらいの位置まで近づき、いったん水面に顔を出す。息を大きく吸い込んでから潜り、下から突き上げるように脇あたりに手を差し込み、持ち上げようとする。が、そこでようやく、おれは自分のあまりにも浅はかな行動に気づく。あ、しまった。そう思う間もなく、男がものすごい力でおれにしがみついてきた。足先が冷えた水に掴まれどきっとする。あわてて男を弾き飛ばすが、そのたびに彼は文字通り死にものぐるいでこちらにしがみついてくる。マスクの中は大粒の水滴に満たされており、表情は伺えない。絡みついてくる水の冷たさと体温のぬくもりを交互に感じながらもがくが、体はなかなか思うように動いてくれない。頭上で揺れる水面とその向こうにある太陽が、ひとごとのようにゆらゆらとしている。やっとの思いで口や鼻のあたりを出し、やめろとか離せなどとわめこうとしたが、それはあえなく泡に変わってしまう。何度か同じことを試みても無駄だった。会話はおろか、ろくに息を吸うことすらも叶わない。
おぼれている人を飛び込んで助けようとしてはいけません。そんな文言が、赤く点滅しながら頭の中をくるくると回っている。おぼれる。息。水。死ぬ。死ぬ。だんだんとそれしか考えられなくなり、自分の体の感覚があいまいになっていく。その中で、目の前の彼がくわえたままのシュノーケル、その周りを覆う唇の様子がやたらとくっきり見えた。紫色。ふやけて皮もむけている。藻のようにふよふよとするそれの動きを、ひとごとのように目で追ってしまう。
そうこうしているうちに、日が差す水中にいろいろな景色が浮かんでいく。会社。ひとりで住んでいる高円寺の1K。大学の大教室。高校や中学の教室や部室。よく通った友人の家。後ろから見上げる大きな背中。下着に描かれたでかい犬。ぎゅっと握られたてのひら。おれの口から生じる泡が、手足や目の前の男の体をすり抜け昇っていく。だんだんともがくのが億劫になってくる。もう、どうでもいい。苦しいはずなのに、毛布にくるまれているかのようなあたたかな気持ちを感じていた。上に向かって泳いでいるのか下に向かって泳いでいるのか、そもそも陸にいるのか水の中にいるのかすらよくわからない。
その中で、はっきりと人の声のようなものがしているのを感じていた。なにかをくわえたままで喋っているらしき、うめきとも言葉ともつかないくぐもった声。おれはそれになにも返すことができない。ごぼっ、ごぼっ。体が勝手に痙攣し、手でふさいでいる口から泡の塊がもれた。すぐ目の前にある真っ黒で冷たい終わりが、まったくぴんとこない。目の前の男が、ようやくシュノーケルから口を離す。そこから小さな泡がいくつかあらわれ、消えていく。が、それだけだった。もうその口は動かない。なにかを言ってくることもない。あたりは静かになった。冷え切ったそれにいだかれながら、意識が少しずつ遠ざかっていこうとする。
その瞬間、足先がなにか固いものに触れた。それは形を変えて足をずぶずぶと飲み込み、また消える。何度かそれが繰り返され、徐々に足が沈み込む面積が増えていった。走馬灯のみを映していたはずの透明な水に、茶色いもやが混じる。足元から舞い上がるその砂粒ひとつひとつが、肌や腕の毛に跳ね返っては落ちていく。
そこでおれは我に帰る。ごぼり、と大きな泡の塊を吐き出し、急いでかたわらの男の肩を抱く。だいぶ下のほうに見えていた川底が近づいてきている。どうやら浅瀬へ向かう流れに体が引っかかったようだ。彼を引っ張りながら、渾身の力で水をかく。普通ならそんなことはぜったいに無理だが、幸か不幸か彼の体はすっかり脱力してぐったりとしてしまっており、おれのなけなしの体力と泳ぎでもなんとか運搬することができた。
ややあって、両足が砂利をしっかりと捉える。そのままそこに体重をかけ立ち上がると、水から出た顔や上半身が久方ぶりの日光のぬくもりに包まれた。草と川の水のにおいも鼻に届く。それを勢いよく、何度も吸い込んでは吐き出す。ゴーグルを外した視界がぼやけて震え始める。助かった、助かったんだ。そう思うとさらに涙があふれた。先ほど水中にいるときはすべてが他人事のように思えていたのに、こうして陸に上がると、その状態がいかに危なかったのかということがよくわかった。
ごぼごぼと咳き込みながら足を動かし、深みから離れていく。完全に両足が水から出た瞬間、限界がきた。受け身も取れないまま、おれはその場にいきおいよく倒れ込む。支えを失った男も、とうぜんいっしょにおれの隣へどさりと倒れてしまう。急いで立ち上がろうとするが、体がまったくいうことを聞かなかった。どんなに頑張っても、すこしも手足に力が入らない。
なんとか動かすことのできる首をかたむけ、かたわらで倒れる男の顔を見る。シュノーケルは口から外れていたが、あいかわらず顔を覆うくもったマスクはそのままだった。肩や胸が激しく上下しているのを見るに、どうやらちゃんと意識はあるらしい。ときおり、おれよりも数段多く水を含んでいそうな咳払いもしている。そのことにひとまず安堵しつつ、すこしずつ動くようになってきた腕を使って彼のマスクをゆっくりと外す。そこからあらわれた焦点のさだまっていない細い目が、ゆっくりとこちらをとらえていく。なにか言うかと思ったが、口からは湿った咳が出るばかりだった。おれよりも長くおぼれていたのだから、無理もないだろう。というか、意識を保てているのが不思議なくらいだった。
立ち上がれないまでも身じろぎくらいはできるようになった体で、大の字にあおむけになる。降り注ぐ日の光を全身で受け止め、彼がしゃべりだすのを待つ。それにしても運が良かった。あのままでは自力の脱出は無理だっただろう。もし、岸へ向かう流れにつかまることがなかったら。そうでなければ、今ごろ。
「俺たち、死んじゃったんすかね」
彼のほうへ目を向ける。瞳の光と顔色はすこしずつ戻ってきていたが、唇は水中で見たときと変わらず真紫のままだった。え? 思わず笑いそうになる。が、楽観的だったその気持ちは徐々に不安へと変わる。草原と石だらけの河原。おれたちが流されてきた川を挟んで広がる林と藪。おれたちの周りにあるそれらに、肉が焼けるにおいとアルコールの香り、人のざわめきや怒声はない。気配すらも感じられない。あたりは不自然なほどの静寂に包まれていた。
「ごめんなさい。俺のこと助けようとしてくれたんすよね。嬉しかったっす。でも、ごほっ、うえっ、すみませ、まだ水が」
「いやいやいや」
たしかに走馬灯っぽいのは見たけど、そんなことある? 本当に? が、可能性を頭ごなしに否定できるような材料も見つからない。おたがいおぼれながらもこうして意識もあり問題なく会話ができている以上、そう長い時間流されていたわけではないだろう。バーベキュー場として整備されていた河原はそれなりの広さがあったし、そこからすこし離れるとこのような景色の場所がある、ということは行きの車中からもなんとなく確認できていた。が、それだけといえばそれだけだ。死後の世界はそういうものです、といわれてしまえば納得するしかない。仮にそう遠くないところに流されただけにしても、あれだけ多くの人がいてあれだけ大騒ぎしていたのだから、ある程度余波というか音漏れというか、そういうのが雰囲気だけでもただよってきてもいいはずだった。おれは湿った頭をかく。どっちだ。どっちなんだ。
「どっちなんでしょうね。天国か、地獄か。地獄は嫌だなー」
「まって、勝手に話を」
「あ、引きましたよねすみません。でも、どうせなら天国がよくないっすか。この世界がもう地獄みたいだし。楽しくないじゃないっすか。つらいこととあらゆることが引き換えでーす、みたいな顔して。狂わないようにえさと漫画だけ与えられて後の時間は殴られながら檻に入れられているみたいな。はーあ、死にたい。いや死んでるのか、死、あ、あははは! だめだなんか、酸素吸いすぎてハイになっちゃってる。ごめんなさいこんな話、ひきますよねすみません」
「い、いや。別にひきはしないけどそうじゃなくて。死んでる前提で話を進めないでって」
「ひかないんですか」
「え。あ、うん」
男がのそりと起き上がる。血の気が戻り始めている顔色のまま、彼の目がすこしだけ見開かれる。
「いや、でもたぶん死んでるっすよねこれ。俺たち以外に誰もいないし」
「いやいや。息吸えてるじゃん話せてるじゃん。それに、腕をつねると痛いし」
「そういう感じなのかもしれないじゃないっすか、本当は」
「まあそうかもしれないけど。そんなこと言い出したら」
そう言い合っている間も、他の人間や生きものの気配を感じることはない。だんだん余裕が出てきたのか、男はへらへらと笑い始める。そっかー、俺死んだのかー、へへ。後ろ手をついて彼は空を見上げた。それを見つめるおれの視線に気づいたのか、今度はあちらがおれのことをじっくりと観察してきた。瞳が一瞬のうちに上から下へ動いたのを感じる。
「てか、初めましてっすよね。あの、一緒の会社の、方……?」
「そう。おれも会うのは初めてだよ。さっききみが川に飛び込んでいくのを上司と眺めてたときに、同僚だって聞いた」
「お恥ずかしいところをお見せしたっす。川でバーベキューするっていうから、どうしても泳ぎたくって。でもみんなぜんぜんいかないから。これでも我慢してたんすよ」
おれもだよ。そう言うと、彼はまたこちらにじっくりと視線を向けてきた。耳にかかっていた髪が、濡れた重みでぷらんと下へ垂れ下がる。彼の笑みが、ひとまわり大きく花開く。
「え、まじすかまじすか。気が合いますね。じゃあ一緒に泳いだってことになるんすかね。やっぱ川に来たなら泳がないと損っすよね! まあおぼれて死んじゃいましたけど」
「ちょ、まだそうと決まったわけじゃ」
「冗談っすよー、でもごめんなさい」
「おいおい」
河原であぐらをかき、おたがいけらけらと笑い合う。あいかわらずあたりは静かなままだったが、だからこそおれと彼の放つ言葉と笑い声はよく響いた。体が乾いて暑くなってきたな。もう一回川入ればいいじゃないっすか。さっきしっかりおぼれたのに? 大丈夫っすよ、もう死んでますから。だからさぁ、はぁ、まあ、もういいか。肩をすくめると、彼は勢いよく立ち上がっておれの手を引っ張った。どうやら体の回復はあちらのほうが早かったらしい。まだ重さの残る足で彼についていき、膝下くらいまでの深さのところへ思い切り倒れ込む。きもちいー! 楽しーい! お互いに水中でそう叫びながら、おぼれる前に立ちあがる。その後はどちらともなく水をかけ合ったり、足をひっかけて柔道のようなことをして遊んだ。肉を焼くより酒を飲むよりぜんぜん楽しい。仮にここが本当に死後の世界だとしたら。今までいたあそこはいったいなんだったのだろう。
「あ、そういえば。川名カナタっていいます。このまま死んだやつらどうしふたりきりってこともあるでしょうから、まあ、よろしくお願いします」
「え、えっと、樫野カイトです。第二営業部の」
「そういうのやめましょうよ! もうどうでもいいっす!」
川名が思い切り両手で水を飛ばしてくる。腕でそれを防ぎつつ、おれはあいている右足で水を蹴り上げた。カナタって呼んでくださいよ。おれもカイトでいいよ。水音のさなかでおれたちははしゃぎあう。コンロの煙も肉のにおいも、おれたち以外のざわめきもない河原。不自然な静けさは、今や心地よくすらあった。
「そういえばさ、聞きたいことがあるんだよ」
「なんすか」
「なんでおぼれてたの。いや、陸から見てるぶんには途中までは普通に泳げてそうだったし。足とかつっちゃったのかなって」
「ああ、そういうわけじゃないっすよ」
「じゃあどうして」
「いや、あの、その。シュノーケルって、水中で呼吸できるもんだと思ってて」
え。つぶやきがぽろっと水面に落ちる。川のせせらぎに混じり、蝉がシャワシャワと鳴き始めるのが聞こえた。
「ほら、よくテレビとか動画とかでシュノーケルくわえたまま潜ってるじゃないっすか。それにほら、口のところにもういっこ息が抜けるところがあるタイプのシュノーケルあるじゃないすか、俺がつけてたやつみたいに。なんか、そこでうまい具合に潜水してても一呼吸ぶんくらいは息が吸えるのかなって思ってて」
「あ、あれは管にすこし水が入ったときに排水するためのやつだよ」
「はい。やっぱりそうですよね」
よくわかりました。初めて彼は笑顔を引っ込め、しゅんとした顔をしてみせた。おれは顔がにやついていくのをとめられなかった。そんなことで道連れにされたかもしれないのに、わかっているのに、おかしくてたまらなかった。
「ぎ、疑問には思わなかったの。調べたりとかそんなわけないとか思いとどまったりとか」
「いやいやさすがに思いましたよ。本当にそうなの、って。でも、思いついたのがああやって川に突撃する直前で。部署の人とピザ食べながら考えてたらああそういえば、って。だったらちょっと試してみるかって。そういうとき止められないんすよ、疑問に思っててもたしかめたくなっちゃって」
「で、しっかり水を飲んでおぼれたと」
「予想はしてたんですけどパニックになっちゃって」
にやつきは、今や完全な笑みになってしまっているのが自分でもわかった。なおも鳴り続けている蝉の声に、リズムの違う別の蝉のものが重なっていく。目線の先で肩を落とす彼から、目が離せなくなる。死んでしまったかもしれない、ということはもはやあまり気にしていなかった。どちらかというと、最後の最後にまでこんなことをしてくるのか、という気持ちのほうを強く感じていた。そんなアホみたいな理由で巻き込んで、ほんとすみません。ますますうなだれるカナタへ、おれは勢いよく水をかける。顔をかばった腕をのけ、彼は目を丸くする。そこへ、さらに水を飛ばしてやる。カナタが、さらに目を見開く。引っ込んでいた笑顔が戻ってくる。今おれがしているだろう表情と、それはよく似ていることだろう。冷えた水がおたがいの肌をすべる。それは妄想でもなんでもない。仮に今際の際に見た幻だったしても、そう呼ばせたくない。今このときだけは、この気持ちだけはおれのものだ。
「せっかくふたりきりだし、もっとちゃんと遊ぶか」
「そうっすね」
しっかりと地に足をつけながら、おれたちはおのおのゴーグルやシュノーケルを装着する。そこでもう一度目が合い、またけらけらと笑い合った。蝉の鳴き声が強くなる。見つめる先の川面も深い緑でうねっている。ふくらはぎに当たって砕けるその流れが気持ちいい。川を越え向こうに広がるやぶも、せわしなくがさがさと揺れている。
ん? 今は風などまったく吹いていない。
「あれ、人がおるでよ」
熊かなにかかと身構えたが、そこから出てきたのはショルダーバッグを提げたサングラスの男性だった。ポケットがたくさんついたベストやつるつるとした長袖のラッシュガード、大きな長靴などを装着し、持っているかばんの横には立派な竿が差し込まれている。どうやら釣り人のようだ。しかもひとりではなく、後から三人ほど似た服装をした人が草をかきわけ登場した。一瞬の間の後、彼らはぎこちなくおじぎをしてきた。おれたちもそれにならって会釈をする。鬼、だろうか。地獄の鬼が休暇を楽しみにやってきたのだろうか。
「こ、こんにちは。川遊びの人はあんまここらへんこないのにね、珍しいな」
「ね、けっこうバーベキュー場から離れてるしね」
「あ、あの」
バーベキュー場、あるんですか。カナタがシュノーケルを外しながら質問すると、彼らはよりいっそう怪訝そうな表情を浮かべた。
「え、きみらそこからきたんじゃねえの」
「いや、あの、ええと」
「ちょっと歩きづらいかもだけど、その後ろの草っぱらまっすぐ進んでけば五分くらいでつくよ」
「そ、そうですか。ありがとうございます。あ、あの」
「どしたの」
「その。ここは死後の世界だったり」
「はい?」
「あっすいませんなんでもないっすとにかく行ってみまっす」
ぺこぺことおじぎをしてさっさと歩き出したカナタの後を追う。長く伸びた草の先端がふくらはぎをなぞる。そのたびに、安堵の気持ちとおかしさがこみあげてくるのを感じていた。乱暴にシュノーケルを外したカナタの耳は真っ赤になっている。おれたち、死んじゃったんすかねえ。声色を真似してそう言うと、彼は無言のまま歩調を早めた。あんなに重かったおれの体はほぼ回復しており、その速度にも難なくついていくことができる。
「ここはぁ、死後の世界だったりぃ」
「うるさいっすね、カイトさんと俺初対面なんすけど」
「死んだものどうしふたりきり、って言ってくれてたじゃん」
「忘れてください。あ、戻ってきちゃいましたよ」
ほどなくしてバーベキュー場が姿をあらわした。おたがいにため息をつきながら、社員が集まっているところへ向かう。が、そこにはおぞましい光景が広がっていた。散乱した食材や机、キャンプチェア。めちゃくちゃになったコンロ。めちゃくちゃになっていないが炭になった肉や食べものが黒い煙を吐いているコンロ。泣き叫ぶ子供や気まずそうに微笑むその親。歯を食いしばったり怯えたりまあまあーとへらへら笑ったりしているうちの社員。烈火のごとく怒っている柄の悪い見た目のグループ。遠巻きにそれを眺める他の利用客たち。うつぶせに倒れ、ぴくりとも動かない須藤さん。それらすべてを、ただじっと見ているだけの高倉さん。
「うわみんなどしたの、なんすかいったいど」
慌ててカナタの口を手でふさぐ。川で泳いでいたから、いきさつがよくわかっていないのだろう。だったらここで存在を主張するのは悪手だ。これこそ、おれたちが出ていってもどうにもならないことだろう。解決可能なタイミングは、もうとっくに過ぎ去っている。そう考えることに対するためらいのようなものはもう浮かばない。だって、おれはもう知ってしまっていた。同僚や上司や社長、高倉さんと過ごした日々と、カナタと一緒におぼれて助かり、遊んでここに戻ってくるまでの数十分が、交互に頭へ浮かんでくる。
「あのさ、提案があるんだけど」
「奇遇すね、俺もたぶん同じこと考えてます」
どちらを選ぶかは明白だった。だって、おれたちはもう『地獄』にいるのだから。
「荷物回収して、帰っちゃお」
「そうっすね」
道の駅寄りましょうよ。その前に病院が先だろ。酒やおいしいものを食べて語らうことで生まれた、平和な場所。そこに背を向け歩き出す。てめえらマジで殺すからな。須藤さんの胸倉をつかんでいた男の声がする。が、それは吹き抜ける風にさらわれ、おれたちのもとには届かない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
試し読みは以上となります。
ぜひ、本編をお楽しみいただけると幸いです。
イベント以外の入手経路
大滝のぐれの通販、渋谷ヒカリエ八階「渋谷〇〇書店」内の棚「ウユニのツチブタ書店」、Kindle Unlimitedにも、イベント終了後少し時間をいただきまして、販売、配信を開始する予定です。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
