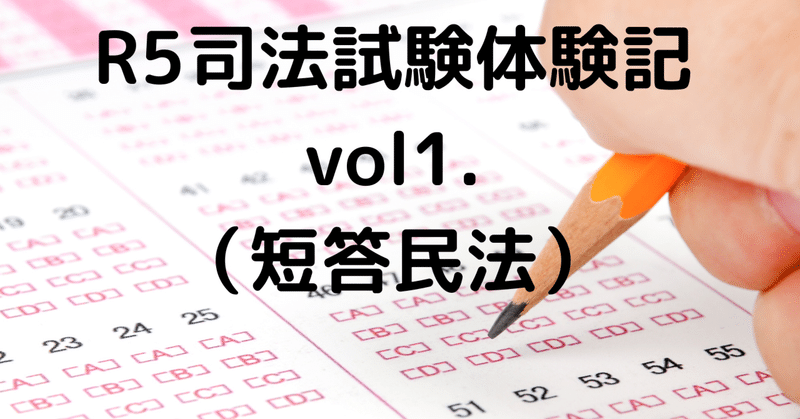
アラフォーR5司法試験体験記vol1.(短答民法)
はじめまして
みなさんこんにちは、
アラフォー司法受験生のボーダーです。
本ブログでは私のR5の司法試験の体験記を書いていきたいと思います(現在2023年の8月、論文発表前です)。
来年以降受験される方に少しでも役に立てばうれしいです。
なお、私の属性は下記の通りです。
・アラフォー社会人
・ロー既習在学中、非法学部
・予備の受験、勉強経験なし、司法試験直行組
・学習開始3年と2か月、総学習時間約7,000時間(日平均6時間)
・ロー成績:30人中20位。中の下って感じ。授業予習復習しないタイプ
・基本書や演習書利用ゼロ(国際私法のみ演習書利用)
・基本7科目の基礎テキストはLEC矢島先生のスピードチェックテキスト
・短文事例(旧司&予備過去問約50問)は、伊藤塾の問題研究
・司法試験過去問はLEC矢島先生の論文過去問講座
司法試験、目指すは1300位で合格!
今回の司法試験の準備は、全く計画的に進みませんでした。ほとんどの受験生も同じですね。特に予備試験も受験経験のない私にとっては短答対策が最後まで足を引っ張りました。
・論文の目標
そんな状況でしたので、私は試験半年前には現実的な目標を1,300位に設定しました。直前期は常にこの1300位合格をイメージして逆算してました。
1300位の私なりの具体的イメージは、論文8科目全てでDを取らない(=2000位以上/短答合格3100人=下位3分の1に入らない)。
確実にCを確保して、その延長戦上でBを狙って、A取ったらラッキー。こんなイメージでした。
・短答の目標
また、短答は過去問もままならず、とりあえず受験者平均の115点前後取れればOKとのイメージでした。具体的には①民法50点②刑法35点③憲法30点が現実目標でした。
うそでしょ。民法短答65点もとれちゃった。

民法は50点を絶対確保。これが私の目標でした。
でも、ふたを開けてみたら、なんと65点/75点も取れちゃいました。
この上振れ要因は何か考えてみました。
私の気づきを共有します。
気付き①過去問全部潰さなくても点数は取れる
短答対策はとにかく過去問(短答過去パーフェクト)。予備校の先生、合格者のみなさんがとにかく過去問を回せというので、私もそれを信じちゃいました。でも、、、、、短パフェはあまりに量が多くて回せないし、すぐ忘れるし。
ある予備校の先生は、「短パフェの95%の肢を確実にできるまで繰り返してください。」と言ってました。それを信じていた私はとにかく短答民法が最後まで最大のストレスでした。。。
結局、一通りは解いたものの、繰り返す復習はできず、中途半端な状態で本番を迎えました。本試験前に一番の不安科目は何かと聞かれたら、「民法の短答」でした。
・私の本番時点での短パフェの定着具合

私は全ての肢をOK、△、×に区分していました。
OKは論文知識やら常識的に最初から正解し、時間が経っても間違えない肢です。これが全体の20%程度ありました。
△は、条文そのまま知識や、曖昧だけど理解はできているし、記憶もしやすいものです。これが全体の35%程度。
×は、難しい条文や記憶してないもの、理解できていないものです。これが全体の45%程度ありました。
民法の勉強としては、まず①矢島スピチェ(270ページほど)で論文コア知識を血肉にしました。②条文素読も1年で10回ほどしてました。この①②を土台にした結果、上記OKと△の肢についてはほぼ血肉にできていたと思います。
一方でバツ肢は、最後まで繰り返すことができず、おそらくバツ肢の4割くらいしか血肉化できませんでした。
➡つまり、最終的には短パフェ全肢の約7割ほど知識定着率で本番に挑むことになりました。OK肢と△はほぼ完ぺきにできたけど、、、バツ肢は復習終わらなかった。
本番2週間前のセルフ模試してみたら、、、
私の使っていた短パフェはR2までのものだったので、R3,4の試験は手をつけていない状態でした。択一テストも十数年ぶりですし、マークシートのチェックも本番前に一回はやっておきたかったので、セルフ模試をしました。
直前の追い込み前段階ではありましたが、結果は47点と45点。厳しい戦いになることを覚悟しました。
試験本番「あれ、肢めっちゃ切れるじゃん」
短パフェを潰せなかった不安の中での本番。
私は少し面くらいました。
「めっちゃ肢切れるんだけど、、、、」
短パフェの〇△肢の確実な知識と直前期の条文素読の効果で、サクサクと正誤でき、そして、組み合わせ問題のため、ズバッと肢が切れます。
ズバッと一刀両断してるので、読まない肢もたくさんありました。
問題によっては30秒ほどで切れるものもありました。
手応えとしては、確実にあってそうな問が24個ほど。6個が7割くらい合ってそう。6問ほどは超マイナー分野で5割くらい合ってるかなって感じでした。
全体的な手応えとしても55点くらい取れてそうな感じがありました。
そして、結果としてなんと65点も取れてました。かなり驚きました。
難しい肢の取得や網羅的より、確実な知識を増やすことの大事さ
なんで65点も取れたんだろう?と自分でも驚きましたが、普通に考えれば当然でした。
だって、民法短答は組み合わせ問題だから。5つの肢のうち3つ分かれば確実に正解できる。また、5つのうち2つ分かるだけでも正解できる問題もあります。つまり、理論上は全体の肢の6割の正誤がつけば十分。
私は本番の時点でおそらく短パフェ過去問の7割ほどの肢の正誤をつけれる知識はあったと思います。復習できなかったバツ肢(全体の3割)の知識はなくとも、〇△肢は確実にしていたし、条文の素読もしてました。
組み合わせ問題を解くには、これで十分だったんだと思いました。
・18年分だと3000肢以上あります。それを完璧にするなんて、ほぼ無理です。あまりに量が多すぎる。それを潰せずにストレスを感じ、不安に感じる必要はない。
・「分からない肢を潰していくのではなく、分かる肢を増やしていく、加点式のイメージでいいんだ」
・難しいバツ肢の習得よりも、時間がかからず高速回転できる△肢を超確実にし、本番で肢を即ギリできるレベルにしておくこと。条文素読で基礎条文を身に着けることが重要なんだな
と、試験終わってから気付きました。
要検討)短パフェは必須か。どこまで解くべきか。
短パフェ18年分を全て解くと、民法の肢は3000以上あります。。。ほぼ無理ゲーです。また、全部潰せなかった私でも65点取れていることからすると、全部潰す労力と効果が見合っていません。
・短パフェを全てを潰す必要はない。これは色々な予備校の先生も同じことを言っています。辰巳の福田先生も正答率70%以上の問題だけでよい、と言っています。でも、、、、問題集を一部だけ解くっていうのはスッキリしないですよね。やはり理想は最初から取捨選択してくれた一冊の問題集がいいですね。ということで、もし私が昔に戻れるのであれば、もし後輩にアドバイスするのであれば、伊藤塾の合格セレクションを使います。短パフェの3分の1のページ数ですね。。。。。なんでもっと早く気付かなかったのか。。。おそらく今後は短パフェからこちらに受験生の定番も移っていくと思います。

気付き②順不動、解ける問題から解こう!(解法編)
本番で想像以上に高得点が取れた要因として、気分よくサクサク問題を解くことができたからです。
私は本試験を通じて論文科目についてはそこまで緊張せずに解くことができました。目標を「Cを守る」としていたため、ある程度気楽に解くことができたからです。一方で短答前日はとてつもない緊張が襲ってきました。
論文を解いている時は一つ一つCを守ることを淡々とこなしたのですが、論文が全て終わった途端に「合格できるかも、、、、」と急に合格を意識してしまったのです。短答は模試も受けたことがなく、十数年ぶりの試験でもあります。解法方法も、マークの仕方も自分の中で固まっていません。
こんな緊張の中では問題文を読める気もしませんでした。特に物権などの関係図を書くような問題を解ける気がしません。
そこで、試験開始直前になって急遽「順不同で、解ける問題から解こう、まずは家族法から解こう。物権などの関係図を書く必要のあるものは最後に解こう」と決意しました。
これが初めての試みにして大成功!!!!!驚くほどにサクサクと高速で問題を解くことができました。
パッと見開きの問題4問を眺めて、第一印象で解けそうと直感で思う問題から解きました。具体的にはまず34問の遺言を解き、次に特別養子縁組、その次に親族関係といった感じです。(直前まで家族法の条文を素読していたので、ついさっき見たばかりの条文そのままの肢もたくさんありました。)
この解法によると、問題の順番通りに解くわけではないので、「どの問題を解こうか」という意思決定に10秒ほど使います。また、マークシートミスリスクは多少あります。しかし、一方で、緊張状態の自分の脳みそに負担のかからない直観的に相性のいい問題から解くことができ、心に余裕が出てくるというメリットがありました。
私はこの方法により、全ての問題を解くのに、1問目から37問目までを4回転しました。解きやすそうなのから解いてるので、時間的にも相当余裕を持って解き進められました。
そして、最後の4周目に残ったのは、物権や契約などの複雑っぽい問題6問。それまでの問題をサクサク平均1分半ほどで解いていたこともあり、25分ほど余ってました。また、30問解いた時点で9割ほど手応えもありました。そのため、複雑系の問題を一問あたり4分ほどかけて、ゆっくりと余裕をもって解くことができました。
「第一問から順番に解く必要はない」
「緊張した脳みそにやさしい問題から解くべき」
ということに後から気付きました。
私のように本番行き当たりばったりは危険なので、みなさんは事前にセルフテストはした方がいいと思います。
気付き③)前日・当日の詰め込みで10点以上UP
私的には当日の超直前詰め込みで10点くらいUPした感覚があります。
それくらい、直前にみた条文がそのまま選択肢で出たりします。
特に家族法の分野は、30分前に見た条文がそのまま出るようなイメージです。「これさっきみたばっかりじゃん」。
直前の直前まで貪欲に知識を思いっきり詰め込みましょう。
※超詰め込み、鬼の追い込み、一夜漬けは効果的か。(リスクあり、お勧めではない。)
以下はリスクもあって、お勧めはできません。でも、短答に不安を抱える方は検討の余地があるかもです。参考程度にしてください。
結論からいうと、私は前日22時に寝て、当日午前2時半に起きて、そこからひたすら民法の条文素読をし、そのまま本番に突入しました。
睡眠時間8時間が理想だと思います。特に論文の場合は8時間睡眠を強くお勧めします。6時間は必須です。頭をフル回転させる論文においては睡眠不足は致命傷になります。直前見直しよりも睡眠確保の方がはるかに大事です。
一方で、短答の前日はどうか。
特に民法の短答については、直前でも得点がかなりUPする感覚があります。実際私も当日に10点はUPしたと思います。
一方で、論文に比べると短時間であり、脳への負担、体力的には、多少の寝不足であれば勢いで乗り切れなくもありません。
私は8時間睡眠で挑むか、早起きして超詰め込みをするのか、、、けっこう悩みました。その結果、短答に不安を抱えていたのでリスクを取ることにしました。4時間半睡眠、鬼の詰め込みをしてそのまま本番突入戦法です。
実際に、2時半に起きてからから9時までノンストップで詰め込みをしたので、試験前にはけっこうフラフラでした。一方で、条文知識としてはかなり詰め込めたと思います。
試験についても、体力的にもギリギリ持ちこたえました。
結果として、私の場合はリスクを取ったことが正解でした。
あまりお勧めはできませんが、短答が不安の方については「アリ」かもしれません。検討してみてください。
ちなみに、繰り返しになりますが、論文は本当に気力体力勝負となるので、睡眠確保はマストです。絶対に寝ましょう。それよりも「考えれる脳体力」の方が大事です。
まとめ①)民法短答で8割取る学習法
以上から私見をまとめます。あくまで私見なので参考まで。
1.土台構築(論文基礎テキストの血肉化)
論文のコア知識がないと、いくら短答過去問をやっても効果は薄いです。まずは絶対条件として論文の基礎テキスト(薄いもの)を血肉にする。
私はLEC矢島先生のスピードチェックテキストを基本テキストとしていました。基本7科目は全てこれです。
ページ数は250ページくらい、講座時間も25時間程度で、短時間で繰り返せました。
伊藤塾なら論文ナビゲートに相当するようなまとめテキストですかね。
予備校テキストでも、基本書でもなんでもいいと思うので、ご自身の使われているメインテキスト一冊(薄いもの)を徹底的にやる。

2.条文素読
重要条文の素読、収得は必須だと思います。論文でも条文知識が問われるので論文対策としても必須ですね。今年は論文で短期配偶者居住権ががっつり出ましたね。
家族法分野は条文さえやればほぼ短答は正答できると思われます。
また、債権法や改正も多く、論文でも問われるし、短答過去問も蓄積していないので、特に条文素読の重要性が上がると考えます。
※どの六法で素読する?
ちなみに私は以下の理由から素読には司法試験用の六法を使っていました。
理由①判例六法だと情報が多く、ページ数も多く短時間で回せない。ポケットに入らず、常に見ることができない。②論文本番中の条文検索スピードを考えると論文本番で利用するものと同じもの、同じフォントのものを使いたかった。場所で覚えれますね。

3.短答過去問
全部は不要。むしろ害の方が大きい。私は全部をやろうとして失敗しました。決して私のような無駄な失敗はしないようにしましょう。短パフェ全部を潰す時間があれば、条文素読をする方が論文点数がアップすると思います。
過去問集としては、私がもしもう一度受験するとすれば、伊藤塾の合格セレクションを使います。短パフェの3分の1のボリュームなので、繰り返し回すことができる。
まとめ② 試験本番での振る舞い方
1.順不動、解ける問題から解く!
問題1の頭から解く必要はない。
緊張している中で、直観的に解きやすそうな問題から解きましょう。
例えば、直前まで家族法の条文を見ていたのであれば、そこから解きましょう。脳みそに入っている条文文言と問題選択肢が見事にリンクして、スムーズにサクサク解けますよ。
「順不同で、解ける問題から解こう、まずは家族法から解こう。物権などの関係図を書く必要のあるものは最後に解く」
これにより、時間切れもなく、複雑な問題もじっくり解くことができます。
2.前日・当日の鬼の詰め込みで10点以上UP
民法短答は本当に前日、当日の詰め込みで驚くほど点数がUPします。感覚的には10点以上UPできます。諦めずに最後まであがきましょう。
そして、もしリスク負ってでも詰め込みたい人は、4時間半睡眠で鬼の詰め込みから本番突入戦法もアリかもしれません(体力に自信ある人に限る)。
おわりに
以上、私の経験及び気付きについて共有しました。
もちろん、全ての人に当てはまるわけではないです。
あくまで参考として、ご自身に合うかどうか考えてみてください。
最後に、R5今年の民法論文問題では設問1と設問3は短答で学ぶ条文と判例でした。民法単体に限れば、短答の点数と論文の点数には相当程度の相関関係があると思います。短答で8割の60点の知識があれば論文も相当期待できると思います。頑張ってください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
