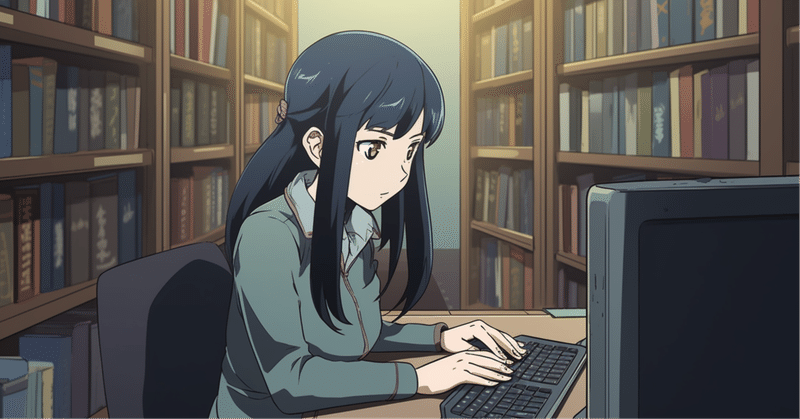
インプットは手段として考える
五月病なのだろか?
ここ最近身体の調子が今ひとつだった。
ゴールデンウィーク中に体調を崩し、身体も頭もすっからかん。
「疲れていたのかな?」と振り返ってみると、おそらく精神的な疲れが大きかったのであろうと思う。
腕を組んだまま朝日を浴びる日も多く、「心が休まった」と感じた日が少なかったように思う。
「このままではマズイな」と感じ、
色々と自分を見つめ返すことでみえてきたものがあったので、備忘録として書き留めておこうと思う。
インプット過多になっていた
とにかくインプット過多になっていたと感じる。
AI関係の情報をインプットし始めて以降、情報が流れるスピードが早すぎてとてもついていけない。
そして、そのAIの情報を今の自分の生活や仕事などの環境面でどう活かすの?
というモヤモヤが常に心の中にあった。
情報をとれば取るほど、現実との乖離が進む。
大型ショピングモール内の1店舗で働いていると肌感覚で実感する。
特に絶望するのは、お客様とのやりとりではなく、取引先様との会話の中でAIなどの話題になることはまずない。
なったとしても「どうせ流行りでしょ」くらいにしか捉えていないようにも感じる。
未来がどうなるかなんて誰にも分からないし、この生成系AIブームは一過性のものかもしれない。
しかし、世界に放たれたその技術がそのまま無くなるとは考えにくい。
ジリジリとみえないところで進化を続け、知らず知らずのうちに身の回りに浸透しているではないだろうか。
そして、身の回りに浸透し多くの人が認知した頃には生産性の安定期にさしかかっているだろう。

インプットは手段である
話をインプットに戻そう。
ここで「インプットってそもそも何?」 を自分なりに定義しておこうと思う。
わたしの中でのインプットは、
インプット = 手段の一つ として捉えている。
何か目的を達成するため、何かを実行するための手段として考える。
紙の制作物で例えるならば、
画用紙で制作物をつくるという「目的」があり、その為に紙を切って使う必要がある。
手で切ることもできるが、ハサミという道具があるならばそれを使う方が効率的。
ハサミを使って生みだした時間を、紙を切ることとは別のことに充てる。
そうすれば別のアイデアを構想する時間を確保することができるだろう。
インプットによる知識の蓄積も同様と考える。
「お店で売上を上げる」目的があった場合、知識はハサミと同様手段でしかない。
「接客が必要」というお店で、来店した100人全員に接客することは不可能。
この時、行動心理学・色彩学などの知識があったならば、接客しなくとも接客に近いような効果を生むことは可能だ。
行動動線・心理動線を配置し、最後の最後に販売員が接客をする。
その最後のフォーカスできる状態をいかにつくり出せるか?
「知識」は考え込むための手段のひとつ。
そう言えるのではないだろうか。
みえない未来を考えるために
前章では目的を「ハサミ」と「売上」と設定し例を出した。
このように明確な目的がある場合は理解しやすいのではないだろうか。
「自分の人生の目的は何か?」を設定できたならば、やるべきことが見えてくるだろうし、活力も湧いてくる。
しかし、未だにわたしの「人生の目的」は設定できていない。
いまだに最終目的・中期目的・短期目的はフワッとしたまま。
だからこそ、たくさんの情報をとろうとしてしまうのかもしれない。
不安だからこそ、情報を得て安心したいのだろう。
ただし、上部の知識を大量に取り入れてもあまり効果がないことは本当は分かっている。
あくまで情報は情報でしかない。
単体で何かを生み出すわけではなく、何かとの結びつきの作用で新しいものが生まれるから。
「新しい知識」は「すでに今ある自分の知識」と繋がることで自分の知識は拡大する。
糸一本くらいの切そうな繋がりでもいいから、繋がっている部分を見つけること。
ジャンルを問わず、繋がっている要素、同じ要素を見つける作業、そのことがとても重要なのだろうと思う。
当然、繋がりを見つけ出すには考える時間が必要になる。
「繋がりを見つける」 = 「考え込む」
「考える」の状態をどれだけ「考え込む」の領域に持っていけるか。
これが今の課題と言えそうだ。
「知識が正しい」「知識が古い」「知識が間違い」とかそういったことではない。
未来が不確定要素のかたまりであるからこそ、知識は「みえない何か」を自分で判断するための道具であり、「どう使うか」という手段の一つである。
(自分で判断できた事実は、その判断が失敗だったとしても、他人に委ねた失敗より自己肯定感は高い)
アウトプット量に適したインプット量にする
色々と自分との対話で見えてきたことはこれまで書いてきたとおり。
では最後に「今何をするか?」について簡単に指針を定めておこうと思う。
まずはインプット量の見直し。
アウトプット量に対してインプット量が多すぎることで、情報に飲み込まれてしまう。
だからアウトプットとインプットの比率を考えなくてはいけない。
一般的に良いアウトプットとインプットの良いバランスは、
アウトプット:インプット = 7:3 とも言われているが、
「 アウトプット 7 」は意識的に行わないといけないのがわかる。
以前は毎日Twitterで1ツィートはしていて、noteで日記を毎月10記事くらいは書いていたことを考えるとアウトプット不足気味であるのは事実。
これらをやらなくなった理由として、アウトプットする媒体や方法が変わったこともあるかもしれない。
しかし、これらのSNSの良いと思える点は、有益かどうかに限らず自分の思考をブラッシュアップするには効果的だと改めて思う。
Twitterなどをビジネスに絡めて活用するという目的ではなく、日常のささいなことにアンテナを立て思考を整理することが目的と考えるならば、それはそれでいいのではないだろうか。
もう一度、一日1ツィートを目標にしてみようと思う。
続けたという実績が可視化できるという点は良い点だが、
あくまで「手段」でしかないということを忘れないようにしながら。
===整理のためのメモ===
事象
・インプット過多になっていた
・余裕がない
・頭が働かない
・何をすればいいかが分からない
要素
・インプットはあくまで手段
・自分で考え、判断をするための栄養素
取るアクション
・空白の時間を作る
・アウトプット大全を読み返す
・ライティングの本を読む
WHY?
・空白の時間を作る
→インプットばかりでは何も生まれない
何もない時間にぼーっとして、軽く体を動かしている時に思考が深まる。
(外的環境から隔離され、あらゆるストレスから解放されている状態を作り
出せるかが重要なキーになっている)
・お風呂で良い発想が生まれるワケは?
外的な情報がないので、脳が自分の中にある情報を整理しようとする。
その時に、自分の中の情報と情報同士が繋がり、新たな発想が生まれる。
例、 昼の出来事や光景を思い出す。
思い出すというよりボーッとしているだけで、昼間の映像が浮かんでくる。
「見た」認識がなかったとしても、あらゆる情報は脳のハードディスクに保存されている。
・ライティングの本を読む
→アウトプットする目的のための「伝え方」の方法が詰まっているから。
うまく伝えられる → 伝える量が増える → アウトプット量が増える
→頭に空き容量が生まれ、インプットがしやすくなる
その他
・日記でアウトプットを増やす
・有益にこだわらず、日常の些細な気づきをアウトプットする
アウトプットが形として残った状態にする
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
