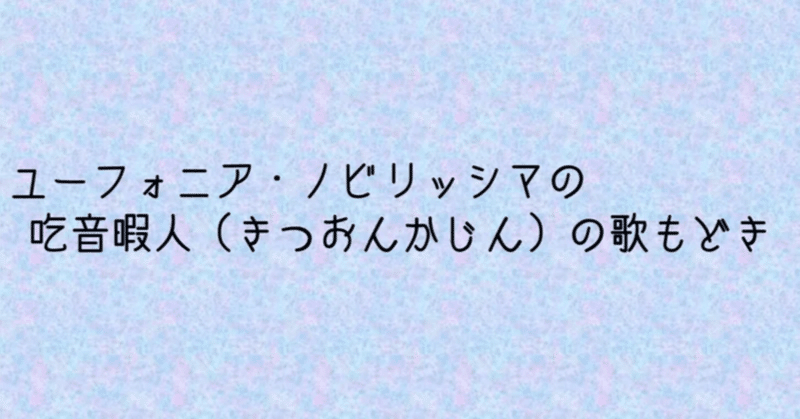
Vol.25 お話の基本構造。
19歳の頃、劇団四季によるミュージカル「オペラ座の怪人」(アンドリュー・ロイド・ウェバー作曲版)(注1)の上演を観劇した際、購入したパンフレットを読んでいたら、ある方が
『この物語は、一人の若い女性が「今は亡き父親」「音楽の師であるファントム(怪人)」「幼馴染にして青年貴族のラウル」という3人の男の狭間で揺れ動きながら成長する話なのだ』
…といった感じで、話の構造を要約されていたことを妙に覚えています。
もっともその頃の私は、年の割には感性がお子ちゃま過ぎて!?、その要約がイマイチ飲み込めてなかったのですが…(笑)
さて、そんな思い出話が頭をよぎったのは、先行公開された映画「哀れなるものたち」(注2)を見たからでして(※ちなみに原作小説は未読です)。
先日、映画本編を観終わった後は、とても感情が揺さぶられて「暫定今年ベスト!」と叫びたい心境だったのですが、「パンフレットの表紙にもなっている ” ポスターアート ” 」だけが、妙に違和感を覚えたんですよね。
どんなポスターアートなのかと言うと「(エマ・ストーンが演じる)ベラの顔が大きく映されたデザイン」なのですが、なんだか道化の様なメイクに見える顔のアップなので、
「これって、物語序盤の未熟なベラを表現しているのだろうか?」
…なんて邪推したのですが、今日 ストリーミングサービスでオリジナルサウンドトラックを聴こうと考えつつ、画面に大写しになった、例のポスターアートを見てようやく気付きました!
「メイクに見えるラインは、劇中に出てくる3人の男たちを示しているじゃないか!」
…我ながら、まぁなんと鈍いことか(笑)
そう考えると、
『「三人の男の狭間で一人の若い女性が成長する話」という意味では、お話の構造は「ミュージカル版の ” オペラ座の怪人 ” 」と近い』と言えるかも?…
…という、新たな邪推が頭をもたげたのでした。
しかしまぁ、ほとんどの方は私ごときの邪推というか戯言には目もくれず、予告編で見て取れる『「フランケンシュタイン」とか「ピグマリオン」といった作品や寓話からの類似点』を探るんでしょうね(←当たり前!!)。
ま、何はともあれ、かなり癖の強い作品ですが、映画『哀れなるものたち』おススメです。
では今週も締めの『吃音短歌(注3)』を…
鳴り響く 心の中の サイレンの 様な悲鳴を 聴いてみますか?
【注釈】
注1)ミュージカル「オペラ座の怪人」
「1861年 パリのオペラ座で、コーラスガールの一人だったクリスティーヌ・ダーエは、代役として主演を務めあげた事がきっかけで、幼少時の遊び相手だったラウル子爵と再会する。再会を喜ぶ二人だったが、ラウルからディナーに誘われた途端にクリスティーヌの表情が曇る。クリスティーヌに歌唱を仕込んだのは、オペラ座を影から支配する謎の人物 ” ファントム ” だったのだ…」
ガストン・ルルーによる同名小説の舞台化作品。
アンドリュー・ロイド・ウェバーが音楽を手掛けたバージョンは、ロンドンのウェストエンド、ニューヨークのブロードウェイ双方で、歴史的なロングランを記録した。
注2)映画「哀れなるものたち」
「若き医師マックス・マッキャンドレスは、師であるゴドウィン・バクスターに招かれ、邸宅内で奇妙な行動をとり続ける若い女性ベラ・バクスターの観察を依頼される。やがて少しづつ、ベラに変化が起こり始めるのだが…」
映画監督ヨルゴス・ランティモスが手掛けた、アラスター・グレイによる同名小説の映画化作品。
注3)吃音短歌
筆者のハンディキャップでもある、吃音{きつおん}(注4)を題材にして詠んだ短歌。
この中では『「吃音」「どもり」の単語は使用しない』という自分ルールを適用中。
注4)吃音(きつおん)
かつては「吃り(どもり)」とも呼ばれた発話障害の一種。症状としては連発、伸発、難発があり、日本国内では人口の1%程度が吃音とのこと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
