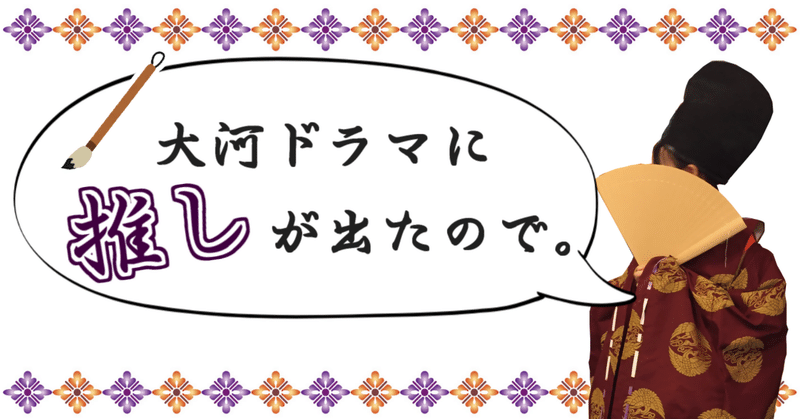
推し、評する。✿第16回|実咲
関白道隆がこの世を去った、「光る君へ」第17話。
穏やかな旅立ちとはとても言えない、なかなか壮絶な最期でした。
妹である詮子に「お若い頃はお優しい兄上だったのに」と過去形で語られるほど、物語序盤の鷹揚な姿がまるで嘘のよう。娘定子を無理に中宮へ押し上げたり、疱瘡(天然痘)の流行対策を進言する道長の言葉には耳を貸さず、息子の伊周に高い地位を与えることで家の権力を保持しようと固執するなど、ある意味権力者らしい晩年でした。
この道隆の死をきっかけに、中関白家と呼ばれるこの一家の朝廷での立場は危ういものになっていきます。
道隆が必死で一条天皇に最期の力を振り絞って伊周に欲しいと要請した「内覧」の地位。
これは、天皇に書類を見せる前に先に閲覧できる地位のことですが、確かに関白に匹敵するものではあります。
しかし、まだ若いながらも思慮深い一条天皇はこの内覧の地位を、「道隆が病の間」という条件付きで伊周に与えました。
つまり、伊周が内覧の地位を得られるのは、道隆が生きていることが前提だったのです。
「アフター道隆」をめぐり、さまざまな謀略が行き交うと共に、そこへ疱瘡の流行が襲いかかる時期になります。道隆を皮切りに一話ごとに目まぐるしく、人の生き死にで左右されていくことになりそうです。
さて今回、行成は一条天皇と中宮定子の御前で伺候する中に姿がありました。
しかしやはり、第17話の段階ではまだギリギリ無職継続中です。
次回、いや正直まだもうしばらくは微妙な気がしてきました……。
なお、この無職期間である長徳元年(995年)に、ここのところ流行り始めた疱瘡(天然痘)に感染したのかは不明ですが、行成は数少ない身内の一人である母を亡くしています 。
行成は本当に、ことごとく支えてくれる身内が早く亡くなる運命か何かのようです。
公卿たちが会議を行っているシーンで、藤原顕光と藤原道綱(道長の異母兄)がどこかとぼけた会話をしています。
この二人は、「光る君へ」の時代、都にその名をとどろかせていた「アホ枠」貴族でした。
第6回でもお話しましたが、この時代には、藤原道長の『御堂関白記』、藤原実資の『小右記』、藤原行成の『権記』という三者三様の日記が残されています。
その中に、この二人に対する当時の人々の評価が事細かに記されているのです。以下、現代語意訳で紹介してみましょう。
まず顕光。藤原実資は『小右記』に「失態を一々書いていたら、筆が擦り切れる」と書いています。
さらに実資は、顕光について「馬鹿そして馬鹿」と道長が口にしていたことまで書き残しています。
それだけでなく、「馬鹿すぎて全員失笑物だったわ」と書くなどと実資の筆は止まりません。
また、三条天皇が即位する際に宣命使に任じられた行成は、先代の一条天皇の即位の際にこの役を務めた顕光(つまり前任者)のところへ作法を尋ねに行きました。
しかしなんとも要領を得なかったようで、行成は『権記』に「参考になる所はなかった」と書いています。
行成は普段あまり人のことを悪く書かない傾向にあるのですが、わざわざ書くということはよっぽどだったのでは……。
道長の兄道綱も蜻蛉日記の作者を母(「光る君へ」では藤原寧子)に持つにしては学才に乏しかったようす。
はたまた実資に「何も知らない」、「自分の名前しかまともに書けない」、「ただ給料もらってるだけの奴」とこき下ろされています。(悪口のバリエーションが豊富!)
ほかにも着てくるべき装束を間違えたり、仕事を忘れまくっていたりすることもしっかり実資に書かれてしまっているのです。
実資は人の悪口をよく書く人ですが、道綱と顕光が共に執り行っていた儀式で二人だけがそのやり方を間違える事件が発生したことも、行成が『権記』に書いています。
二人の評判は、実資の主観だけではないようです。
このように、失敗事件簿や悪評には枚挙にいとまがない二人ですが、なんだかんだこの朝廷をうまく泳ぎながら長生きするのです。
顕光は子供たちの処遇に少々苦労しますが、最終的に左大臣にまでなり、77歳の長寿をまっとうしています。
道綱は道長の兄の中で唯一長生きし、大納言になり65歳で亡くなりました。
人に恨まれない生き方をして、なんとなくぬるっと官職を上げていくのも平安貴族の生き方としてアリなのかもしれません。
第17話でこの世を去った道隆は、作中で「(恨まれている)心当たりがありすぎる!」と口にしています。
権力の頂点に立つと、他人から死を望まれ、死んだときに喜ばれてしまうことだってあるのです。
さて、この長徳元年の天然痘は作中の公卿の会議のシーンの中にいるメンバーを一新することになります。
まさに内閣総辞職ビームといったところで、あと数話のうちにガラッと面子がいれかわっているはずです。
死ぬ間際に胸の内に「心当たり」があった人はどれほどいたのでしょうか。
書いた人:実咲
某大学文学部史学科で日本史を専攻したアラサー社会人。
平安時代が人生最長の推しジャンル。
推しが千年前に亡くなっており誕生日も不明なため、命日を記念日とするしかないタイプのオタク。
