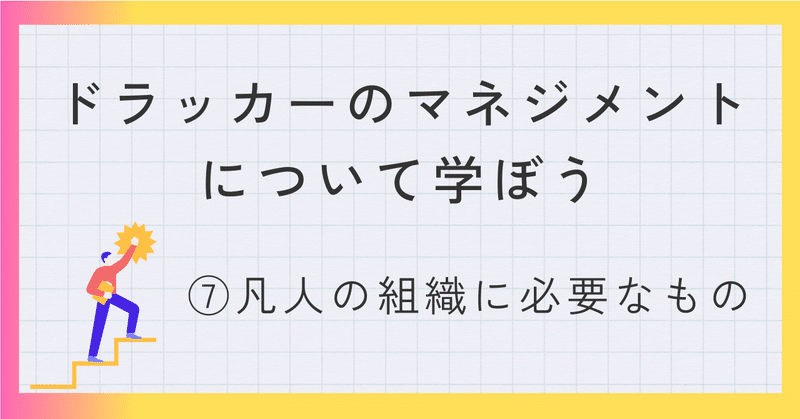
ドラッカーのマネジメントについて学ぼう -⑦凡人の組織に必要なもの
さあ、金曜日だ。
金曜日は、ドラッカーの「マネジメント」について学ぶ日だ。
この本は非常に緻密に書かれており、記事としてはドラッカーが書いた内容を順になぞっていくようなものになってしまうかもしれないと思っているが、可能な限り現代的な解釈をして、わかりやすく解説を加えていきたいと思っている。
先週、マーケティングとイノベーションの深堀をしたが、今日は一つ戻って「マネージャーとはどんな職なのか」の続きを書こうと思う。
真摯さを身に着けている人を見極める
マネージャーに必要なたったひとつの資質は「真摯さ」だ。
この「真摯さ」というワードはこの本の中で何度も出てくる。ドラッカーは「真摯さなくして組織なし」とまで言い切っている。マネージャーたる者は先天的なものであるかのように真摯さを身に着けていなければならない。またマネージャーを選出するにあたって、真摯さが欠如している人物を「決して(ドラッカーはかなり強く表現している)」選んではいけない。
とはいえ、真摯さの定義は難しい。
ドラッカーもそこは認めていて、逆に「真摯さの欠如」の定義をしようと提案している。それが以下の5つの項目だ。
1. 何かできるかより何ができないかに目を向ける者
2. 何が正しいかより誰が正しいかに関心を持つ者
3. 真摯さよりも頭の良さを重視する者
4. 部下を脅威と感じる者
5. 自分の仕事に高い基準を設定しない者
会社にとって最も重要な資産は「人」である。
例えマネージャーが知識や判断力や行動力に欠けていたとして、そんな人がマネージャーになっても(プラスになることがなくても)会社にとってマイナスになることはない。しかし、いくら頭が良くて判断力や行動力がある人でも、真摯さに欠ける人がマネージャーになると、徐々に組織の精神を低下させていき(会社にとって最も需要な資産である)「人」が離れていくことにつながる。
天才をあてにするな
組織であることの強みは、ひとりの凡人の中からほんのちょっとの非凡な部分を見つけ出し、それを組織の中に投入することによって、それが他の凡人の助けになるという活動を繰り返すことができることだ。
独りで活動するアーティストは天才であるべきだろう。
Vaundyにしても米津玄師にしても、村上隆も小松美羽も、アートビジネスという観点で見るならば、多くのスタッフが彼らを中心にして動いていて、そこに複数のステークホルダーが関係している。だけどそれは彼ら天才が持つ圧倒的な才能をビジネス化したもので、彼らありきのビジネスモデルだ。しかし、一般的なビジネスはそうではない。
最近では「タレントマネジメント」というワードが注目されていて、いろいろなタレントマネジメントシステムが発売されている。すでに導入されている会社も多いと思う。タレントマネジメントとは、従業員が持っているタレント(能力・資質・才能)を一元管理し、適材適所な人事配置をしよう、もしくは個人のキャリアアップの計画を立てようという考え方だ。
ドラッカーは「マネジメント開発」という表現で、どのようにマネジメント(ここで言うマネジメントは管理や育成を行うチームの意)を組織・育成していくべきかを説いているが、その中でいくつかの警鐘を鳴らしている。
マネジメントには人の性格をとやかく言う資格はない。雇用関係とは特定の成果を要求する契約しか過ぎず、それ以外のことを要求することは人権やプライバシーの侵害に当たる。なので、従業員に対するタレントマネジメントがその人の性格を変えさせようとするもの、もしくは人格を改造しようとするようなものであってはならない。そして、タレントマネジメントがエリート探しになってはいけない。
どんな組織にも20%ほどのエリート(もしくはエリート候補者)が存在するものだ。しかし実際の仕事は残りの80%の「凡人」も含めて進めていかなければならない。最悪なのは、20%のエリートを育成するために80%の凡人を放ってしまうことだ。彼らは自分が軽んじられていることを敏感に感じ取る。そしてそれを忘れない。
凡人の組織に必要なもの
天才を中心としたアートビジネスであれば、短期間で大きな成果を上げることが期待できる。天才には明確な目標があり、彼らは自分が生み出すべき成果がどんなものかを知っている。しかしボクたちのビジネスはそうではない。
ボクたちのビジネスは、凡人たちが集まってそれぞれのほんのわずかな非凡な部分でお互いをカバーし合って成果を出していくものだ。それは長期的なものであり、ややもすると混乱し、方向性を見失う。なので、ボクたちには組織としての明確な目標が必要だ。そして目標を定めるためには「ボクたちはどんな成果を上げるべきなのか」を問うところから始めなければならない。
(続きはまた来週)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
最後まで読んでくださってありがとうございます。
これまで書いた記事をサイトマップに一覧にしています。
ぜひ、ご覧ください。
<<科学的に考える人>>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
