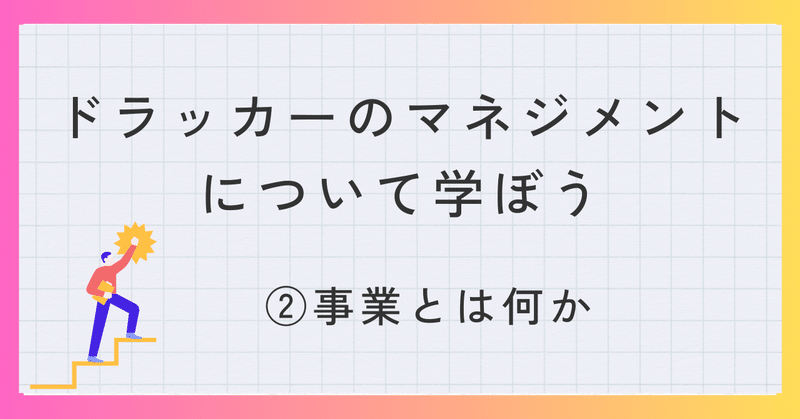
ドラッカーのマネジメントについて学ぼう -②事業とは何か
さあ、金曜日だ。
金曜日は、ドラッカーの「マネジメント」について学ぶ日だ。
改めて、ドラッカーのマネジメントを読み返してみると、やはりこの本は非常に緻密に書かれており、ボクの解釈が入る余地は非常に少ないように思う。ひょっとするとドラッカーが書いた内容を順になぞっていくような記事になるかもしれないとも思っている。
そう考えると「もしドラ(もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら)」は発想が抜群に素晴らしいと言える。ドラッカーの「マネジメント」はあまりに完成されていて、なんらかの手を加えることが非常に難しいが、それをあんなストーリーに仕立てるなんて…。さすが原作者の岩崎さん、東京藝術大学卒は伊達じゃないと思った。
とはいえ、おさらいするだけでも時間をかける価値はあると思う。この本は70年前に書かれたものなので、可能な限り現代的な解釈をして、わかりやすく解説を加えていきたいと思っている。
ご興味おありの方は引き続きお読みいただけると幸いだ。
では、今日はドラッカーが次に述べている「事業とは何か」という部分にフォーカスしていこう。
利益とは何か
ドラッカーは、市場を作るのは神や自然や経済的な力ではなく企業であると言っている。企業は市場の欲求があるところに、その欲求を満足させる手段を提供するべきで、企業とは何かを決めるのは顧客である。そして顧客が求めるのは製品やサービスそのものではなく、それら製品やサービスが提供する「効用」である。
企業の基本的な機能はマーケティングとイノベーションの2つである。
マーケティングで重要なのは「我々が何を売りたいか」ではなく、「顧客は何を買いたいか」だ。マーケティングが目指すものは、顧客を理解し、製品やサービスを自ずから売れるようにすることだ。そしてイノベーションは「新しい満足を生み出すこと」である。イノベーションで重要なのは、経済的なイノベーションや社会的なイノベーションだ。その結果として企業が大きくなっていく必要はないが、常に良くなっていかねばならない。
そのためには、生産性の向上も必要なファクターとなる。知識・時間・自らの強みをフル活用し、プロダクトとプロセスを最大限に組み合わせて(イメージとしては共有できる部分は共有して…になるのか)、労働力やコストを最適化することは非常に重要なポイントになることは明白だ。
「企業は営利組織」だという考えは間違っているとドラッカーは説く。利益が企業の目的になってはいけない。利益は企業活動の「条件」であり「妥当性の判断基準」であるべきものだ。故に企業活動の目的は、利益を追求することではなく「顧客を創造すること」と定義すべきだ。
利益とは原因ではなく結果だ。
利益は、マーケティング、イノベーション、生産性向上の結果として手にするものなので、企業が経済的機能を果たす上で必要不可欠なものとなる。
自社の事業をどう定義するか
企業の目的と使命を定義するとき、その出発点は顧客でなければならない。その企業の事業の定義は、顧客がプロダクトやサービスを購入することによって得られる満足で定義されるのだ。
そうなると「顧客は誰か」を定義しなければならなくなる。
顧客は一方向だけではない。利益をもたらしてくれる人たちが顧客と定義するならエンドユーザーだけが顧客ではない。さらに「顧客はどこにいるか」と「顧客は何を買うか」を定義しなければならない。
環境は変化する。
人口構造・経済構造・流行や意識・競合他社は時代とともに(非常に短いスパンで)変化するものだ。その中で、現在のプロダクトやサービスで満たされていない欲求は何か」を問い、それに正しく答える能力を持つことが、普通の企業と成長企業の差になるのだ。
ここから先は
¥ 150
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
