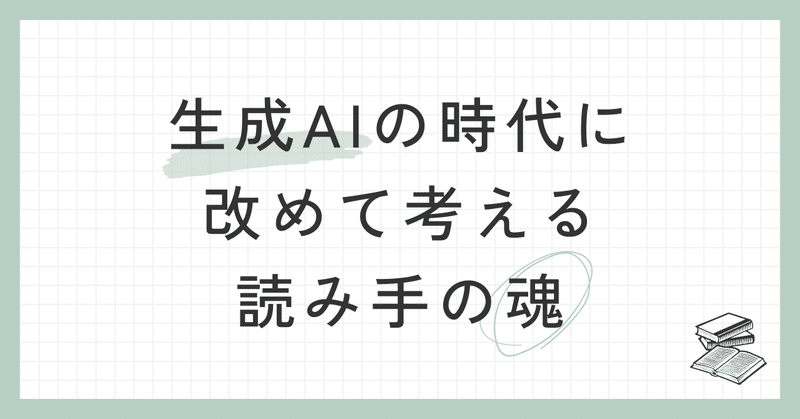
生成AIの時代に改めて考える読み手の魂
はじめに
コミティアの「魂」
2008年から16年間、コミティアという同人誌即売会に、どちらかと言えば読み手の立場で通っている(たまに評論でサークル参加もしていた)。この note でも時々話題にしているが改めて説明すると、即売会や同人誌と聞けばコミックマーケット(コミケット、コミケ)やパロディ作品(二次創作)が思い浮かびがちではあろうが、コミティアはオリジナル作品(一次創作)に特化した、マンガやイラストが中心の即売会である。以前から一般参加でコミケの一次創作エリアを回っていた私は、会場全体が一次創作であるコミティアにすぐにハマり、就職が関東になったこともあって足しげく通うようになった。心に刺さる数々の作品に出会うとともに、その描き手が必ずしも商業誌で活躍しているようなプロとは限らずアマチュアも数多く存在したことに、面白い作品にはプロもアマもないんだという思いを抱くようになり、さらなる作品を求めてのめり込むようになっていった。
そこで重視されるものは「魂」である。コミティアはその自己説明の中で「作品を介して魂と魂が握手するような出会い」というフレーズを掲げている。
コミティアとはプロ・アマを問わないマンガ描きたちが自主出版した本を発表・販売する展示即売会です。
そこは、枠にはまらない自由で新鮮な個性を持つ作家が腕を試す自己表現の舞台であり、既製品に飽き足らない読者にとってまだ見ぬ、そして求めていたマンガを発見できる宝探しの山でもあります。
コミティアは、そうした一人一人の描き手と読み手がダイレクトに出会える「場」として開催されます。
そんな描き手と読み手の、あるいは描き手同士の作品を介して魂と魂が握手するような出会いが、新たな創作への刺激とエネルギーになることを信じています。
「魂」は長い間コミティアのキーワードであり続けてきた。コミティアの中村会長と吉田代表の対談によれば、20年以上使われている言葉である。コミティアの誕生は1984年11月であることから、その歴史の半分以上を生き続けてきた重みのある合言葉と言える。
吉田:今のコミティアに繋がる「ごあいさつ」というとコミティア17(P20)〔引用者駐:1990年9月開催〕に「コミティアスピリッツ」って単語が出てくるのは面白いですよね。
中村:「コミティアスピリッツ」は結局その後一度も使いませんでしたけどね。色んな人が色んな所から参加しに来てくれる参加者みんなの想いをそう呼びたかったんです、当時は。
吉田:確かに「スピリッツ」はこの回限りなんですけど、「魂」という言葉はコミティアのキーワードなんですよ。コミティア56〔引用者駐:2001年5月開催〕のサークル参加申込書あたりが初出で今も使われている。中村さんが書いたコミティアの説明に「作品を介して魂と魂が握手するような出会いが、新たな創作への刺激とエネルギーになると信じてコミティアは開催されます」というのがあるんですけど、その源流を発見できて嬉しかったです。
『コミティアの作り方 ティアズマガジンのごあいさつ完全版』p.279(強調は引用者による。)
私も読み手としてコミティアの趣旨に賛同してこれまで参加してきた自負がある。スペースを網羅的に回り、提出された見本誌を読み込んだりしては、面白かった本や感動した本のレビューを書いてきた(振り返って数えてみたところ、16年間で書いたレビューは440作品だった)。そういった営みこそが、やはりコミティアが謳う「読者(読み手)の役割」であると信じてきたし、そしてこれからも信じているからである。
私〔引用者駐:コミティア前代表・中村〕にとっての読者とは「ゴール」ではなく、まだどこかに向けて走り続けねばならない「最終走者(アンカー)」です。
つい、そんなことを考えてしまうのは、このコミティアそのものが「読者の役割」を考えるところから出発しているからだと思います。
アマチュアでも面白いマンガを描きたいと思う人がたくさんいて、自分もそれをとても読みたくて、もっと他の読者にもこの面白さを伝えたくて、ではそれを自由に発表したり、教えあったりできる場があればいいなと思いました。
きっとその時、自分が受け取ったバトンがたくさん増えすぎて、それならみんなが集まってバトンを渡しあえる場所を作ればいいんだと考えたのでしょう。
それが、マンガが描けないマンガ好きで、マンガを読むことしかできない自分が、マンガに出来る唯一のことだったのです。
コミティアはそうして生まれました。
『コミティアの作り方 ティアズマガジンのごあいさつ完全版』p.196(強調は引用者による。)
しかるに、そもそもコミティアの「魂」とは何であるか、これまであまり言語化はされてこなかったように思う。私も「魂」という言葉が持つ力強さに心動かされてきたところが大きかった。先日のコミティア147で先行販売された『コミティア魂』でも、「魂」を定義する、という吉田代表の言葉があった。
吉田 中村が作った「魂」を継いでいくために、「魂」を定義するというんでしょうか。中村がいるうちは「それは魂だよ」って言ってもらえるんですけど、いなくなった瞬間に「これって魂だっけ?」ってなったらマズいので(笑)。これまでコミティアが何を大事にしてきたのか、何をやってきたのかをもう一回全員で共有するために『コミティア魂』の連載を『ティアズマガジン』で始めた意図もあったと思います。
『コミティア魂』p.301(強調は引用者による)
『コミティア魂』はその終盤で、この記事の冒頭でも引いた「コミティアについて」に回帰し、そこにコミティアの「魂」の説明は全て書かれている、といった旨を論じている。まあそりゃそうなのだろうといった感じだが、正直なところ少し物足りなさも感じている。それはきっと、「魂」の定義は道半ばであり、究極的には参加者ひとりひとりが考え続けていくべきものであることの裏返しだ、と私は思っている。
生成AIに対する危機感
さて、近時のこの社会では「生成AI」の言葉を聞かない日はない。計算機科学やクリエイティブの分野にとどまらず、ビジネスから行政まであらゆる場所で話題になっている。大量のデータを学習したモデルと自然言語などのプロンプトによって瞬時に文章、画像、音声などを生成するこの技術は、しかし学習に用いられたデータの権利やモラル、あるいは生成物の依拠性や真実性といった法規的または倫理的な問題を抱えており、世界各国で議論が行われて法整備に向けた動きが進んでいる。あらゆる技術は実用化される時に社会と無縁ではいられないのだから、こういった動向は妥当と言えよう。
こうした動きにコミティアも無縁ではいられず、2023年2月には生成AI作品に関するサークル販売物規定について暫定的な発表をし、そして2023年8月にはガイドラインを発表した。その内容は次のとおりであり、いわゆるポン出しの生成AI作品の頒布を不可とするものであった。
生成AIの出力結果そのままを主体とした作品の頒布を不可とします。AIは作品制作の補助となる範囲で使用してください。
このガイドラインは一定の効果があったのではないか、と私は感じている。私は見本誌読書会などでコミティアの見本誌を読み込んでおり、ガイドライン発効前の COMITIA145 ではイラストジャンルで生成AIポン出しの本を5冊ほど見かけたが、発効後の COMITIA146 ではそれと疑わしきものを1冊見かけた程度だった。その一方でこれまでに、評論情報本の体裁で生成AIのイラストをいくつも掲載した本や、表紙に生成AIのイラストを用いた小説本も、わずかだが見かけている。今後も同様の本が増えれば、もしかしたらこのガイドラインが厳格化されるのかもしれない。
それでも、このサブセクションのタイトルにも書いたように、私は生成AIに対して危機感を持っている。その理由は法規的または倫理的な問題はもちろんのこと、仮にそれらが全て解決された世界(もちろん現在の世界はそこからほど遠いことを念のため書き添えておく)においてもなお、生成AIポン出しの「作品」群に人間の作品が圧殺されてしまわないか、という懸念があるからだ。計算機処理の特徴は、疲れを知らず、別個のマシンでも再現度高く、同様の処理を反復できることであり、これは生成AIにおいては大量の「作品」を次々と出力できることである。人手の工程であるプロンプト入力がボトルネックとなるはずなのだが、それにもかかわらずデジタルなコンテンツの世界ではこの懸念はとっくに現実のものとなっており、AI生成物の応募が殺到して募集の中止を余儀なくされたSF誌や、AI生成物を既存の作品と区別したり申請数に上限を設けたりしているデジタル作品プラットフォームなどがある。同人誌のように物理的な紙に印刷する工程が挟まればこういった懸念は薄まるのかもしれないが、例えば Twitter や pixiv で連載して同人誌でまとめるというハイブリッドな発表方法もあることを考えれば、懸念が完全に払拭されることはないだろう。
文化は人間のためにこそある。そして生成AIとその利用者が人間を圧殺してしまうのならば、私はそのような状況を文化的などとは決して呼びたくない。読み手もまさしく当事者である。こういった状況を懸念して、私も先日の文化庁のパブコメには意見を送っている(ひとまずの結果は文化庁のページで公開されている)。
◇
前置きが長くなってしまったが、この記事の目的は、生成AIの時代においても同人誌や即売会を愛し、ひいては文化を愛する読み手(読者)が、いかに思考し、また振舞っていくべきかを、コミティアが言う、そしていくらかはより一般的な意味での「魂」を言語化することを通じて、とらえようと試みることである。
魂は傷つき得るが、それゆえに強くなる
表現行為は自身の技量だけでなく価値観すなわち真善美の基準をさらけ出すことでもある。そしてひとたび表現が作品の形を取れば、そこに宿った技量や価値観は否応なく評価の対象となる。稚拙だね、良くないね、伝わらないね――言葉であれ言外の態度(卓上の見本誌をパラパラとめくっただけで買わずに立ち去るなど)であれ、描き手には「好ましい」反応だけでなく「好ましくない」反応も届くことになる。その全てを受け入れる必要はないが、少なくとも受け止めることはしなければならないだろう。線の一本一本に、彩りの一色一色に、セリフの一語一語に、想いを込めれば込めた分だけ、期待と異なる反応に描き手は落胆して傷つくものだ。
しかし、それゆえに描き手の魂は強くなる。正確に言えば、傷つくことそれ自体ではなく、傷つくリスクを負うことで強くなるのだ。不安を抱えながらも、この描線こそ、この彩色こそ、この言葉こそ、己が信じる真善美だ、と決断して作品を世に送るからこそ、作品が高く評価されたときの賞賛や満足を、まさにその描き手こそが得られるのである。
洒落た言葉を使えば、これがコミットメントなるものだ。作品に込めた表現の責務を一手に引き受けるからこそ、その見返りもまた独り占めできるのである。こうして描き手の魂は磨かれ、さらに新しい表現へと歩みを進めていくのだ。これこそが描き手と読み手の緊張感ある信頼関係の根底に存在するものであり、また文化の発展を駆動していく根幹である、と私は信ずるところである。
ひるがえって、AI生成物をポン出しで発表する生成AIの利用者には描き手としてのコミットメントがない。「ない」は過分に柔らかくした言い方で、正確には責務を負うことさえできない。線の一本、彩の一色、セリフの一語、その何ひとつも己が真善美に由って自ら描いたものでないのだから、そもそも描き手のコミットメントを負うことができないのだ。いわゆる二次創作でさえ、描き手は自らの意思と技術によって描いた翻案に対する責務を負っている(否が応でも負わざるを得ない)のに、生成AIの利用者はそれさえできない(できようがない)のだ。
そしてコミティアにおける生成AI作品のガイドライン(次に再掲)も、こういったコミットメントに重きを置いているように読める。
生成AIの出力結果そのままを主体とした作品の頒布を不可とします。AIは作品制作の補助となる範囲で使用してください。
このガイドラインにおいて重要な点は、生成AIのモデル作成やプロンプトに用いられるデータの清浄性は無関係である点だろう。すなわち、清浄でないデータ(権利関係をクリアしていない、倫理的に問題がある、など)を利用した場合はもちろん、清浄なデータのみを利用した場合であっても、生成AIの出力結果そのままを主体とした作品の頒布は不可である、ということだ。これは利用したデータうんぬんの前に、そもそも生成AIがポン出ししただけの作品は、ガイドラインの補足にあるように「コミティアで規定する「自主制作」物に含めることは難しい」ということのように読める。裏を返せば、これまでどおり明に人間の意志と作業と責任によって作られたもの(であってパロディでないもの)こそが、コミティアが規定する自主制作物ということなのだろう。
魂は複製され得ず、自らに由って在る
不特定多数の描き手による作品を学習させるのではなく、特定少数の描き手の作品を学習させてその描き手の作風を模倣しようという動きもある。生成AIの出力結果そのままを主体とした作品の頒布を不可としたコミティアから少し離れると、国内では手塚治虫のマンガの模倣を試みる TEZUKA2020・TEZUKA2023 プロジェクトがその最たるものだろう。そしてこのプロジェクトには手塚プロダクションも関わっている。なるほど、権利を管理している組織を巻き込めば財産権の問題はクリアできるかもしれない。
ところで、 TEZUKA2020 の成果である『ぱいどん』の紹介ページにはこのような言葉がある。
手塚治虫が今も現役でマンガを描いたなら...、そんな思いを巡らして読んでいただきたい1冊です。
キャッチコピーとしては理解できる。しかし生成AIの時代において私たちは「手塚治虫が」という言葉に警戒しなければならず、少なくとも意識的であらねばならない。なぜなら『ぱいどん』を「描いた」のは手塚治虫自身ではないからだ。そんなの当たり前だろ故人なんだから、と多くの方は思われるだろう。しかし将来、この『生成AIなるもの』を手塚治虫と同一視して神格化し、偶像崇拝する輩が現れないとも限らない。現在でも、TEZUKA プロジェクトに参加した林海象は「AIの向こうに手塚治虫を感じた」と語っているのだ。もちろん、これは単なるリップサービスに過ぎないとしても、人間は様々な想像を現実にしてきた(あるいは「想像が現実になってしまった」)生物であることを忘れてはならない。
しかし、もっと恐ろしいのは別の想像だ。誰某が描いていた作品と似たようなものを生成AIが出力できるようになったら、その誰某は放棄されてしまわないだろうか? そしてその誰某が、手塚治虫のように既に亡くなった者ではなく、まだ生きている人間だとしたら? 模倣する機械が存在するが故に人間の方が棄てられるというこういった想像力は私のオリジナルでも何でもなく、例えば私が最近読んだSFマンガ『妹・サブスクリプション』の「もっと利口な子に」回などにもあらわれている。
これら二つの根っこは同じである。そもそも人間の人格は、魂は、複製され得ないものであり、それはしょうがないことなのだ。そして前者のような偶像崇拝は魂が複製され得るという誤認が、後者のような放棄は複製できない=「私の所有物にならない」ことをしょうがないことだとしない悪辣さが、問題を引き起こすである。
さて、TEZUKA プロジェクトを挙げるまでもなく、手塚治虫が後世に与えた影響は大きい。手塚に触発されて生まれたマンガ家は枚挙にいとまなく、その多くは手塚治虫のように自分もすごいマンガを描けるようになりたい、と思っていたことだろう。しかし、自分は手塚治虫そのものになりたい、などと思う者はいなかったのではないか。彼をお手本とて修練しつつも、その先ではいかに自分自身のマンガを確立させるかに腐心していたはずだ。あの田中圭一でさえ、手塚のパロディをしていた時期を顧みて自身の新たなスタイルの礎としているのだ。また読者の側でも伊藤剛の『テヅカ・イズ・デッド』のように、手塚を神格化することなくそのマンガ表現の解析を試みた評論も存在する。神格化は敬愛のように見えて、実は人格との相互対話を棄てる態度である。『テヅカ・イズ・デッド』は評論の内容のみならず、そもそもマンガ表現を通じて手塚治虫なる人間と真正面から向き合う姿勢そのものが画期的だったのだ。
これは、複製されないからこそ理解しようとする態度が尊い、という主張ではない。それに先立つ話であり、そもそも触発されることや相対すること自体が尊いのだ。なぜなら、そこには自分と相手という二つの魂が在るからだ。それも、異なる二つがひとつに溶け合うことなく二つのまま、それぞれの魂が自らに由って在ろうとするから尊いのだ。あなたとは違う私が、しかしあなたから抗いがたい影響を受けて、この身に沸き起こった感情にどうしようもなく突き動かされる。かくして二つの人格が呼応し、時には何かが継承されることが「魂と魂が握手する」ことだ、と私は考える。握手をするためには二つの『手』が必要なのだ。
読み手の立場を積極的に選択する、ということ
『テヅカ・イズ・デッド』のように評論の形を取らずとも、感想や書評といったレビューの形で、読み手は作品やその描き手に応えることができる。ともすれば作品の消費のみで終わっていたはずのところ、それだけでは終わらせたくないという情動が、読み手をレビューへと突き動かすのだ。
ここにおいて重要なことは、レビューは読み手による表現行為ということである。描き手でなくても、読み手であっても、表現は可能なのだ。それは単に「面白かった」「感動した」と綴ることだけではない。なぜ面白かったのか、なぜ感動したのか、その情動の根源たる真善美の基準を追究するために自分自身と対話し、レビューを通じて自身の技術だけでなく価値観までも否応なくさらけ出すことなのである。描き手と同じように、読み手もまたレビューという表現に責務を負っている(否が応でも負わざるを得ない)のだ。少なくとも私は、描き手が真摯に表現行為を営んでいると信じ、読み手としてそれに応えるために高い技術と誠実さを持ってレビューを行おうとしているし、実際にそうしてきた自負がある。
私は、これこそが中村会長の言う「読者の役割」であり、「マンガを読むことしかできない自分が、マンガに出来る唯一のこと」だ、と信ずるところである。私もマンガは描けない。しかし、このように言葉を紡ぐことはできる。それならば、「できる」ことをひたむきに「やっていこう」じゃないか。積極的な諦念の先に自らの確立した意思でもって読み手の立場を積極的に選択し、その責務を負おうじゃないか。かようにやっていくからこそ、描き手と読み手は生産者と消費者といういささか一方的な関係ではなく、まさに描き手と読み手という相互対等な立場になることができるのではなかろうか。これはまた、コミティアやその他の多くの同人誌即売会にいわゆる「お客さん」は存在せず、全てが対等な参加者である、という理念にも適うものである。
おわりに
私は責任ある読み手として高らかに言い切る。「描き手」を嘯く生成AIの利用者に向けてやる読み手の魂などありはしない。そのような者はカッコ書き抜きの描き手の魂など持ち得ない。私の魂は真に描き手であろうとする者と相対するためこそにある。表現行為における恐れを克服してより強くあらんとする描き手とこそ、この魂は向き合うのだ。
私は魂ある読み手として高らかに言い切る。生成AIなるものと握手できる読み手の魂などありはしない。たかが道具に過ぎないものに対して人格や魂など期待しようもなく、偶像など崇めるべくもない。私の魂は描き手たる人間とこそ握手するためにある。他者に触発されてどうしようもなくペンを執り、自らの情念で作品を作り上げる人間とこそ、この魂は通じ合うのだ。
私は『これしかできない』読み手として高らかに言い切ろう。生成AIの利用者は自身が『できる』立場を未だ積極的に選択していない。描けない者でも文化に対して、人間に対してできることがあるにもかかわらず、それに気づかない、あるいは気づいていても選び取らない、蒙昧で、臆病で、卑小な存在である、と。それでも生成AIの利用を選択しようとするのなら、文化を、人間を、バカにするのも大概にしろよ畜生が!と言い返そう。そのような人倫からほど遠い輩に、人間が向けてやれるものは何ひとつ、一片たりとも存在しない。私の魂は自身の立場を積極的に選択した者たちと連帯するためにある。『やっていく』人間たちとこそ、この魂は手を取り合うのだ。
全ての描き手へ。生成AIの時代においても、どうか絶望しないでほしい。あなたが描く線の一本、彩の一色、セリフの一語を待っている読み手は、この世界に必ずいる。生成AIなどではなく人間こその作品を求めている人間が、必ずどこかにいる。時に悩み、時に惑い、それでも己が真善美を貫こうとする魂を求める別の魂が、この世界には必ずや存在する。そう信じて、どうか心折れることなくやっていってほしい。
全ての読み手へ。私たちにできることはまだある。そう信じてやっていこう。読むことしかできないのなら、読み手にしかなれないのなら、せめて誇り高い読み手であろうではないか。我々ひとりひとりが自らに由ってそのように選び、これからもやっていこうではないか。そうし続けることこそが、きっと読み手の「魂」であり、コミティアはもちろん、コミティアを離れても、きっと通じることであろうから。
