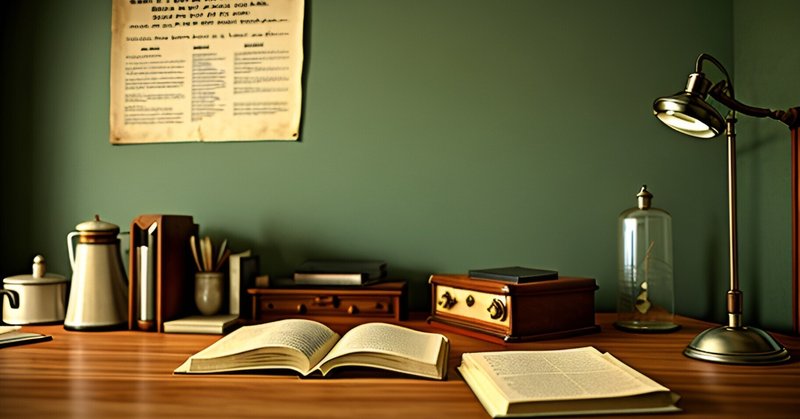
不健康管理社会、あるいは“シビュラメデュケーション”
※地域医療ジャーナル2018年01月号 vol.4(1)より転載です。情報の鮮度にご注意ください。
先日、とある研修会でシネメデュケーションという言葉を知る機会がありました。シネメデュケーションとは映画の「Cinema」、医療の「medical」、教育の「education」を掛け合わせた造語で、1994年にAlexanderが提唱したそうです。[1]
シネメデュケーションは映画作品に描かれた世界を通して、人の身体的、精神的健康とそれに関わる医学・医療のさまざまな行き詰まりや未解決課題を明確化し、新たな展望を切り拓くことを目的とした医学教育コンテンツと言えます。
映像作品に心動かされたり、何かを学ぶきっかけになったりすることは多々あると思います。
僕自身、薬学部へ進学する一つのきっかけとなったのが、1997年に公開された落合正幸監督の『パラサイト・イヴ』という映画と、その原作小説[2]でした。
こうしてみると、映画のような娯楽を目的とした創作作品が、人の学びに何らかの影響を及ぼすことは実際多々あるように思います。そしてこれは映画に限らず、テレビドラマ、小説、漫画あるいはアニメーション作品についても同じことが言えるのではないかと考えています。
医師3040名を対象にした医療漫画に関するアンケート調査[3]によれば、回答者の過半数におよぶ54.1%の医師が『ブラック・ジャック』(手塚治虫)を「最も好きな医療マンガ」であると回答したそうです。 同作品は世代別の解析においても、20~60代以上の全世代で最も支持を得ていたという結果でした。なお、2位は『JIN-仁-』(村上ともか)で6.0%、3位は『ブラックジャックによろしく』(佐藤秀峰)で5.7%となっています。
実際、こうした漫画作品に影響を受けて医療系の学校へ進学された人も多いのではないでしょうか。創作作品には時に大きく人の感情を揺さぶるような力が宿っていて、人のふるまいやその思考に多大な影響を及ぼすことがあると言っても良いでしょう。
2012年にフジテレビで『PSYCHO-PASS サイコパス』というアニメーション作品が放送されました。この作品の総監督を務めたのは、同放送局での大ヒットドラマ作品、『踊る大捜査線』で演出を担当していた本広克行さんです。いくつかのシリーズと映画化もされましたが、僕にとってはとても衝撃的な作品でした。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
