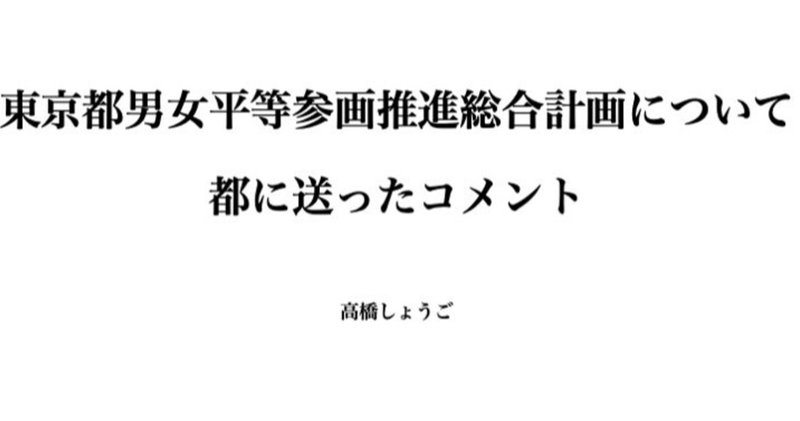
東京都男女平等参画推進総合計画について都に送ったコメント
ご担当者様へ
いつも大変な業務に従事していただき本当にありがとうございます。
お疲れ様です。
乱文ご容赦ください。何卒よろしくお願いいたします。
以下 計画への意見
はじめに に関して
これまでの国と東京都の取り組みや法律と条例の変遷などについて、
できるだけ網羅するように具体例が記載された事について高く評価したい。男女平等参画の理念を表す態度と言える。
人権擁護に直結すると言っても過言ではない計画のため、
偏りのあるまた隠された思惑などが入らないよう注意する意義が非常に大きい。
市民の精査の目に性別の壁はない。今後も是非この方針の堅持していただきたい。
東京都女性活躍推進計画関係と東京都配偶者暴力対策基本計画関係、双方の基本(p1)と概観について
計画策定にあたって、複数回の法改正そして具体的事例に合わせ設けられた立法など、それらの経緯を確認することは重要である。
ただ、経緯や策定された法律や条例また国連からの提起などを「それぞれを確認すること」と「計画の策定で重んじるべき態度」には違いがある事を念頭に置かなければならない。
なぜなら、この計画を元に行われる保護や救済、あるいは生活や職場など様々な場面での参考、行政側が基準として参照する場合など計画の使用には様々な場面が想定される。
それらの場面で【基本的考え方】で示されたような多岐に渡る動きや方針などが重視されてしまうと、根幹であるはずの人権(個人の尊厳)を守るという主眼から意識が逸れさせてしまう恐れが生じるからである。
それを防ぐためには、経緯、関連する法律、地方自治体としての取り組み、新たな懸念や新語等、これらをカテゴライズし、そしてその間を三段論法的に横断する解釈を計画として認めてしまう事のないように配慮する必要がある。
例えば、国連で策定された議定書や目標、昨今より幅広く用いられるようになった「ジェンダー理論」などは平等参画のテーマで積極的に盛り込まれるものである。
しかし、それぞれの提唱元はそれぞれ別個の問題意識や提起の具体的な範囲そして目標などが設定されているものである。文言が日本社会に広まっていたとしても、正確に発信元の具体的な背景が共有されているとは限らない。
その言葉や理念には、往々にして海外の宗教や文化を前提とした人間観や性別観や、それらが背景となって起きた問題の分析などが土台とされていることは、日本においては中々省みられない。
その言葉が日本国内で学術的な定義付けがされていても、日本の今現実に生活をする人々の実情を反映した言葉という確証は無いと警戒心を持たなければならないということを意味する。
地方行政から市民に向けてのものであるため、そこには予算や人員のみならず法律による具体的な限界が存在する。
よって、国連の特定の委員会発の提唱や学術の分野からの発信や世間で大きく取り沙汰される言葉などがあっても、計画策定にあたって最重要となる目標は、都の最大限可能な行動の範囲の中での具体的な救済方法の追及である。
「ジェンダー」など、医学的定義や診断も絡む言葉は安易に扱えるものではない。社会学方面から積極的に発信されているものの、社会学の中でさえ身体的と精神的と社会的等の様々な用いられ方がされておりブレがある。そして性自認に関する重大な事故も起きている(少年ブレンダの事件で有名。また昨今も二度の性転換手術を受ける若者などの事例がある)言葉である事も注意点として共有すべきであろう。
ジェンダー理論を含め参考とする理論について、東京都は検証は可能であっても定義そのものに踏み込むことは困難であるという再認識する必要があると提起する。
これは歴史上に見られる、性別に関する理論や断定が悲惨な弾圧引き起こした事からみても警戒すべきである。
理論の例としては、「神が世界を作った 意思を含め全て神の思し召しである だから(女性に)自由意志はない」といった三段論法が前提のもの。こうしたものは聖者が伝えた元来の教えに対し、後世の人間が行った解釈が暴走したものと言える。
様々な専門家や現代の世相が重視するスローガンがあったとして、それらを網羅するような理論すなわち三段論法的な計画に陥らないことが肝心である。
以上を踏まえまとめると
・計画は行政として行えることや提供しているものをシンプルに示す
・市民がそこにアプローチしやすくする具体的な配慮や窓口対応の設計に時間を割く(あるいはその具体案をまた市民に募る)
・(再三になるが)スローガン的に掲げる文言なども乱暴な三段論法を用いないよう注意する
※男女平等参画が歩んできた道のりや時間を鑑み、市民を性別で二分した上でバランスを取ろうというところから、少子化から想定される具体的な問題への注視や、「平等参画の目標から”男性あるいは女性として”という押し付けが生じないように」といった慎重な態度を提起などが行われるべきタイミングではないだろうか
主に3つの点を計画策定にあたって踏まえるべきものとして提案する。
いかに様々な方針や制度が設けられたとしても、市民に申請主義が完全に浸透しているとは言えず、また追い詰められている人が申請に漕ぎ着けるのは尚更に困難である。
示された計画が市民にとって極めて具体的なものであったなら、それは法の範疇という限界の中で人権を守る挑戦を続けている、男女平等参画の理念にも合致するのではないだろうか。
ジェンダーギャップという言葉について
極めて問題のある言葉である。理由は主に2点。
・経済、政治、教育、健康、それぞれの分野の具体的な関係性が示されていない指数である
・それら4つの項目に深く関係していない問題にも「ジェンダーギャップの現れ」と乱暴に用いられている
例えば独裁国家や戦災被災などの著しくバランスの崩れた国家を指して、具体的に人権を回復すべき部分に注目するための目安として用いるなら有意義であろうと個人的には思う。
なぜなら、市民の政治参加や経済活動への参加に選択肢が生じるのは、ある程度の社会の豊かさや教育や法制度が成立してこそだからである。
戦争で男性の人口が減り様々な労働分野への女性の進出や遺産相続に関する法改正が進んだのは第一次世界大戦以降の各国に起きた事であるが、その状況を「ジェンダーギャップ指数」が示す問題とすべきだろうか。
その状況での女性の労働者の増加を「改善」とみなすのか、生活のために女性が身体に無理をしてでも労働せざるを得ない社会として「悪化」とみなすのか、ジェンダーギャップ指数は一切答えを出すものではないのである。
医師の男女格差についても、経営に関する具体的な問題から重労働を継続して指示しやすい男性医師が用いられやすいという面がある。
そこから医療の現場においてもジェンダーギャップ指数を用いて、短絡的に男女同数にせよと働きかけをしてよいものだろうか。
そのような事をして満足するのは成果だけを気にする政治家と、権威を高める事に夢中になっている顧問として抱えられた学者だけである。
苦しみを背負うのは市民だ。
ジェンダーギャップ指数という言葉を否定しなくとも、こうした問題意識を持つ事は可能である。
東京都が全世界に先駆けて、ジェンダーギャップ指数と具体的な問題との隔たりに注目し、解決を行った行政という名誉を得るのを一市民として期待する。
東京都配偶者暴力対策基本計画関係について 提案
全体に渡って提言したいものがあるが、配偶者暴力やストーカーやリベンジポルノ等の抑止と、被害者の救済率上昇が見込める案をひとつ提案したい。
この計画の名を冠した、通報窓口の一覧を載せた小冊子の配布、また通報や相談窓口に直結するアプリを作成し積極的に広めることである。
加害者側にとっては、相手が通報窓口を知っているまたはそのアプリが携帯に入っていると意識するため一つの抑止力になる。リベンジポルノや未成年等の相談の困難な方々に向けても意義のある手法ではないだろうか。
配布を含めた「具体的な行動」の発表は、スローガンではなく市民に問題に対する具体的な意識の想起を促すものである。
男女はこうあるべき、暴力を防ぐためにどうすべきというスローガンを掲げられるよりも、「あなたはここに向かいなさい」「こういう問題はここに相談しなさい」と具体的な道筋が示された方が、加害する側にも被害を受けた側にも、本当の手助けが行われる社会という認識に基づき、提案する。
「表現」という言葉について
人権を基礎とする民主主義社会において、表現とは個の意志に基づく内面を表すものまたは社会の改善のために提起するものを指す言葉でもある。
これは2つの計画双方に言えることだが、例えば「性別的役割を固定するような表現には気をつける」という表現は、後付けで良い悪いを行政側で判断する余地を残そうとする文面になってしまっている。
そのような表現と判定する主体の存在が現れなければ、そのような表現と定まらないからである。
これは論点先取といって、証明すべきものが始めの方に提示され、あたかもその証明が済んだかのように話を進めるという詭弁の一種である。
このような言葉はいわゆるお役所的なものかもしれないが、人権を基礎とし守ろうとする計画においては甚だしくそぐわないものと言わざるを得ない。なぜなら、性別に関する定義や問題だという断定を権力側が定めるものではないという理念が人権にあるからである。
問題のある表現が存在するというのなら、具体的に定義すべきである。
例えば差別すべき対象は誰それであるとか、仕事場で「男性は率先して○○をやれ」といった表現はダメだというようにである。それを見て市民は意見や判断を重ねられるからだ。
まして、問題とされる差別や犯罪行為などは現代において刑法で規定されているものである。
男女差別をしてはならないとはスローガンとして有意義ではあるが、現実的に私達が必要としているのは助け合いである。どちらかに偏った仕事を分配し直して「平等に行われています」と権力者様に示すことではない。
表現など上記の通り内面を表すものであり、かつ仕事によっては助け合いを促すために性別が標記される場合もあるだろう。根本的に2つの計画内における「表現」という言葉の使い方は極めて雑なものがあると指摘せざるを得ない。
例えば東京都配偶者暴力対策基本計画関係の
※p53「不快な表現に接しない自由」などは
人権を扱う文章として明らかに問題がある。
快不快は情動であり主観である。平等の人権を基礎とする社会において、主観で社会を左右できる人物とは一体誰を指しているのか。これも後付で行政が判断する余地を残すもののようにも見受けられる。
人権思想が広まり人としての徳目を重んじようとする時代の話であれば、
マナーの概念や公共の概念など、市民としてのあり方に関する言及と読もうと思えば読めなくもない。
しかし、これは具体的な問題に対する計画である。この計画が、全ての表現に対し優越する権威性を帯びているというニュアンスが含まれているのだろうか。
誤った三段論法の理論やジェンダーギャップ指数の乱暴な使い方など、時代に沿った対応の変化は大切なことである。
具体的なテーマである以上、表現に関する指針としては個人の主観や曖昧模糊としたものを避けるべきであろうし、むしろ表現云々よりも、今存在する具体的な被害の最中で抜け出せなくなっている人の救済にこそ徹底して力を入れる方針に切り替えた方が、より良い結果を生むのではないだろうか。
以上
高橋尚吾
(住所省略)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
