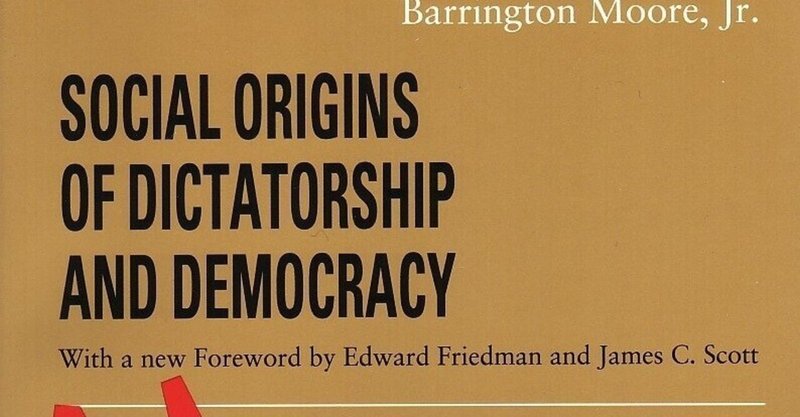
政治体制の違いを権力闘争で説明する『独裁と民主政治の社会的起源』の書評
世界には軍事独裁体制から民主主義に至るまで、多種多様な政治体制があります。そのような政治体制の多様さを説明することも、政治学の重要な課題の一つですが、近代化の道筋はそれぞれの国の歴史や地理に左右される部分が大きいために、体系的、包括的な説明を組み立てることはたやすいことではありません。
しかし、ハーバード大学教授の歴史社会学者バーリントン・ムーア(1913~2005)が書いた『独裁と民主政治の社会的起源(Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World)』(1966)は政治史における近代化のパターンを体系的に分析することを試みた研究です。今でも比較政治学の研究領域でよく知られている古典的業績であり、その大まかな構成は以下の通りです。
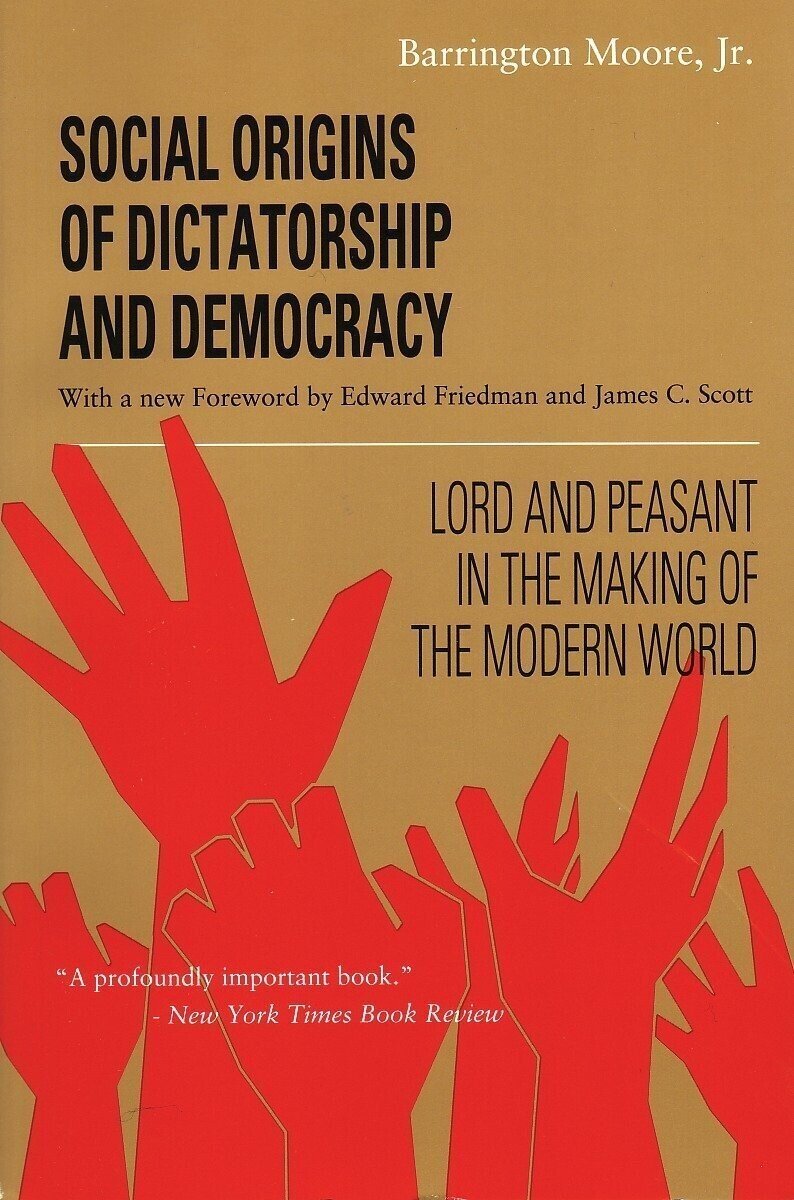
第1部 資本主義デモクラシーの革命的起源
第1章 イギリス―漸進主義に対する暴力の貢献
第2章 フランスにおける発展と革命
第3章 アメリカ南北戦争―最後の資本主義革命
第2部 近代世界に向かうアジアの3つの道
覚書 ヨーロッパとアジアの政治過程―比較に際しての諸問題
第4章 中華帝国の衰退と共産主義型近代化の起源
第5章 アジアのファシズム―日本
第6章 アジアにおけるデモクラシー―インドとその平和的変革の代償
第3部 理論的意味と客観化
第7章 近代社会への民主的径路
第8章 上からの革命とファシズム
第9章 農民層と革命
終章 反動的思想と革命的思想
補論 統計と保守的歴史叙述についての覚え書
以下では、この著作で国内の権力闘争がどのようなメカニクスで動いているとムーアが考えていたのかを説明してみたいと思います。国内政治で重要な主体となるのは、地主、農民、国王、そして市民とされています。
地主、農民、国王、市民の権力闘争
ムーアの説を簡単に要約してしまうと、近代化の結果として形成される政治体制の種類は、農民の動向で決まると考えられています。つまり、政治制度が変化する際に常に注目すべきは農民の存在であって、彼らがどのような社会構造の下で暮らしているのか、それぞれの農家は自前の土地を所有していたのか、経営や財産を処分する自由をどれほど持っていたのか、などを調べることが政治学的に重要な意味を持っているのです。
ムーアの理論に従うと、あらゆる政治的近代化のプロセスは3種類のパターンに分かれます。一つ目は、資産を持った都市の商工業者、つまり市民階級が近代化で力を持ち、抜本的な民主化が進むパターンです(議会制民主主義体制)。二つ目は近代化の後でも地主貴族のような封建的階級が生き残り、民主化が限定的にしか進まないパターンです(ファシズム体制)。三つめは近代化の過程で農民を大規模に動員した革命が起こり、共産主義国家が形成されるパターンです(共産主義体制)。
近代化がどのパターンに入るかは、その国の地主、農民、国王、市民の4者の勢力関係や利害関係によって異なると考えられており、農民の役割もこの国内政治の構図によって変化します。ただ、農民はほとんどの社会において最大の人口集団なので、その動向は権力闘争の展開に直接的な影響を与えます。
ムーアの研究成果に沿って、いくつか代表的な事例を見てみましょう。まず、イギリスの近代化はヨーロッパ諸国の中でいち早く議会制民主主義体制を実現した例です。この国では、農民と国王が革命の勢力として重要な役割を果たすことができず、その代わりに地主貴族と都市市民が台頭しました。これは中世以来の伝統的な農村制度が地主貴族によって、農村人口が都市人口へ強制的に再編されたことに理由があるとムーアは説明しています。
イギリス史では16世紀に海外輸出向けの羊毛生産を拡大して利益を得ようとした地主貴族が一斉に農地の確保に動いた時期がありました。そのときに地主貴族は村落ごとで慣習的に共同使用していた共有地を次々と囲い込んだので、わずかな私有地しか持たない小規模農家は農地を捨てて、都市へ流入せざるを得ませんでした。この「囲い込み運動」によってイギリスの農民の動員力は大幅に低下せざるを得なかったのです。
一部の農家は国王の庇護を受けながら地主貴族の強硬な囲い込み運動に抵抗しようと試みましたが、17世紀に起きたピューリタン革命の争いで国王が敗北したことにより、勢力を巻き返すことに失敗しました。このような歴史的背景があるために、イギリスでは農民は革命の勢力として重要な役割を果たすことができず、地方の地主貴族と都市の市民階級が中心となった議会制民主主義が確立されたとムーアは説明しています。
次にドイツの事例を取り上げると、イギリスとはまったく違った政治史の展開を見ることができます。ドイツでは国王の権威を中心とする国家機構、つまり軍隊と官僚の組織が拡大しましたが、それは国王大権を強化するだけでなく、地主貴族が農民を支配する上でも大きな助けとなりました。イギリスとは異なり、ドイツの農業では多数の農民を労働力として動員する必要があったことから、農民を都市に追い出すことはしませんでした。その代わりに地主貴族は国家権力の助けを受けて、農村で起こる反乱を確実に封じ込める制度を発達させてきました。
もちろん、ドイツ史においても都市の市民階級は一定の役割を果たしましたが、その影響力が地主貴族の影響力を上回ることはなかったとムーアは解釈しています。第一次世界大戦の末にドイツ革命(1918年)が起きてドイツ皇帝が逃亡した後でさえも、市民階級が産業利権と引き換えに地主貴族の既得権益を承認し、その後で成立したファシズム体制を経済的に支援しています。ドイツ社会における農村人口はイギリス社会よりも大きな割合で存続しましたが、農民は地主の権威の下で統制されていたので、国家権力を打倒する勢力ではなく、それを守る勢力として動員されました。
このようなドイツの歴史とは異なり、ロシアの歴史では農民が体制を打倒する革命的勢力として出現しています。ドイツ史と同じようにロシア史では農民を支配する強大な国家権力が構築されてきました。ところが、第一次世界大戦の末に皇帝が追放されると、地主貴族を財政的、経済的に支援できる都市の商工業者、市民階級がいなかったため、農村の反乱を封じ込めることができなくなりました。ムーアの見解によれば、ロシア革命が共産主義体制をもたらしたのは、暴力革命を封じ込めるべき立場にある貴族が市民階級の支援を受けることができなかったためだとされています。
まとめ
ムーアの研究は『共産党宣言』で有名な思想家のカール・マルクスやフリードリヒ・エンゲルスが考えていた共産主義革命のモデルが根本的に間違っていた可能性があることを裏付けています。少なくとも、マルクスとエンゲルスの議論では農民が共産主義革命の担い手として戦略的な役割を果たすとは認識されていませんでした。20世紀に内発的に共産主義革命が成功した国は、ロシア、中国、キューバなど、産業構造の中で農業従事者が占める割合が大きな国ばかりです。
ムーアの著作には難解な部分も数多く含まれているため、お薦めしやすい本ではありませんが、日本語にも翻訳されているので興味があるという方は挑戦してみてください。農民の動向が政治体制の形成において重要な影響を及ぼすというムーアの指摘は、グローバル化が進展している現代の農業が各国の政治情勢に与える影響を分析する際に非常に参考になると思います。
基本的にムーアは政治体制の変化を説明するために国内政治の要因を重要視していましたが、彼に師事した政治学者のスコッチポルは『国家と社会革命』(1979)の中で国際政治の要因、特に戦争の影響を強調しています。こちらの書評も書いているので、このテーマに興味がある方は一度ご覧ください。
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
