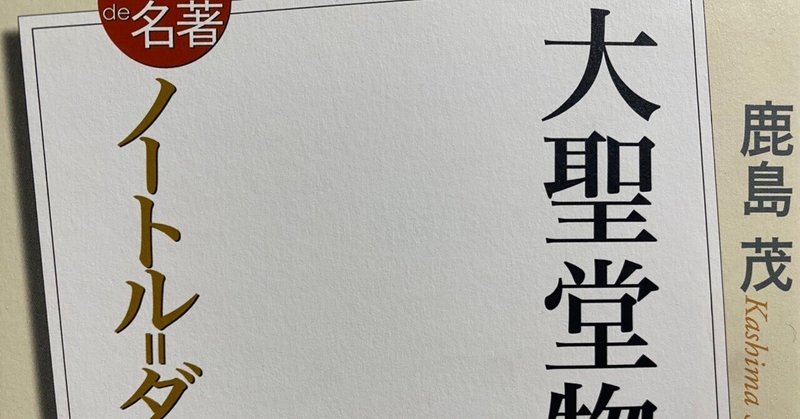
ユゴー ノートル=ダム・ド・パリ 大聖堂物語/鹿島茂
パリの街とその街の代表的なゴシック建築であるノートル=ダム大聖堂。それらへの愛を綴ったのが、ヴィクトル・ユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』だ。印刷本に取って代わられる前まで、人間の知と思想をアーカイブし人びとに伝える役割を一身に担っていたのが中世までの建築だったことをユゴーは、その作品で伝えてくれる。
そのユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』を読んだあと、すぐに読んだのはNHKの「100分de名著」から出ている鹿島茂さんによる『ユゴー ノートル=ダム・ド・パリ 大聖堂物語』だ。

ノートル=ダムの火災の後に
2017年の2月に方法された番組テキストを底本としているが、面白かったのは特別章と収載されている「ノートル=ダム大聖堂とその時代」と題され、その誕生の歴史をパリそのものの誕生から追って書かれた章だ。2019年の4月15日から16日にかけて発生し、尖塔および身廊と翼廊の屋根の大部分を消失したノートル=ダム大聖堂の火災をきっかけに書かれたものだ。
ちょうどその年もゴールデンウィークにパリを訪れる予定でいたこともあり、この火災は僕自身の心にも強く残っている。何度か訪れたこともあり、愛着もあったノート=ダムが火災にあい、煙をあげ、尖塔が燃え崩れていく様子を伝えるTwitterなどにあがる映像で落ち着かない気持ちで見ていた記憶はしっかりと残っている。実際火災から1ヶ月も経たないうちにノートル=ダムの近くまで行き、警察によって封鎖された大聖堂を離れたところから哀しい気持ちで見た。コロナ禍もあり、それがノートル=ダムを見た最後でもある。

日本時間の4月16日の朝7時半に起きると同時にインターネットで大聖堂の大火を知った私は、とっさにヴィクトル・ユゴー『ノートル=ダム・ド・パリ』の次の一節を思い出しました。
「15世紀以前には、人類のいだいた少しでも複雑な思想はみな、建築という形式によって表現されていたのである。民衆の思想も、宗教上の掟もすべて、これを象徴し記念する建物によって表現されたのだ」
こう書いて鹿島さんは、火災で失われたのは屋根や尖塔だけではなく、「中世の最も貴重な「石の思想」が失われてしまったことになる」と言っている。その失われた「石の思想」をすこしでも復元できればとして書いたのがこの追加された章だそうだ。
司教座聖堂
ノートル=ダム大聖堂は、正式名称「パリ大司教座聖堂」という。
ローマ帝国のキリスト教会では、ローマの行政単位のキウィタス(都市区)に相当する単位を教区(司教区)として、それぞれの教区に教区教会=エグリーズと管理者としての司教を置いた。
しかし、キリスト教が広まるにつれ、この単純な区域割では処理しきれなくなる。教区は小教区に分割され、複数の小教区を管理する司教座が置かれるといった管理構造となる。
それに従い、すべての教区教会がエグリーズと呼ばれていたものが、小教区司祭のいる教会が今日のエグリーズと呼ばれる教会、司教座のいる聖堂をカテドラルと呼ばれて区別されるようになる。
さらに、大都市圏の司教区が大司教区と呼ばれるようになり、その管理者を大司教と呼ぶようになる。ただし聖堂の名前は、大司教のいるカテドラルも同じようにカテドラルと呼ばれるのは変わらない。
ノートル=ダム大聖堂がパリ大司教座聖堂という名をもつのは、パリが大司教区であり、その大司教座の聖堂だからである。

2019年5月撮影
シテ島とパリ
パリはローマ帝国内でキリスト教が公認された時代から司教区だった。
ローマ帝国崩壊後にフランク王国となっても首都とされ、その際、聖ステファヌスに捧げられたバシリカ(特権を認められた教会堂)が建てられ、これが司教座聖堂として認定されたという。
しかし、メロヴィング王朝の時代からカロリング王朝の時代になって首都がドイツのアーヘンに移ると、聖堂は打ち捨てられてしまう。この場所に後のノートル=ダム大聖堂が建てられるのは、400年近く待たなくてはならない。
カロリング王朝フランク王国4代目の王シャルルマーニュ(カール大帝)がヨーロッパを覆う王国を建設した後、その孫の代に王国は、東フランク、中部フランク、西フランクに分割されて、パリは西フランクの首都になる。その頃、ヴァイキングの船団がセーヌ川を遡ってきてバリへの襲撃を繰り返し、王や民衆は、シテ島の周囲に城壁を築いて要塞化した島に閉じこもった。
ヴァイキングの侵略で弱体化したカロリング王朝は解体し、978年にカペー王朝が成立。西フランク王国はフランス王国に名前を変え、パリはフランス王国の首都になる。しかし領土は少なく、パリ周辺のイル・ド・フランスとオルレアン周辺に限られ、当時の寒冷な気候のために餓死や伝染病が拡大し人口は減少の一途を辿っていたという。

まだ尖塔の残る2017年
フランスの拡大、そして包囲されるフランス
そんな状態が好転したのはミレニアルが明けて100年ほど経ち気候が温暖化してからだ。温暖な気候が収穫物を増やしただけでなく、シトー修道会による開墾運動が森を農地に変え、作付面積を大幅に増やしたことも大きいという。収穫量の増加で人口も増え、12世紀にはフランスの人口は10世紀に比べて3倍になった。人口が増えて農村に居場所のなくなった余剰人員がパリに流れこみ、シテ島の外にも人があふれ出し始める。
12世紀に入って大開墾運動のおかげで王領地からの収穫も増え豊かになったフランスに危機が訪れたのは1154年にプランタジネット帝国と呼ばれたノルマンディー、アンジュー、アキテーヌといった公国を相続していたアンリが、後継を残さず薨去したイングランド王の跡も継いでヘンリー2世となったことで、フランスは数倍の面積をもつ帝国に対峙せざるを得なくなったときだ。
この危機に対して、当時のルイ7世は、国家的な統一と国民の団結のため、キリスト教信仰を強化するしかないと考えた。1160年、多くの国民が祈りを捧げられる巨大な大聖堂を建立すると決定を下し、1163年になって工事が開始されたのがほかならぬノートル=ダム大聖堂だ。
12世紀の終わりに一旦の完成を見、その後、13世紀のなかば、北と南の塔も完成する。

フランス革命での破壊とユゴーの作品をきっかけとした修復
こうして12世紀から13世紀にかけて作られたノートル=ダム大聖堂は当時の人びとにとって単なる建物ではなかったはずだ。ユゴーが「15世紀以前には、人類のいだいた少しでも複雑な思想はみな、建築という形式によって表現されていたのである」と書くとおり、「民衆の思想も、宗教上の掟もすべて」、この大聖堂が「象徴し記念する」役割を担っていたのだろう。
しかし、その大聖堂も18世紀のフランス革命以降、破壊活動や略奪の対象となってしまい、彫刻などが壊されたりした。その残骸がクリュニー修道院を改装した中世美術館に展示されている。

こうして一旦廃墟となったノートル=ダム大聖堂の修復のきっかけをつくったのがユゴーの『ノートル=ダム・ド・パリ』だという。
今回、ユゴーの作品を読んで、あらためてノートル=ダム大聖堂を普通に訪れる日々がくるのが待ち遠しくなった。ユゴーの作品がノートル=ダムを蘇らせたように、再び、大聖堂が蘇るのを夢みて。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
