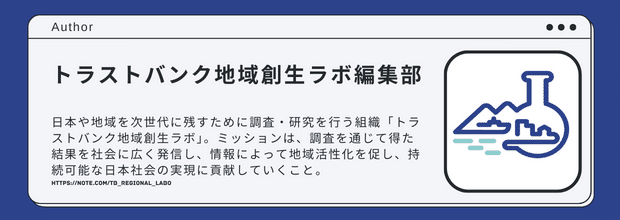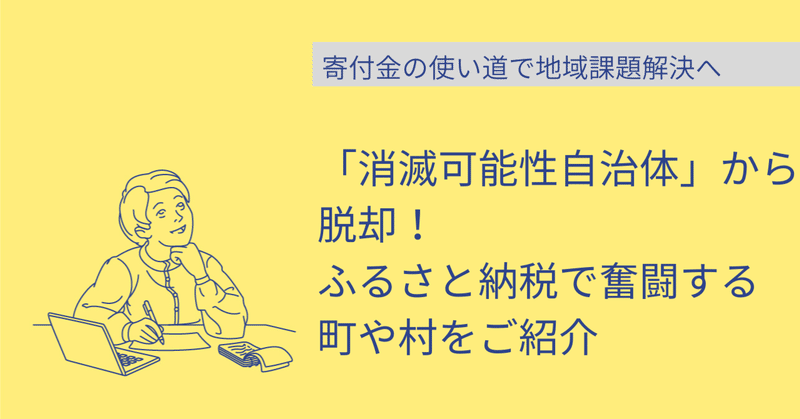
「消滅可能性自治体」から脱却。ふるさと納税で奮闘する町や村/子育て、産業育成、災害復興など、さまざまな寄付金の使い道で地域課題解決へ
2024年4月24日、民間の有識者グループ「人口戦略会議」により、人口から見た全国の地方自治体の「持続可能性」について分析を行ったレポートが公開され、10年ぶりに「消滅可能性自治体」が発表されました。
前回「消滅可能性自治体」と指摘された自治体のうち、今回脱却した自治体は239あります。それらの「消滅可能性自治体」を脱却した自治体の中で、ふるさと納税の使い道を工夫し、自立した持続可能な地域を目指して奮闘している自治体を3つご紹介します。
①北海道上士幌町:ふるさと納税で子育て支援に力を入れ、人口増に取り組む

(出典:『地方自治体「持続可能性」分析レポート』)
北海道の十勝平野にある、北海道上士幌町では、「上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金」を設立。子育て支援に力を入れることで移住者を呼び込み、人口増に取り組んでいます。
東京23区にほぼ匹敵する面積に、約5,000人の町民が暮らしている同町は、牧場で飼育されている牛の頭数が34,000頭と、人の数より牛の数の方がはるかに多い酪農王国。少子化が進み、1955年をピークに人口は減少。高齢化率も高く、人口の自然減少が年々進んでいました。しかし、ふるさと納税とその寄付金を活用した子育て支援策や積極的な人口増への取り組みにより、2016年に13年ぶりに人口増になりました。その後増減あるものの、今回、消滅可能性自治体を脱却!
町は寄せられた寄付金の一部を積み立てて、子育て支援・少子化対策に充てる「上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金」を設立しました。これまでにも限られた財源の中で数々の子育て支援策を実施してきましたが、ふるさと納税の寄付金を活用することになってからは、より思い切った施策が実施できるようになったようです。中学卒業時までだった医療費無料は高校卒業時まで延長することになり、予防接種にかかる費用も給付するようになりました。
さらに上士幌町の寄付金活用で注目を浴びたのが、2015年4月施行の子ども・子育て支援新制度を受けて設立された、町立の認定こども園「ほろん」の10年間の無料化です。中には千葉から上士幌へ移住してきて子育てをする移住者もいらっしゃり「先生のほかにも大人がたくさん関わっていて、見守る対応がしっかりしているなという印象があります。給食が無料なのもすごく助かっています」と語っていました。

②島根県海士町:人口減少・少子高齢化…地域課題が山積する離島の挑戦

(出典:『地方自治体「持続可能性」分析レポート』)
海士町は、日本海に浮かぶ中ノ島にある、人口約2,200人ほどの半農半漁の町です。「誰もが安心して暮らせる島の環境整備に関する事業」「島まるごと教育の魅力化に関する事業」など、島の持続可能な未来実現のためにふるさと納税を活用しています。島の未来を支える産業を支援・育成する「未来共創基金」の設立においては、2021年に「ふるさとチョイスAWARD」の「未来につながるまちづくり部門」の大賞を受賞しています。

③熊本県南阿蘇村:熊本地震の復興を経て「自立持続可能自治体」にまで発展

(出典:『地方自治体「持続可能性」分析レポート』)
2016年4月に起きた熊本地震で被害を受けた南阿蘇村。ふるさと納税の災害支援で多額の寄付を受け付け、寄付金は崩落した阿蘇大橋に代わる新阿蘇大橋の建設やインフラ整備にあてられてきました。
今回のレポートでは、消滅可能性自治体から脱却しただけでなく、「自立持続可能性自治体」と呼ばれる、2050年までの若年女性人口の減少率が20%未満にとどまっている65の自治体のひとつにもなりました。

以上、ふるさと納税の活用をはじめとするさまざまな工夫によって「消滅可能性自治体」から脱却した自治体を一部ご紹介しました。
トラストバンク地域創生ラボは、今後も、地方自治体が持続可能な地域社会を構築するための手がかりとなる情報を発信していきます。
<参考>
ふるさとチョイスAWARD 2021 「未来につながるまちづくり部門」大賞受賞事例