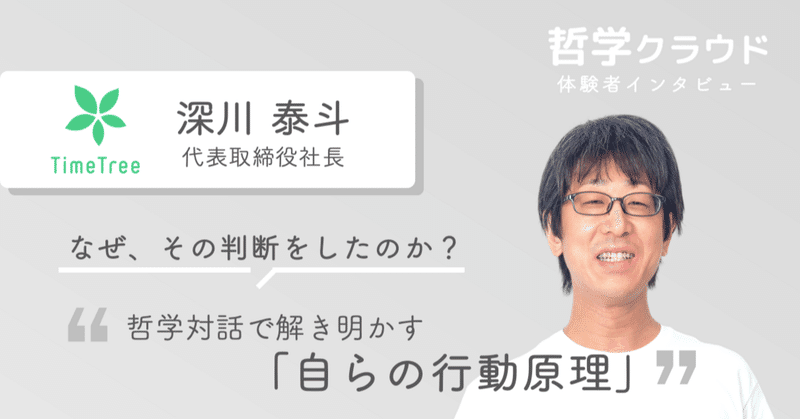
TimeTree深川社長が体験した「哲学対話」の価値
今回は、株式会社TimeTreeの代表取締役の深川さんに経営者・管理職向けサービスの1つである「哲学対話forリーダー」を体験いただき感想をお聞きしました。このサービスでは、選んだテーマで哲学者と1対1で対話する「哲学対話」と、対話から見えた考えやその前提を哲学者が分析する「哲学分析レポート」をお届けしています。
深川さんは「良い組織とは」をテーマに哲学対話を行いました。
ぜひ答えのない環境で経営や組織開発に取り組まれるリーダーに読んでいただきたいインタビューです。
生き難さや反抗の先にあった「哲学」

上館:今回は、もともと深川さんが哲学や人文知が好きだと聞いていたので、ぜひ哲学対話を体験いただきたいと思い、僕からお声がけしました。
最初に、そもそも深川さんが哲学や人文知に興味をもった経緯について伺いたいと思います。
深川さん:大学で文化人類学を学んでからかな。ゼミで触れてから文化人類学や哲学に興味を持ちましたね。
上館:大学時代に文化人類学や哲学に触れて「面白い」と思う方はなかなかいない気もします。
深川さん:そうですね(笑)。高校時代からメインストリームに苛立ちを覚えていたことも関係しているかもしれません。
深川さん:高校が進学校で厳しくて、就職先まで見据えて大学を選ぶようなところだったんですが、やれと言われた通りにやりたくなくて反抗していましたし、当時からロックバンドなどもやっていました。
生き難さみたいなものをずっと感じていたこともあって、文化人類学や哲学に興味を持ったんだと思います。
哲学者による一見“ぎょっとする”ような「問い」
上館:今回体験いただいた哲学者と1対1で対話する「哲学対話」や、対話終了後にお届けした「哲学分析レポート」の感想をぜひ教えてください。

深川さん:感覚的には、楽しい。ひたすら楽しい感じでした(笑)。
上館:素直に嬉しいです。どのあたりから感じてくれましたか?
深川さん:普段あまり考えることのない問いに対してじっくり考えるチャンスは無いので、それ自体が楽しかったです。1対1なのでフォーカスして自分のことがわかりますし。
あと感じたことは、一見ぎょっとするところを深掘りするのが面白かったです。
例えば、「良い組織とは」というテーマで哲学対話をした際に、冒頭で哲学者の梅田さんがこんなふうに問いかけてくれたんです。
「政治が語られる時に人々の人生や生命が蔑ろにされることがあるけど、政治の問題は同時に組織の問題でもあると思うんです。関わる人の人生をどう展望しているかを含めて良い組織についてのお考えをぜひ教えてください」
普通は政治の問題は組織の問題に直結すると考えないですよね。

深川さん:あとは僕が何気なく出した「復讐」という言葉がメインテーマになって、良い意味として解釈や分析をしてくれました。
上館:仰る通り、哲学対話における哲学者からの問いかけや、対話をふまえた哲学的な解釈・分析は哲学クラウドの強みなので、体感いただけて嬉しいです!
哲学対話は、自分が世界をどう見ているかがわかる対話
上館:他にコーチングなどの対話サービスを受けたことがあれば、違いを感じた部分などもぜひ教えてください。
深川さん:コーチングとの違いはすごく感じますね。
言語化が難しいですが、コーチングが個人を深堀りして内省できるサービスだとしたら、哲学対話は、僕が世界とどう向き合っていて、世界をどう見ているのかが分かるサービスだと思います。
なぜそれが行動原理や判断基準になっているのかがわかる。それが面白いですね。
上館:ありがとうございます。
深川さん:全てのビジネスが該当するか分からないんですが、スタートアップや新規事業をやる人たちって、「自分が世界をどう見ていて、何がしんどいと思っていて、事業がどう世界と繋がっていくか」を考える人たちだと思うんです。哲学対話の価値はそこと繋がりますよね。

深川さん:あと組織のリーダーをしていて思うのは、リーダーの人間観や世界観の歪みは組織にそのまま出るし、その歪みで苦しむ人もいるということ。
例えば、僕はアイデアを出すのが好きで、みんなにアイデアを求めたりするんですが、アイデア出しが苦手でうまくできない人もいると思うんです。そういう人に対して「この人やる気ないのかな」と思ってしまってその人が生きづらくなる可能性もあると思います。
僕自身が世界をどう捉えてるかを自分で知って、それを組織のみんなにも知ってもらうというのは、メタ認知として大事な気がしました。
上館:ありがとうございます!「世界の見方」は人や組織の課題の本質だと思ってサービス開発をしているので、非常にありがたい言葉です。
深川さん:ほとんどの人は自分の見方以外の世界の見方があるなんて思ってないですよね。僕が持っている考え方の偏りについて自問自答したり、哲学者の梅田さんにレポートで出してもらった問いをチームメンバーとも対話してみたいと思いました。
哲学は、「『わからない』ということ」への耐性をつくる筋トレ
上館:ちなみに、深川さんだからこそお聞きしたいのは、人文知や哲学の価値についてです。どのようにお考えですか?
深川さん:やっぱり、自分の世界の見方がわかるという意味で人文知は重要だと思いますね。
あとは、ビジネスにおいて「わからないことへの耐性」が重要になっていると思うんです。
今では分業化や専門化が進んで、ITの仕事をしている僕ですらなぜパソコンが動いているか分からない。わからないことが多いなか、色んなことへのフィードバックだけが早くなって、わかるための方針だけは簡単に与えられるから、すぐに「わかったような気」になってしまう。
実際はわからないものと繋がって向き合わないといけないのに、その能力と機会が人類から失われている。その足腰を鍛えるのが哲学だと思います。
僕は哲学や人文知の本を土日に読みますが、これは筋トレに似ているんですよね。知らないことがあって、それを知る負荷がある。わからなさへの耐性を作ることがビジネス上すごく大切だと思うので、大事な筋トレだと思います。
上館:わからないことへの耐性、面白いですね。ありがとうございます。

上館:最後に、もし「哲学対話forリーダー」を友人に勧めるならどんなサービスだと言いますか?
深川さん:経営者にはメタ認知が大事だと思いますが、「メタ認知を普通とは違う角度でできるサービス」ですね。
合理性だけでは判断できないことはビジネス上たくさんありますよね。「赤字でもこれだけはやる」とか。その判断がブランドになったりもする。軽い意味で言うのは嫌ですが、そこを最後に決めるのはその人自身の哲学や価値観のようなものなんだと思います。
合理性で判断できないことに対して何を基準にするのか、その原動力の理解を助けるのがこの哲学対話だと思います。
上館:経営者は答えのない課題と日々向き合っていると思います。その課題をどう乗り越えるかは、まさに哲学を通してご支援できると確信しています!
深川さん、本日はありがとうございました!
哲学対話には、経営者・管理職向けの「哲学対話forリーダー」とチーム向けの「哲学対話forチーム」があります。
サービスの詳細や哲学分析レポートに興味がある方はぜひお気軽に以下のフォームからお問い合わせください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
