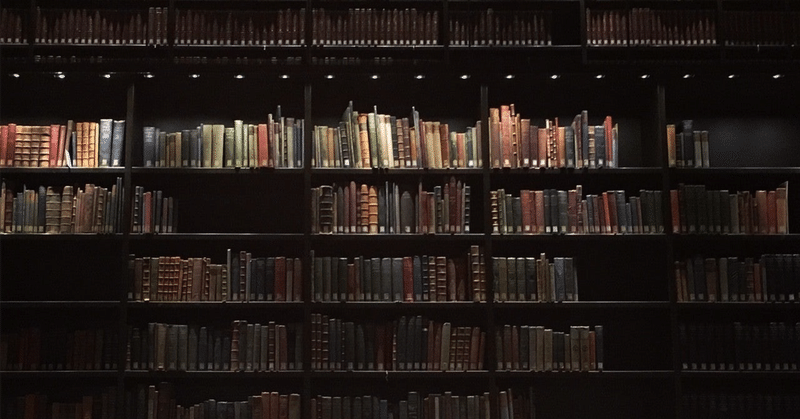
2024-02-11: 最近読んだ本
マジで忙しくてnote書く時間が無かった。
1月末から2月頭は特に厳しくて、そもそも本自体ほぼ読めてないし。
脳がおかしくなりそう。
したがって、読了からかなり時間がたっている本もあるため、かなり印象寄りの感想を手短に書く。ご容赦ください。
平野啓一郎『私とは何か 「個人」から「分人」へ』
小説家・平野啓一郎が自作において展開している「分人」という考え方を、小説でなく新書の形式をもって解説するのが本書。
平野先生の「分人」については、昨年受けたインタビューで少し触れているのだが、インタビューを受けた時点では本書は読了していなかった……。
分かりやすい本なので是非読んで欲しい(平野先生としては、やはり新書よりも小説を読んで欲しいところだろうが)。
分人についてざっくり理解で言うと、私たちは「本当の自分」と社会的なペルソナである「キャラ」によって人格が構成されるのでなく、「父であるときの分人」や「会社での分人」、「地元の友達と遊ぶ時の分人」……など、相手や環境に応じて「分人」という、個人よりも分割可能な単位の人格を切り替えているのだという。
我田引水で恐縮だが、私も昔『たらちねパラドクス』という4コマ漫画において、このような分人概念に到達しており、分人が衝突する状況下における「パラドックス」をコメディとして描写しようとした。
描写に成功したかどうかについてはここで省察しないが、平野先生(彼は私より14歳年上だ)と同時期的に上記のような考え方に達してたのは、どこか奇縁というか、時代によるものなのかな、とも思う。
キャラ化という概念について言えば、2008年前後から荻上チキ、土井隆義、斎藤環ら多くの論客が、若者のコミュニケーションプロトコルとして主題的に論じている。
斎藤や鷲田清一は2000年前半から「キャラ化」による関係性構築に着目しており、さすがに慧眼である。
「キャラを演じる」という考え方は、「本当の私」という剥き出し自己を措定した上に成立するが、分人主義においては「私」とは分人の集合であるため、分人を剥いても何も残らない、脱中心的な考え方である。
私はこの考え方が(私もずっとこのように考えてきたから)とても自然に感じられるのだが、皆さんはどうだろうか。
今井翔太『生成AIで世界はこう変わる』
東京大学松尾研究室所属の今井先生による単著である。
内容としては、2023年断面での世の中的なAI技術とその活用や問題点についてのサーベイが主だ。
私は当人と面識こそないが、今井先生とはX上でわりと前から相互フォローだ。ゆえに、普段この手の一般向けの解説書(というと乱暴だが、伝わるだろうか)はあまり手に取らないものの、おっとり刀で買ってみた。
2023年、Xを見ていると生成AIは毎日各所で大小の炎上を起こしていた。
2024年現在も、文化庁が「AIと著作権に関する考え方について」というパブコメ募集を行っている(2月12日まで)。
AIについては私もちょいちょいnoteで記事を書いたりして、たまにちょいバズしているが、私の記事の内容が秀でているというよりは、多くの人の関心が強い論題なのだと思う。
私自身、大学院時代は機械学習を研究していたので、ニューラルネットワークなどの要素技術は一応理解している(と思っている)が、昨今の爆速技術発展にはまったくついていけていない。
なので、私の視座は研究者というよりも、もっぱら「漫画家・イラストレーター・ソフトウェアエンジニア」だ。
極めて個人的なことを言うと、ソフトウェアエンジニアとしてはAIによる恩恵やエンドユーザー(エンジニア)への価値提供を高く感じるものの、いち絵描きとしてはノイズとしか感じていない。
著者は機械学習の研究者であるから、本書は基本的に機械学習をポジティブに評価しているし、「いろいろ課題もあるけど今後が楽しみです」というテイストだ。
私も半分は賛同する一方で、画像生成AIがもたらす課題はZiv Epsteinらの課題区分のように、様々な性質の領域においてそのインパクトを増しつつあると感じる。
単純に「楽しみだなぁ」と言い切れない、歯切れの悪さは、技術を利用する側である私たち人間の未成熟さに起因するのかなぁと、Xの炎上を眺めるたびに心苦しい。
吉田茂『回想十年』
年末、白洲次郎関連の本を色々読み漁っていた関係で、吉田茂の回顧録にも手を出してしまった。
吉田は麻生太郎元首相のおじいさんだ。
本書は、戦前の外交官時代から、戦中・戦後の総理大臣指名後を吉田自身が振り返る内容で、エッセイ的な読み口の本である。堅苦しさはなく、のびのび書いているように思う。
本書に白洲次郎は1箇所(次郎が奔走した日本国憲法制定関連)しか登場しないが、白洲次郎関連の本には(彼の自著含めて)吉田が「じいさん」として頻出し、次郎の忌憚ない吉田評も少なくない。
なので、吉田茂に興味がある方は、次郎関連の本もぜひ併読をおすすめする。
ところで、本書には吉田の酒に関する失敗エピソードが1つ挙げられている。
戦後であるから、吉田も60歳後半であろうが、あるあるな小市民的失敗であり、多少の親近感を禁じえない。
ここでは記さないので、ぜひ本書を読んで欲しい。
月ノ美兎『月ノさんのノート』
にじさんじ所属バーチャルライバーの月ノ美兎によるエッセイ。
月ノ美兎がどんな授業にでも使えるズボラな「なんでもノート」にエッセイを描き、読者がこれを拾い読みしてしまった(郵便的誤配!)というコンセプトの本だ。
こういう仕掛けも月ノらしい。
私はあまりVTuberに詳しくなく、月ノについても耳学問的な認識が多分にある。であるからして、月ノのファンアイテムとして本書を読んだというよりも、黎明期からVTuber活動している人物のエッセイを求めて紐解いた格好だ。
後述の『虚空経典』についても言えるのだが、「VTuber」というのはかなり特殊な「分人」である。
紛れもなく「月ノ美兎」は演者(魂)の分人の1つであるが、パブリックに「月ノ美兎」を分人として扱うことを、演者は許可されていない。
ゆえに、このようなエッセイを書く場合も、演者は「月ノ美兎」としての分人性と、キャラクターである「月ノ美兎」の両者を意識して執筆せねばならないだろう。
そのような難しいコンセプトの書籍が本書である。
剣持刀也『虚空経典』
にじさんじ所属バーチャルライバーの剣持刀也によるエッセイ。
本書もまた、月ノ美兎同様に難しいコンセプト下で書かれている。
剣持のファンには自明であろうが、剣持があらためてライバー活動に対するスタンスを表明していたり、かつてモチベーションが落ちてしまった時期の回顧をするくだりでは、思わずうーんと唸らされた。
私はVTuber史を総覧し語る口を持たないが、かつてあるVTuberの運営組織に接近していたことがある。ずいぶん前の話だ。
当時はまだ、世界観やコンセプト、動画としての完成度を重視していたVTuberが多かったものの、次第に配信者型のVTuberがメジャーになっていった。時代の要請はそちらであり、結局オルタナティブ・ラディカルなものよりも、ピアキャス以前からの「配信者」的なものこそが、タイムレスな強度を持っていた、と言えるのかも知れない。
新野安・氷上絢一ら『エロマンガベスト100+』
編著です。ありがとうございます!
— 不屈の新野安@ティアち41b (@iorin_the_3rd) January 21, 2024
読んでいたら、Xで編著者からお礼を言われてしまった。恐縮。
さて本書、永井豪『ハレンチ学園』から始まって、本邦のエロマンガ史を総覧していくという内容。
論者の選好が史観に左右するため、盲目的に受容することは無論避けたいが、このような本が存在することがともかく偉大な仕事である。
とくに、後半に伝説の同人誌『シベール』に端を発する同人誌史が掲載されていることは白眉。同人誌まで言及するとは!
ちなみに私のナンバーワン・エロマンガは、胃之上奇嘉郎『奉仕委員のおしごと』です。
鈴木清剛『ロックンロールミシン』
西尾雄太『下北沢バックヤードストーリー』において言及されていた本作。
まず行定勲監督・加瀬亮主演の映画版本作を視聴し、次いで原作を読んだ。
著者は日本のデザイナーズブランドであるコムデギャルソンに数年勤務経験があり、元々はアパレルプロパーだったようだ。
デビュー後、アパレル時代の経験を尋ねられることが多く、それならいっそ、アパレルの話を書いてみたのが本作とのこと。
映画版と原作ではいくつかの点が異なるが、私の趣味として映画版がより好きかもしれない。ただ、物語として整理されている点においては原作に軍配が上がると思う。
ところで、本作に影響を受けてインディーズブランドを始めようとするキャラクターが『下北沢』に登場するが、本作を読んで(観て)なおそう思えるのか……と、ちょっとびっくり。
映画についても少し触れると、行定監督の『GO』は勿論、2000年代前半の日本映画の雰囲気が色濃い。
ネタバレは避けるがクライマックスのとあるシーンは豊田利晃監督『青い春』を思い出すし、加瀬亮も池内博之も当時の黒沢清作品で目にしたプレイヤーだ。
「あの頃感」が詰まった一作。スマホでなく、家電がガジェットとして機能している点も見逃せない。
山田太一『夕暮れの時間に』
脚本家・山田太一は、2023年11月に逝去した。
『岸辺のアルバム』や『ふぞろいの林檎たち』といった名作を世に送り出し、後年は小説家として活動していた。
『さくらの唄』『バカ姉弟』などで知られる漫画家・安達哲は、山田太一作品からの影響下にあるとしばしば言われるが、そもそも山田脚本の影響を受けた作品は枚挙にいとまがない。
ただ、私は世代でなかったこともあり、山田脚本の作品にはほぼ触れずに生きてきた。
安達哲関連の調べ物をしている線上で山田を知り、とりあえずエッセイから入ってみた次第。去年訃報が出ていたことも知らなかった。
山田先生のエッセイは本当に面白い。なによりも語り口が柔らかく、堅苦しいところがまるでない。
本書を読んでいて、実に我が意を得たりを感じたくだりがあったと記憶しているのだが、呆けていて電子的なブックマークを失念しており、パーッと読み返しても記載箇所が分からなかった。
不確かなことを書くのは避けたいので、該当箇所を見つけられたらまた別途記すこととする。
山田太一のエッセイを、物理本でもう数冊購入してしまった(電子はなかった)。私の近日のひそかな愉しみである。
チバユウスケ『チバユウスケ詩集 ビート』
チバさんが逝ってしまった。
彼の訃報は周知の事実だが、今も私にはどこか現実感のない響きとして耳に残っている。
本書はチバが生前参加していた各バンドにおいて詩作した歌詞を掲載し、軽くコメントなんかも付録している詩集である。生前出版されていたが、長らく入手困難であったものが、彼の逝去に際して再出版された様子。
詩集であるが、もともとは楽曲の歌詞であるから、詩を読んでいるとそこにはチバの独特のヴォーカルが、そしてバンドサウンドが聞こえてくる。
伝説のバンド、TMGEはギタリストのアベフトシに次いで、ヴォーカルのチバを失い、フロントマンはみな逝ってしまった。
歳を取るということは、つまりこういうことなのだと、ヒーローたちの訃報に接するたびに反芻している今日このごろである。
九井諒子『デイドリーム・アワー』
読んだ漫画に言及していると際限ないので基本的に「読んだ本」で紹介しないことにしているのだが、九井先生の本著は良かった。
漫画ではなく、著者の落書き本にあたるのだが、これがとても良い。
本当に絵を描くのが好きなのだろうな、と(著者を)知りもせずに勝手なことを言いたくなる程度には、楽しい画面が広がっている。
マルシルたちの現代服イラストなどは本当に「俺たちが見たかったやつ」である。
蛇足だが、ファリンがこんなに魅力的なキャラクターなのだと落書き本を読んであらためて思った。本編ではストーリーの都合上、あまり出番がなかったファリンであるが、作者の愛情がたっぷり注がれていたキャラなのだった。
かつて、ハイファンタジーは漫画家の高い技量を求めるため、特に新人には不向きなジャンルだと言われていた。少なくとも、私の身辺におけるプロの世界ではそういう声があった。
『ロードス島戦記』のような作風の画面を描ききれる画力があるか、という話である。
近年、なろう系の勃興隆盛によりファンタジー作品が勢いを取り戻し、ローファンタジーだけでなくハイファンタジーな作品も多い。
ただ、『ダンジョン飯』ほどに高い画力と作品に閉じた世界観(読者のメタな知識、たとえばJRPGのお約束やなろう系一般のお約束などを強く要請しない)の構築は、本作を特異な位置に押し上げている。
近年では『葬送のフリーレン』が同様にハイファンタジー作品としてメジャー化しているが、ハイファンタジーは本来、新本格ミステリやハードSFのようにマニアックさと表裏一体である。
メジャーさとジャンル「らしさ」を維持しつつ、「飯」モノとしてのコンセプトも維持しきった本作は文句なしの名作だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
