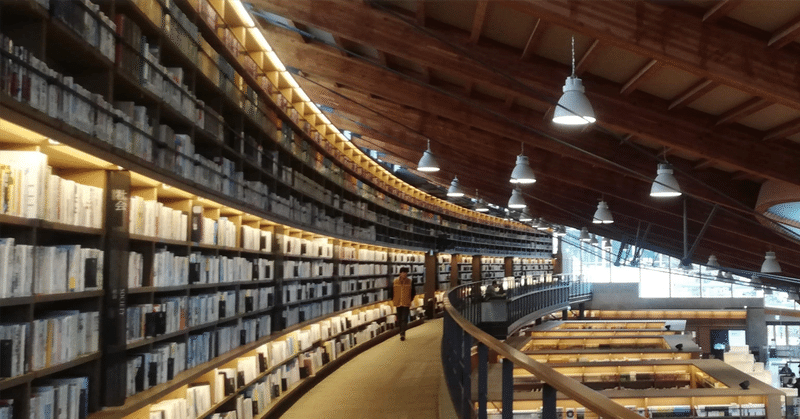
2024-04-15: 最近読んだ本
最近読んだ本。
といっても、足掛け数ヶ月みたいな本もある。
同じ本でも、遅々としてページが進まない日があれば、わりとスイスイ集中して読める日もあるんだけど、なんでだろう。
『美術手帖「NFTアートってなんなんだ?!」』
2021年12月号の美術手帖。なのでちょっと昔の特集。
2021年はNFTバブルの只中で、投機対象としてNFTの注目度が加速度的に上昇していた時期だった。
狂乱の時期が過ぎ、2023年には過熱したブームも下火。
Crypto Punksなどと並び、クリプトアートの代表と目されていたBored Ape Yacht Club(BAYC)の価値暴落が報じられている。
一過性のブームだったんだね、と切り捨てられるほど、私はNFTアートやジェネラティブアートの現在について詳しくない。
はっきり言って門外漢。とはいえ、NFTアートを購入したいと思わないものの、界隈で何が起きているのかは知りたかった。
本誌の特集は2021年のものであるから、NFTアートの基礎教養と、界隈の著名人へのインタビューを通じてその展望を提示することが主題となっていた。
ところで、本誌でインタビューを受けていたラファエル・ローゼンダールへの、2023年末におけるインタビューが下記だ。そこには印象的な言葉がある。
いまはデジタル作品の販売で生計が立てられているおかげで、アナログ作品に挑戦することができています。物理的な作品で知られるようになった後で、デジタル作品に着手する作家が多いですが、僕はその逆ですね。
NFTアートによって得た利益によって生活基盤が安定し、それによってアナログの制作に着手するためのリソースを確保できたアーティストがいるということは、単純に喜ばしいと思う。
NFTアートはその黎明期から、アーティストが生計を立て、制作を継続していくための新しい手段であると期待されてきた。
ローゼンダールのように、実際に成功を掴めたNFTアーティストがどれだけいるのかは分からないが、この点において私はNFTアートの意義を感じる。
しかし、肝心のNFTアートについては、その美術的価値をどう求めるか、また見出だせるのか、いまだに懐疑的である。
NFTアートと一言で言っても、その内容は幅広い。
私はCrypto PunksやBored Ape Yacht Clubのような、コンピューティングリソースによって膨大に自動生成されるジェネラティブアートを、たとえばSupremeの限定アイテムのように捉えている。
つまり、レアなマスプロだ。
少なくとも、既存の西欧中心的なアートルール上で評価可能とは思わない。現行のコンテンポラリーアートは、美術史の参照とテーマ・コンセプトが重要であり、その俎上でマスプロ・ジェネラティブアートは評価しうるのだろうか?
かつてアンディ・ウォーホルは多くの似顔絵を制作し、NFTアーティストの中にはウォーホルの仕事を参照し我田引水する人もいるだろう。
その場合、NFTアートでウォーホルを最初にやったアーティストだけが、既存のアートルールでは評価対象となるのではないか。
無論、NFTアートが既存のアートルールに縛られる必要はない。むしろ、権威的なアートルールの外部で市場とコンテクストを醸成し、古いアートルールに打撃を与えることを企図するようなアーティストも存在するのではないか。
とはいえ、オールドタイプな私には、NFTアートやジェネラティブアートの多くが似たりよったりに見えてしまう。
特に、NFTとして自立的なフルオンチェーン(ブロックチェーン上に、アートの所有権だけでなく、アートそのものを電子的に保存すること)の作品はその容量的制約から、いかんせん表現力に乏しいと感じてしまう。
私はNFTアートがブームか、投機対象としてどう評価できるかには関心がない。
ただ、それがどうなっていくのか、既存の美術界や美術家はどう捉えていくのか。
それだけに興味がある。
庄野祐輔ら『THE NEW CREATOR ECONOMY』
本書もNFTアートについての寄稿集である。
2022年末に刊行された本なので、上記の美術手帖の特集よりは後出しだ。
内容としては、美術手帖の特集よりも幅広く、NFTアートに関わる人々が様々なテーマを論じている。
それらの多くは2024年においても議論に耐えうる内容であるから、興味があればぜひ一読をおすすめする。
余談だが、私は昨年にNFTマーケットプレイスを運営するAdam byGMOがスポンサードするTBS系のラジオ番組にゲスト出演させていただいた。
また、昨年は副業でNFTプラットフォームに関する案件にスポット参画するなど、個人的にNFTをやや身近に感じる一年となった。
NFTコンテンツとは、簡単に言えば電子データながら代替(複製)不可能なコンテンツであり、ユニークであることが技術によって保証されている。
現実世界であれば、私が所有している『ドラゴンボール1巻』と、友人が所有する同書は内容こそ同じであれ、物理的にユニークであり、それらは客観的に識別可能だ。また、現実のリソース(紙やインク、印刷機械など)を利用して複製されている以上、無限に複製されることはありえない。
他方、電子データは無限に複製可能であり、手元に「モノ」として残らない。
この電子データに、現実の「モノ」的価値を付与できないか、というビジネスをNFTによって実現せんとするプレイヤーが存在する。
私も昨年、この点について浅学ながら色々考えたが、「それ(がヒットするビジネスに結実するの)は難しそうだなぁ」という結論を出なかった。
電子データは電子データである。
それがブロックチェーンによって、その所有権や一意性を保証されているとしても、そこに手触りや量感はない。
そして、この手触りや量感というもの、そして「物理的」であるがゆえの生産・流通・購買に私たちが触れる「古典的で素朴、非効率的な体験」そのものが、この電子的な時代においても、実は依然として固有の価値を生み出し続けているのではないか。
このような見解は保守的で古色蒼然として聞こえるかもしれないが、私はNFTを否定しているわけではない。
ただ、NFTによって既存の電子コンテンツに「現実のようなモノ感」を付与できるのでは、という期待感は無理筋ではないか、と感じているのである。
この素朴な感性を裏切り、キャズムを越えていく新しいNFTコンテンツや市場が今後生まれるのか、私は見に回ろうと思う。
鈴木敏夫・押井守『されどわれらが日々』
ジブリのプロデューサー・鈴木敏夫と、映画監督・押井守との対談集。
二人の関係は80年代、両者が30代の頃から始まっている。いわゆる腐れ縁だ。
ゼロ年代から20年近く、両者はさまざまな場所で対談を行い、だいたい同じような話題、掛け合いを再演している。
鈴木が記憶を捏造し、押井が呆れながらツッコむ。「もうええわ! ありがとうございましたー」という幕引きが聞こえてきそうな応酬だ。
ビジネスマンの鈴木と、クリエイター然とした押井とはいかにも水と油という感じだが、両者は映画好きという点で、その得難い関係を維持しているようだ。
鈴木も押井も映画についての著作を持ち、それぞれ造詣が深い。日本を背負う映画人同士のリラックスした対話を楽しめる一冊だ。
『ガルム・ウォーズ』の日本語版コピーを担当した虚淵玄との鼎談も楽しい。
鈴木敏夫ら『スタジオジブリ物語』
こちらは鈴木敏夫責任編集、とあるように、鈴木による執筆ではなく彼が監修した一冊。
ジブリの成り立ちや、それに関わった監督をはじめとするスタッフ、歴史を彩る作品群について明るくない人は、この本からはじめてみるのが良いかも知れない。
東浩紀『ウクライナと新しい戦時下』
『ゲンロン16』所収の、東と上田洋子とが2023年末に取材を刊行した、戦時下のウクライナ取材レポートを切り出した電子版である。
2024年現在、世界情勢不安の象徴は東欧からイスラエル・ガザへ推移しつつあるように思えるが、それは報道傾向と私たちの「戦争疲れ」によって共犯的に醸成されるものであり、ウクライナとロシアの戦争は依然として継続している。
ウクライナを訪れた東は、戦時下のウクライナ・キーウの市民たちが、彼らの平時的日常を継続しているように見えることに驚く。
私たち現代の(戦争を経験していない)日本国民の多くは、戦時下といえば太平洋戦争末期の「欲しがりません勝つまでは」に象徴されるような、悲壮一辺倒で困窮した世相を想像するのではないか。
キーウでは戦争と平和とがその境界を曖昧にして混濁している。そこでは、都市機能が戦前のように維持されており、戦争を「ネタ」化したグッズが販売される点は現代的だ。
とはいえ、プロパガンダを目的とした国民に対する意図的な歴史認識のミスリードや、アーティストの戦争加担といったお定まりの「現実」の前で、東たちは悩み、考える。
ぼくはウクライナの問題が、もっと直接にぼくたちの問題だと考える。なぜならば、かの国でいま展開しているのは、欧米的でリベラルな価値観があるていど浸透し、ネットもスマホも普及した民主的な社会が「有事」にどのように反応するかという、たいへん残酷な社会実験だといえるからだ。
東は戦時下のウクライナ社会の中に、日本ないし欧米的価値観下にある現代的社会一般に通じるものを見出す。
キーウと東京とは8000km以上離れているそうだが、両者はその地理的乖離と比較にならないほどに近しいのだ。
斎藤環『承認をめぐる病』
『おたく神経サナトリウム』に引き続き、ひさびさに斎藤の著書を読んだ。
本書は斎藤が各誌に寄稿した文章の集成であり、表題にある『承認』を全的に扱った著作でない点には注意したい。
2章に大別された本書は、前半が思春期の若者と著者の専門である「社会的ひきこもり」をめぐる論考集。
後半では著者が現状の精神医学、その研究や臨床に対しての疑義や意見を述べていく。
掲載誌は、日本評論社から定期刊行されている専門誌『こころの科学』や学会誌が多く、内容も一般向けというよりはややプレイヤー向けの趣がある。
斎藤の著書には、ひきこもりに関心のある大衆やひきこもりの子供を抱える家庭向けのものも多いので、それらよりは少々専門的と言えるかもしれない。
アクセル・ホネットに代表されるような社会哲学的承認論をめぐる本ではないので、その点は注意すること。
井上俊之『井上俊之の作画遊蕩』
現在も第一線で活躍する有名アニメーター・井上が、やはり著名な重鎮アニメーターや新進気鋭の若手と対談を重ねていく。
井上はアニメーション制作において「レイアウト作業」と呼ばれる作業が、歴史や現場によって異なる作業メソッドを渾然一体に指してきたという事実を整理し、次いで現在もっとも各現場で一般的となっている「レイアウトラフ原制」が現代の現場では既に機能不全に陥っていると指摘する。
つまり、本書はアニメーター同士による気ままな対談集ではなく、井上が目的意識と仮説をもって、確かな力量を持ったシニア・若手それぞれのプレイヤーにヒアリングを行った記録である。
私は井上と面識こそないが、彼の周囲で働くマネージャー(アニメーションの現場では「制作進行」と呼ばれる)たちが、「技量はもちろん、人間としても大変尊敬できる人」と一様に評していたことを覚えている。
自身の身の回りのみならず、業界全体のカイゼンを検討し訴える姿勢を率先して見せる、井上の大きい背中のような一冊だ。
石ノ森章太郎『章読 トキワ荘の青春』
石ノ森の実姉は、石ノ森が二十歳の春急逝した。
喘息の持病を抱えながら、かけだし漫画家として心身を酷使する弟を気遣っての同居生活であった。
本書は、石ノ森が備忘録として若かりし頃の思い出を書き記した回顧録である。
トキワ荘関係者の多くは何らかの形で回顧録を残しているが、石ノ森もまた彼の思い出を1冊にまとめた。本書が特別なのは、やはり看取れなかった姉の死が全体を覆っている点であろうか。
漫画、そして姉を失った自責の念から逃げるように石ノ森は国外へ外遊するが、もはや彼の逃げ場はどこにもなく、帰国後に名作『サイボーグ009』の連載に着手する。
トキワ荘に縁のある漫画家の回顧録を読むと、誰も彼も、将来の不安を押し殺しながら眼の前の仕事に忙殺されていたことがうかがえる。
大成した漫画家たちの梁山泊と目され、神話的に語られてきたトキワ荘であるが、そこにはありふれた若者一人一人の現実的な汗と涙がにじんでいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
