
UCS行動指針の基盤「当事者意識」とは(その①)――常に全体最適を意識し、自分自身の役割を組織戦略に接合すること
※必要最小限の時間で撮影しました。撮影の時のみマスクを外しております。
Ubieのスケールとグロースに特化した組織であるUbie Customer Science(以下UCS)は、医療機関(病院・クリニック)のパートナーとして、安心や安全、業務効率化といった価値を提供しています。
UCSメンバーは医療機関に向けてAI問診ユビーを始めとするソリューションの価値を届けるため、日々顧客満足度を高めることや、顧客価値を最大化することに努めています。
そんなUCSの行動指針やカルチャーの基盤となっているのが、4つの人材要件(誠実さ、GRIT、当事者意識、ラーニングプロフェッショナル)です。それぞれの要件が指し示す方向性や目指す姿を伝える本記事は、「当事者意識」がテーマです。UCSのテクニカルアカウントマネージャーを務める樽谷(写真下から2段目の一番右)が、UCSにおける当事者意識の重要性や、込められた願いについて語ります。
※人材要件をどう設計したか、については「リスク回避をベースに設計した人材要件が圧倒的なオペレーションの最適化につながった話」をご参照ください。
当事者意識とは「全社のビジョン・ミッションにコミットして”主体的に”事業を成功させるという意識を持って言動すること」
――樽谷さんのポジションと仕事内容を教えてください。
樽谷「私はUCSのテクニカルセールスチームのマネージャー(役職名:テクニカルアカウントマネージャー)を担当しています。顧客に安全なクラウドへの接続方法を提案し、AI問診ユビー利用のためのシステム環境を整えてもらうことが、私の主な仕事です」
――UCSにおける「当事者意識」とはどんな要件なのでしょうか。
樽谷「言葉のとおり『当事者であることを意識して言動できること』。もっと端的に言うと『経営者の意識』です。実際に経営の舵を取るわけではないですが、全社のビジョン、ミッションにコミットして”主体的に”事業を成功させるという意識を持って言動することが求められます。
UCSでは組織戦略に対して自身の役割がどう接合されているかを理解したうえで目標を設定し、業務を遂行していくことがベースになります。
当事者意識を強く持つ人は、自部署の課題はもちろん、部署外に及ぶ課題にも気づき、戦略にアラインしながら自らの役割を通じて改善に向け自発的に動くことができます」
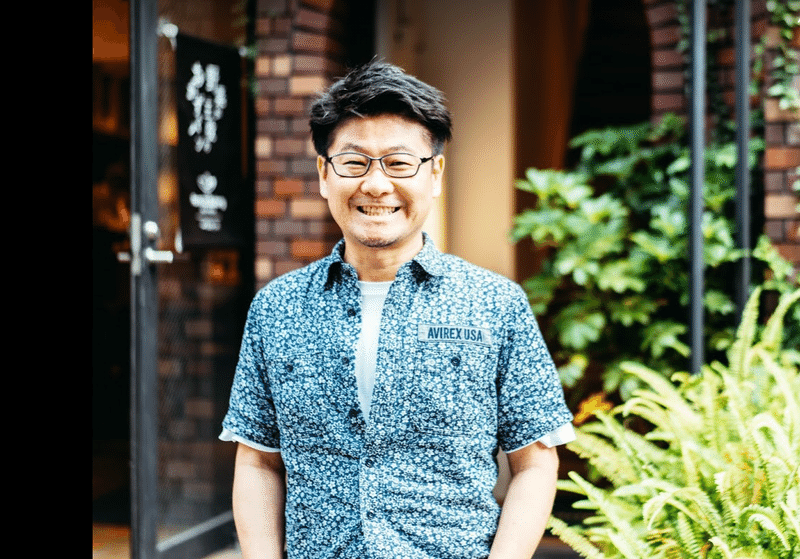
常に全体最適を意識すること
――当事者意識はどんな言動に繋がるのでしょうか。まずは樽谷さん個人の具体的なエピソードを教えてください。
樽谷「医療機関とクラウドを繋ぐための手段として、NTTグループ各社様(以下、NTT様)とのパートナーシップを構築しました。各社とどのような関係を築くか、という点は私に任されていました。
回線代理店のように契約に応じてフィーをいただくことも一般的には考えられますし、社内からそのようにしたらどうかという声も挙がりましたが、そうしませんでした。
発注元=Ubie、回線事業者の1つ=NTTという関係に終始しては両社の発展に繋がらないと考えたからです。
『医療を支える志を共にするビジネスパートナー』という関係性を構築することがUbie・NTT様双方にとってwin-winであり、安定的に医療機関様に良質なサービスを提供+運用することができると考えたからです。
何度もミーティングをする中でUbieの要望を伝えることはもちろん「NTT様にとってどんなメリットがありますか?」と常に確認してきました。
結果的に、現在はNTT様と地域医療連携の取り組みを共に検討させていただいたり、大学病院をご紹介いただけたりと意義のあるパートナーシップを強めています」
※参考:NTT東日本のソリューション事例にもUbieが紹介されています。
――他に特徴的なエピソードはありますか?
樽谷「UCS発足後すぐに、医療機関向けの『導入支援Webサイト』を作りました。サービス紹介資料のほか、ネットワークや機器に関する資料、Q&A、動画を格納したサイトです。
社内では『(セキュリティレベルが高い)医療機関へ資料をメール添付で送るとフィルタリングされ受信してもらえない』『検討段階で閲覧して欲しい資料や動画が多岐に渡るが、メールでは情報量が多くて伝えきれない』などの問題が生じていました。
当時、資金調達を計画しており、多くの商談を成立させることが事業戦略上の重要目標でした。しかしセールスメンバーは数人しかおらず、生産性を最大化しなければ目標には到達しない状況でした。
医療機関はクラウドサービスに馴染みがないうえ、AI問診は今まで存在しなかったプロダクトですので、Ubieが提供できる価値を伝えるのは困難な仕事でした。
加えてネットワークの責任分界点、セキュリティの強固さなどに加え、将来のビジョンまで伝えなければ商談は前に進みません。リードタイム遅延は計画未達に直結するリスク要因でした。『十分な情報を確実に届けること』は、組織として重要な課題だったのです。
そこで『導入を検討するうえで必要な資料はすべてここにあり、すべて自由にダウンロードできます』と支援Webサイトを案内できれば、コミュニケーションコストを低減し、課題解決に繋がると考え、当時のセールスチームに提案。即決で作成に至りました」
――Webサイトを作ることも樽谷さんの担当領域なのですか?
樽谷「サイト作成は私のロール(役割)ではないです。コストパフォーマンスや運用の利便性を踏まえて私が作成することが最適と判断しましたが、誰がやるかは重要ではないです。担当領域に固執せず、組織全体としてどうすれば課題をクリアできるか、生産性を高めることができるか、を考えてアクションをとることが重要です」
――自分自身の役割を組織戦略に接合することが重要なのですね。
樽谷「そうです。自身の仕事が組織全体や顧客への価値貢献にどう繋がってどう影響を及ぼすのか?を意識して大きなリターンが得られるように業務を進めることが重要です。
全体を見ず自身の領域内で役割をこなすだけでは、戦略との接合が明確でなくなり、課題の重要度やリターンの大小も曖昧に捉えたまま仕事をすることになります。頑張ってたくさん仕事をしても組織が求める成果が出ないので、個人はもちろん組織の生産性も落ち、顧客への価値提供を最大化することができなくなります」
――多くの会社では機能ごと役割が決められているので自身の部署だけに意識が向いてしまいます。常に組織全体をみて当事者意識を発揮するには、どうすればよいのでしょう?
樽谷「UCSでは現在、事業セグメントを病院向けとクリニック向けに分けています。
そのうえで部署はマーケティング~インサイドセールス(IS)~フィールドセールス(FS)~カスタマーサクセス(CS)に分かれています。
各部署で目標も役割も異なりますが、UCSでは『各部署の業務がどう繋がって顧客への価値を最大化できるのか』をループ図にして可視化しています。
このループ図において『全ては繋がっていて互いに深く関連している』ことを全員が理解しています。他部署で起きていることは、自部署に影響が出ることを分かっているのです。
そのうえで毎週の事業報告会では、各部署の事業進捗状況や課題について報告しあっています。
こうして当事者意識を発揮できる土台を作ってきました。組織戦略だけでなく、各部署の繋がりを理解することでおのずと互いに関心を持ち、各々が全体の生産性向上、課題解決に寄与できる組織づくりをしています」
――当事者意識を阻害してしまう要因として、どんなことが挙げられますか?
樽谷「各部署の役割分岐点は事業成長によって変化する可能性があります。そのため現時点の役割分担の切れ目はさほど重要ではありません。重要なことは『全てが繋がっていることを深く理解すること』です。
この理解がないと、自部署の役割や機能を孤立化させ、他との接合を意識せずに業務を遂行していく、という個別最適の要因になり、当事者意識も薄れてしまうリスクがあります。
お互いが繋がっていることを理解していれば、例えばCSはFSの立場に立ち、どんな情報を還元すれば商談成約率に貢献できるのか?という課題感を持つことができます。逆にFSはCSがスムーズな運用開始を実現するために契約締結時に顧客とどんなコミュニケーションをとっておくべきかを意識して改善を図ることができます」
組織戦略に対して部署や自身の役割がどう接合されているかを理解し行動、改善を行う当事者意識。後編 「UCS行動指針の基盤「当事者意識」とは(その②)」では「当事者意識を支えるカルチャー作り」について語ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
