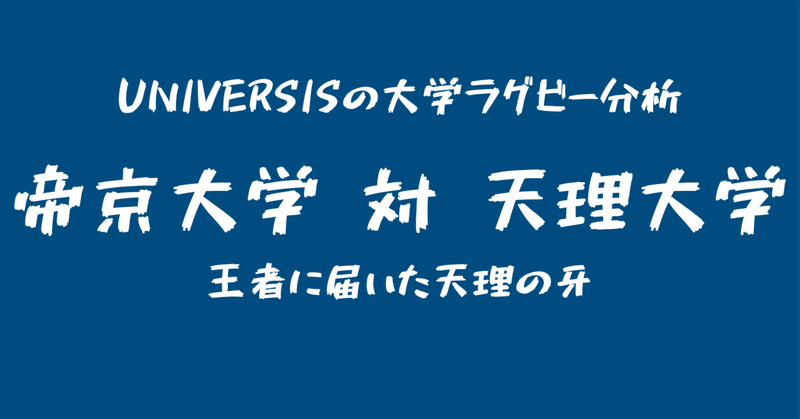
2023大学選手権準決勝:帝京対天理を簡単な数字で見てみた
みなさんこんにちは
健やかにお過ごしでしょうか
今回は1/2に行われた大学選手権準決勝、帝京大学対天理大学の試合についてレビューをしていこうと思います
まずはメンバー表から

次にスタッツです

それでは順番に見ていきましょう
帝京のアタック・ディフェンス
帝京のアタックシステム
帝京のアタックの魅力はどの選手も前に出ることのできる決して下がることのない強さに、状況に応じて適切な判断を下すことのできるしなやかさを兼ね備えた万能性にあると考えています
それぞれの選手が各ポジション・各選手に求められている最低限の仕事と特化した仕事を漏れなくこなしている感じですね
しかし、今回の試合では少しギアが全体的にかかっていないというか、見ていて不安になる程「これが本気なのかがわからない不気味さ」というものを感じました
基本的なスタンスは1−3−2−2に近い、中央付近を手堅く配置しながらも青木選手や奥井選手のような強くて走れる選手を外に配置する攻撃的なスタイルになっているかと思います
主に立ち位置を見るとフロントローの選手が中央寄り、LOの選手と延原選手は10シェイプなど、青木選手と奥井選手を外寄りに配置するような形ですね
どの選手もきっちりと自分の役割を果たす勤勉さがありますが、その中で江良選手と青木選手、奥井選手に関しては少し精神的な立ち位置が違っているように思います
SOとまではいきませんがフィールド全体を見通すことのできる広い視野と苦しい場面を打開できるスキルを兼ね備えているように見えるので、イメージ的には3選手が様々な位置に顔を出しながら試合全体をコントロールしているように感じています
ただ、先述したように今回の試合では少し普段の試合と様相が異なっているというか、良く言えば余力を残しながら、言い方を変えれば様子を見ながらラグビーをしていたように見えました
戦略的な様相は大きく違ってはいなかったと思いますが、全体的なモーメンタム、勢いに関しては天理の勢いもあって少し抑えめだったような印象です
代表的なシーンでいくとキックオフを受けた後の数フェイズで、秋シーズンの公式戦ではキックオフを受けた選手がラックを作った後は少し意識的に外に動かしていたようなイメージですが、最近の試合では早い段階でエリア獲得に動いていたように見えます
大学選手権という状況がそうさせているのかは分かりませんが、これ以外にも全体的に安定感をもたらすような盤上の駒の動かし方をしていたような印象です
どちらがいいとは言えませんが、個人的には印象的な要素でした
一方で天理のディフェンスのインパクトに押されていたという様子もあったかと思います
関西勢という意味では準々決勝で既に関西学院大と当たっていますが、天理は関西を代表するにふさわしい強度でタックルで体を当てこんでくるので、帝京としても容易に前に出ることはできないという状況に陥っていました
その中で試合を動かすのに役立っていたものの例として9番の李選手のボックスキックが挙げられると思います
他チームと比べるとBoxで高いボールをあげる機会は比較的多く、ハイボールの中でも李選手のボックスキックが占める割合は大きかったです
もちろんこれくらいのレベルになるとSHの選手に求められるキックスキルは非常に高くなってくるのですが、李選手も帝京を代表するに相応しいキックスキルの高さを誇り、特にボックスキックにおいて長短・高低の使い分けはゲームを動かしていたと感じました
ラックのテンポに言及すると早く出したいタイミングとコントロールするタイミングが絶妙であるように思いました
個人的にはラックからの球出しはただ早ければいいわけではなく適切なタイミングがあると思っているので、その点では帝京は非常に高いクオリティでゲームのテンポをコントロールしていたと言えます
帝京のキャリー
アタックシステムの項目でも述べましたが、今回の試合での提供のキャリーは天理に少し押し込まれていたように思います
物理的にグッと押し下げられていたわけではないのですが、「本来前に出られる場面で前に出られない」「抜けるはずのところで抜ききれない」など、おそらくはイメージとのギャップが生まれていたように見え、若干攻めあぐねている様子もあったように感じました
ただ、キャリー自体は強烈ですね
フロントローの中でも津村選手・上杉選手はキャリーが安定していてアタックの勢いをスムーズに流していて、尹選手と本橋選手は砕氷船のように相手ディフェンスを突き破るようなキャリーを見せていました
そういった選手が揃っている中でも特別なのが青木選手で、シンプルに1人で局面を打開できるのでバケモノです
青木選手に注目してみると、姿勢が特別うまいというわけではないのですが当たり負けしない強さがあり、勝手な印象ですが単純な体の強さに関しては既に十分リーグワンで戦えるレベルにあるのではないかと思っています
キャリアーとしては2トライを記録した高本選手も強かったですね
長い手足を活かしたしなやかなランニングも魅力ですが、高めの重心のランニングポジションから重心を下げてコンタクトするまでのフローが非常にスムーズで、追い縋るようにタックルしてくる相手選手をうまくいなすシーンも見られていました
キャリーを回数で見ていきましょう
試合全体で前半44回・後半36回、全体で80回のキャリーが生まれています
天理が97回のキャリーとなっているので約2割減のキャリー数となっていますね
あまり外まで振り続けるようなアタックはしていなかったと思うので、おそらくはポゼッションの比率も似たようなものではないかと思っています
FWのユニットを使ったキャリーでは9シェイプで28回、10シェイプで10回のキャリーを使っています
傾向的には普段のアタックの形と似ていますね
井上選手がうまくボールを散らしながらアタックをうまく取りまとめていたと思います
シェイプ外のキャリーとしては中央エリアで5回、エッジエリアで11回のキャリーが生まれています
普段の帝京の様子と比べると、シェイプ外のキャリー全体が少し少なめな印象でしょうか
もちろん試合全体でのキャリー数が少なくなっているということも影響しているとは思いますが、全体の雰囲気的には安定感を持たせるためにパス回数が増えることになるシェイプ外のキャリーを減らしているような印象も受けました
帝京のパス
帝京のパスは正直な感想を言うと「至ってシンプル」で、選手が一度に多く走り込んできて複数のパスオプションを準備したり、複雑な動きとパスワークで相手を翻弄したりといった形のラグビーをするわけではないと思っています
オプションが全くないわけではないですが、策を浪するようなチームオプションの多さと比べるとかなりシステマチックでシンプルな動きをしているように見えます
今回の試合ではパス回数も比較的抑えめで、チャンスが見えていないシーンでは細かく、チャンスができたと見るやいなや素早く大きく外に展開したりと、「正統派のアタック」をしている形ですね
サポートの選手のコースもいいのでオフロードパスがチャンスになる場面も多く、効果の薄いパスはそこまで多い数となっていない印象です
帝京のラグビーのミソになってくる部分としては「9シェイプの先頭に位置する選手の働き」にあるように感じています
当然ラックからの1stレシーバーになる回数が多い位置ではありますが、ここに位置する選手は単にキャリーで前に出ることが求められるだけではなく必要に応じてボールを後ろや横に散らす働きが求められる位置でもあります
個人的な感覚としてこの位置関係でのプレーが大学レベルで最も上手いのは早稲田大学の佐藤健次選手だと感じているのですが、帝京の江良選手も同等のクオリティのプレーを見せており、ポッド内のパスやバックドアと呼ばれる後ろのラインへのボールの供給を姿勢を大きく変えることなく行うことのできる器用さを持っています
パスをしたことに伴うサポートコースへの動きも素晴らしく、余計なランニングをしないところも高評価ですね
また、今回の試合では目立ってはいませんでしたがLOの本橋選手もこの辺りのプレーが上手い選手ですね
前に出ると言う働きでも随一のものを見せる選手ですが、手先も器用なので姿勢を大きく変えずに後ろに放るスキルは非常に高いものがあると思っています
パス回数を見ていきましょう
試合全体でパス回数は前半56回・後半64回の合計120回となっています
キャリー・パス比としてはちょうど2:3となっているので、正統派のラグビーをしていると言うことが数値からも見て取れるかと思います
普段から2:3を大はずしすることもないので、この辺りが一般的な帝京のラグビー様相であると言うことができるでしょう
ラックからのボールは34回が9シェイプへ、17回がバックスラインへ渡っています
バックドアへのパスワークも6回見られているので一概には言えないのですが、傾向的にはかなりFWの働きに賭けた展開ではないかと見ています
主に9シェイプで用いられるポッド内のパスも7回見られていることから、大きくボールを動かして数的優位を狙うと言うよりは細かいズレを生み出して位置的な優位性を取ろうとしていたと言うことができるかもしれません
バックスラインへ回ったボールは12回が10シェイプへ、14回がバックスライン上でのパスワークとなっています
シチュエーションによってはOtherにバックスライン内のボールの動きが含まれることもありますが、Otherの回数を鑑みると傾向的にもそこまでバックスライン上でボールが大きく動くシーンは少なかったのではないかと思います
数値を見ると10シェイプは前半3回で後半が9回となっており、パス全体の増加率よりも10シェイプの増加率のほうが大きいと言うことが言えます
このことから、意図的か偶然かはわかりませんが、キャリーをするエリアが後半にかけて少し外方向に広がったと言うことができるかもしれません
イメージを膨らませるとしたらラックの近くでキャリーしていた前半の展開を見て「後半は少し動かしてエリアを変えよう」となったのでしょうか
帝京のディフェンス
あくまでも個人的な印象ですが、今回の帝京のディフェンスにはそこまで「必死さ」というような様子が見られなかったと思っています
「ひたむきさ」とはちょっと違うのですが、「全力感」とも言い換えられるような「必死に体を当てて相手を止めようとする」様子はそこまでなく、どこか余力を残しながら相手のコンタクト強度に合わせているような、そんな印象を受けました
もちろん相手を甘く見ているというわけではないと思いますし、実際帝京の堅いディフェンスをこじ開けることのできる選手も限られていてラインブレイクもほとんど起きていませんでした
激しさのレベルがもう一段階上にありそうな感じに見ています
ただ、正直なところタックルの強度単体で見ると全体的に精度を欠いていたようにも見えました
もちろん肩をちゃんと当てていましたし、教科書的なタックルも随所に見られていましたが、少しムラがあるようにも見受けられ、グリップがイマイチ効いていないようなタックルもあったように思います
一方で「一般的な上位校レベルの激しさ」は間違いなく見せており、ディフェンスラインも大崩れすることはなかったと思います
極端に前に出るようなことはなく、幅感も揃っていてしっかり前に出ることができているように見えました
天理のアタック・ディフェンス
天理のアタックシステム
今回の天理のアタックでは特にFWの選手の検討が光ったように見えました
BKの選手も鋭いランニングや献身的な動きで天理のアタックに貢献していましたが、今回のような「帝京に一方的に押し切られない試合」になったのはFW同士の格闘戦で後手に回らなかったのが大きかったと思います
天理のアタックは9シェイプ周辺の選手の立ち位置や人数が柔軟に変わるような形を見せていて、特に9シェイプの端に立つ選手の部分で可変性があったように見えました
最初は9シェイプに4人立って、SHが2人目と3人目に投げ分けた上で外の選手はラックに入るか次のアタックに備えるかを判断するといった感じですね
また、時に10シェイプに4人立っている時もあったので、どちらかというとFWの選手の大まかなレーンを規定してその間をBKの選手が動いて埋めるようなスタイルだったかもしれません
9番の北條選手も10番の筒口選手も攻撃的で動きの多彩な選手なので、中央エリアは人数のバリエーションが豊かなアタックをしていたように見えました
ポッドを用いたアタックで重要な役割を果たしていたのが12番のハビリ選手ですね
ハビリ選手は多くのキャリーで9シェイプの中央に立っており、突破役となってアタックに参加する機会が多かったように見えました
そのためFW9人体制でアタックをしていたようなものなので、FWの選手を比較的ちらしやすかったというのもあるかと思います
ハビリ選手は当然のことながらBKの選手なのでパスも得意としており、天理の2トライ目にも繋がった一連のパスワークでは自分に相手を引き寄せてのパスなど多彩な活躍を見せていましたね
自身のキャリーが天理の選手の中でも随一なので帝京のディフェンスも意識を外すことができないため、うまく自分を囮に使っていたと思います
それ以外にも献身的にボールキャリーをする選手が揃っているためゲインラインの戦いの部分で帝京に押し切られることなく試合を繋げていくことができており、ある程度自分たちの思うような流れでゲームを運ぶことができていたのではないでしょうか
あとは個人的な願望ですが、15番の上ノ坊選手が疾走する場面をもう少し見てみたかったような気もします
上ノ坊選手はしなやかなランニングと思い切りのいいアタック参加が売りの選手で、自分のイチオシの選手でもあります
ただ、今回のような局地戦の連続になるような場面ではあまりボールキャリーが目立たなかったので、今後の活躍に期待です
天理のキャリー
天理のキャリーを語る上で外せないのはNO8のヴァカタ選手のキャリーでしょう
サイズも大きく走力のある選手なので帝京のタックルを容易に弾いており、前に出て勢いをもたらすという意味では大学レベルでは随一ではないかと思っています
システム的には9シェイプの先頭であったりボックスと呼ばれるラック後方のエリアでボールを待つことの多い選手ですが、今回の試合ではキックレシーブからのランは強烈なものがありましたね
そもそも少し勢いをつけた状態でボールを受けることの多いシチュエーションですが、徐々に加速するようなランニングをしているにもかかわらず疾走状態からコンタクト姿勢への移行がスムーズで、弾いたところからさらに走り出すまでのタイムが短いため一度ついた勢いを抑えるのが非常に困難になっています
本来であればスピードに乗る前にタックルに入ったり体を当てて勢いを殺したところに次のディフェンスが入ることで抑え込む形が多いですが、ヴァカタ選手は勢いが止まらないので帝京の選手を連続で弾いて走り続けるシーンが印象に残っています
似たタイプの選手では東海のオフィナ選手、流経のロケティ選手、京産のポルテレ選手などが挙げられるかと思いますが、彼らはコンタクトをした後の加速がうまくいかないシーンも多いため、ヴァカタ選手の唯一無二のキャリーが目立っていますね
また、両LOも堅実にしっかりと前に出ることができるキャリーをしていましたね
特に5番の岡崎選手は相手ディフェンスラインを置き去りにするシーンこそ少ないものの自身のコンタクトで確実に前に出ることができ、相手のタックルを弱いポジションで受けることがないために楽にも安定感をもたらしていました
キャリーの回数を見ると、試合全体で97回のキャリーが生まれています
これは帝京の3割増しくらいの値になるので、結果的には天理の方がより多くボールを持っていたということができるかと思います
これまでの多くの試合では帝京がポゼッション的にも圧倒してキャリー数の多さからトライを量産していた様相もあったと思うので、この辺りでうまく立ち回ることができたのも比較的スコア差を抑えることができたことにも繋がっているかもしれませんね
9シェイプのキャリーが40回で10シェイプでのキャリーが7回と、傾向的には圧倒的に9シェイプが多く用いられていることがわかります
FWの強烈さを武器にしていることもあると思いますが、安易に外に振ることでプレッシャーを受けるのを嫌がっていたのかもしれないですね
経由するパスを減らすことでミスを減らすこともできますし、パスを経由して下げる必要がないために比較的にフラットにアタックすることができるのも要因としては考えられます
シェイプ外のキャリーでは中央エリアが21回でエッジエリアが8回と、回数的には中央寄りのアタックをしているということができるかと思います
弘田選手や藤原選手といった外で勝負できるランナーを揃えてはいますが、両選手も積極的に逆サイドに行ったりと少し流動的に中央に寄っているようにも見えました
Otherに分類されるようなキャリーもそこまで多くはなく、ある程度は意識したアタックができていたのではないでしょうか
天理のパス
こちらも帝京と同様に凝ったパスは少なく、シンプルに一定の角度でパスを放ってアタックの勢いに一貫性をもたらしていたように思います
内返しパスのような相手の逆をつくようなパスがほとんどなく、選手の一連の動きに反さないパスワークだったように見えました
パスという観点で見ると北條選手の貢献度は非常に高いと思います
ラック周りの攻撃に関しては北條選手がうまく捌いていましたね
自分である程度持ち出すこともできる選手ですし、鋭いパスと投げ分けるセンスでアタックに勢いをもたらしていました
全体的なテンポもよく、ポンポンと強い選手にボールが渡る様子は見ていて爽快でした
パス距離は全体的にそこまで長くはなく、比較的近い選手同士が細かいパスで繋がることによって微妙なずれを生かすような形になっていたと思います
とはいえポッド内のパスやバックドアへのパスもほとんどなく、文字通りシンプルなパスワークでした
パス回数を見ていくと、試合全体で126回と回数的には帝京と大きな差がない数値となっていました
キャリー・パス比は5:6あたりと若干キャリー優位の比率となっており、この辺りにも天理がFWを中心としたぶつかり合いで勝負を挑んでいたことが見て取れるかと思います
ラックからのボールは36回が9シェイプへ渡っており、バックスラインへ渡った回数は23回となっています
前後半で回数の比率にそこまで違いはないので、おそらくは前半のゲーム展開を経て自信を得ることができていたのではないかと思います
実際、アタックの流れを見ても十二分以上に戦うことができていましたしね
バックスラインへ渡ったボールは8回が10シェイプに送られ、16回のバックスライン上でのパスワークが生まれています
Otherに含まれるパスも鑑みると、これらの数字からもパスを重ねて外方向へ展開するといった流れではないことがわかります
単純計算ラックから2パス以内でのキャリーが多く生まれているということを示しており、キャリーで中央エリアのものが多かったことからも同様のことが言えると思います
天理のディフェンス
多くのチームが帝京のアタックのモーメンタムに屈し、多くのトライを献上することになっていましたが、今回の試合での天理はディフェンスラインの連携も含めて堅いものを見せており、特にコンタクト・フィジカルバトルの部分で互角に渡り合っていたと思います
関西のチームに多い飛び込むような極めて低いタックルはそこまで多くなく、ある程度姿勢を低くしながらも相手との組みあいに持ち込むような体の使い方をしていたように見えました
バインドをしっかりする、足をかき続けるといった基本的な部分の遂行力も高く、「ひたむきさ」とも取れる必死さが見て取れました
奪われたトライもコンタクト場面で押し負けたというよりは少しの油断やシステムのずれをうまく帝京に利用されたようなものだったので、コンタクト場面では全く負けていなかったと思います
一方外方向のエリアで生まれたコンタクトでは弾かれたりいなされたりすることも多く、結果的にタックル成功率はそこまで高くないという結果にはなっていましたね
中央エリアでの勝負の土俵に立った分、外エリアでは外されることが多くなっていました
中央エリアに選手が多く残っていたシーンも散見されました
まとめ
天理の健闘が光った試合でしたが、「負けないこと」に定評のある帝京が天理のひたむきさを上回ったということもできるかと思います
帝京にはまだ伸び代があるようにも感じられるので、上がり調子の明治とぶつかった結果どのような試合になるかが非常に楽しみになってきました
今回は以上になります
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
