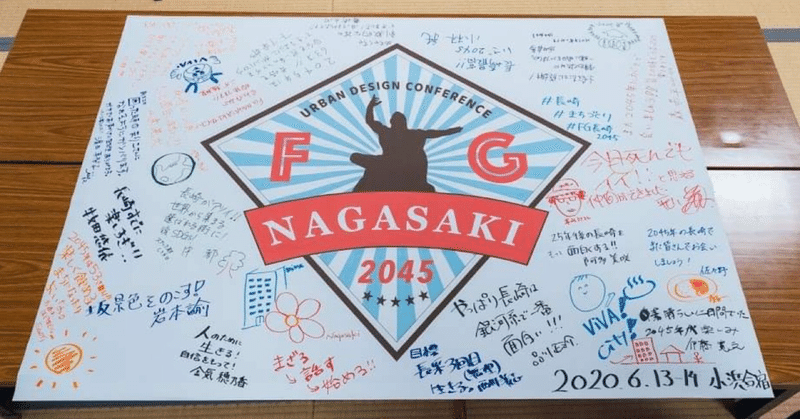
【イベントレポート】2045年のパースペクティブin小浜(2日目)
こんにちは。UNNYAライターのhoNikaです!小浜合宿1日目(レポートは1日目の1、1日目の2)は大いに盛り上がりました。この日もまた濃ゆ~い一日でした!
2日目の行程はこんな感じ。
▼7時~8時 早朝アクティビティ<コーヒー談義>
▼9時~9時半 ゲスト講演
▼9時半~10時55分 まちづくりの基礎となる営み
―まちにおけるコーヒーショップの役割
―生徒の主体性を伸ばす教育
―長崎のイベント
―発表者のディスカッション
▼11時~12時 まとめワークショップ
▼12時 解散

午前7時から始まった早朝アクティビティは、カリオモンズコーヒー伊藤寛之さんによるコーヒー談義。こだわった淹れ方をレクチャーするのではなく、各々が隣の人のために思い思いに淹れていきます。コーヒーの香りが部屋中に広がり、ゆるやかに活動モードになっていきました。

この日のゲスト講演は京都大経済研究者の山東晃大さん=小浜町在住=。これまでの小浜で活動した内容を報告しました。
兵庫県神戸市生まれ。2012年に友人と小浜を訪れたことがきっかけで、まちを気に入り、そのまま小浜に移住しました。
生活に慣れていくと、移住者同士の交流が少ないことに気づいた山東さん。デザイナーの古庄さんが開いたカフェ「景色喫茶室」で、参加者が食材を持ち寄り、カウンターを囲んで語り合うイベント「夜景色」を開催。このことがきっかけで、「小浜の塩」という商品の開発にも至りました。
さらに、地域の人たちが意見を出しやすくする「OBAMAST(オバマストリート)2030」も発足。ワークショップで小浜町の住人のうち約1割の人が集まりました。ここでも新たな事業が生まれそうです。
何かやっていると地域でうわさになり、やりたいことがある人が相談に来てくれています。「まちを変えたい人が集まっても、実現につなげるのは難しい。小さな事でもやってみることが大切」と語りました。
ここからは「まちづくりの基礎となる営み」をテーマにしたセッション。

初めは、カリオモンズコーヒー(西彼時津町、長崎市)の伊藤寛之さんが「まちにおけるコーヒーショップの役割」についての発表がありました。
伊藤さんによると、「コーヒーショップ」の役割は単にコーヒーを提供することに限らず、さまざまな役割・機能があるとしています。例えば▽シチュエーションに根付く空間づくり▽自由度の高い利用方法の提案▽商品を通じた社会情報を伝達すること(環境保全)▽人と人をつなぐ場や情報窓口▽お客さんの相談の聞き役ーなど。文化が発展していくためには、コーヒーショップをはじめとしたさまざまな機能を持つ場がたくさん必要だと説明しました。
2045年までには「『健全なコーヒー』が当たり前に流通する基盤をつくり、コーヒーを『味わいベース』の楽しみ方から『体験ベース』の楽しみ方へ提案する。『カリオモンズコーヒー』が長崎を訪れる一つの理由となるように整えていきたい」と意気込みを語りました。
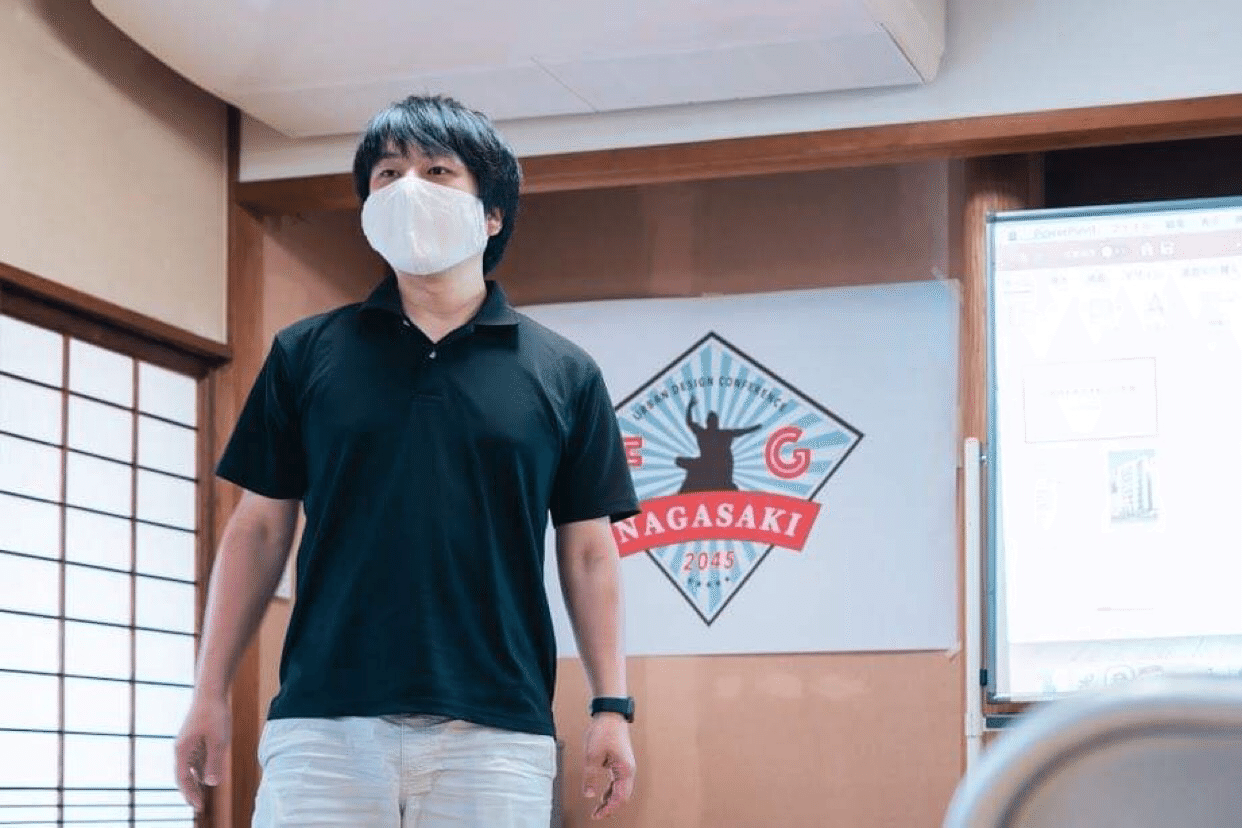
次に「生徒の主体性を伸ばす教育」についてプレゼンしたのは高校教諭、樫本英人さん。生徒が主体的に学習できるプロジェクト「Problem-based Learning(PBL、問題解決型学習)」を説明しました。
樫本さんによると、日本の高校生を対象にした統計では「自分で社会を変えていけると思う」「将来の夢がある」と志がある生徒は少ないという。この統計から浮かび上がってきたのは「どうせ日本、未来は変わらない」という考えに至ってはいないか、ということ。「高校生は受験勉強だけやっている。果たしてこれで良いのだろうか」と疑問が湧きました。
そこで考案したのが、PBL。生徒の主体性を伸ばし、地域と連携しながら「答えのない問い」に取り組むことで、地域課題に対して良い刺激を与えられると考えました。例えば、ドローンレースをしたい生徒が、クラウドファンディングで資金を調達し、地域内外から人を集めたことや、廃業しようとしている農家に6次産業化を提案し、生徒らでピザを制作・販売することを実現しました。
PBLの実践は学校を超えて、地域社会にまで及ぶため「いかに学校が地域のリソースを活用できるかということと、学校を地域に開かれた場所にすることが重要」と話します。地域社会や地域の大人との関係性が深い生徒ほど定住意向が高まる傾向が出ている研究結果もあるそうです。
樫本さんは「ぜひ生徒たちとつながって欲しい」と会場に呼びかけました。

最後は、テイクアウト長崎・長崎宅飲み向上委員会の下川卓郎さんが「長崎はイベントがしやすい」と実体験を述べました。
下川さんはこれまで長崎で、男女500人ずつ集めた大規模な合コンの開催や、ウェブメディア「ながさーち」を設立。近年、拠点をマレーシアに移し、「街コン」や長崎県民同士のネットワークの構築、長崎の物産展を開催してきましたが、新型コロナウイルスの影響で、帰国しました。
「飲食店のために力になりたい」。新型コロナの影響が大きい飲食店を救おうと、テイクアウトができる店をまとめたウェブサイト「長崎テイクアウト」を有志で発足。その後、「おうちがレストランTAKE OUT長崎」に活動を広げていきました。この企画は話題を呼び、長崎市だけでなく長崎県全域でテイクアウトネットワークが拡大。さらに、国民へ10万円が給付されたことを機に「10万円を長崎で使おうキャンペーン」として、長崎県内の消費を促しています。
おくんち、ランタンフェスティバル、精霊流し…。多種多様な祭りで長崎は賑わいます。「長崎は魅力が多く、支援してくれる人も多いためイベントや企画を立ち上げやすい。2045年までイベントの企画をし続け、長崎の新しい伝統をつくりたい」と話しました。

発表者3人に対する質問タイムがありました。
Q 健全なコーヒーのために消費者が気を付けることとは。
(伊藤)たくさんのコーヒー屋と話をしてもらいたいです。本職同士の情報交換も大切ですが、そこを回遊するお客さんから得られる情報も大きな役割を果たします。単純に我々本職の圧倒的な勉強不足もありますが、その学びを共有するハブとしてお客さんが機能しています。プロと消費者が同時に育っていく環境が理想だと思っています。
Q イベントやプロジェクトを始めたいときに何をするのか。下川さんのスピード感の秘訣は。
(下川)基本的に「人が死ぬ以外はいいだろう」というスタンスだけど、リスクはもちろん考えていて、何をやるべきかリストに起こしてできることから始めています。今までの実績から、信頼関係も生まれているので周りの協力を得られるようになったので、想いを発信する時は“素直に伝えること”を大切にしています。スピード感の秘訣は、24時間・人の倍以上働くこと、本業はそのあとに倍以上働く(笑)
Q 教員の異動でPBLの継続はどうなるのか。
(樫本)事業の引継ぎのためには、なぜこれをしているのか共有し、共感してくれる人を増やすことが必要。地域側のアプローチの必要性もある。「学校はこんなこともできる」という気づきにつなげることは大切で、基本的に「できないことはない」。ただ、学校と地域との隔たりの問題性を指摘できる教員はいない。「忙しい」で言い訳ができるので教科以外の学びがない。しかし、この旧態依然のシステムを変えたい、と思う教員はぽつぽついる

全てのセッションが終了した後は、まとめのワークショップがありました。参加者は「まちなか」「斜面地」「観光」「営み」の4つの班に分かれ、2045年の長崎の姿をそれぞれ宣言しました。
「まちなか」 ノービバ、VIVAシティ 何かがあるとつながるまち
VIVAには「バンザイ」の意味があることから皮肉も込めての宣言!長崎で、何かやりたいときに相談できる場所がないのは課題で、まちのことで困ったときに助けを求めることができる場所や窓口が必要。問題意識を常に共有し、「井戸端」をまちなかに増やしていく。
「斜面地」 人が行き交う坂景色
斜面地の良いところをブランディングしていく思いを込めて宣言!長崎の高校は坂の上にあるため、高校生の主体性を活かす場として斜面地を活用したい!また「坂景色」を活かし、インバウンドに応えることもできそう。斜面地にも「井戸端」コミュニティ、アルベルゴディフーゾのような宿泊施設、坂暮らし体験を通したおもてなしなど、可能性はたくさんある。
「観光」つながりでイノベーションを起こし親から子へ継承していく観光
点と点を結びつけて「線」を結ぶための宣言!長崎の観光で稼ぐ人をさらに増やしていきたい。また、歴史や平和学習といった長崎の継承を使命に観光につなげていきたい。マーケティングをしたうえで、交流人口、関係人口、そして定住人口の創出へつなげていく。
「営み」 まざる・話す・始めるを世界中で!
人間の営みの本質はこれからも不変であることをふまえた宣言!「井戸端会議」といった見られなくなった景色も、今は姿を変えて続けられていて、その例としてオンライン会議は挙げられる。さらに長崎が良いまちになるために、何かを始める場として、老若男女混ざって、話を共有する場をつくっていきたい。
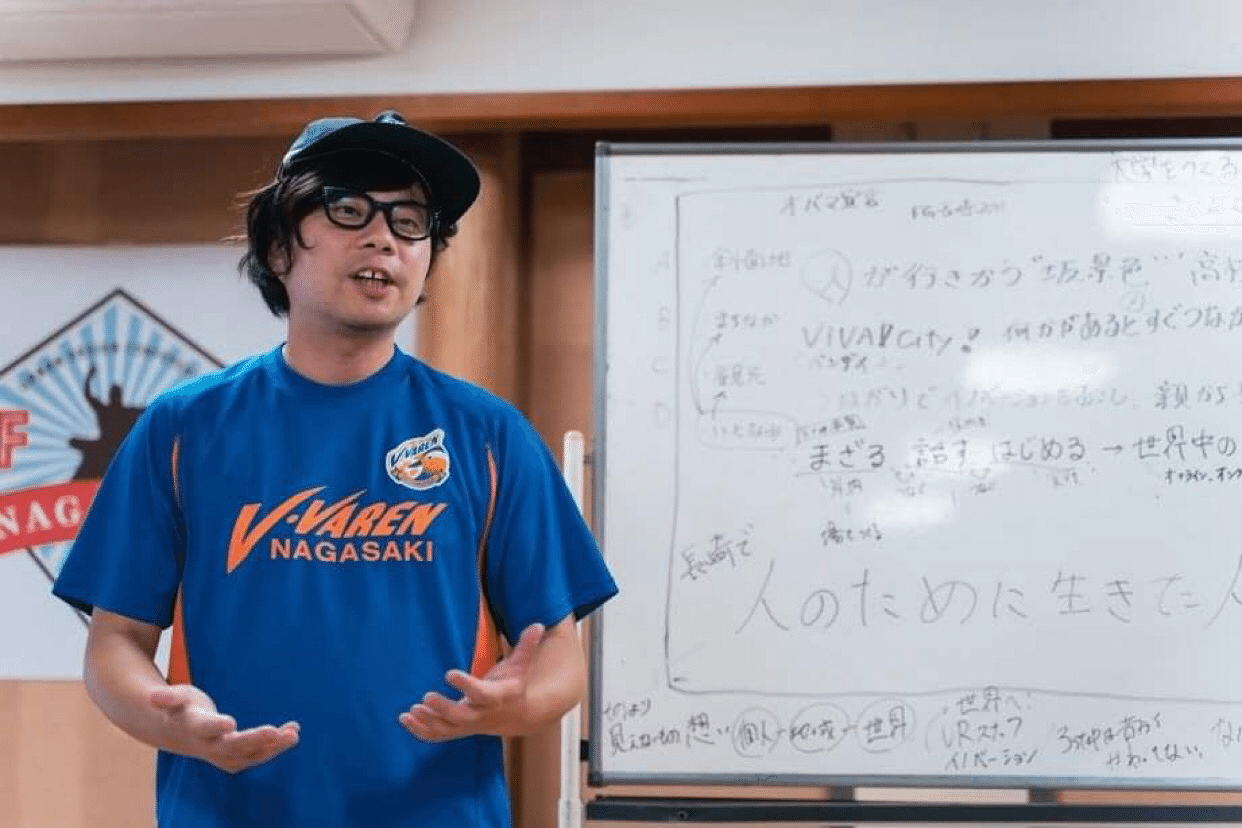
合宿の総括として、ゲスト講師の山東さんが「2045年までに大学をつくりたい。まち(長崎)と田舎(小浜)で良い補完関係なのでお互いに協働したい」、長崎市の平山さんは「この小浜合宿でみんなの想いを共有できた。自分のためでもいいが、長崎で人のために生きよう。『混ざる・話す・始める』を通して次の世代にバトンを渡していこう」とそれぞれ話しました。
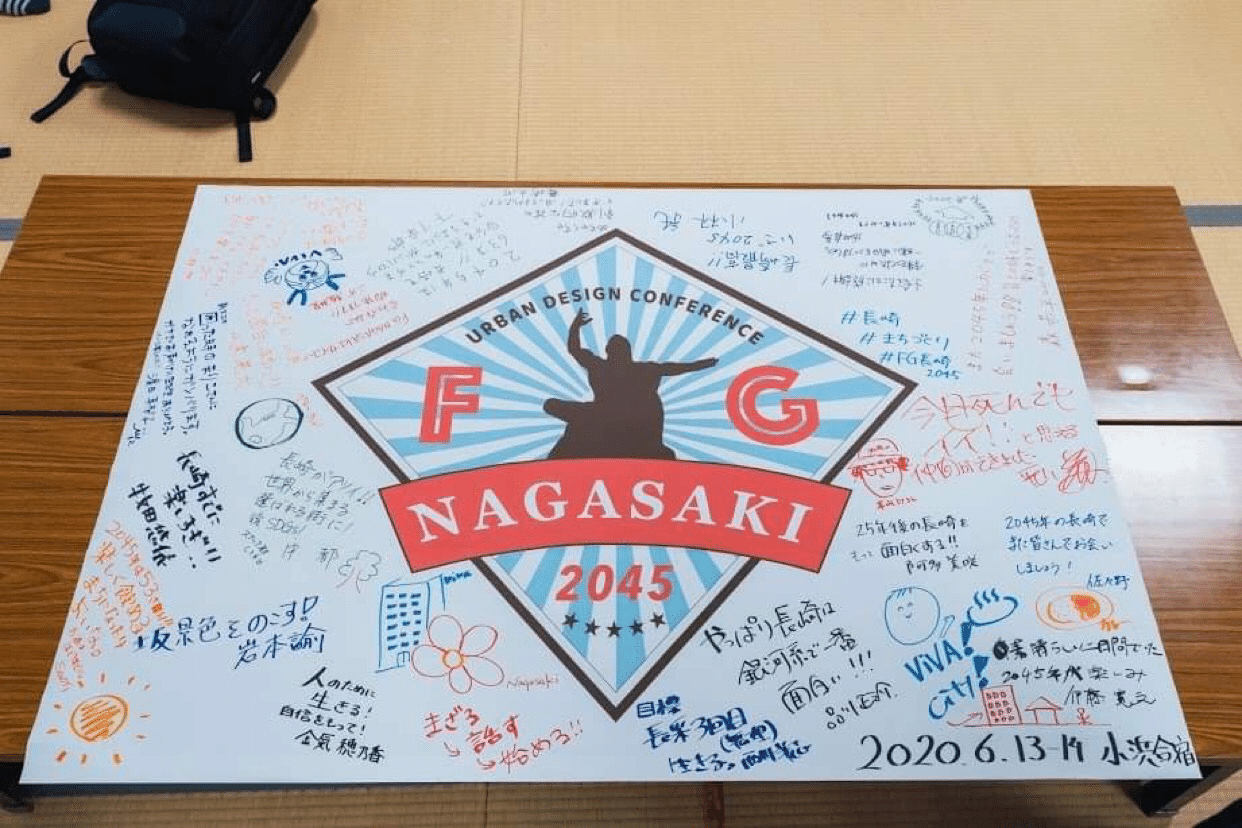
こうして、濃密すぎた小浜合宿は幕を閉じました。起業を宣言する参加者もいて、各々が刺激を受け、2045年にむけて動き出しています。
長崎には面白い人たちがたくさんいます。可能性に満ちた長崎を想像すると、なんだかワクワクしませんか?
=連載おわり=
写真・さおりん
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
