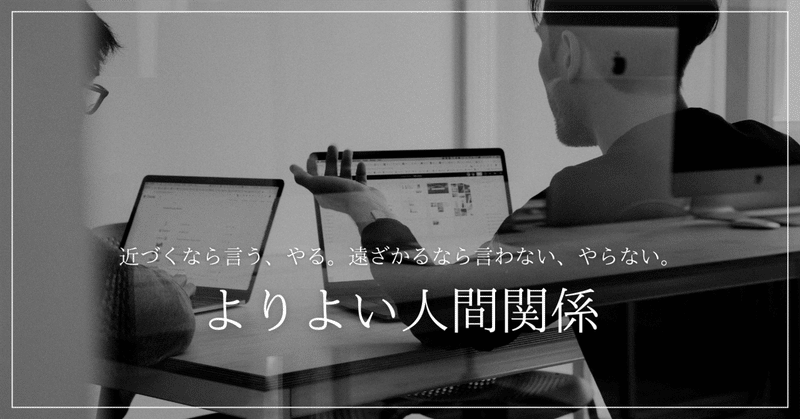
よりよい人間関係
前回の投稿に続き、今回も選択理論心理学についてお話をさせていただきます。
選択理論心理学とは、アメリカの精神科医ウイリアム・グラッサー博士が提唱した心理学で、すべての行動は自らの選択であると考えます。
前回は『落ち込みの選択』という考え方についてお話をさせていただきました。
今回は『よりよい人間関係』というテーマでお話をさせていただきます。
『あなたの感情の95%は、あなたが起きた出来事を自分自身でどう解釈するかにかかっている』
ブライアン・トレーシーの言葉です。
起きている出来事は事実です。
ですが、その出来事から抱く感情は・・・・
すべて解釈なんですよね。
車を運転していて、前に割り込まれる。
「この野郎・・・」と思う。
車に乗っていると、大抵の人はなぜか強気になります。
クラクションを鳴らそうとした瞬間、ハザードランプが点滅すると、スーッと気持ちが収まる。
相手の運転手が女性で、ニコッとされると・・・
余計に、『まぁ、いっか〜』となる。不思議ですよね、感情って。
そして次の言葉、大好きな言葉です。
『私が今、彼に言おうとしていること、やろうとしていることを言ったりやったりすることで、二人の関係は近づくだろうか、離れるだろうか?
近づくなら言う、やる。遠ざかるなら言わない、やらない』
(幸せを育む素敵な人間関係 柿谷寿美江 著 より)
この言葉を知った時、
『これを習慣化することが、人間関係を良くするためには絶対に必要』って感じました。
夫婦、親子、親しい友人・・・
近い関係になると、感情を言葉にすることが多くなります。
そして、互いの考えを押し付けようと言葉が強くなります。
そんな時、選択理論心理学の考え方が、大きなヒントになるんじゃないかと思います。まず、2つの心理学をお話します。
刺激反応理論心理学と選択理論心理学。
前者は外的コントロールとも呼ばれ、後者は内的コントロールとも呼ばれます。
外的コントロールでは、『私は相手をコントロールできる』と考えます。
人間の行動は、外部からの刺激に反応することで起こる。
・電話が鳴ったから出る。
・赤信号だから止まる。
私の行動は、私に刺激を与えた誰かのせい、何かのせいであり、私に責任はない。
他者は私の行動を変えることができるし、私も他者の行動を変えることができる。
何だか自分勝手な考え方ですね。
それに対して内的コントロールでは、『私は自分だけをコントロールする』と考えます。
生きていく上で、起きている現象、状況は情報にすぎない。
私たちは情報をもとに、自分で判断している。
自分にとって、その時最善と思われる、内発的に動機づけられた行動を「選択」している。
・電話に出るのは相手と話がしたいから。
・赤信号で止まるのは危険だから。
私の行動は、すべて私の選択。
さらによりよい方法を知れば、行動は変わるかもしれない。
自分で選択したのだから、その結果についての責任はすべて自分にある。
納得しますよね。
大抵の人は外的コントロールの経験があるのではないでしょうか。
親は子を所有している、と考えている。(所有の錯覚)
自分が子どもの頃にしていなかったこと、できなかったこと、嫌だったこと。
自分の子供にさせていないでしょうか。
会社において、組織上の関係で、上司が部下を怒鳴りつけている。
そんな姿を見たことあるのではないですか?
これらはすべて、外的コントロールの考え方が表面に出ています。
本当は誰もがみな同等で、役割として今の立場をこなしている。
ただそれだけなんです。
外的コントロールから内的コントロールに移行する上で、
『2種類の7つの習慣』があります。
『致命的な7つの習慣』と『身につけたい7つの習慣』
致命的な7つの習慣
批判する
責める
文句を言う
ガミガミ言う
脅す
罰する
目先の褒美で釣る
身につけたい7つの習慣
傾聴する
支援する
励ます
尊敬する
信頼する
受容する
意見の違いを交渉する
『致命的な7つの習慣』は人間関係を破壊する習慣と言われています。
そして、『身につけたい7つの習慣』は人間関係を良くする習慣です。
『致命的な7つの習慣』を排除する。
『身につけたい7つの習慣』を実践する。
これを意識して行動することで、人間関係は今よりさらに良くなっていきます。
みなさんも意識してみませんか?
よりよい人間関係を築く。
今日も読んでくれて、ありがとうございます。
感謝です。
ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
