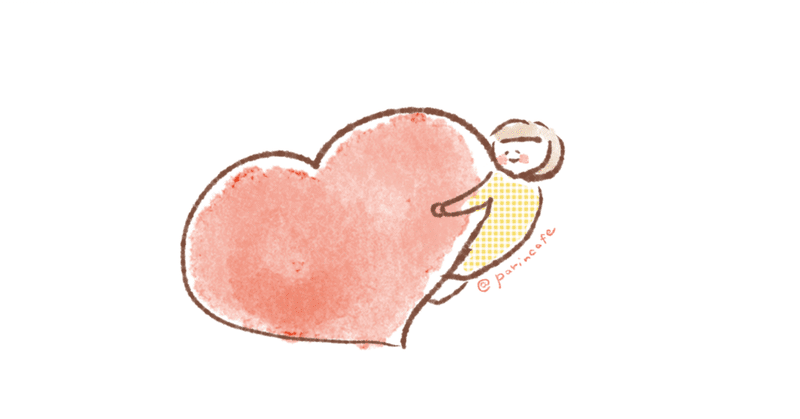
【私の思考整理①】自己効力感とは何か
どうもこんにちは、モンです!!
ところで…最近恥ずかしながら人生で初めて「自己効力感」という言葉を意識するようになった。私も「自己肯定感」はよく耳にしてきたが、皆さんも「自己効力感」をご存知だろうか?
この言葉には、自分自身の能力に対して持つ自信や信じる力という意味がある。自己効力感を高めることで、人はより積極的に自身の力を発揮し、目標を達成することができると言われているらしい。さて、今日はわたくしモンの過去に遡ってみて、「私と自己効力感」をテーマに呟いてみたいと思う。(専門的な知識はなく、まとまりもないので、あくまで呟きです)
私と自己効力感
自己効力感とは、自分自身の能力に対して持つ自信や信じる力であるが、人は人生の中でどのステージでどんな時から意識するのだろう。記憶を遡ってみると、少なくとも私は「幼稚園児」の時代から一人でに「自分はやればできるのではないか」と感じていたと思う。
では、どんな幼稚園児だったのだろうか?母いわく、幼稚園では工作が何よりが好き。そして泥団子も好きで、お友達と仲良くつるむというよりも「自分が好きなこと」を優先して遊んでいたらしい。年長さんの時は、立候補して劇のリーダーになり、一人で5役の脇役を演じて張り切っていたらしい。一方で、親と先生の1ヶ月ごとの一言コメントには、おままごとコーナーを朝から占領する女子グループに話しかけようとするが、日々模索するエピソードが書かれていた。自己評価すると、ある意味マイペースだが、悪く言うと打ち解けるまで群れが怖いと言う人見知り気質である。(それは今も変わらないかもしれない)
そんな幼稚園時代の私は、なぜ自己効力感が高かったのだろうか。その答えは、やはり何より周りの環境に恵まれていたからだと思う。家族には、否定されず「いい子だね」と言われ育ってきた。だからと言って必要以上に支配されず、自分のテリトリーを囲まれず、「私は何したいのか?」と言う気持ちを尊重してもらった。自由に過ごさせてもらったことが大きいと思う。例えば、演劇で自分で立候補して準備、本番とやり切った経験。自分がやりたい演劇ができて、それを様々な大人の人(友達のお母さん)からも褒めてもらう。年長の劇を通した成功体験と他者承認が自分の中の財産になった。
現代社会の子育て
私が今回のnoteで伝えたいことは自慢話ではない。今の子どもたちにとって「自己効力感」が大事になってくるということを述べたい。
学術的なデータがあるわけではなく、教育現場で仕事をしてきた者としても肌感覚であるが、今の子どもたちは「自分ができる」と感じることができる成功体験が少なすぎる。私が子どもだった頃は、こんなにも大人に囲まれていなく、もっと無法地帯だったと思う。ドラえもんに出てくる土地の管理者が誰なのかわからない空き地…今はもう東京では絶滅危惧種だ。つまり、管理社会になりすぎたのだ。
先月妹の大学にモグリした際、「柳田國男」の授業を聞いた。柳田先生曰く、あの時代母親は労働力。教育は学校で、子守りや育児は兄弟。それが大正以降から徐々に教育が子ども本位になった。今日では最も大切な家庭の論題が我が子の幸福や将来になったとのこと。まさにフィリップ=アリエス Philippe Ariés(1914〜84)の「小さな子ども観」である。忘れていた「教育社会学」の授業を思い出した日だった。
個人的には、子ども本位の社会になることは悪いことばかりではないと思う。しかし、令和の社会は大人が子どもを囲みすぎている。「自分からやってみる、大変かもしれないけどチャレンジする」機会がないのではないか。転ぶかもしれないから、公園には遊具を設置しない。怪我するかもしれないから、トゲトゲしている丸太を撤去しよう。受験失敗するかもしれないから、安全圏内の学校を受けさせよう。親が決めたレールの上で「自分の子が傷つかないように」大人が先回りする社会になっている。
では、何をしたらいいのか
子は親を選べない、変えられない。それは仕方がないことだ。しかし、その子の周りにいる大人たちと言うのは、ライフステージごとに変わる。教育に関わる全ての大人たちが、子どもを大人の視点で囲みすぎず、子どもたちが「本当に何をしたいのか」を一人で考え、「自分からやりたい!」という意志があれば認めて、応援する存在になることが理想だと考える。
「君たちはどう生きるか」
現代社会において、最大のテーマである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
